- ITmedia エンタープライズ
- 書評:情報技術はどこまで「知」に接近できるか ―...
書評:情報技術はどこまで「知」に接近できるか ―「ナレッジ」と「経営」を結ぶための4冊―
「ナレッジ」と「経営」の困難な関係
以前、この書評欄(呪文から現実になるCRM)で書かせていただいたが、情報技術をマネジメントに適用していく道のりには、2つの大きな落とし穴が待ち構えている。第1の落とし穴は、「呪文化」であり、第2の落とし穴は「オール・イン・ワンシステム依存症」である。CRM、SCM、ERP、……これらは生産から販売に至る企業経営のプロセスを流れる「情報」を集約し、複雑なプロセスをコントロール可能な対象とするための、フィードバックの回路をもたらす概念であるが、いずれもがこの2つの落とし穴を抱え込んでいるといえよう。そしてもう1つこの列に加わりつつある概念がある。それは「ナレッジマネジメント」である。
今回紹介する4冊の本には、それぞれわれわれがこれらの落とし穴にはまらないためのガイドとしての役割が期待できる。それは、(逆に、安易な期待とは裏腹に)「ナレッジ」という対象と、「経営」の間の困難な関係を、僕たちに気付かせてくれるからである。企業によるIT(もう使い古された感もあるが……)導入も、そろそろしっかりとした足取りで第2フェイズに進まなくてはならないだろう。大規模システムベンダが残したハードウェア、ソフトウェア、そして数々の事業の累々たるしかばねを乗り越えるために、われわれはいま、情報技術にどのような可能性を見いだしたらよいのだろうか。その入り口をこれらの本は「言外に」指し示しているように思える。
まず、これらの本を読み始めるに当たって、あなたのこの分野に向けられた関心をポジショニングしてみよう。第1の軸は、「ナレッジ」から「経営」を見るか、「経営」から「ナレッジ」を見るかというあなたの立ち位置を問うものである。第2の軸は、あなたが得たい知見(ソリューション)は何かという問いに対応している。つまりあなたは、「問題の本質を見極めたい」と考えているのか、「具体的なシステムや組織の構築に関する課題に直面しているのか」というものである。さて、こうして分かれた4つの象限のどこからあなたは、この問題を考えていくのだろうか。4冊の本の概略を紹介しつつ、まずはそれを考えていただくことにしよう。
4冊の概略
■ナレッジ・サイエンス──知を再編する64のキーワード
ナレッジ・サイエンス──知を再編する64のキーワード
北陸先端科学技術大学院大学 知識科学研究科監修、杉山公造/永田晃也/下嶋篤編
紀伊國屋書店
2002年12月
ISBN4-314-10153-9
2500円+税
まず、「ナレッジ」と「経営」にかかわる問題全般をふかんするには、この1冊が最適であろう。「知のダイナミクス」「知のエレメント」「知のメソドロジー」「知のエンジン」「知のオデッセイ」の5つのカテゴリで、このテーマにかかわるキーワードをかなりの範囲で網羅している。実にうまく編集されているなあと思うのは、この5つのカテゴリの順番である。まず“企業の変革”という課題が目の前にあるというところが、この編者たちが共有している意識なのである。
展開されているのは、
企業変革には、ナレッジの動員が不可欠である
↓
その対象になる「知」とは何か
↓
それに接近する方法とは
↓
コンピュータでは何をどこまで扱い得るのか
↓
これまで問題にしてきた「知」とは、ビジネスからどのような射程にまで拡張し得るのか
といったストーリーである。もちろん、自分がビジネスパーソンであるという前提で読めば、この流れは「すうっ」と入ってくる。しかし、ここでは、そもそも「人間の“知”を考えるというテーマは、本来ビジネス的な課題が中心なのであろうか」という根本的な問題が後回しになっている。果たして「知」=「知識」と言い換えてもよいのだろうか……。こういった疑問が、頭に浮かぶようになったら、ぜひ、ほかの3冊に挑んでいただきたい。
僕は、(後で触れるが)人間の「知」と「経営」を媒介するものとして、「ナレッジマネジメント」が本当は“どのような役割を果たす(べきなの)か”を見定めることが、この問題のかぎを握っていると考えている。その役割を考えるうえで重要な点は、実は「知」を意識する場面は多様であるということである。僕たちがこれから接近しようとしている「知」とは、<「知」の集団性--つまり“コラボレーション”の問題、「知」の階層性--つまり“暗黙知”の問題、「知」の操作性--つまり「知」と「実践」の関係の問題>の3つの局面で、その容易に手の届かない奥行きの存在を知らせてくれるものなのだ。
■協同の知を探る--創造的コラボレーションの認知科学
まず、第1の局面である「知」の集団性について考える手掛かりとしては、この本をお勧めする。とはいえ、実はこれは認知科学の研究者たちの論文集なので、内容はちょっと手ごわい。まずは、人間は集団となることでどのような有益(?!)な「知」を得ているのか、そのキーワードである「創発」「協調」「問題解決」といった言葉に触れるだけでも、この本を手に取る価値はあるだろう。認知科学は、操作的な理性=数量化の方法論である。実験によって「知」の在りかを「数」で把握しようという、こうしたアプローチも、ビジネスパーソンには感覚的に近いものがあるのではないだろうか。
■暗黙知の解剖--認知と社会のインターフェイス
ビジネスの現場における有益な「知」とは何だろうか。意識をせずに、意識して手を動かした以上のことができてしまうこと、すなわち「ルーチンワーク」が、それを実感し得る最も身近な表れではないだろうか。著者はそのような仮説から、「暗黙知」に挑む。しかも、その「暗黙知」そのものを捕そくするというよりは、その階層性を意識して顕在化した「知識」とのインターフェイスの在り方(「語りの技法」)に問題の焦点を絞り込んでいることは興味深い。「知」に対する適切なアプローチの一例として十分参考になる1冊である。
■コミュニティ・オブ・プラクティス--ナレッジ社会の新たな知識形態の実践
コミュニティ・オブ・プラクティス――ナレッジ社会の新たな知識形態の実践
エティエンヌ・ウェインガー/リチャード・マクダーモット/ウィリアム・M・スナイダー著、野村恭彦監修、野中郁次郎解説、櫻井祐子訳
翔泳社
2002年12月
ISBN4-7981-0343-8
2800円+税
コミュニティとは本来は、地縁や血縁に根差した共同体を意味する言葉であった。集団生活の基礎となるこの形態の中においては、確かにさまざまな「知」が蓄積されてきた。こうしたコミュニティの原理をビジネスの現場に再構築する際、その成否を握るのは「集団」の形態というよりも、「実践」というアクティビティにあると著者たちは考えている。
なぜならば「実践」こそが、限られた「自己の超越」を可能にし、「持続的な変容」を集団にもたらすものだからである。もちろんこのことは、「知識」として外化した「知」に対する操作的な態度とは対極にある。「実践知」とは自らの手元にあって、かつ自らのモノではない対象なのである。
さて、この4冊を先ほどの2軸に対応させて置いてみると、(これはあくまで僕の印象ではあるが……)下のような関係になるのではないだろうか。いずれにしても「ナレッジ・サイエンス」を総論もしくはインデックス、「協同の知を探る」「暗黙知の解剖」「コミュニティ・オブ・プラクティス」を各論として読んでいくとよいと思う。
この4冊を通読して……得られる「視点」は何か
「ナレッジマネジメント」いわゆる“KM”は、SCMやCRMなど、先に挙げた概念とはいささか異なる性格を持っている。SCMやCRMは、散在しているとはいえ、もともと「生産」「流通」といった企業経営の閉じたシステムプロセスの中で、生み出された痕跡、あるいは結果として顕在化したデータを集約することに主眼がある。それはいわゆる「統合(インテグレーション)」という操作の効用に期待するものである。「ナレッジマネジメント」とはこれらとは根本的に異なる“事柄”を相手にするものである。「ナレッジ」ももちろん経営者の目から見ればこれも同様に「散在したもの」であるには違いない。しかしそれは、ただ散らばっていて捕そくが困難なだけでなく、始末に負えないことに、「人間」という経営とは異なるメカニズムで働くシステムの中に囲い込まれた厄介な対象なのである。
これこそ「知」と「知識」との非同一性という大きな問題である。「僕たち人間」の「生」を構成するさまざまな「情報システム」全体にかかわる概念として、仮に「知」という言葉を当てはめてみることにしよう。そしてその「知」なるものを、人間の社会的な生活の営みに、合理的に援用することをイメージしたとしよう。その途端にこの仮定自体が、その肯定的(ポジティブ)な回路を裏切り始めるのだ。そういったパラドックスに僕たちは、生活環境がIT化に向かうはるか以前からさいなまれてきた。こうした矛盾した動きの背景には、必ず単線的な制御ではない「情報」の錯綜がある。つまり、「知」なるものが作動するプロセスの中には、僕たちの手に負えないものが数多く存在しているのだ。こうした合理化の手が届かない「知」の部分を、「協同知(コラボレーション)」「暗黙知」「実践知」などと僕たちは呼んできた。
これらの「知」になぜ注目が集まるのか。理由は簡単である。「知」の中で僕たちが合理的、計算可能的に扱うことができる部分は、いつも同じ答えを出してくれることに、その存在価値がある。それに対してこれらの「知」の働きは、いつも予想以上の結果をもたらすことで僕たちを驚かせてきた。それと併せて、この不可知のファクターはしばしば予想を裏切ることも経験してきた。だからこそ重要なのである。予想以下を生じさせるリスクをできる限り押さえ込み、予想以上の結果をもたらす力をいかに味方に付けるか……。僕たちと合理化不可能なものとの向き合いは、こうした真剣かつ魅力のある勝負なのである。
ところで人間の「知」の中で、計算可能、合理化可能なファクターに限ってその対象を「知識」と呼ぶことにしよう。「ナレッジ」とは、まずはこの「知識」のことである。しかしここで非常に困難な問題は、この「知識」と「知識」以上のものとの区別をつけることが、決して容易ではないという点にある。「知」をすべて「知識」に置き換えることが可能であるなどと思い上がったり、つい「知」と「知識」のすき間にあるものを見失ったりしてしまうリスクは、そこここに存在している。「ナレッジマネジメント」の課題は、こうして計算可能な「知識」を扱いつつ、いかにして「知」の総体に接近し、不可知のファクターを味方に付けるかにある。<「知」は決して「知識」に回収されることはない>ということを自覚しつつ、また<「知」と「知識」の明確な違い>をしっかり意識しつつ、それでも“あえて”「知」を合理性が支配する経営システムに援用する--経営資源に組み込むことができるか--これは、非常に困難かつ重要的な課題である。その知見(ソリューション)は、いったいどのようにして得られるのだろうか。
ここから先は、先ほど挙げた「知」の「集団性」「階層性」「操作性」という3つの局面について、恥ずかしながら少し僕の考えを書かせていただく。ぜひ、紹介した4冊と比較対照していただき、各々のパースペクティブとの重なり、違いについてお考えくだされば幸いである。
「知」の集団性
「僕たち人間」というとき、それは個々の人間を意味すると同時に、人間の集団的な関係を名指ししている。つまりそこには一定の同質性が想定されており、その上に交流・交換が生まれる可能性が開かれている。「知」と合理性の関係を考えるとき、最初の不可知のファクターはここに存在している。「知」が集団のレベルに押し上げられたとき、そこには個々人の能力を超えるものが生まれる。このことは誰もが経験として知っていることである。
この期待以上の結果に寄与する「知」の集団性は、よく見ると実は3つの異なる現象について語られていることが分かる。1つは「知識」の共有である。これは集団の機能そのものというよりも、存在する他者もしくは共有される外部のメディアに記憶を移すことにより「知識」量のキャパシティを高めること、「知識」とのアクセスを合理的に制御させることを意味する。狭義の「ナレッジマネジメント」はこのレベルの機能を指し示す場合もある。
第2の現象はプロセスの組み替えである。これは初期資本主義の時代に、作業場内分業のメカニズムとして発見されたものであるが、この「個体が行うリニアなプロセス」を、組織の機能として外部化することで分節し、そのことによって生産性の向上に寄与するというメカニズムは、実は作業の切り替えに伴う時間・空間的なロスを極小化し、定型化による反復効率を高めたものにすぎない。この2つの現象は、僕たちが問題としている「不可知のファクター」とは異なるものである。というのは両者とも計算可能な「知識」の範疇で考えることができるからである。これら2つの現象の結合がオートメーションの成立に結び付いていることはいうまでもなかろう。
第3の現象は、これらとまったく異なる表れ方をする。僕たちが「知」の集団性としてイメージする「コラボレーション」「協同」という言葉が意味するものは、「知識」の処理、組み替えとは異なる次元の働きである。どちらかといえば、集団によって発生する交流・交換が、「知識」の生産そのものにかかわる時点の現象である。「知識」を生む「知」のメカニズムといってもよいだろう。この部分においてのみ、個人の集積とは異なる機能を持つ集団のレベルの存在を想定することができる。こうした創発的機能は、もっぱらコミュニケーションとのかかわりで探求されることが多い。しかし、まだまだその実態はなぞに包まれているといえる。
ここで重要な点は、人間特有の「知」の1つの局面としてよく語られる「知」の集団性は、集団(この場合組織)的な「知識」のマネジメントとは異なる現象を指すことに自覚的でなければならないということにある。しばしばこの2つが混同されたり、一緒くたに語られるのは問題ではあるが、しかしながら、3つ目の創発的な「知」の集団性も、前2者のプロセスと一緒に表れる場合が多いことを示しているともいえる。ここに実際は、「ナレッジマネジメント」の有用性と活用条件を考えるヒントがある。
「知」の階層性
集団における「知識」と「知」の関係を見てきたことで、僕たちは「階層」的に「情報」を処理していることを理解できる。「階層」的であるということは、ブラックボックスを作ることにほかならない。計算式で考えると、“括弧”を用いることがこれに当たる。
計算可能な世界では、こうした「階層性」はあらかじめ用意されたプロトコルとして存在する。つまり、操作的に設定され得る世界である。AI的な世界観の(イデオロギー的な)前提が「全知のまなざし」と同じものであることが指摘されて久しい。コンピュータの階層構造が成立するのは、こうしたすべてのプロトコルが設定可能である「閉じた」世界だからである。この条件を反対から見ると、コンピュータには、すべてのプロトコルが漏れなく設定されていないと、十全な機能を発揮しないという不自由さのあることが分かる。
人間というシステムも、同じように「階層性」を持っている。しかし、そのメカニズムはまったくコンピュータとは異なる。それは「括弧」を用いることではなく、「了解」し「忘れてしまう」または「意識しなくなってしまう」ことによって成り立っている。従って人間の「知」の階層性は、あらかじめ設定されたものではなく、その都度、逐次的に機能している。しかも、それは計算式で表すことができるような整然とした構造を持つものではなく断片的であり、飛躍を許容し、それ故散在している。このことが、「ナレッジ」を「マネジメント」することの困難さを生んでいる。外化した「知識」と異なり、人間の中にある「知」は、散在しているだけでなく、同じ場所にとどまっていない。つまりこのような揺らぎの激しい階層を前提に、システムの外部からその構成素たる「知」を指し示すことは、困難を極める。
しかし、だからといって人間の「知」はまったくインターフェイス不可能なのかというとそうとも言い切れない。なぜならば人間は「忘れる」けれども「思い出し」もするからである。ずっと思い出せなかった人の名前を、何かの刺激によって突然思い出すことはよくある。この「思い出し」は、外部の事象との結び付けが生成されたという意味で、創発的な出来事であるといえよう。僕たちは、「階層」そのものを固定的に設定することはできないが、「内部」から生まれるシステム外への指し示しの記録を「外部」に「知識」として残すことはできる。この写像関係を習慣化させることで、人間とコンピュータ的構造物とのインターフェイスを作ることはできるのである。
もちろんこのことは、経営システムの中に、人間を構成するファクターすべてを取り込むことを意味しない。人間の情報処理と、経営システムとの関係を「記録」として「保存」するにすぎない。
「知」と操作性
人間の「知」にかかわる不可知性は、単に複雑さに還元できるものではないという仮定でここまで話をしてきた。しかしこれに対し、集団におけるコミュニケーションの創発性、個人の意識における思い出しの創発性なども、その現象を引き起こす膨大な条件が与えられ、それに対する計算が可能にさえなれば予測可能になるはずという技術の進歩に肯定的な立場を取る反論が一方にはあり得る。
この反論が成立するには、2つの前提がある。コンピュータ技術の進歩が将来計算量の爆発を許容し得ることと、すべての条件を数え上げることが可能になるということである。僕は、これらの展望に対して、取りあえず答えは保留しておくことにする。なぜならば、これまでのコンピュータ技術の発展は、ある意味こうした夢を追ってきた成果であることを否定するわけにはいかないからである。
とはいえ、おそらくこうした目標に向けた試みは、漸近線を描くにとどまるものになるであろう。だからこそ僕たちは、このこと、すなわちあくまで与えられる「解」は近似的なものにすぎないということに真摯に向き合う必要があるのだ。言い換えれば、この近似値と求めるものの差こそが、「知識」と「知」の違いであるということになろう。
つまり僕たちは、人間の「知」そのものを、捕そくすることができない。接近し得るだけなのである。でも、それで十分ではないか。「ナレッジマネジメント」は、上手に接近し創発の可能性を呼び込むための方法である。そう考えれば、どのように「知識」を操作するべきか、おのずと答えが出るであろう。
操作可能であるとは、その対象がすでに構造化されていることを意味する。「ナレッジマネジメント」が「知識」を操作することができるのは、「知識」が構造化されている、すなわち言語化が前提となっている。僕たちが、「知」そのものを操作することができないことの意味は、「知」すべてを言語的なものとして外部的に対象化できないことにほかならない。しかし、こう考えてみたらどうだろう。僕たちの存在自身が、すなわち「知」であるとするならば、言語的に理解-操作しなくとも、僕たちの振る舞いそのものを「知」として、内部観測的に向き合うことは可能なのではないか。
「実践コミュニティ」とは、こうした「知」の集団性、階層性、操作性に、「知」そのものの在り方に従って向き合う方法である、ということもできるだろう。大事なことは、その内部的なアプローチと、外化された「知識」との関係性をマネジメントすることである。Webという不安定なネットワークは、その方法を考えるにはうってつけなのではないだろうか。計算可能性に身を委ねてしまう「経営」の方法は、実は安定した環境を前提とした理念型にすぎないものである。僕たちにとって、いま何よりも必要な能力は組織内部的な存在として「環境の変化に耐え得る心」を持つことである。変化そのものに対する感受性を鈍らせてしまう「知」の物象化に抵抗していくことが、本当の意味で「知」を経営資源に結び付けていく道なのではないだろうか。
各書評にある「注文ページへ」ボタンをクリックすると、オンライン書店で、その書籍を注文することができます。詳しくはクリックして表示されるページをご覧ください。
著者紹介
水島 久光(みずしま ひさみつ)
1984年慶應義塾大学経済学部卒業後、旭通信社でダイレクト・マーケティングを手掛ける。1996年、インターネット広告レップ「デジタルアドバタイジングコンソーシアム」の設立に参加し、インターネット・マーケティングに関する多くのプロジェクトに携わる。そのうちの1つ、情報検索サービス「インフォシーク」の日本法人設立準備に合わせて旭通信社を1998年10月に退社し、「インフォシーク」を運営していたデジタルガレージに入社。1999年6月、インフォシークの設立後、編成部長を務める。2001年4月末インフォシークを“卒業”し、東京大学大学院学際情報学部 修士課程を経て、2003年4月より東海大学文学部広報メディア学科助教授として現在文・理系を横断する“情報学”の視点から、メディアをふかんする視座を探求している。2002年度まで(社)日本広告主協会傘下の「Web広告研究会」の事務局を務め、同会編『Webマーケティング年鑑2002』『Webマーケティング年鑑2003』(インプレス刊、2002.3、2003.4)の編集、およびいくつかのセクションで執筆を担当。論文としては「情報バラエティーのダイクシスとアドレス」(『社会の言語態』東大出版会刊シリーズ言語態第5巻所収 2002.4)などがある
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
チェックしておきたい人気記事
人気記事ランキング
- 情シスは多忙でも「あのツール」は使わない おカネ以外の3つの理由とは?
- Outlookが標的 高度に難読化された新型マルウェア「Strela Stealer」が登場
- AWSやAzureの「認定資格」が昔ほど評価されない理由
- 非情な現実? セキュリティ担当者の置かれた過酷な立場
- 「C++」存続の危機? 生みの親が安全なプログラミング言語への転換を模索
- 大規模DDoS攻撃によって「X」で世界的な障害が発生 ハクティビストが関与主張
- より自社に合うERPはどっち? SAP S/4HANAとOracle Fusionを5つの観点で比較
- S3の標準機能だけでランサムを実現? マルウェアも脆弱性も使わない新手口
- 日立がOracle、Microsoftと共同検証 ミッションクリティカル系システムのクラウド移行を推進
- セキュリティ人材不足の裏にある“からくり”と“いびつな業界構造”




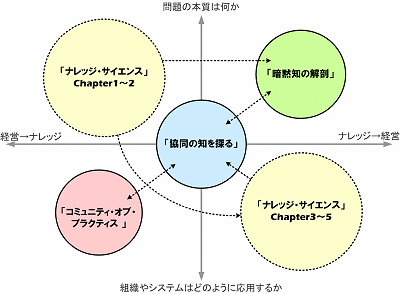 4冊のポジショニング・マップ
4冊のポジショニング・マップ