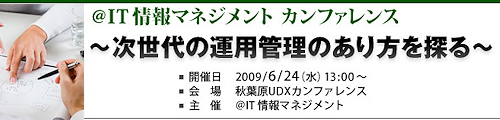
@IT情報マネジメント編集部主催の「@IT情報マネジメントカンファレンス 〜次世代の運用管理のあり方を探る〜」が、6月24日に都内の秋葉原UDXカンファレンスで開催された。
基調講演ではBSIマネジメントシステムジャパン BSI教育事業部長の打川和男氏が『ITサービスマネジメントのためのベストプラクティス実践活用』と題して、ISO 20000や27000、ITILなどの規格やフレームワークの特徴と使い分けに関して解説した。特別講演では、カブドットコム証券のITプロフェッショナルエバンジェリストである谷口有近氏が『会社活動の全てをITサービスとして捉える ISO 9001/20000/27000の実践と開示』の題で、同社におけるマネジメント規格の活用についてのプレゼンテーションを行った。さらに特別講演としてニュートン・コンサルティングの代表取締役 副島一成氏が『ITIL効果倍増計画』と題し、ITILに基づくSLAの明確化やIT事業継続計画策定について解説が行われた。
以下では、当日行われたセミナーの中から4つのセッションについて概要を紹介する。
 セミナーレポート インデックス セミナーレポート インデックス |
|
セッション1 |
ITサービスマネジメントの中核、ITポートフォリオ管理の考え方を整理する ――日本アイ・ビー・エム |
セッション2 |
潜在価値を引き出してスリムなITを 〜CAサービスマネジメント・ソリューション ――日本CA |
| セッション3 | 運用管理の超効率化 〜NetIQの次世代運用管理ツール ――NetIQ |
| セッション4 | 安全、コスト、お任せください! ICT機器は「所有」から「利用」の時代へ! ――ユニアデックス |
| セッション1:『ITサービスマネジメントの中核、ITポートフォリオ管理の考え方を整理する』 日本アイ・ビー・エム |
 |
| 日本アイ・ビー・エム ソフトウェア事業 Tivoli事業部 サービスマネジメント担当部長 久納信之氏 |
ITILがV2からV3になって強調されるようになったのが「ライフサイクル」と「ポートフォリオ」だ。日本アイ・ビー・エムの久納氏は、これからのITサービスマネジメントの中核となるポートフォリオ管理について講演を行った。
中長期にITがビジネスに貢献するためには、ITにも戦略的な取り組みが必要だ。それはすなわち、どういう優先順位で何に取り組んでいくのかを考えていくこと。久納氏は「その中心的活動になるのが“ポートフォリオ管理”だ」と説明する。
新規のITプロジェクトに取り組むとき、多くはプロジェクト起案書を書く。ここにはプロジェクト名、ビジネスの背景、目的や現状の問題、到達点、プロジェクト範囲(あるいは範囲外)、成功指標、ベネフィット、スケジュール、リソース、そして費用などの項目が含まれる。
複数のプロジェクトやITサービスでこうした項目をまとめ、ビジネスに対する効果や提供価値を証明できるようにしたリスト――それが主要なポートフォリオだと久納氏は定義し、「昨今のように景気が悪い状況では、マネジメント層に対してIT部門がこういう状況で活動している、ということをいつも説明できるようにしておくことが重要だ」と訴える。
ポートフォリオ管理の大きな目的は、投資に優先順位を付けることだ。IT投資には、「業務改善型・改革型投資」「情報活用型投資」「戦略的投資」「IT基盤整備型投資」といった種類がある。加えて、投資効果が確実か、不確実なのかという区分もある。ここでのポイントは業務改善型のようにビジネス・デマンドに基づく投資の場合、そこにIT基盤整備型を含めておくべきだということ。そしてプロジェクトの起案やITの組み立てを考えていく際には、3〜5年のタームでその後のオペレーションにかかるコストを含めて考えていくのがポートフォリオ管理なのだろうと久納氏は語る。
投資の優先順位を付ける方法について、久納氏は「一般的にはROIが基本になっている」としながらも、コンプライアンス(法令遵守)に関する案件はROIを超えて優先度が高くなるほか、社会的責任や自社のスキル、ベンダスキル、リソースの有無、期間やスケジュール、ビジネス戦略との整合性、プロジェクト計画の品質、プロジェクト企画書の正確性などを踏まえて、総合判断することが大切だとした。
その総合判断はできるだけ客観的な方法がよい。「リスクについては5点」というように数値化し、さらに評価項目の重要度に応じて点数のウェイトを配慮して、総合点で評価するといったやり方が一般的だ。
経済性指標について、久納氏は「ROIは分かりやすいのでよく使われるが、私はNPV(正味現在価値)を使っている。ROIはパーセンテージなので実際の額がはっきりしない。ROIが100%で1000万円のもうけと、50%で1億円のもうけでは後者の方がいいかもしれない。そうした具体的額面で出てくるのがNPV」とした。
ROIもNPVも算定要素は、「初期投資」「経過費用」「生み出される利益」が基本だが、久納氏は「IT分野は経過費用の算定が弱い」と指摘。例えば、受発注システムがそれに使ったサーバや開発費は分かるが、ほかにもネットワークやデータセンター、そこで働く人の人件費を考慮しなければならない。データセンターの「庭の整備代」というものさえあるという。特に久納氏は、ベンダ費用や法人税、固定資産税、原価償却費などは経理部の人とよく議論した方がいいと強調した。
ポートフォリオ管理とは、ITプロジェクトやITサービスのあらゆる情報を集約し、それに基づいてすべてのリソースの最適分配を行って、IT戦略とビジネスの整合性を証明する活動だ。重要なポイントは基盤整備――すなわち、IT資産管理やITサービスの財務管理などがきちんとできているのが大前提だということだ。
久納氏は、「ITサービスマネジメントは、イコール運用ではない。サービスマネジメントは、ITリソースを使って価値=バリューを作るという考え方。サービスマネジメントにはポートフォリオ管理が含まれる」としたうえで、「ポートフォリオ管理は、計測結果に基づいたアプローチが必須。可視化が不可欠だ。私の経験では、サービスマネジメントの取り組みでは可視化が一番重要だった」と強調した。
最後に久納氏は、「可視化すればコントロールできるようになり、それを自動化すればさらに有効だ。IBMでは“ビジビリティ”“コントロール”“オートメーション”の3つの分野に分けてTivoli製品群を用意しています。皆様の会社の可視化に貢献します」として、セッションを締めくくった。
| セッション2:『潜在価値を引き出してスリムなITを 〜CAサービスマネジメント・ソリューション』 日本CA株式会社 |
 |
| 日本CA株式会社 サービスマネジメント・ソリューション営業部 テクニカル・ソリューション・グループ コンサルタント 松波孝治氏 |
「Lean IT」とは、“すなわちムダのないITを作っていこう”という、CAが今年度から掲げるビジョンだ。セッション2では、日本CAの松波孝治氏がその方法について講演を行った。
ムダのないサービスマネジメントは、まず現状診断に始まる。CAはそのために「ITIL有効性アセスメント」というサービスを提供している。大きな流れとしては、「問題の抽出」「課題の抽出」「活動の提案」「サービスマネジメント・ベースラインのデザイン」となる。
問題の抽出は、CAのコンサルタントがファシリテータとなって、関係部門の人々が参加する「ワークアウト」を開催し、具体的な問題を挙げていく形で行う。問題はいろいろなレベルで挙げられるが、これを2つの方向に整理・構造化する。すなわち、「なぜそれが起こったのか」という方向性で整理・分析して「根本原因」に至る方向と、「それによって何が困るのか」という方向性で「UDE(Undesirable effect)」に収斂(れん)させる方向だ。
このような構造化・分析を行うと、関係のある問題をひとくくりにしていくことができる。それを優先順位付けして、どこから手を付けていくかを決定していく。その優先順位付けの指針となるのがUDEだ。このUDEが会社のゴールとする目標に対して、どの程度の影響があるのかを見ていくことで、こうした意思決定が行える。
問題の構造化ができたら課題の抽出を行う。課題とは「解決するためにすべきこと」である。課題が設定できれば、それに対してITILのどの活動が有効かを定義する。一連の活動が定義されると、これがITサービスマネジメントのベースラインとなる。
ここまでが「ITIL有効性アセスメント」だが、現実には定められたベースラインと、実際のITサービス提供活動にかい離がないように“維持”することが大切になる。これには日々の活動を記録していくことが前提となる。
松波氏は、「記録のための器(うつわ)はCMDB(構成管理データベース)であるべき」という。CAでは、CMDBを中核に6製品からなるITサービスマネジメントツールをラインナップしている。
「CA CMDB」はその名のとおり構成管理データベースで、ITIL V3でいう構成管理システムの考えに基づいて、CMDB Federation(CMDBf)という団体で決定された仕様に準じてデザインされている。これはCA、マイクロソフト、IBM、BMC Software、HP、富士通の6社が共同で構成管理に関する仕様を策定する団体で、「CA CMDB」はこの仕様に準拠した製品と情報を連携させて、“論理的”に一元的なデータベースを構成できる。
「CA CMDB」には、構成アイテム(CI)の関係性を可視化する機能を備えているのも大きな特長である。「AサーバはBサーバをバックアップする」「CサーバはDルータと通信している」といった関係を含めてCMDBに記録し、グラフィカルに表示する。各CIをアイコンで示し、矢線で結んでどの方向からサービスが提供されているのか、どのような意味があるのかを見ることができるので、影響分析や根本原因分析を行うことができる。
「CA Service Desk Manager」は、ITIL V3で定められているインシデント管理、イベント管理、問題管理、変更管理、サービス資産管理、構成管理などのプロセス活動をオールインワンでサポートする(CA CMDB含む)。ウェブレポート/約200のレポートテンプレートを搭載し、KPIに基づく評価・改善を支援する。また、マルチテナンシー機能によって、1つのシステムで複数の顧客の管理も行える。ナレッジ管理が強化されることで、トラブルや問い合わせを文書化してメンバーで共有したり、ユーザーに公開して自己解決を促進したりすることもできる。
「CA IT Client Manager」と「CA IT Asset Manager」は、IT資産ライフサイクルを管理する製品となる。「CA IT Client Manager」は、インベントリ情報の自動収集やパッチ配布などの機能より、IT機器の現状把握とメンテナンス業務を自動化・省力化。「CA IT Asset Manager」は、ハードウェア/ソフトウェアの財務的な価値、契約やライセンス、ライフサイクル状況など、IT機器を会社資産として管理する。
「CA Service Catalog」と「CA Service Accounting」は、サービス提供者と利用者のコミュニケーションポータルである。「CA Service Catalog」は利用可能なITサービスのサービス内容、価格、サービスレベルといった情報を提供し、「CA Service Accounting」は提供したサービスに課金したり、部門配賦したりといった機能を提供する。
最後に松波氏は、「ムダのないITとは、最低限のコストで最大限の価値が提供できるものである」とし、「この次世代といわず永遠の運用管理のテーマに対して、今後もCAはアセスメントやソリューションを通して皆様の会社を支援していきます」と講演を締めくくった。
|
さらに詳しい資料を、TechTargetジャパンでご覧いただけます。 潜在価値を引き出してスリムなITを 〜CA Service Management Solutions〜 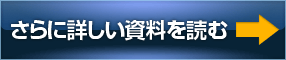 |
| セッション3:『運用管理の超効率化 〜NetIQの次世代運用管理ツール』 NetIQ |
 |
| NetIQ 製品企画担当マネージャ 堀田昌昭氏 |
今日のシステム運用管理の現場の多くは、「新しい技術の登場とそれへの対応」「サービスレベルの向上」「守るべき法令が次々に出てくる」「ITILなどのプロセス導入」など、やらなければいけないことが増えているにもかかわらず、人的資源やコストは減ることはあっても増えることはないという状況に置かれている。
NetIQの堀田氏は、ここでありがちな間違いに「安い人件費で人を雇うこと」があると指摘する。歯車のように運用管理者を扱ってしまうと、新しいITサービスを設計して、それを実際に適用していくという作業をする人材が社内に育たないというのだ。
低コストによる運用と人材育成を両立する解決策として堀田氏が提案するのが、プロセスの自動化だ。それを実現するのが、NetIQが6月17日に発表したITプロセス自動化ツール「NetIQ Aegis」。これはさまざまな管理ツール/テクノロジをまとめてコントロールし、一連の作業として人手を極力排した形で実行する製品である。
一般に運用管理の現場では、すべての管理ツールが同一ベンダ製品にそろえられていることはまれで、いろいろな管理ツールが混在している。こうした導入済みの管理ツールを有効活用して、よりよい運用を行うというのが「NetIQ Aegis」のコンセプトだという。
「NetIQ Aegis」は、プロセスとランブック(手順書)の両方のレベルで自動化を実現する。プロセスとはITILプロセスのように部門をまたいで行う作業であり、ランブックとは部門内や作業者レベルの手順である。これを「NetIQ Aegis」上でモデル化し、各種管理ツールと連携することで運用管理作業の自動化が行える。例えば、増えすぎたファイルを消すという作業であれば、管理者が運用管理ツールで手作業を行うのではなく、あらかじめバックアップするファイル、アーカイブするファイル、削除するファイルを「NetIQ Aegis」で定義しておくことで、運用管理者は実行の承認を行うだけで、「NetIQ Aegis」が管理ツールに指示を出して削除やバックアップの作業を自動化する。こうした自動化作業はモデルを再検討する“PDCAサイクル”を回すことで、いっそう効率的なプロセスになる。
個人レベルのノウハウは「NetIQ Aegis」のモデルにすることで、属人的な知識が機械的に発揮できるようになり、人依存の業務から脱することができる。インシデントの発生のように大きなプロセスの場合、属人的作業中心だと多くの部門メンバーが参加する会議を都度開いて対策を話し合ったりすることになるが、こうしたプロセスを「NetIQ Aegis」上で整備すれば、非常に効率的な対処が可能になる。
「NetIQ Aegis」のアーキテクチャとしては、最上位のプレゼンテーション層には「Configコンソール」「Opsコンソール」「レポート」の3種類の“コンソール”が用意されている。「Configコンソール(コンフィグレーションコンソール)」は、実際にワークフローを作るデザイナー機能と、作ったワークフローの履歴を管理する機能を提供するコンソールだ。他社製品を含めて、各種管理ツールがつながっているかどうかを確認する。ワークフローのデザインはグラフィカルな環境でドラッグ&ドロップでアイコンを並べ、それを矢線で結び、パラメータをセットする形でモデリングを行う。
「Opsコンソール(オペレーションコンソール)」は、実際に「NetIQ Aegis」を使って運用を行う人のためのコンソールで、現在動いているプロセスは何か、そのプロセスの進行具合はどうか、管理者の許可/不許可の状態はどうか、などを確認できる。「レポート」は、動作が終了したワークフローについて、よく起動されるものはどれか、どれくらいの時間がかかったか、どれくらい工数が減らせたかといったことを知ることができる。これを見ながらさらにワークフローを改善していくことも可能だ。
続けて堀田氏は、「NetIQ Aegis」につなぐ管理ツールの例として「AppManager Performance Profiler(AMPP)」を紹介した。AMPPは「いつもと違う動き」に警告を発するパフォーマンス管理ソフト。余計なアラートを減らすことができるなど、運用現場の“超効率化”を支援する。
最後に堀田氏は、まずは各種の運用管理ツールを活用して、大きなレベル(プロセス)の自動化を行い、さらに接続する管理ツールを工夫することでさらなる効率化が行えると述べて、講演を終えた。
|
さらに詳しい資料を、TechTargetジャパンでご覧いただけます。 運用管理の超効率化 〜NetIQの次世代運用管理ツール〜 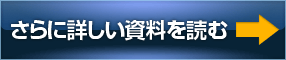 |
| セッション4:安全、コスト、お任せください! ICT機器は「所有」から「利用」の時代へ! ユニアデックス |
 |
| ユニアデックス 企画部 LCMビジネス推進センター長 森下清高氏 |
現在、「クラウド・コンピューティング」「SaaS」の掛け声の下、ITの“所有から利用へ”という流れが加速している。この流れは全社レベルで利用するアプリケーションについては鮮明だが、それでも企業のオフィスには、個人のデスク上のクライアントPC、そして部門サーバー、ネットワーク機器が残る。これらの運用管理を請け負うのがユニアデックスの「ICT LCMサービス」だ。
これはクライアントPC、部門サーバー、ネットワークの3つを「ワンストップ」「リモート」「月額料金」で行うサービスで、「計画」「調達」「導入」「運用」「撤去」の5つのフェイズでライフサイクルを管理する。ユニアデックスの森下氏は、「システムの導入・構築は1年程度だが、運用は約10年間。運用設計を先に考えて、システム構築をしないと運用費用が2倍〜3倍、あるいは5倍ぐらいも違ってくる。ユニアデックスでは運用設計をしてから、システム設計、ハードウェア選定、システム構成することが重要と考えており、運用の分野に知恵・スキル・ノウハウを凝縮している」と説明する。
「クライアントPC LCMサービス」の基本メニューは、「障害受付」「資産・構成管理」「ポータルサイト」となる。リモートで自動収集したインベントリ情報を利用企業は専用のポータルサイトで閲覧できる。「サーバー LCMサービス」ではこれに「運用代行」「リモート監視」「運用テスト移行」が加わる。「ネットワーク LCMサービス」も同様に、顧客オフィスですでに稼働しているネットワークの管理だけを移管する「運用テスト移行」が基本メニューに含まれる。また、サーバー LCMサービスとネットワーク LCMサービスのメニューを再配置して「サーバー/ネットワーク LCMサービス」、そして3つをともに運用支援する「オフィス総合LCMサービス」もある。
森下氏は、LCMサービスには3つの効果があるとする。1番目はサービスの標準化、ICT機器の標準化の促進。全国に拠点展開する企業でも均一の品質でICTサービスが受けられ、IT統制にも効果があるという。
2番目はシステムによる管理によるコスト削減。システム化によってサービス品質の均一化を図るとともに、各種の自動化によってコストダウンを実現しているという。サービス提供の方法はハイブリッド型になっており、「オンサイト」「リモート」「レディメイド」「カスタムメイド」といった形を顧客ニーズに合わせてサービス提供する。
3番目は、料金モデルで「月額定額制」の採用による財務面の効果だ。ソフトウェア/ハードウェアの導入、キッティング、廃棄、機器の入れ替え(レンタル)が定額制の中で行える。必要以上に購入していた機器がある場合でも、適正範囲で使用したい数量、期間での設定が可能になっている。従来型の購入やリースの場合、導入のための初期費用が大きく掛かった後、運用段階では一度コストが下がるが、運用管理費は利用期間を経るとともに負担が上昇する。対して、「LCMサービス」のレンタル(賃貸契約)型では運用管理コストは平準化され、その中での機器の更新が可能になる。
同サービスのコスト削減は、LCMサービスでは運用委託開始の段階でのコスト削減だけではなく、運用管理の自動化、適用範囲の拡大、継続利用によって運用がこなれてきた段階でのLCMサービス自体のスリム化などを通じて、約2割のコストダウンが実現できているという。森下氏はこの実績を踏まえて「今年度は運用費用の3割削減を目指して、日夜努力している」と述べた。
続けて森下氏は、LCMの新サービスを紹介した。まず、「LCM/Liteバージョン」。これは使用PC台数100〜500台程度の企業を想定したサービスで、基本サービスをクライアントPCの「資産構成管理」と「障害対応」に絞り、安価・簡便にLCMサービスを導入できるように図ったものだ。
「みどりLCM」と「みどりICT」はグリーンITを実現するサービス。前者はクライアントPCの消費電力量の可視化、そのCO2換算、さらに電源管理ポリシーの策定とポリシー違反のPCのリモートコントロールを実施する。後者は、サーバーやネットワーク機器の集約化・仮想化などによって、温室効果ガスの削減を図る。
ほかにシンクライアントを使う「シンクライアント LCMサービス」、中堅企業向けに安価・簡便にネットワークを提供する「おまかせ」、ITアウトソーシングにこれから取り組む企業に対して現状調査とアウトソーシング方法の提言を行う「ICT運用アセスメントサービス」を紹介した。
最後に森下氏は、「ユニアデックスは50年の運用保守の歴史を持ち、ベンダーフリーの立場である点が強み。運用管理ツールの自社開発などを含め、お客さまのニーズに応じたさまざまなサービススキームが用意できる」と訴えた。
|
さらに詳しい資料を、TechTargetジャパンでご覧いただけます。 ICTライフサイクルマネジメントサービス 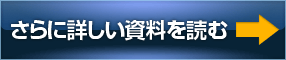 |
提供:日本アイ・ビー・エム株式会社
日本CA株式会社
NetIQ株式会社
ユニアデックス株式会社
日本コンピュウェア株式会社
企画:アイティメディア 営業企画
制作:@IT情報マネジメント編集部
掲載内容有効期限:2009年08月14日
 セミナーレポート インデックス セミナーレポート インデックス |
|
セッション1 |
ITサービスマネジメントの中核、ITポートフォリオ管理の考え方を整理する ――日本アイ・ビー・エム |
セッション2 |
潜在価値を引き出してスリムなITを 〜CAサービスマネジメント・ソリューション ――日本CA |
| セッション3 | 運用管理の超効率化 〜NetIQの次世代運用管理ツール ――NetIQ |
| セッション4 | 安全、コスト、お任せください! ICT機器は「所有」から「利用」の時代へ! ――ユニアデックス |
 ホワイトペーパー ホワイトペーパー |
| |
| |
| |
|
 スポンサー スポンサー |
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
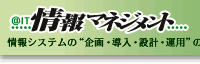
 潜在価値を引き出してスリムなITを 〜CA Service Management Solutions〜
潜在価値を引き出してスリムなITを 〜CA Service Management Solutions〜



