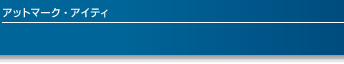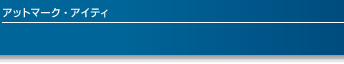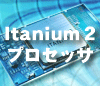 |
|
インテル(R) Itanium(R) 2プロセッサの現在、そして未来
ムーアの法則の2倍で性能向上を続けるItanium(R)プロセッサ・ファミリ |
インテルが初代Itaniumプロセッサを出荷してから丸3年が経過した。Itaniumプロセッサ・ファミリは、Intel(R) Xeon(TM)プロセッサやPentium(R) 4プロセッサなどの32bitアーキテクチャ(IA-32)ではなく、まったく新しい64bitアーキテクチャであるEPIC(明示的並列命令コンピューティング技術)を採用している。EPICとは、従来のプロセッサのように同時に実行できる命令を実行時に動的に判断するのではなく、あらかじめコンパイル時に、並列に実行できる命令を解析して、明示的にプログラム中に記述しておき、実行時にはそれらの命令をすべて同時に実行する、という技術である。このようにアーキテクチャが変更されたことで、ソフトウェアを含めたプラットフォームの整備に時間がかかったが、ここにきて本格的な普及期を迎えつつある。
Itaniumプロセッサ・ファミリ自身もItanium 2プロセッサとしての2代目に生まれ変わり、すでにデル、日本IBM、NEC、日本ヒューレット・パッカード、日立製作所、富士通、ユニシスを始めとするほとんどのサーバ・ベンダに採用されるまでに至っている。ソフトウェア・サポートの点でも、HP-UX*、Linux*、Windows* Server 2003といった幅広いサーバOSのサポート、SQL* Server 2000 64-bit EditionやOracle*9iに代表されるデータベース、さらにはSAPのようなERPパッケージまで、バックエンド・サーバを運用するのに必要なエコシステムが整ってきた。また最近では、日本BEAのWebLogicなどのアプリケーション・サーバ製品でもItaniumプロセッサ・ファミリへの対応が進んでいる。
性能面でも、世界のスーパー・コンピュータの性能ランキングを発表している「TOP500.org」に、いくつものシステムがラインクインするなど、Itanium
2プロセッサの優位性が目立ち始めている。
プラットフォームの整備が進むにつれて、徐々に企業システムを64bit環境へ移行させようという先進的なユーザも現れつつある。富士写真フイルムは、バックエンド・サーバとアプリケーション・サーバに8ウェイ×1ならびに4ウェイ×4構成を1台に集約したItanium 2プロセッサ搭載サーバ(NEC Express* 5800シリーズ) を採用し、64bit対応版Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition上で64bit対応版のSQL Server 2000とSAPビジネス・インフォメーション・ウェアハウス(SAP BW)を運用している。
また、F1のレーシング・カーの空力設計にも用いられるなど、その応用範囲は広がりつつある。このように実績という面でも、Itaniumプロセッサ搭載サーバは安心して導入が可能なシステムになっている。
コラム
Itaniumプロセッサ・ファミリとIA-32アーキテクチャの64bit拡張技術 |
|
IntelはIA-32プロセッサに64bit拡張メモリ技術を採用すると発表した。しかし、64bit拡張メモリ技術が加わったとしてもIntel Xeonプロセッサの性能向上がムーアの法則を大きく超えることはない。アドレス空間の拡張は、大規模アプリケーションの性能を高めるというより、アプリケーションが大規模化した場合の性能低下を防止する、という性格に近いからだ。もちろん追加されたレジスタなど性能強化につながる要素がまったくないわけではないが、64bit拡張メモリ技術の有無にかかわらず、Itaniumプロセッサ・ファミリの性能向上率がIntel Xeonプロセッサの約2倍になる、という予測をインテルは変えていない。
また、本文でも述べたように、信頼性という点に関してItaniumプロセッサ・ファミリとIntel Xeonプロセッサには大きな差がある。現行のIntel Xeonプロセッサを用いたクラスタリング・システムが、すべてのメインフレームとItanium 2プロセッサ搭載サーバを置き換えられないのと同様、64bit拡張が施されたからといってIntel XeonプロセッサがItanium 2プロセッサを置き換えることはない。両者は補完し共存する、というのがインテルの考え方である。
|
| |
インテル(R) Itanium(R)プロセッサ・ファミリの約束された未来 |
Itanium 2プロセッサ搭載サーバの普及に時間がかかっているのは、まず冒頭でも述べたように新しいアーキテクチャを採用したことによる。新しいアーキテクチャはそれだけ制約が少なく、今後の性能向上幅が大きく見込まれる半面、ハードウェア、OS、開発環境、ミドルウェア、アプリケーションとプラットフォーム整備を順番に積み上げていかねばならない。加えて、Itaniumプロセッサ・ファミリがターゲットとする大規模ミッションクリティカル・サーバの分野は、当然ながら高い信頼性が要求されるため、導入前の検証にも時間がかかる。助走期間として3年を要したのも無理もないというところだろう。
こうして導入されたシステムは実際に稼働した後も、そのプラットフォームのサポートが突然打ち切られたりしてはならないし、将来のシステム拡張やリプレースも円滑に行われなくてはならない。将来にわたって継続性と発展性のあるプラットフォームでなければ、企業の未来を任せることなどできないからだ。長い歴史を持つIA-32プロセッサについては1〜2世代先のロードマップの公開にとどめているインテルが、Itaniumプロセッサ・ファミリに関しては常に2〜3世代先までロードマップを公開しているのも、Itaniumプロセッサ・ファミリの継続性を保証する意味がこめられていると思われる。
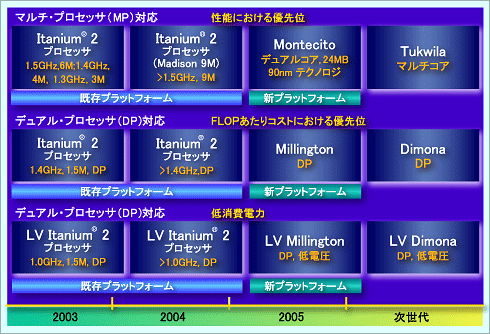 |
| Itanium(R)プロセッサ・ファミリのロードマップ |
| インテルは、長期間にわたるItaniumプロセッサのロードマップを常に示している。 |
このロードマップでも明らかなように、現在Itaniumプロセッサは、「4ウェイ以上のサーバ向け」「2ウェイのサーバ向け」「低電圧化を図った高密度2ウェイのサーバ向け」の3シリーズで構成されている。4ウェイ以上のサーバとして、64ウェイや128ウェイといった極めて大規模なSMP構成をサポートする一方で、2ウェイ・サーバのクラスタリングによる並列機構成も可能としている。Itaniumプロセッサ搭載サーバというと、基幹業務系のバックエンド・サーバというイメージがあるが、このように用途に合わせた幅広い構成が実現可能なのである。
2005年に導入される予定の「Montecito(開発コード名:モンテシト)」では、動作クロックの引き上げと3次キャッシュの大容量化のみならず、1つのダイに2つのプロセッサ・コアを集積するデュアルコア化と、1つのコアで同時に複数のスレッド処理を可能にするマルチスレッド対応(現在IA-32プロセッサに採用されているHyper-Threading技術と同じコンセプト)が図られることになっており、処理性能は飛躍的に向上する見込みだ。その次の世代の「Tukwila(開発コード名:タクウィラ)」では、さらの多くのプロセッサ・コアが1つのダイに集積される。
こうした性能向上技術の一部、例えばデュアルコア化などは、IA-32プロセッサにも採用され、その性能を高めることは間違いない。しかし、性能向上の比率という点に関してインテルは、IA-32プロセッサがムーアの法則*1に沿った形になるのに対し、Itaniumプロセッサ・ファミリの性能向上はその2倍を予測している。この比較は、IA-32プロセッサ、Itaniumプロセッサ・ファミリともに、デュアルコア化のような性能強化技術が導入されることを踏まえたものであり、現在のIA-32プロセッサと比較したものではない。IA-32プロセッサが採用するスーパースカラ技術は、登場からすでに10年近い歳月を経ており、性能強化のために打つべき手が徐々になくなりつつある(さらにその基盤となるRISC技術はすでに15年近い歴史を持つ)。それに対してItaniumプロセッサ・ファミリが採用するEPIC技術は製品化からまだ3年で、これからさまざまな強化を図っていく段階にある。IA-32プロセッサとItaniumプロセッサ・ファミリで、性能に対する伸びしろ(余裕)が違うのもある意味当然のことといえる。
|
*1 ムーアの法則:18カ月で半導体の集積度が2倍になる、ということから転じて、しばしば18カ月で性能が2倍になるとも読み替えられる。これは半導体の集積度の向上が性能向上に振り向けられることにも起因する。 |
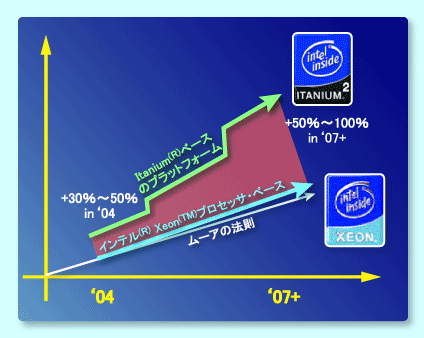 |
| Intel XeonプロセッサとItaniumプロセッサの性能向上の差 |
| Intel Xeonプロセッサ・ベース(IA-32)のプラットフォームは、ほぼムーアの法則に沿った性能向上を実現する。それに対し、Itaniumプロセッサ・ファミリは、そのほぼ2倍の性能向上を実現することから、2007年になるとIntel Xeonプロセッサの約2倍の性能となる。 |
| |
メインフレーム級の高い信頼性を実現するインテル(R) Itanium(R)プロセッサ |
大規模サーバにとって性能以上に重要なのは信頼性だ。IA-32に基づくサーバ向けプロセッサであるIntel(R) Xeon(TM)プロセッサとそのプラットフォームは、デスクトップPC向けのPentium 4プロセッサに比べれば、信頼性の点に大きな比重が置かれている。それでも、デスクトップPC向けのプロセッサからスタートしたIntel Xeonプロセッサと、最初からメインフレーム級の信頼性を前提に開発したItanium 2プロセッサでは、信頼性における到達点にはどうしても差が出る。加えてMontecitoでは、3次キャッシュのハードウェア・エラーを自動チェックし、障害が発見された場合は問題のあるキャッシュ・ラインを切り離すという、キャッシュの信頼性を高めるPellstonテクノロジ(開発コード名:ペルストン・テクノロジ)が採用されるなど、さらに信頼性を向上させるための努力が続く。
| |
Itanium 2プロセッサ |
Intel Xeonプロセッサ |
Sun UltraSparc* |
| Error recovery on data bus (ECC) |
○
|
|
○
|
| Internal soft error logic check |
2005年対応予定
|
|
|
| Lockstep support |
○
|
○
|
|
| Bad data containment |
○
|
|
|
| Cache Reliability (Pellston) |
2005年対応予定
|
|
|
| Memory SDEC, retry on double-bit |
○
|
○
|
○
|
| Memory spares |
○
|
○
|
○
|
| Partitioning |
○(ノード)
|
○(ノード)
|
○(ノード)
|
| Electrical isolated partitions |
○(ノード)
|
○(ノード)
|
○(ノード)
|
| サーバ・アーキテクチャの信頼性比較 |
クラスタリング技術の進歩による大規模並列機により、IA-32ベースのシステムでも高いピーク性能を得られるようになりつつある(大規模並列機で所定の性能を得ることは決して容易ではないが)。しかし、1つ1つのパーツ・レベルからの信頼性の積み重ねに裏付けされたシステム全体としての信頼性という点で、ItaniumプロセッサとIA-32プロセッサは同列に比較できるものではない。現在稼働しているメインフレームを、すべてIntel Xeonプロセッサによるクラスタリングで置き換えることが果たして可能なのか。恐らく100%イエスとはいえない。それをイエスに変えるためのプラットフォームがItanium 2プロセッサなのである。
このように高い信頼性を持つItaniumプロセッサ・ファミリ搭載システムは、Intel Xeonプロセッサなどと比べると、どうしても価格が高くなる。それは現時点で否定できない事実だろう。しかし、Intelは2007年をめどにIntel Xeonプロセッサ・ベースのサーバと、Itaniumプロセッサ・ファミリベースのサーバのプラットフォームを共通化すると同時に、プラットフォームの価格を同じにする方向で現在開発を進めている。だからといって、単純なプリント・サーバやファイル・サーバの分野にまでItaniumプロセッサ・ファミリサーバが採用されるとは考えられないが、いまよりもItaniumプロセッサ・ファミリサーバがカバーする範囲は広がることだろう。
コラム
IA-32 ELによる32bitアプリケーションの性能向上の可能性 |
|
Itaniumプロセッサ・ファミリが採用するEPICアーキテクチャは、インテルの代名詞でもあるx86命令との互換性を持たない。だが、サーバであってもすべてのアプリケーションが64bit化されているとは限らないし、中には64bit化する必要のないものも存在する。そうしたアプリケーションを実行するために、Itaniumプロセッサにはx86命令互換のハードウェア(x86実行エンジン)を備えることにした。これは最新のItanium 2プロセッサにおいても同様だ。
しかし2003年末、インテルはIA-32エクゼキューション・レイヤ(IA-32 EL)と呼ばれるソフトウェアをOSベンダ向けにリリース、OSベンダより順次提供されることになった。IA-32 ELは、64bit OS中からx86命令(IA-32)互換の32bitアプリケーションを実行可能という点でx86実行エンジンと同様だ。だがソフトウェアで実装されることで、x86命令の拡張に柔軟に対応可能となる。例えば、Itanium 2プロセッサのIA-32互換ハードウェアが対応するx86の拡張命令はストリーミングSIMD拡張命令(SSE)までだが、ソフトウェアなら既存のプロセッサに対しても、容易に命令セットの追加を行うことが可能だ。
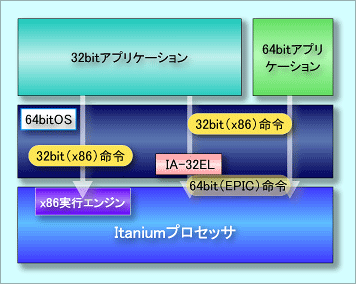 |
|
IA-32 ELの概念 |
| IA-32 ELでは、32bitアプリケーションを64bit命令にソフトウェアにより変換することで、直接Itaniumプロセッサ・ファミリで実行することを可能にする。これにより、IA-32の拡張命令に対する互換性を高めることが可能であるという。理屈の上では、IA-32の64bit拡張技術に対する対応も可能だ。 |
x86命令互換機能がソフトウェア化されることでもう1つ期待されるのは、x86命令互換機能の性能向上だ。IA-32 ELがItaniumプロセッサ・ファミリで実行されるソフトウェアである以上、Itaniumプロセッサ・ファミリが高速化すれば、当然ながらIA-32 ELもその恩恵を直接受ける。特にItaniumプロセッサ・ファミリがIA-32プロセッサの2倍の割合で性能向上するとしていることから、将来的にはItaniumプロセッサ・ファミリとIA-32プロセッサのx86命令の実行性能が拮抗する時代も来るはずだ。
現在、64bit版Windows Server 2003用のIA-32 ELは、マイクロソフトのホームページからダウンロード可能となっている。
|
| インテル、Intelロゴ、Itanium、Xeonは、アメリカ合衆国及び、その他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。その他、広告に記載の会社名は各社の商標または登録商標です。 |
|
* Windowsは、米国Microsoft Corporationおよびその他の国における商標または登録商標です。 |
|