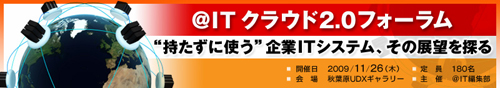
11月26日に、東京都内で@IT編集部の主催による「@ITクラウド2.0フォーラム」が開催された。基調講演では、NTTデータ 技術開発本部 SIアーキテクチャ開発センタ部長の村上明彦氏が、クラウドサービスとは何か、クラウドサービスのあるべき姿とは何かについて語った。
以下では、その後に行われたセッションのなかから、一部の内容を抜粋してお伝えする。
| イベントレポート インデックス | |
|
|
クラウドの時代には、それにふさわしいストレージを ‐ アイシロン・システムズ |
|
|
企業が安心して使えるクラウドサービスのあり方とは ‐ ITコア |
|
|
企業のITインフラは、仮想化するだけでは十分ではない ‐ プラットフォームコンピューティング |
| アイシロン・システムズ クラウドの時代には、スケールアウトNASが必須 |
アイシロン・システムズの営業本部長兼マーケティング本部長である関根悟氏は、ストレージベンダの観点から、クラウドサービスについて語った。
関根氏は、多くのクラウドサービスが立ち上がりつつあるが、クラウドに適したストレージを活用しているケースは少ないと指摘。利用者が使うことに集中できるような環境を提供するには、スケールアウト型のストレージが必要と訴えた。
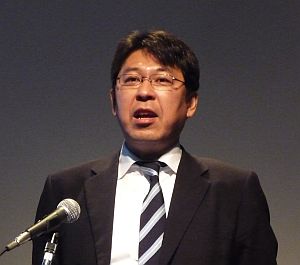 |
アイシロン・システムズ 営業本部長 兼 マーケティング本部長 関根 悟 氏 |
ストレージの世界では、データの急増にどう対応するかが目下の最重要課題になっている。これに伴い、ブロックベースよりもファイルベースのストレージへと注目が集まるようになってきた、と関根氏は話した。クラウドサービスのストレージでも、どのように効率よく拡張性を確保するかが大きな課題だ。これを解決するにはNASが適していると関根氏は話した。
ただし、ファイルベースのストレージ、つまりNASを使いさえすれば問題が解決するというわけではない。コンピュータではメインフレームからIAブレードサーバへの移行が起こった。ストレージでもニーズの拡大に、ローエンドからミッドレンジ、ハイエンドへとストレージをスケールアップして対処していくのではなく、ストレージを追加してスケールアウトしていくことで対処できなければならないと関根氏はいう。これまでのNASは少数のコントローラ(NASヘッドとも呼ばれる)にハードディスクドライブを追加することでしか拡張ができない。すると、ある程度まで容量は追加できたとしても、少数のコントローラにI/Oが集中してしまい、この部分がボトルネックとなってデータの渋滞が発生し、パフォーマンスが向上しない。
必要なのは、スケールアウトNASだと関根氏は話す。アイシロンのIsilon IQシリーズに代表されるスケールアウトNASは、コントローラとハードディスクドライブを一体化したノードを追加していくことで、オンラインのまま容量とパフォーマンスを同時に拡張していくことができる。ポイントは、これらの複数のノードが別々のものではなく、あたかも単一のストレージシステムであるかのように管理し、利用することができるという点にある。実際にIsilon IQシリーズでは、複数のノードで1つのファイルシステム、1つのボリュームを構成し、利用することが可能だ。従来のように、いちいちアプリケーションごとにLUNを設定して、個別の管理を行う必要はない。サーバファーム全体のために単一のボリュームをつくり、これに例えば仮想マシンのデータを保存していけばいい。こうすることでディスクスペース利用の無駄を省くことができるし、各アプリケーションのためのストレージ容量拡張も、LUN拡張などの面倒な作業をせずに行うことができる。
Isilon IQはデータ保護の点でも有利だ。従来型のブロックストレージで複数LUNを構成する最大の理由は、アプリケーションごとにRAIDレベルを制御したいからだ。Isilon IQシリーズは、1つのファイルを保護レベルに応じて生成したパリティと合わせ、各ノードに分散配置させることでRAIDを凌駕する高いデータ保護を実現した。クラスタ、ディレクトリ、サブディレクトリ、ファイル別に保護レベルをオンラインで設定・変更することができる。データ保護はRAIDを使わず、データ単位でN+1〜4パリティや2〜8面ミラーが可能だ。従来は、データ保護レベルを変えるだけで、サービスの停止と膨大な変更に伴うコストがかかっていたが、アイシロンスケールアウトNASは、管理作業およびコストを大幅に減らしている。
関根氏は、こうした俊敏性がこれからの時代には最も重要で、それを提供できるのは現時点ではアイシロンしかいないと訴えた。Isilon IQではWebベースの管理ツールで、システム全体を一括管理できる。導入作業も拡張も、瞬時に終えることができる。管理負荷の低いスケールアウトNAS は、クラウドサービスになくてはならない要素だとしている。
|
さらに詳しい資料を、TechTargetジャパンでご覧いただけます。 クラウドサービスを支える仮想ストレージ 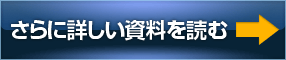 |
| ITコア 企業が安心して使えるクラウドサービスのあり方とは |
ITコアのITコア東京・準備室長である飯塚雅也氏は、同社が11月1日に提供開始した日本版仮想化クラウドサービス「GrowServer2010」(GS10)を紹介した。
ITコアはエンタープライズ向けのメール配信サービスやGoogle Appsへの安全なアクセスを実現するゲートウェイサービス、Webインテグレーションサービス、そしてVMwareを用いた仮想化ホスティングサービス(IaaS)を5年前から展開してきた。
その同社が仮想化ホスティングの新バージョンとして提供開始したのがGS10だ。
飯塚氏は、「今回のサービスは5年前に比べると、10分の1の価格になった」と話した。その価格とは、CPU 1コア、メモリ1GB、ディスク領域実効30GBで月額1万円だ。実効30GBというのは、ディスクを3重化しているから。物理的にはそれぞれの仮想サーバが90GBを使う計算になる。インターネット回線、ファイアウォール/負荷分散、24時間監視、復旧作業も無償であり、この利用料に含まれている。標準のディスク容量で足りない場合は、月額1万円のオプションで実効100GBを追加することができる。
IT コアはこの低価格を、さまざまな最新技術や運用の効率化などによって実現した。サーバ仮想化技術にはVMware vSphere 4を採用。Distributed Resource Scheduler(DRS)機能によって、仮想サーバの負荷を自動的に分散することができる。従って、利用する側も、同一の物理サーバ上に処理負荷の大きい仮想サーバが同居することによる悪影響を心配しなくていい。ストレージも「SANsymphony」により仮想化しており、筐体間ミラーや1日に1回のスナップショット実現している。さらに今回のGS10では、シーゴシステムズの「I/O仮想化コントローラ VP780」を新たに採用し、I/Oの高速化と自在な分割・制御を実現した。このように利用している技術を公開することも、ITコアの仮想化ホスティングサービスの特徴だ。サーバは、発注後最短2営業日で利用開始することができる。
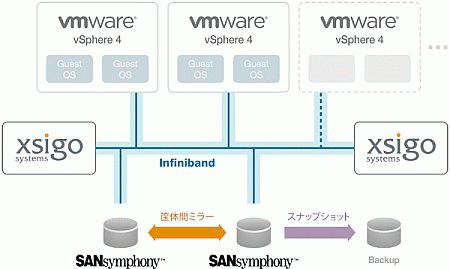 |
| ITコアのGrowServer2010は、サーバ、ストレージ、ネットワークと全層にわたって最新の仮想化技術を導入し、運用効率化を図っている |
GS10 では、柔軟にネットワークを構成できることも大きな特徴となっている。例えばWebサーバ(の仮想マシン)はインターネットに接続するが、その背後にあるデータベースサーバ(の仮想マシン)はインターネットに露出せず、Webサーバとプライベートネットワーク経由で接続することができる。
GS10 では、東京・飯田橋にあるビットアイルの第4データセンターを使用する。耐荷重1トン・実効6kVAの大容量ファシリティを生かし、機器の集積率を大幅に向上させた。ITコアは、1年後に1000ユーザー、3000台の売り上げを目標にしているが、出足は好調と飯塚氏は語った。
| プラットフォームコンピューティング 企業のITインフラは、仮想化するだけでは十分ではない |
プラットフォームコンピューティングは、これまで主にHPC(ハイパフォーマンスコンピューティング)でアプリケーションの並列処理を実現し、あるいはグリッド・ワークロードの自律的な運用最適化を実現するミドルウェアを提供してきた。同社は12月初め、プライベートクラウド環境を構築・運用するためのソフトウェアプラットフォーム「Platform ISF」の国内出荷開始を発表した。
Platfrom ISFは、企業の社内システム部門、あるいは企業の社内ITインフラの運用代行を行う事業者に向けた製品だ。クラウドコンピューティングはエンタープライズコンピューティングにおける重要なキーワードとなってきた。しかし、多くの企業は、クラウド的な世界の実現に向け、仮想化環境の構築を進めているものの、仮想化を実現するだけでは十分ではないことにも気がつき始めている。サーバ仮想化環境の運用を自動で最適化してくれる技術が求められるとともに、ユーザーが即座にかつ自在に仮想サーバ環境をプロビジョニングできる仕組みも求められるようになってきた。既存の環境との統合的な管理も欠かせない。こうした課題を解決するのが同製品の役割である。
Platform ISFは、図のように「リソース一元管理」「リソース最適化エンジン」「サービスデリバリ」の3つの層にわたる運用環境だ。
 |
| Platform ISFは、「リソース一元管理」「リソース最適化エンジン」「サービスデリバリ」の3つの層で構成されている |
リソース一元管理のレイヤでは、VMware vSphere、Citrix XenServer、Red Hat KVM/Xen、Microsoft Hyper-Vと、主要なサーバ仮想化技術のすべてに対応し、API経由でこれらの仮想化環境の管理ツールを制御することができる。さらにシステム管理/プロビジョニングツールについてもAPI経由で制御することができる。すなわちPlatform ISFに備わっているWebベースの管理コンソールから、物理/仮想環境を一括して管理できる。サーバや仮想マシンの稼働状況をモニタリングしつつ、ユーザーへ提供するアプリケーション定義(ソフトウェアとOSをパッケージ化したもの)のイメージを管理し、適切なサーバに投入する。
リソース最適化エンジンでは、事前に定めたポリシーによって、アプリケーション定義を最適なサーバ機に配置することが可能。アプリケーション自身の要件や、各ユーザーグループに適用するルール、特定の曜日・時間などに基づいて、サーバリソースを自動的に割り当てられる。このポリシーでは、例えば、重要なワークロードに対しHA構成がとれるリソース割り当てを行う、新規のワークロードに最も負荷の低い、あるいは最も消費電力の低い物理サーバを割り当てる、などを設定できる。
サービスデリバリでは、アプリケーション定義の生成から運用開始、停止、削除までのワークフローを設定し、制御できる。Platform ISFの管理権限は、クラウド管理者、アプリケーション管理者、アプリケーションユーザーといった立場に応じてきめ細かく制御できる。このレイヤにおける Platform ISFの重要な特徴は、セルフサービスポータルの提供にある。これを通じ、管理者は提供するサービスを定義し、ユーザーはこのなかから選択して仮想マシンやアプリケーションをあたかもオンラインショッピングのように「購入」し、自ら投入できる。管理者はユーザーに対して、従量制の課金体系を適用することが可能だ。このために、Platform ISFでは課金対象のリソース利用データを保持している。
欧米では、すでに先駆的なユーザーの間で、Platform ISFが利用され始めている。例えば北米のある大手金融グループでは、これまで一部アプリケーションで利用されてきたグリッド運用環境を拡張し、クラウド環境に進化させた。これによって、コスト削減とパフォーマンス改善を両立させた。同社では、サーバ機の稼働率が20%から80%に改善したと報告している。
|
さらに詳しい資料を、TechTargetジャパンでご覧いただけます。 クラウドは買うのではなく、作るもの!「エンタープライズクラウド」によるITの変革 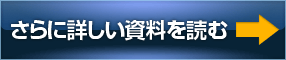 |
提供:アイシロン・システムズ株式会社
ITコア株式会社
プラットフォームコンピューティング株式会社
アイティメディア営業企画
制作:@IT 編集部
掲載内容有効期限:2010年1月31日
イベントレポート
インデックス |
|
| クラウドの時代には、それにふさわしいストレージを ‐ アイシロン・システムズ |
|
| 企業が安心して使えるクラウドサービスのあり方とは ‐ ITコア |
|
|
企業のITインフラは、仮想化するだけでは十分でない ‐ プラットフォームコンピューティング |
|
ホワイトペーパー ダウンロード |
|
|
|
|
スポンサー |
|
|
|
|
|
|

 クラウドサービスを支える仮想ストレージ
クラウドサービスを支える仮想ストレージ

