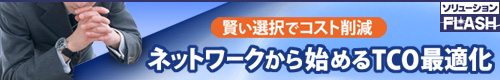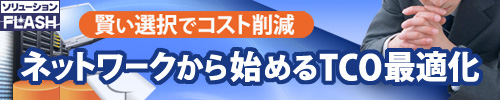
サーバが統合された後のWANのことまで考えていますか? WAN最適化アプライアンス「WXC」が サーバ統合を成功させる理由 |
| サーバ統合によって得られるメリットとして、人件費を含む総所有コストの削減やシステム全体の信頼性向上、セキュリティレベルの確保が挙げられる。しかし、WANを流れるデータ容量の増加によって業務効率が低下してしまう可能性も潜んでいる。ジュニパーネットワークスのWAN最適化アプライアンス「WXC」シリーズで、この落とし穴を回避しよう。 |
| 加速するサーバ統合の動きとその課題 | ||
1990年代以降、企業の業務システムは分散化の傾向にあった。高速なネットワーク網は高価であり、サーバを拠点単位で分散配置することで信頼性が向上すると考えられていたからである。
ところが、この2、3年の間にトレンドはサーバ統合へと変わった。ハードウェアやソフトウェアの高性能化や仮想化技術の登場に加え、高速で大容量なネットワークのコストが下がった結果、企業が取り組むべき指針は人件費を含む運用コストの削減へと振れたのである。
サーバ統合によって得られるメリットは、総所有コスト(TCO)の削減だけにとどまらない。基幹となるサーバを冗長化し一元管理することで、むしろ“止まらない”ITシステムが実現できるようになる。データのバックアップも容易となる。また、拠点ごとにばらつきが生じてしまうセキュリティの確保もしやすい。
こうしてITリソースの最適な再構築を目指すサーバ統合だが、課題も残されている。WAN側の最適化については、十分な回線帯域の確保のみを重視するあまり、WAN経由での通信を得意としていないプロトコルの存在を無視してしまいがちなことだ。
例えば、Windowsファイル共有で使われるプロトコル(CIFS)やWebへのアクセス(HTTP)は、プロトコルの仕様上、細かいやり取りが多く、広帯域な回線であってもレスポンスが低下しやすい。従って、いままで同一拠点内で完結していた通信がWAN経由で行われるようになると、アプリケーションの反応速度が低下し、データ転送にかかる時間が大幅に増加してしまう。
このような状況に対して、利用者がストレスを感じてしまったり、情報システム部門へのクレームが増えたりすることが容易に想定され、サーバ統合後に、システムやWAN回線帯域の見直しなど、さらなる対策を迫られるケースも散見される。
このようなサーバ統合のデメリットを補完する製品が、ジュニパーネットワークスのWAN最適化アプライアンス「WXC」シリーズである。WXCを導入することによって、データ転送にかかる時間がサーバ統合前とほとんど変わらないものにできるという。その理由を探っていこう。
| WXCがWANの遅延原因を徹底的に取り除く | ||
WXCは、WANアクセラレータに分類されるアプライアンス製品である。WAN上で発生する遅延の原因を探り、回線が持つパフォーマンスを適切に使い切るために、回線を流れる「データの圧縮」、TCPプロトコルやCIFSなどアプリケーションが利用するプロトコルの「高速化」、VoIPやテレビ会議のような遅延を極力避けたい重要アプリケーションの「優先制御(QoS)」、ネットワーク上を流れる通信の「見える化」を同一筐体上で実現している。導入構成として、インライン、オフパスの両方式での導入が可能だ。
WXCでは、独自に開発したDNAパターンマッチング方式によるデータ圧縮(特許取得済み)によって、一般的な圧縮技術よりも効率の良いデータ容量の削減が可能となった。対象となるのは、UDPも含めたすべてのIPトラフィックである。ダイナミックにデータの繰り返しパターンを学習し、すでに圧縮済みのファイルであってもさらにデータ容量を削減することができる。
WXCでは、TCPベースのアプリケーションの高速化だけでなく、一般的な業務アプリケーションで利用されるプロトコルにも個別に対応したアプリケーション高速化機能を搭載している。ある企業では、サーバ統合後にファイルサーバへのアップロード/ダウンロードが遅くなってしまった。回線を増速してみたものの、転送時間に改善は見られなかった。そこでWXCを導入したところ、東京−福岡間で5MBのファイル転送にかかっていた時間が3分から10秒へと短縮されたという。

なお、利用するアプリケーションによっては、QoSを確保することが重要なものがある。例えば、VoIPやテレビ会議といった通信がこれにあたる。このような重要通信には、柔軟に帯域を割り当てることが可能だ。
また、利用中のWAN回線の中をどのような通信が流れているのかを把握するためのレポート機能も充実している。例えば、帯域使用率、利用アプリケーション上位10件、圧縮率などを個別に確認でき、導入後のパフォーマンス確認も随時行うことが可能だ。
| WXCによるプラスの効果 | ||
 |
| WXCシリーズ(画像をクリックすると拡大します) |
WXCは、WAN最適化に必要な機能をオールインワンで実現している点以外にも、WANの実効容量を大幅に増加させる独自の圧縮機能や、OSをハードディスクではなくメモリに搭載することによって実現する高い耐障害性など、優れた特徴を多数兼ね備えている。
また、導入後にはトラフィック量の把握や重要アプリケーションの確保による通信の安定も実現可能となり、想定以上のプラス効果を得ることができる。
WXCには、対向拠点数や回線帯域に応じて最適な製品を選べるようなラインナップが展開されている。小規模な拠点には対向10拠点、最大帯域2Mbpsまでの「WXC1800」、中規模な拠点には対向50拠点、最大帯域10Mbpsまでの「WXC2600」、大規模拠点には対向140拠点、最大帯域100Mbps【注】の「WXC3400」を推奨している。
事業継続計画(BCP)などから、データセンターを東京と大阪の2カ所に構える企業も多くなってきた。東京−大阪間といえども、WAN経由でのデータの転送遅延は発生する。サーバ統合によって得られるコスト削減のメリットを最大限享受するためにも、この機会にWAN回線まわりの最適化についても一度見直してみてはどうだろうか。
|
提供:マクニカネットワークス株式会社
アイティメディア 営業企画
制作:@IT 編集部
掲載内容有効期限:2009年8月3日
ソリューションFLASH Pick UP!
WAN最適化アプライアンス「WXC」シリーズ
マクニカネットワークス
 サーバ統合によって得られるメリットとして、人件費を含む総所有コストの削減やシステム全体の信頼性向上、セキュリティレベルの確保が挙げられる。しかし、WANを流れるデータ容量の増加によって業務効率が低下してしまう可能性も潜んでいる。ジュニパーネットワークスの WAN最適化アプライアンス「WXC」シリーズで、この落とし穴を回避しよう。
サーバ統合によって得られるメリットとして、人件費を含む総所有コストの削減やシステム全体の信頼性向上、セキュリティレベルの確保が挙げられる。しかし、WANを流れるデータ容量の増加によって業務効率が低下してしまう可能性も潜んでいる。ジュニパーネットワークスの WAN最適化アプライアンス「WXC」シリーズで、この落とし穴を回避しよう。
エンタープライズ向けスイッチ「APRESIA」シリーズ
日立電線
 日立電線のエンタープライズ向けスイッチ「APRESIAシリーズ」は、「壊れにくくする」ことと「迅速な復旧」の両面で、ネットワークのTCO削減を実現する。そして同時に、シャーシ型スイッチに匹敵する性能と信頼性、拡張性を提供する。
日立電線のエンタープライズ向けスイッチ「APRESIAシリーズ」は、「壊れにくくする」ことと「迅速な復旧」の両面で、ネットワークのTCO削減を実現する。そして同時に、シャーシ型スイッチに匹敵する性能と信頼性、拡張性を提供する。
WAN最適化装置「Steelhead」
ネットマークス
 各地の拠点に散在していたサーバを統合するプランを練っている企業は少なくない。だがその際、ネットワークについても十分考慮しないと、コスト削減効果が得られるどころかかえって生産性を阻害する可能性もある。そんな事態を防いでくれるのが、リバーベッドテクノロジーの WAN最適化装置「Steelhead」だ。国内・海外ともにリバーベッド製品の豊富な導入実績を誇るネットマークスが手掛けた2つの事例を元に、その効果を見てみよう。
各地の拠点に散在していたサーバを統合するプランを練っている企業は少なくない。だがその際、ネットワークについても十分考慮しないと、コスト削減効果が得られるどころかかえって生産性を阻害する可能性もある。そんな事態を防いでくれるのが、リバーベッドテクノロジーの WAN最適化装置「Steelhead」だ。国内・海外ともにリバーベッド製品の豊富な導入実績を誇るネットマークスが手掛けた2つの事例を元に、その効果を見てみよう。
ホワイトペーパーダウンロード
コスト削減! サーバ統合+WAN最適化という最強解
サーバ統合の懸念点としては、想定していない問題により思わぬコストが発生することが挙げられる。 そこで、WAN最適化ソリューションWXCの導入により約30%の運用コスト削減を実現した例を紹介する。
1Gのコストで、10Gを。
TCO削減は、初期投資だけではない。一度導入すると5年は利用するネットワーク機器。実は運用コストが大事!! 障害発生時の回避策と壊れにくい設計ポリシー、しかも柔軟な拡張性を持った国産スイッチ。新たに「1Gのコストで、10Gを。」をキャッチコピーに新製品を投入。
事例から見る、WAN最適化アプライアンス導入の理由とは
今やファイルサーバ統合に欠かせないWAN最適化装置。ユーザ事例からその導入経緯をご紹介する。