
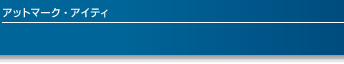
 |
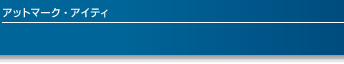 |
@IT|@IT自分戦略研究所|QA@IT|イベントカレンダー+ログ |
|
Loading
|
| @IT > SPSS Data Mining Day 2004 イベントレポート前編 |
| 企画・制作:アットマーク・アイティ
営業企画局 掲載内容有効期限:2004年6月25日 |
|
|
|
|
今年で6回目の開催となる「SPSS Data Mining Day 2004」は、会場の新高輪プリンスホテルに1500名もの参加者を集めて、中味の濃いプログラムが展開された。
今回のテーマは「戦略とデータマイニング」。SPSSは、近年その設計思想を「分析ツール」という位置付けから、「ビジネスの成功につなげるためのツール」に大きく変えてきているが、このテーマには、マーケティング部門で利用されるような戦術レベルを超え、経営層が活用できる、戦略レベルでの役割を推進するという意図が込められているようだ。
以下、各プログラム内容についてポイントを紹介していこう。
プログラムの皮切りは、SPSS米国本社の社長兼CEO、ジャック・ヌーナン(Jack Noonan)氏が登場した。30分ほどの短い講演だったが、同社の提唱する「Predictive Analytics(PA)」がビジネスにどのように貢献できるかについて、具体的な数字を挙げて説明。このため、非常に説得力のある内容だった。 ヌーナン氏によると、PAとは「いま存在するデータを分析することで将来を的確に予測し、それによって現在のビジネスのやり方を変えること」だという。つまり分析だけではなく、その結果を具体的なアクションに落とし込むことを重視しているのである。 現在、企業のデータのほとんどがデータウェアハウス内に蓄積され、データマイニングツールも充実し、コールセンターやWebサイトなどの顧客接点もIT化が進みつつある。こうした中、PAが果たす役割としてヌーナン氏は次の3点を挙げた。
すなわちデータの分析に加えて、日々の業務への展開を可能にするのがPAなのだ。 PAが重視されるようになってきた背景には、製品自体の機能・性能や価格上での差別化が困難になった点が挙げられる。そこで製品以外の部分、例えばブランドやサービス、顧客との関係性などにおける差別化を図る必要性が高まった。こうした付加価値を向上させるため、例えば過去のデータから顧客の将来のニーズを予測し、リアルタイムで適切なコミュニケーションを行うことで、顧客との関係性を強化することが有効になる。 米調査会社ガートナー・グループの調査によると、企業の関心事項として上位4番目に挙げられるほど、PAの重要性は高まっている。またIDCの調査によれば、PAへの取り組みによって、より高いROI(Return on Investment)が得られることが判明している。現段階では、実際のPAへの取り組みはまだ揺籃期にあるとのことだが、その中でも金融や通信業界は先行してPAに取り組んでいるそうだ。ヌーナン氏は、その中の1つの事例としてオランダの金融サービス企業 Spaarbeleg社を挙げた。 Spaarbeleg社は180万人の顧客を有する企業であり、代理店、ダイレクトメール、eメールなどを通じて金融商品を販売している。今回紹介したのは、コールセンターの事例だ。同社のコールセンターシステムには、データ分析に基づくモデルが組み込まれており、電話をかけてきた顧客の取引データに応じて、適切なクロスセル(現在利用している商品と関連した未購入商品)を行うよう、オペレーターに指示する画面が表示される。コールセンターには年間100万件の電話が掛かってくるそうだが、これに対し、通算18万件のクロスセルの指示が画面表示され、実際には、6万件に対して具体的な製品がオペレーターによって提案された。その結果、有力な見込客を3万人獲得し、最終的には2万2000件の製品販売につながったという。売上ベースで見ると、コールセンターだけで3000万ドルの増収をもたらしたのである。 ヌーナン氏は、この事例を通じて、「PA」が、実際にビジネスに役に立つアプローチであることを証明したといえるだろう。SPSS製品の今後のロードマップの方向性がより明確に見えてきた講演であった。
戦略論の第一人者である竹内弘高氏は、実はSPSSを利用して博士論文を書いたという。「もしSPSSがなければ、博士論文提出後、ハーバードビジネススクールの教授にはなれなかったのではないか」と考えているそうだ。以来、SPSSとは30年来の付き合いになるという。 竹内氏は、含蓄に富む戦略論を分かりやすく解説してくれた。そもそも、戦略ついての考え方には2つの視点があるという。1つは「競争戦略」の視点、もう1つは「資源ベースの戦略」である。
「競争戦略」とは、外部の状況、すなわち業界分析と企業レベルの競争を重視するものである。そして、企業レベルの競争の場合、「オペレーションの効率化」と「戦略的ポジショニング」の2つの競争手段がある。「オペレーションの効率化」とは、“Doing things better”ということ。つまり仕事の効率化や品質向上など、業務プロセス自体をより良くしていく取り組みだ。この分野に関して日本企業は、TQCや改善運動などを通じ、優れた結果を出してきた。 だがこれには落とし穴がある。すべての企業がオペレーションの効率化に取り組めば、最終的にはお互いに差がなくなってしまうのだ。つまり競争の同質化が起こる。したがって、他社を上回る継続的な利益(SSP:Superior Sustainable Profitability)を獲得できない。またITの進展によって、1980年代には優位にあった日本企業が1990年代には米国企業に逆転されたというようなことも起きてしまう。 ビジネスにおいて重要なのは、他社を上回る継続的な利益(SSP)であるが、これを獲得するために必要なのが「戦略的ポジショニング」だという。「戦略的ポジショニング」とは、“Doing different things”、すなわち「他社と違うこと」をするということである。これは「何をやらないか」を選択するということでもある。具体事例として竹内氏は、HOYA、アスクル、武田薬品工業、セブン-イレブンなどを挙げ、「こうした勝ち組企業は、明確なターゲット設定や、他社が簡単にまねできない優れた仕組みを構築し、戦略的ポジショニングが明確である」と述べた。 一方「資源ベースの戦略」とは、企業がその内部に保有している資源を基に、競争優位を築いていこうとするものである。具体的には、コア・コンピタンスと呼ばれる企業の強みやブランド力のことを指す。そして、そうした資源の1つに「知識」があると竹内氏は指摘する。 竹内氏は、いま「200年に1度の大きな変化」が起きているという。それは産業社会から知識社会への移行である。産業社会における生産手段は「機械」や「ロボット」だった。知識社会においては、すべての従業員の「HEAD」と「HAND」が生産手段となる。「HEAD」とは言語や数字、データなど目に見える知識(形式知)を意味し、「HAND」とは、言葉やデータでは表しにくい経験、五感や直感、感情、信念、価値観(暗黙知)を意味する。 企業が競争優位の源泉として新しい「知」を生み出すためには、暗黙知を形式知に変換したり、あるいはその逆に、形式知を暗黙知に変えることができなければならない。「実はデータマイニングがやろうとしていることも同じだ」と竹内氏は語る。すなわち形式知である「データ」から、分析を通じて「知見」や「洞察」といった暗黙知を生み出すこと、あるいは「直感」や「体験」「感情」「思い」といった構造化されていないものを、構造化された言語データベースに変換するのがデータマイニングなのである。 新しい「知」を生み出すためには、矛盾した状況を受け入れたり、対立を助長したり、意外性を追求することが求められるが、データマイニングによって追求するのは意外性の発見である。よくデータマイニングの事例として引き合いに出される“販売データの分析結果から、紙おむつとビールが同時に買われていた”という発見は、その典型的なものであろう。 竹内氏は最後に、「競争戦略においては『オペレーションの効率化』と『戦略的ポジショニング』が重要である。一方、資源ベースの戦略においては、これからは知識をベースとした戦略を取るべきである」という戦略のエッセンスを述べ、「この中で、データマイニングが新たな“知”を生み出す方法である」と強調して講演を締めくくった。
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||