| 今あるストレージを使いつくせ PART 2 ストレージを有効利用 するための新技術とは |
| データセンター内にあるストレージの利用率を上げるため、現状を把握してデータの最適配置を行う。これがストレージにかかるコストを減らす1つ目のポイントならば、さらにデータのライフサイクル全体にわたって戦略的に管理し、ストレージを有効利用するのが2つ目のポイントとなる。それを実現する技術として、シンプロビジョニングや重複排除、アーカイブなどがある。これらの新しいテクノロジがどのように適用され効果を上げるのか、ストレージ削減の観点から紹介する。 |
ネットワークストレージを無駄なく使う「シンプロビジョニング」 |
||
利用率を上げてストレージを有効利用するには、プロジェクト間や部署間で融通し合えるような仕組みになっている必要がある。つまり、サーバーに直接ストレージを接続するのではなく、SANなどのネットワークストレージにする必要があるわけだが、サーバーとストレージを組み合わせてシステムを構築する際、必要な量のストレージを割り当てることをプロビジョニングという。これは、無駄のないようにしつつも頻繁に追加が発生しないようにと、神経を使う作業でもある。多くの場合、ストレージの容量不足が発生して業務が滞ることの回避を優先し、余裕を持って割り当てる。これが、ストレージの利用率を下げる原因ともなっている。
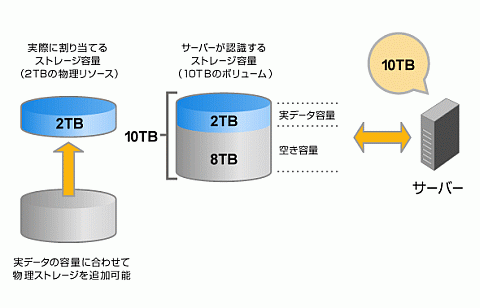 |
| シンプロビジョニングでは、例えばサーバーには10TBを割り当てたと認識させるが、実際にはそれよりも少ない容量を割り当てる |
そこで登場したのが、「シンプロビジョニング」と呼ばれるストレージ容量の仮想化技術だ。例えば、あるアプリケーションではストレージ容量は10TB必要だという場合、サーバーには10TB割り当てたと認識させ、実際の物理的なストレージ装置には、差し当たり必要な2TBだけを割り当てるのである。これにより、ストレージのプロビジョニングを行う毎に増大していく未使用領域の無駄を格段に減らすことができる。物理的な保存領域はリソースプールとして複数のシステムで共用されているので、割り当てられたストレージボリュームが足りなくなれば自動的に拡大する。結果として本当にそのストレージの容量が不足しそうになったら、ストレージを物理的に追加するのである。これにより、ストレージの追加やアップグレードの頻度を下げることができるとともに、設置スペースや消費電力、冷却コストなども抑えることが可能になり、グリーンITの観点からも有効な技術になるだろう。
ただし、無駄がまったくなくなるわけではない。このシンプロビジョニングではほとんどの場合、データの作成時に割り当てが行われ、その割り当てはファイルが削除されてもそのままになる。次のファイルが作成された時には、元データがあった領域は避けて割り当てられるのだ。つまり、ボリュームとしていったん割り当てられると、データを削除した結果空き容量となったとしても、使用領域として確保されたままになるという無駄が発生する。
この問題は、ファイルシステムの空き領域を再利用する機能に依存する。未使用領域を積極的に再利用するような機能を持ったファイルシステムを使えば、このような細かな無駄もなくなる。例えば、シマンテックが提供する「Veritas Storage Foundation」に含まれる「Veritas File System」は、シンストレージに対応し、空き領域を積極的に再利用する。つまり、ファイル作成時に確保された領域のうち、後に削除されて使われていない領域があった場合は、その部分を再利用することで不必要な領域割り当てを最小限にできる。
バックアップ用ストレージを効率的に使うだけではない「重複排除」 |
||
事業継続性の維持はビジネス上の重大な課題であり、万一の障害に備えてシステムやデータのバックアップをとっておくことは、企業の情報システムにとっては不可避だ。かつてはそのバックアップデータは、テープメディアなどに保管しておくことが多かったが、最近ではディスクへのバックアップが主流になりつつある。ディスクストレージの価格が下がったことがそれを可能にしたのだが、迅速なリストアが可能になるなど、使い勝手の面でも大きなメリットがある。
しかし通常、バックアップには少なくともその対象となるデータと同じサイズの容量を、バックアップ側に確保しておく必要がある。従って、データ量の増大はバックアップ・ストレージの必要容量が増大し、ストレージ運用管理者にとっては頭痛の種が増える結果をも招いている。
バックアップデータを削減することで、この問題を大きく解決してくれるのが「重複排除」と呼ばれる技術だ。これは文字通り、重複のないデータのみを保存することで、必要なストレージ容量を削減できる技術だ。
重複排除の技術がターゲットとするのは、同報送信メールや、営業活動用のPowerPointデータなど、ほとんど同一か、共通の部分が多いデータが複数存在している状態だ。重複排除技術では、それぞれのデータを細かなブロックに分割して相互比較し、すでに保存されているデータブロックと同一なものについては書き込まない。これにより、元データを20分の1、場合によっては100分の1まで削減することができる。
重複排除の手法として、ハードウェア製品に一般的なのが、まず全てのバックアップデータを一度ストレージに保存し、その後に重複しているデータを排除するというものだ。もう1つ、ソフトウェアベースの事前重複排除という手法があり、シマンテックの「Veritas NetBackup PureDisk」はこれを実現している。こちらはバックアップ対象のサーバーにエージェントをインストールしておくことで、あらかじめ重複しているデータを排除したうえでバックアップ用ストレージに書き込めるようになる。
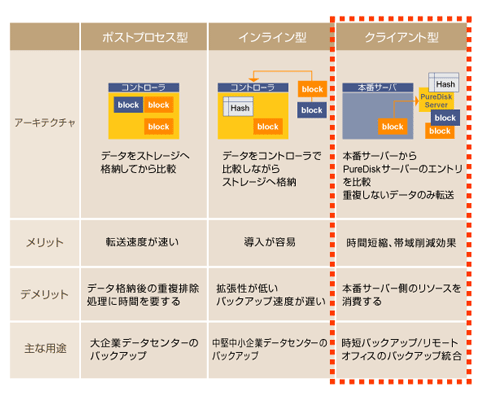 |
| 重複排除は処理を行うポイント別に、大きく3つに分類できる。ポストプロセス型やインライン型もあるが、クライアント型に大きなメリットがある |
結果としてストレージが無駄なく使われるということではどちらも同じだが、Veritas NetBackup PureDiskの場合はストレージへ転送するデータ量がそもそも少なくなっている点が注目できる。これは、転送する際のネットワーク帯域を圧迫せず、しかも短時間で終了するということを意味する。つまり、インターネット経由などの方法で遠隔地にバックアップすることも容易だということだ。この機能によって遠隔地にバックアップサイトを設置すれば、災害時の事業復旧などのためのディザスタリカバリの用途にも利用できるのである。
プライマリストレージを追加せずに「アーカイブ」 |
||
実は、ストレージが増加する最大の要因はメールだ。受発注の取り引きから社内の打ち合わせまで、重要度もさまざまなメールが毎日飛び交っている。ユーザー1人当たり1日に100通以上のメールを送受信しているともいわれ、その容量は平均17MBという調査もある。これに人数と日数をかければ、1年間に溜まるメールが膨大な容量となることは明白だ。しかも、電子メールは公的な証拠能力を持つものとして長期保存が義務付けられている場合があり、そうでない場合でもコンプライアンス上、長期保存が強く推奨されている。メールのためのストレージは高品質のものでなければならないし、容量追加の必要性、頻度ともにかなり高くなる。
また、メールには添付ファイルがついている場合も多い。このため、ファイルサーバーやSharePointサーバーのデータと同じデータが、メールの一部としてメールサーバーのストレージにも保存してあるという状態になることもある。ここにも重複データの問題が発生している。
これらの問題を解決するのがアーカイブだ。メールサーバーのデータをアーカイブ用のストレージに移行し、メールサーバーが使用するプライマリのストレージの容量を少なくするのである。
例えばシマンテックの「Enterprise Vault」では、このアーカイブの保存の際に重複排除を行える。メールでは、完全に同一か、ほとんど同一のファイルを添付して同報送信するケースが多いため、重複排除の効果は高い。また、メールだけでなく、ファイルサーバーやSharePointと複数のアプリケーションに対して包括的な重複排除が行えるため、規模が大きくなるほど効果も高くなる。
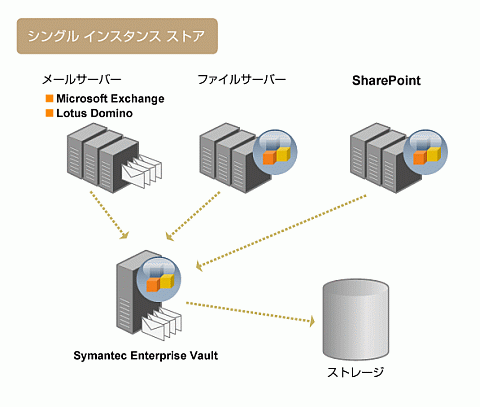 |
| アーカイブでは「シングルインスタンスストレージ」、つまりファイル単位の重複排除が行われる、ということができるかどうかがカギ |
Microsoft Exchangeでは、メールボックスが大きくなり過ぎるとパフォーマンスが低下する。また、障害発生時にバックアップデータからシステムを復元するのにも時間がかかるなど不便なことが多い。これを避けるために、サーバーのメールボックスから削除してユーザーがローカルに保存しておくという使い方もあるが、これだとメールデータ管理上の問題が生じる。例えば法的な係争となった時、証拠としてメールを提出するように求められても、メールデータが各ユーザーのPCに散在している状況では、確実な対応ができない。コンプライアンスのためには、企業として電子メールの全ての情報を保存し、検索して該当のメールを迅速に取り出せるようにしておかなくてはならない。そのためにも、アーカイブのソリューションを導入しておいたほうがよい。
以上のように、ストレージの追加・アップグレードの頻度を抑制するような工夫はいくつかある。これらのソリューションを導入してデータの最適配置を実現するストレージ管理を行うことで、データセンターでのストレージコスト削減に貢献できるだろう。そして、この機会にストレージ管理を刷新するなら、より戦略的な管理でデータセンターの基盤そのものを強化するところまで目指してみてはいかがだろう。
◆ 「Webキャスト」でもっと詳しく!! ◆ |
|||||||||
|
提供:株式会社シマンテック
アイティメディア営業企画
制作:@IT 編集部
掲載内容有効期限:2009年09月30日
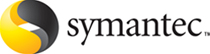
「今あるストレージを使いつくせ」 INDEX |
|
| 【PART 1】 新規ストレージを買い足す前にできることはいろいろある |
|
| 【PART 2】 ストレージを有効活用するための新技術とは |
|
◆ 「Webキャスト」でもっと詳しく!! ◆ |
|||||||||
|


