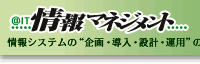@IT情報マネジメント会議室は、2009年4月15日に新システムに移行しました。
新たに書き込みを行う場合には、新しい会議室をご利用ください。
新たに書き込みを行う場合には、新しい会議室をご利用ください。
- @IT情報マネジメント 会議室 Indexリンク
- IT戦略
- 仕事の改善
- アーキテクチャ
- プロジェクト管理
- ITインフラ
- Webマーケティング
- BPMプロフェッショナル
- 業務アプリ
- - PR -
プロジェクト撤退と法律について
| 投稿者 | 投稿内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
投稿日時: 2005-01-30 16:47
いつの間にやら見積スレッドになってますが(笑)
見積には固定費を含む全ての経費や、賞与やベースアップを含む全ての計画された利益が含まれるべきだと思います。 社内にリスクがあるならそれをどうするかはその都度判断。社外(お客さん)にリスクがあるなら、それは明確に提示して受注までに可能な限りゼロにすべきものと思います。 社外のリスクの多くはお客さんの力で軽減できるもので、お客さんから見ればリスクでなく経費の節減です。 プロジェクト管理は受注前のこの時期から始まり、ここでの手抜きは後で桁外れになって返ってくるののではないかと思います。 | ||||||||
|
投稿日時: 2005-01-30 17:45
こんなことを全従業員に考えさせるなんて無理。普通はそういった諸々のコストが、個人に経費として乗ってきませんか? 細かいことは分からなくてくも、技術者 A さんの経費 140万円/月ということになっている。つまり 1日の作業に対して 7万円の見積りを出せば良いとか。 対ユーザー折衝をしない開発技術者であれば、作業日数 * 単価 で(上司に)見積りを出すのは間違いではないと思う。開発技術者は、技術要素を元に作業日数を正確に出せれば十分(まあ、それさえも難しいんだけども)。自己弁護論でもなんでもない。全社的な効率の問題。各フェーズで勝手にリスク係数掛けていったら、最終見積り金額がかなり根拠不明な金額になるだろうし、競争力もなくなると思う。だから、開発技術者は 作業難度を加味した作業工数を出せばいい、というのが一般化しているんだと思うけど。 対ユーザー折衝をしているマネージャーは、プロジェクト規模や内容によってリスク係数を掛けてもいい。ただ、本スレで出ている相手購買部の値引き要求を考慮する必要があるかどうかとなると、ちょっと疑問。 全体で均して、世の中の 50% の会社が平均 10% の値下げを要求してくるのであれば、あらかじめ会社として個人に乗せる経費を 5% 程度あげておけばいいんじゃないのかな。値引き要求率というのは開発技術者やプロジェクトマネージャーが、考慮すべきリスク要素ではないように思う。 まあ、全従業員にトータル経費を考えさせるというのは意識改革・啓蒙という点では評価できるけど、実際には技術者にはその専門分野についてのみ見積もらせるほうがいい。 | ||||||||
|
投稿日時: 2005-01-30 19:34
そりゃ無理です。ちょっとできるSEや営業でも無理でしょう。というか、あまり個人で考えるものではないですよね。 開発側で閉じて考えれば工数が出せればいいですが、開発期間が変われば工数は変わるなど出すのは簡単ではないですね。当たっていてもまぐれ、の世界かも。 | ||||||||
|
投稿日時: 2005-01-30 19:59
[quote]
加納正和さんの書き込み (2005-01-30 12:44) より:
たぶん社内見積と社外見積の切り替えや詳細見積の粒度は会社ごとに違うと思うので はっきりとは言えませんが、自分の感覚では顧客に「リスク分」なんて見積出したら 100%受注できないと思います。。。(下手すると数百万ですし。。) 自分は担当ではありませんが、開発にはどの程度のコストがかかっているのか、 どの程度の(金額としての)リスクがあるのかということは常に意識しておこうと 思っています。なにしろ一社員ですから。 フリーなら赤字でも自分が借金負うだけですが、他人の給料まで減らすわけにいきませんから。。。 | ||||||||
|
投稿日時: 2005-01-31 17:02
見積や計画策定の段階では、次のような事について吟味します。(PMBOKより)
・スコープ :全体の範囲・スコープ定義他 ・時間 :作業定義他 ・コスト :資源計画他 ・品質 :品質計画他 ・組織 :要員調達他 ・コミュニケーション:通信計画、進捗管理他 ・調達 :発注、契約他 ・リスク :リスク予測他 で、ここではリスクというふうに他と同じようなくくりになってますが、その要因 となるものは、上記のリスク以外の項目すべてに含まれます。 スコープが曖昧な為のリスク、要員についても必要なスキルを確保できるかどうか のリスク...等々 ただ、現実問題として、そんな様々なリスクを正確に予測し、ヘッジできるなんてこ とは不可能なわけで、ある程度標準化されたものか、経験者による勘に頼るしかない のではないでしょうか。 で、本題の「購買部による固定的な値引き」というのも上記のリスクに入れても良い かもしれませんが、その勘とか情報を有しているのは開発側サイドの人間よりも、 圧倒的に営業サイドの方が多いわけで、こういう取引上のリスクは営業サイドでヘッジ してもらうほうが効率的でしょう。 今回は単に10%値引きというわかりやすい例でしたが、長期間のプロジェクト等で 分割検収(入金)と終了時一括検収(入金)というのでは、もらうほうにとってかな りの差が出ます。また、手形の場合も同様に。 こういったことは営業で考慮するようにして、技術と営業とでうまくコミュニケーショ ンを取りながらきっちりと説明できる見積をすることが大切だと思いますね。 | ||||||||
|
投稿日時: 2005-01-31 18:28
ええと、、、前のpostが少しすでに流れてしまっているのですが・・・一応、返信を(^_^:
>お金に無頓着でいいのは滅茶苦茶にデキル人だけですよ。 >いわゆる「天才」。 >僕は凡人なんでそんな危険なギャンブルみたいなことはできません。 >会社の金使ってギャンブルって十分な横領罪ですよ。 あ、いえ。すいません、、、ビミョウに単語で混乱していたみたいで、僕の書き方がわるかったかな? お金に無頓着でといったことをいいたかったのではなく、以前に交渉相手に見積もり+予想値引き分した ものをだすというのがどうなのか、という話がでていたので、それに対して相手に見積もりそのままを正直 にすべてをだしてしまうのは、ちょっとマズイのではないかなということが言いたかったです・・・ >他人にできないことをしていると言う自負は必要ですが、 >裏を返せばそれ以外では食べていけないって場合は凡人です。 このあたりは、本題とはあまり関係ないのですが、ph.dとかのspecializedな人たちは 結構それ一筋な人たちが多かったりしそうな気がするので、凡人といってしまうのはどうなのかなと・・・ >交渉があまりうま過ぎてもこき使われている感じが残るので、 >言葉に反応しているだけなんじゃないかと言う自分のアレルギー反応も有ります。 あ、このあたりは、どちらかというと私自身が微妙に感じていることを、るぱんさんが感じとったのかも しれません(^_^; 自分がいる大学が、business schoolがかなり強いので、engineerな人たちも、 片足はbusiness schoolに入っている人が多かったりなど、いろいろみていると、「ひょっとして、engineer をよりよくこき使えるようにするために、ついでにengineeringもしているのでは・・・」など、 いろいろウワサ、etcがあったりするので・・・ いまいち、まとまりのない文章ですみません。がんばります。 | ||||||||