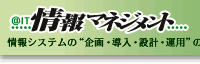@IT情報マネジメント会議室は、2009年4月15日に新システムに移行しました。
新たに書き込みを行う場合には、新しい会議室をご利用ください。
新たに書き込みを行う場合には、新しい会議室をご利用ください。
- @IT情報マネジメント 会議室 Indexリンク
- IT戦略
- 仕事の改善
- アーキテクチャ
- プロジェクト管理
- ITインフラ
- Webマーケティング
- BPMプロフェッショナル
- 業務アプリ
- - PR -
チームとして残業0にするにはどうしたらいいか
| 投稿者 | 投稿内容 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
投稿日時: 2006-12-28 13:24
るぱんです。
見積もり時に値切られることを想定して、 2〜4倍で案件取って、 利益を確定できたらいいのかなぁ・・・と。 予算が無いから、適切に人員配置できないんであって、 値切るほうは、全体の何%コスト落とせた。よしよし。 しか考えてないと思うんですね。 中間に入る営業も然りですが。 「まず、分捕る。」 これが肝要かと。(笑) [追記] 言葉が悪いので説明不足と感じ、追記。 末端に権限が無いから現場が苦労するのであって、 権限が無いならば作り出すのがよいと思うためです。 結局、お金がある人が権限を持つので、 予算を多めに確保して、 権限を現場に作り出すのが良いかと思うためです。 [/追記] [ メッセージ編集済み 編集者: るぱん 編集日時 2006-12-28 13:27 ] | ||||||||||||||||
|
投稿日時: 2006-12-29 14:59
みなさんの書き込みをみて条件不足に気づきました。
はい、そのとおりです。 その条件設定がちゃんとできていないから、あしゅさんのツッコミをいただくわけです。 今回の話題では、原価に対してどのように利益をあげるかは考慮していません。 その辺の話題は経営者とPL/PMに意見の齟齬が起きにくいので。 100単位の作業で100単位の売り上げがあり、20単位の利益があるとでも考えておいてください。 もう一つ大きなミス。
個人的には部長以上の経営者に近い管理職の意識で書きましたが、 改めて読み直すとこの管理職はPL/PMと読めてしまいますね。 「管理職」の部分は「経営者」とでも読み替えてください。 最後に条件漏れのミス。 ・このチームの一月あたりに残業なしで作業できる量は100単位です。 それ以上の作業は残業となります。 で、(A)、(B)の先頭にそれぞれ「一月あたり」という単語を入れてください。 今回は簡単に書いていますが、 「100単位の作業量と見積もれば、100単位の作業できっちりとこなすチームがあったと仮定します。」 がどれだけ困難か、PL/PM経験者であれば分かると思います。 ここを改善することで、前のスレッドで書いた戦術レベルの改善(の一部)ができると考えています。
そういう話になると、残業による労務費の上昇と、 相対的な間接費減少をどのように原価計算式へ反映するかという話題となり、 SEよりも経理の話となるので、今回は置いておきます。 個人的には残業までを考慮した原価計算式にお目にかかったことはありません。 個人ごとに給料が違う以上、その理屈でいうと、個人ごと、時間ごとに計算する必要が出ますし。 前の期の労務費の総額などから残業分も含めて平準化した価格を算出するんじゃないんでしょうか。
自社の従業員であれば36協定でクリアできるので無視しています。 労働者派遣で契約する場合はこの辺をどう契約に盛り込むかも重要ですけどね。 | ||||||||||||||||
|
投稿日時: 2006-12-29 16:11
現状の能力から進歩なしにこなせる(A)ではなく、ハードルは少し高いところに置く。
したがって(B)。 意図は残業させることではない。 ..とシンプルに回答。 | ||||||||||||||||
|
投稿日時: 2006-12-29 16:13
私の回答ですが、
PL/PMの立場としては無条件にAを選択したくなります。 一方で、離職によって発生するコストが 売り上げによって発生するメリットを下回る場合、 経営者はBを選択すると考えています。 また、残業時間と離職率の相関性を意識している経営者は多くありません。 残業時間と離職率の相関性に気づいていても 離職率には残業時間以外の要素も色々影響するため、 残業時間のみで離職率を語れないのも問題です。 そして、作業を達成できなくて困るのはPL/PMです。 売り上げが達成できなくて困るのは経営者です。 ここに、PL/PMと経営者の意見の齟齬が発生します。 Bのようなやり方はうまくいかないという指摘もありますが、 ドレイのようにこき使うことで離職率が高くとも 成功している企業も実在するため、説得力に欠けます。 経営者から利益のために残業してたくさん売り上げろと命令された際に、 PL/PMとして、どのように対抗するか。 このあたりが現場管理職であるPL/PMの限界と考えています。 | ||||||||||||||||
|
投稿日時: 2006-12-29 19:01
ズレますが。
SE 業界が異常なのだろうか。「残業はない」業界が、異常なのだろうか。 私の妻は公務員ですが、残業しまくりです。私の義弟は建築業界ですが、やはり残業しまくりです。運送業・・・になるのかな?義父も、残業が多いですね。 残業がないのは、販売員の実母…とはいえ、イベントがあると残業の嵐ですね。義母も、今の仕事は残業“していません”が、前のパートは自主残業が当たり前でしたね。製造ラインにいる従兄弟も、「残業しないと評価が下がる(でも、給料は上がらない)」とぼやいていました。 ということで、私の感覚では、「残業はないという方が異常」です。 もうひとつズレますが。 100単位の仕事だとして。100単位のお金がもらえるというのとは、また違うんですよね。で、100単位の仕事に100単位のお金がもらえるとして。100単位使ってしまったら、利益が出ないわけです。 前にいた会社では、5%の「無理矢理値引き」が有り、「売上の2%の利益を出す」(本社が利益を吸い上げてしまうので、部門としての利益がない、ということ)という縛りもあったので、仕事量の9割以下で仕事を済ませなければ、利益が出ないということになっていました。 じゃぁ、どうするかというと、残業ですね。20日と見積もって、15日+30時間の残業で仕上げれば、トントンだけど、5日分、別の仕事を割り当てることが出来ます。 結局、こうやって日数稼ぎをして、何とか利益を出しているんじゃないでしょうか。 _________________ | ||||||||||||||||
|
投稿日時: 2006-12-29 19:18
同じ基準で見積もった120単位の作業量を100単位でこなすチームに成長する、と仮定したらどうでしょうか? 単なる数値遊びにすぎませんが、1年かけて実現するには毎月前月比1.5%の効率アップが必要で、1年後には残業なしになっています。 ただ、与えられた作業をこなす為にやっていると、従来120だった見積を100で出されかねません。 それだとあがった20が競争力アップや戦力増強に使えません。 PM/PLにできることは、効率アップするモチベーションを持ち、関係各位へのロジカルネゴの基を作ることではないでしょうか。 上から戦略が降りてくるのを待っていたのでは、降りてきた戦略でモチベーションを下げてしまい、結局LOSE&LOSEになってしまいそうな気がします。 # まあ、言うのは簡単なんですけどね。 | ||||||||||||||||
|
投稿日時: 2006-12-30 00:23
これが条件なら Aが最適でしょう利益率が同じならば 現在のメンバで120単位の仕事には過剰分の20単位をこなせる人を加え 100単位にすればいいのですから (返答者の中に「100単位」を取り違えている人がいそうですが・・) | ||||||||||||||||
|
投稿日時: 2006-12-30 11:24
(SE 業界?) 確かに残業が多いのは考え物ですが、チームとして残業を 0 にする必要はないと思います。 私のユニットでは、残業を進んでやりたいという方には普通に残業させています。 別に仕事に追われているのではなく、前倒しで作業を進めて、次の仕事に早く着手、 結果的に 「売上」 を伸ばすための残業をしているということです。 これならば、経営者に迷惑がかかることもありませんし、むしろ 「そうしてくれ」 と言われています。 つまり、「残業がある == 工数が余分にかかっている」 とは言えないと思うのです。 このように、残業自体には何ら問題はないのですから、0 を目指す必要はないと思われます。
離職者の数は、何も工数というファクタで決まる問題ではありますまい。 与えた単位から、売上が決まるのは当たり前ですが、全社的にはどうでも良い話です。 ところで、残業させない結果、仕上がらなかったという考慮が漏れていませんか? == 終えられると決まっているならば、(A) になるに決まっているでしょう。
この 2 つは、(A) と (B) とは違って、なぜか 「水増し」 という要素があり、 離職者うんぬんについて触れられていなくて、「利益」 がどうこう書いてあって...??? そして、なぜか結果が、180 と 120 とで違う...??? 私には、(A) 〜 (D) どころか、(C) と (D) の選択肢が、同列の状況とは思えないのですが... _________________ C# と VB.NET の入門サイト じゃんぬねっと日誌 | ||||||||||||||||