
第2回 ファイルACLを用いたアクセス制御
面 和毅サイオステクノロジー株式会社
インフラストラクチャービジネスユニット
Linuxテクノロジー部
OSSテクノロジーグループ
シニアマネージャ
2005/12/7
 LIDSの特徴、それは直感的な設定
LIDSの特徴、それは直感的な設定
それでは、図2や図3のような設定を行う方法を簡単に説明しましょう。前回挙げたLIDSの特徴の中でも、最も特徴的なものとして「分かりやすい」という点があります。LIDSでは設定や運用を行う際に、
- lidsconf(アクセス権の設定を行うコマンド)
- lidsadm(状態の変更やパラメータの確認を行うコマンド)
という2つのコマンドしか使用しないため、覚えることが非常に少ないのです。
また、lidsconfによる設定方法も非常に直感的になっています。lidsconfコマンドの書式は基本的に、
| lidsconf -A -s [サブジェクト] -o [オブジェクト] -j [アクセス権] |
のような形になっています。[サブジェクト]とはファイルやディレクトリに対してアクセスしようとしているプログラム、[オブジェクト]とはアクセス権を与えるファイルやディレクトリのことです。[アクセス権]には前項の4種類のアクセス権が入ります。ファイルやディレクトリに対してデフォルトのアクセス権を設定する際には、[サブジェクト]を省略します。
例えば、図2のようなアクセス権を設定する際には、
| lidsconf -A -o /var -j READONLY lidsconf -A -o /var/log/messages -j APPEND lidsconf -A -o /var/www -j DENY |
となります。また、図3のようにプログラムごとにアクセス権を設定する場合には、
| lidsconf -A -s /usr/sbin/httpd -o /var/www -j READONLY |
のようにアクセス権を設定したいプログラムを[サブジェクト]として指定します。
このように、LIDSではアクセス権の設定が非常に直感的にできます。また、この書式はiptablesによく似ているため、LIDSを初めて使うユーザーでも設定方法を簡単に覚えることができます。
 ACL(Access Control List)
ACL(Access Control List)
このようにLIDSでは、まず基本的なディレクトリやファイルに対するデフォルトのアクセス権を決定し、さらに個別のプログラムごとに必要なディレクトリやファイルのアクセス権を与えていくという方法を取ります。
アクセス権を次々と決めていくと、ディレクトリとプログラムに対するアクセス権を記載したリストが出来上がっていきます(表1)。LIDSではこのリストを「ACL:Access Control List(アクセス制御リスト)」と呼びます。
|
||||||||||||||||||
| 表1 ACL |
ACLの中でもファイル/ディレクトリへのデフォルトのアクセス権が規定されているものを特に「デフォルトACL」と呼びます。
 ファイルに対するアクセス制御のフロー
ファイルに対するアクセス制御のフロー
LIDSでのアクセス制御のフローは図4のようになります。
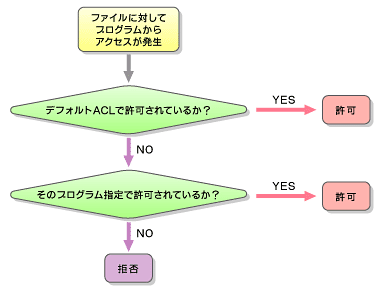 |
| 図4 アクセス制御フロー |
プログラムからファイルに対してアクセスが発生した際には、
- デフォルトACLを調べて、OKならばアクセスを許可する
- 次にそのプログラムに関するACLを調べて、OKならばアクセスを許可する
- いずれにも当てはまらない場合にはアクセスを拒否する
という流れになります。つまりこのフローは、ファイルやディレクトリに対して「デフォルトではなるべくアクセス権を少なくして、必要なプログラムを特定してアクセスを許可していこう」という考え方に基づいて作られています。
従って、次のようなACLを記載しても希望どおりの動きにはなりません。
a. あるディレクトリに対しては、書き込みまですべて許可する
b. ある特定のプログラムに対しては、そのディレクトリに対してのアクセスを禁止する
このようなACLが設定されている場合には、フロー中の1の部分でアクセスが許可されてしまいますので、bのACLは効かないことになります。希望どおりの動作を行うには、ディレクトリに対してアクセスを禁止して、必要なプログラムに対して書き込みの許可を与えていくか、この連載でいずれ説明するSandbox機能を上手に利用することになります。
|
2/3
|
|
| Index | |
| ファイルACLを用いたアクセス制御 | |
| Page1 LIDSのコンセプトと特徴 LIDSのアクセス制御方法 |
|
| Page2 LIDSの特徴、それは直感的な設定 ACL(Access Control List) ファイルに対するアクセス制御のフロー |
|
| Page3 LIDSの内部構造に迫る LIDS-1系列でのファイルアクセス制御 LIDS-2系列でのファイルアクセス制御 |
|
| Security&Trust記事一覧 |
- Windows起動前後にデバイスを守る工夫、ルートキットを防ぐ (2017/7/24)
Windows 10が備える多彩なセキュリティ対策機能を丸ごと理解するには、5つのスタックに分けて順に押さえていくことが早道だ。連載第1回は、Windows起動前の「デバイスの保護」とHyper-Vを用いたセキュリティ構成について紹介する。 - WannaCryがホンダやマクドにも。中学3年生が作ったランサムウェアの正体も話題に (2017/7/11)
2017年6月のセキュリティクラスタでは、「WannaCry」の残り火にやられたホンダや亜種に感染したマクドナルドに注目が集まった他、ランサムウェアを作成して配布した中学3年生、ランサムウェアに降伏してしまった韓国のホスティング企業など、5月に引き続きランサムウェアの話題が席巻していました。 - Recruit-CSIRTがマルウェアの「培養」用に内製した動的解析環境、その目的と工夫とは (2017/7/10)
代表的なマルウェア解析方法を紹介し、自社のみに影響があるマルウェアを「培養」するために構築した動的解析環境について解説する - 侵入されることを前提に考える――内部対策はログ管理から (2017/7/5)
人員リソースや予算の限られた中堅・中小企業にとって、大企業で導入されがちな、過剰に高機能で管理負荷の高いセキュリティ対策を施すのは現実的ではない。本連載では、中堅・中小企業が目指すべきセキュリティ対策の“現実解“を、特に標的型攻撃(APT:Advanced Persistent Threat)対策の観点から考える。
|
|




