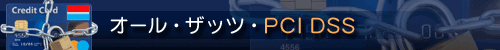
第9回 決済アプリのセキュリティ基準、PA-DSSとは
川島 祐樹
NTTデータ・セキュリティ株式会社
コンサルティング本部 PCI推進室
CISSP
2010/2/24
 求められる安全策はクレジットカード業界以外でも同じ
求められる安全策はクレジットカード業界以外でも同じ
PA-DSSの要件自体はPCI DSSとかけ離れたものではありませんが、アプリケーションやパッチ、アップグレードの配信に関する要件や、実装ガイド、トレーニングに関するものなど、アプリケーション特有の要件も含まれていることが分かると思います。
本要件が対象となる決済アプリケーションは、POS端末に内蔵されているようなアプリケーションだけでなく、決済に関連するさまざまなアプリケーションです。また、PA-DSS対象にはならなくとも、PCI DSS準拠が求められる加盟店やサービスプロバイダで使用されるアプリケーションであれば、直接PA-DSSに準拠し、リストに掲載される必要はないかもしれませんが、この要件で求められるものと同等のセキュリティ対策が求められると考えられます。PCI DSSに比べて期限に多少猶予はあるものの、アプリケーションの更改などを考えると、決して時間に余裕があるとはいえないでしょう。
このように、PCI DSSは加盟店やサービスプロバイダだけでなく、決済環境で使用されるアプリケーションやハードウェアに対するセキュリティ基準も存在し、さまざまなステークホルダーによって全体のセキュリティレベル向上が図られています。単純に1企業がセキュリティ対策を行えば十分、というわけではないのは、おそらくクレジットカード業界以外でも同じでしょう。
セキュリティを専門とする企業で仕事をしている上では、漏えいが起きたら慌てて対策、漏えいが起きてもそれでも隠ぺいしようとする、非常に悲しい現実を目の当たりにします。日本も海外も関係なく、セキュリティ対策はお金がかかる割に効果が目に見えづらく、あと回しになることが少なくありません。しかし適切なリスクマネジメントと費用対効果分析を行えば、効果的なセキュリティ対策を行うことは決して不可能ではありません。
事故が起きてからあたふた、セキュリティについては何かと他人ごと、という現実の中、このような具体的なセキュリティ対策が示されたフレームワーク、基準が、今日のセキュリティの現状を見直すきっかけになればと思っています。
最後に、とある企業で見かけた標語を紹介したいと思います。
“セキュリティ、1人1人が責任者”
1人1人がわが身のことと認識しすることではじめて企業が、そして、1企業1企業がわが身のことと認識することではじめて業界が適切なセキュリティ対策を行えるようになるはずです。ぜひ、これらのセキュリティ基準を徹底活用して、セキュリティレベルの向上を図っていただければ幸いです。
4/4 |
| Index | |
| 決済アプリのセキュリティ基準、PA-DSSとは | |
| Page1 PA-DSSの対象 PA-DSS対応は義務か? |
|
| Page2 PA-DSSの概要 PCI DSSとの違い |
|
| Page3 PA-DSS実装ガイド PA-DSS要件概説 |
|
| Page4 求められる安全策はクレジットカード業界以外でも同じ |
|
| Profile |
| 川島 祐樹(かわしま ゆうき) NTTデータ・セキュリティ株式会社 コンサルティング本部 PCI推進室 CISSP NTTデータ・セキュリティ入社後、セキュリティ対策の研究開発から、セキュリティ製品の評価、サービス開発、導入、運用支援を実施。 その後、PCIDSS公開当初から訪問調査を実施し、セミナーや書籍、記事の執筆など、PCIDSS普及促進も実施している。 |
| オール・ザッツ・PCI DSS 連載インデックス |
- Windows起動前後にデバイスを守る工夫、ルートキットを防ぐ (2017/7/24)
Windows 10が備える多彩なセキュリティ対策機能を丸ごと理解するには、5つのスタックに分けて順に押さえていくことが早道だ。連載第1回は、Windows起動前の「デバイスの保護」とHyper-Vを用いたセキュリティ構成について紹介する。 - WannaCryがホンダやマクドにも。中学3年生が作ったランサムウェアの正体も話題に (2017/7/11)
2017年6月のセキュリティクラスタでは、「WannaCry」の残り火にやられたホンダや亜種に感染したマクドナルドに注目が集まった他、ランサムウェアを作成して配布した中学3年生、ランサムウェアに降伏してしまった韓国のホスティング企業など、5月に引き続きランサムウェアの話題が席巻していました。 - Recruit-CSIRTがマルウェアの「培養」用に内製した動的解析環境、その目的と工夫とは (2017/7/10)
代表的なマルウェア解析方法を紹介し、自社のみに影響があるマルウェアを「培養」するために構築した動的解析環境について解説する - 侵入されることを前提に考える――内部対策はログ管理から (2017/7/5)
人員リソースや予算の限られた中堅・中小企業にとって、大企業で導入されがちな、過剰に高機能で管理負荷の高いセキュリティ対策を施すのは現実的ではない。本連載では、中堅・中小企業が目指すべきセキュリティ対策の“現実解“を、特に標的型攻撃(APT:Advanced Persistent Threat)対策の観点から考える。
|
|




