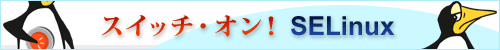
第3回 SELinuxのお行儀を監視する――MRTG/Nagios編
面 和毅
サイオステクノロジー株式会社
OSSテクノロジーセンター
開発支援グループ
グループマネージャー
2007/8/29
 Nagios Pluginsのインストール
Nagios Pluginsのインストール
では、Nagios Pluginをインストールしましょう。
- まずクライアント上にNagiosのPluginをインストールします。Nagiosのダウンロードサイトから「Nagios Plugins(2007年7月時点ではnagios-plugins-1.4.9.tar.gz)」をダウンロードします。
- 適当なディレクトリで展開し、
を行います。# ./configure
# make all - rootユーザーになり、
を行います。デフォルトでは/usr/local/nagios/libexec以下にインストールされます。# make install
 NRPEのインストール
NRPEのインストール
次に、NRPEをインストールします。
- 同様にNagiosのダウンロードサイトからNRPEをダウンロードします(2007年7月時点ではnrpe-2.8.1.tar.gzです)。
- 適当なディレクトリで展開し、
を行います。# ./configure
# make all - rootユーザーになり、
を実行します。このとき、デフォルトでは/usr/local/nagios以下にNRPE関係のファイルがインストールされます。# make install-plugin
# make install-daemon
# make install-daemon-config - さらに、xinetdを用いてNRPEを起動するため、
を実行します。# make install-xinetd - /etc/xinetd.d/nrpeファイルを編集します。
となっていますので、接続を許可するIPアドレスを記載します。only_from = 127.0.0.1 - /etc/servicesファイルにNRPEデーモンが使用するポート(5666/tcp)を追記します。
などのように記載します。nrpe 5666/tcp # NRPE - xinetdを再起動します。
- NRPEがきちんと動作するかをチェックします。クライアント上で、
と入力し、NRPEのバージョンが表示されれば、NRPEがきちんと動作しています。# /usr/local/nagios/libexec/check_nrpe -H localhost - クライアント上にてパケットフィルタリングを設定している場合には、5666/tcpへの外部からの通信を許可するように設定します。system-configu-securitylevelなどを使用して、5666/tcpへの通信を許可します。
 nrpe.cfgファイルの編集
nrpe.cfgファイルの編集
/usr/local/nagios/etc/nrpe.cfgファイルを編集して、監視をする項目に対するコマンドを定義します。ここで、各コマンドに対する定義を見てみましょう。例えばcommandは、
| command[check_users]=/usr/local/nagios/libexec/check_users -w 5 -c 10 |
という行を用いて定義されています。この行では、右辺のプラグインと引数を表すものとして、check_usersというコマンドを定義しています。
ここで定義されたコマンドは、Nagiosサーバのmynetwork.cfgファイルで使用されます。
例えば、クライアント上で上記のようにcheck_usersが定義されている場合に、Nagiosサーバ上のmynetwork.cfgファイルで下記のようにcheck_commandの項のcheck_nrpe!以降の部分にcheck_usersコマンドを記載します。これにより、下記のhost_nameで定義されているホスト上で、最終的にcheck_usersプラグインを(引数 -w 5 -c 10付きで)実行することになります。
| define service{ use local-service ; Name of service template to use host_name plone2 service_description NRPE-users check_command check_nrpe!check_users } |
| リスト6 mynetwork.cfgの内容 |
 Nagiosサーバ上での設定ファイルの変更
Nagiosサーバ上での設定ファイルの変更
Nagiosサーバ上の設定ファイルを修正して、NRPEで実行したいプラグインを設定します。例ではmynetwork.cfgファイルとします。これはnagios.cfgファイル中で、
| cfg_file=/usr/local/nagios/etc/mynetwork.cfg |
などとして定義されているものになります。mynetwork.cfgファイルにクライアント上で監視したいコマンドを定義していきます。
今回の例では、check_nrpeコマンドを用いてクライアント上でcheck_usersプラグインを実行します。
 Nagios+NRPEシステムでの結果
Nagios+NRPEシステムでの結果
最終的にNagios+NRPEによる監視の結果ですが、こちらも前述のSNMP+MRTGでの結果と同様に、SELinuxを有効にしている状態でもNagiosによる監視には問題ないようです。SELinuxでのエラーも特に出力されていません。
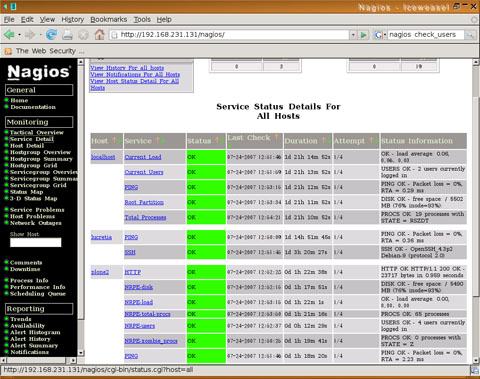 |
| 図5 Nagiosでの監視も問題は発生していない |
次回は、今回の続きとしてNRPEでSELinuxの状態を監視する方法を紹介し、さらにNRPE用のドメインを作成してさらにクライアント上のセキュリティを強化したいと思います。
|
3/3 |
| Index | |
| SELinuxのお行儀を監視する――MRTG/Nagios編 | |
| Page1 「SELinuxはトラブルの元」は都市伝説です SNMP+MRTGによる監視 SNMP+MRTGの結果 |
|
| Page2 SNMP+MRTGでSELinuxが問題になる場合 Nagios+NRPEによる監視 |
|
| Page3 Nagios Pluginsのインストール NRPEのインストール nrpe.cfgファイルの編集 Nagiosサーバ上での設定ファイルの変更 Nagios+NRPEシステムでの結果 |
|
| Profile |
| 面 和毅(おも かずき) サイオステクノロジー株式会社 OSSテクノロジーセンター 開発支援グループ グループマネージャー 学生時代よりUNIXに親しむ。1997年からサーバ構築およびセキュリティ全般を扱う仕事に従事、Linuxを使い始める。 現在はLIDSの普及活動に注力。LIDSユーザ会(LIDS-JP)の立ち上げやLIDS関連文書の日本語化、LIDSを用いたシステム構築の紹介などを行っている。また、サイオステクノロジーでビジネス面でのLIDSの普及活動に注力している。 2005年12月より、LIDS Teamに参加し、LIDSの公式な開発チームの一員として活動している。 |
| スイッチ・オン! SELinux 連載インデックス |
- Windows起動前後にデバイスを守る工夫、ルートキットを防ぐ (2017/7/24)
Windows 10が備える多彩なセキュリティ対策機能を丸ごと理解するには、5つのスタックに分けて順に押さえていくことが早道だ。連載第1回は、Windows起動前の「デバイスの保護」とHyper-Vを用いたセキュリティ構成について紹介する。 - WannaCryがホンダやマクドにも。中学3年生が作ったランサムウェアの正体も話題に (2017/7/11)
2017年6月のセキュリティクラスタでは、「WannaCry」の残り火にやられたホンダや亜種に感染したマクドナルドに注目が集まった他、ランサムウェアを作成して配布した中学3年生、ランサムウェアに降伏してしまった韓国のホスティング企業など、5月に引き続きランサムウェアの話題が席巻していました。 - Recruit-CSIRTがマルウェアの「培養」用に内製した動的解析環境、その目的と工夫とは (2017/7/10)
代表的なマルウェア解析方法を紹介し、自社のみに影響があるマルウェアを「培養」するために構築した動的解析環境について解説する - 侵入されることを前提に考える――内部対策はログ管理から (2017/7/5)
人員リソースや予算の限られた中堅・中小企業にとって、大企業で導入されがちな、過剰に高機能で管理負荷の高いセキュリティ対策を施すのは現実的ではない。本連載では、中堅・中小企業が目指すべきセキュリティ対策の“現実解“を、特に標的型攻撃(APT:Advanced Persistent Threat)対策の観点から考える。
|
|




