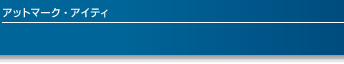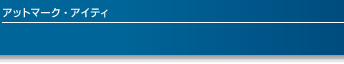|
|
����ȂƂ���ɂ�CORBA�Ȃ́H
�g�ݍ��݂̐��E��CORBA�̎��オ�������� |
�@ CORBA�ƕ����ƁA�F����͑�K�͂ȃg�����U�N�V�����V�X�e���̐��E���v�������ׂ�̂ł͂Ȃ����낤���B���ہA�A�b�g�}�[�N�E�A�C�e�B�̋L���u���܂Ȃ�CORBA�Ȃ́H�v�ł����łɏЉ���悤�ɁA���{���\����I�����C���،���Ƃł���DLJ
Direct SFG�،��̃T�C�g��A�A�����J���q��̑������s�T�C�g�uAA.com�v�Ȃǂ̃o�b�N�G���h�ɂ́ACORBA���g���Ă���B
 |
�g�ݍ��݂̐��E�ɂ܂�CORBA�H |
�@�Ƃ��낪�ACORBA�Ɋւ���ŐV�̃g�����h�́A�ӊO�Ȃ��Ƃɑg�ݍ��݂̐��E�ւ̓K�p�Ȃ̂��B�e���R���l�b�g���[�N�@��̐��E�ł́A���łɑ����̓������i��ł���B�܂��A���x��ʃV�X�e���iITS�j��ETC���u�i�������������V�X�e���j�A�J�[�i�r�ȂǁA�������̐g�߂ȂƂ���ւ�CORBA�̓K�p����������͂��߂Ă���̂��B����ɂ́A�s�K�ȏo�����ł͂��邪�A���܃A�t�K�j���X�^�������s���Ă���ČR�̍q��@�̐���@��A�q��@�Ɗ�n�Ԃ̒ʐM�ɂ�CORBA���g���Ă���B���́A�h�q�̐��E�ł́A���܂�CORBA�͌������Ȃ��e�N�m���W�[�ƂȂ����B
�@�Ƃ���ŁACORBA�́A�l�b�g���[�N��ɑ��݂���I�u�W�F�N�g���N���C�A���g����Ăяo�����߂̊�Ղł���B�������A���̌Ăяo���́A�ً@��̊Ԃł����Ă��A�A�v���P�[�V�����̊J�����ꂪ����Ă��A���ʂ̎菇�ōs�����Ƃ��ł���B�������A�I�u�W�F�N�g�Ԃ̒ʐM�͂��Ȃ�N���e�B�J���ȏ������ł��M�������������Ƃ��������B�������A�{���ŏ��ɏЉ���悤�ȑ�K�͂ȃT�[�o���Ŏg����CORBA�ɑ��āA�F����͎��̂悤�ȋ^������������낤�B
- �g�ݍ��ݗp�r�ɑς����鐫�\���o�Ȃ��̂ł͂Ȃ����H�i�I�[�o�[�w�b�h���傫���A���A���^�C������p�t�H�[�}���X�ɉ������Ȃ��̂ł͂Ȃ����j
- �ғ�OS��������̂ł͂Ȃ����H
- C�ȂǁA�g�ݍ��ƊE�ł̕��y���ꂪ�T�|�[�g����Ȃ��̂ł͂Ȃ����H
- ����������ʂ��傫���̂ł͂Ȃ����H
|
�@���āA�{�e�ł͂����̋^��ɓ����Ă������A�܂����̑O�ɁA�g�ݍ��݂̐��E��CORBA�̓������K�v�Ƃ���闝�R�ɐG��Ă݂����B
 |
�g�ݍ��݂̐��E��CORBA��v�����闝�R |
�@���܂�g�ݍ��݂̐��E�Ƃ����ǁA�l�b�g���[�N�Őڑ�����Ă��Ȃ����E�͏��Ȃ��B�g�ݍ��݂̐��E�قǁAMPU��OS�̎�ނ��L�x�Ȑ��E�͂Ȃ��B�����{���ڑ����邱�Ƃ�������E�����Ԃ̂́ACORBA�̓��ӕ���ł���B���Ƃ��A�}���`�x���_�̋@�ނ����݂�������ł̃l�b�g���[�N�Ǘ��V�X�e���̗���݂Ă݂悤�B
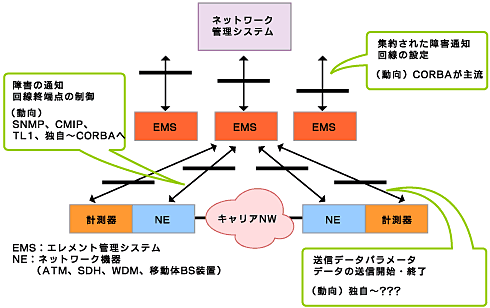 |
| �ʐM�ƊE�ɂ�����v���g�R���W���������B������@��Ԃ�CORBA�̗̍p���g�����h�ƂȂ���� |
�@�ʐM�L�����A�̂悤�Ȑ��\�`���S�̋@����܂Ƃ߂ď�Q�Ǘ�����K�v�����鐢�E�ł́A1�̃l�b�g���[�N�Ǘ��\�t�g�E�F�A�ɂ���āA�}���`�x���_�ō\������邷�ׂĂ̋@��ɑ��ď�ԏ��̎�M�E�Ǘ��R�}���h�𑗏o���A��ԊǗ����s���K�v������B���̏ꍇ�A�I�[�v���ȒʐM�v���g�R�����̗p���ăx���_�Ԃ̍��ق��z������K�v�����邪�A������HTTP�̂悤�Ȍ����̈����v���g�R���͎g�����Ƃ��ł��Ȃ��B���݂����Ƃ��悭�g���Ă���v���g�R����SNMP�����A�����UDP���x�[�X�Ƃ��Ă��邽�߁A�M�������v���g�R���ɗ���킯�ɂ͂������A�A�v���P�[�V�������ŕ⊮����K�v���o�Ă���B
�@���̓_�AIIOP�iCORBA�j���g���ATCP�x�[�X�̒ʐM�Ȃ̂Ńg�����X�|�[�g�w�����B�ۏ���s���Ă����Ƃ����킯���B���ہA����10���ɃX�^�[�g����NTT�h�R����FOMA�̃l�b�g���[�N�Ǘ��V�X�e���ɂ�CORBA���̗p����Ă���B
�@�܂��A�����قǏЉ��ETC���A�����Ԃ�ETC�Ԃō����Ō����I�ȒʐM���v�������B���݂́A�����ł�DSRC�ƌĂ�鋷�ш�̖����v���g�R�����g���Ă��邪�A�����I�Ƀ��C�����XIP�ւ̈ڍs���g�����h�Ƃ��čl�����Ă���A�����̏�ł́A��͂�HTTP���������̗ǂ�IIOP�𗘗p���邱�Ƃ������܂�Ă���B�����Ă��łɁA�Z���^�Ԃ̒ʐM�ł́ACORBA�����ڂ���Ă���̂��B����ɂ��ẮA���c�@�l
���H�V�Y�ƊJ���@�\��Web�T�C�g�ŏЉ��Ă���̂ŎQ�Ƃ��Ăق����B
�@���̂悤�ɁA�g�ݍ��@��̒ʐM�ɑ���j�[�Y�����v���g�R���Ƃ��āACORBA�̗��p���i��ł���B
 |
�g�ݍ��݂̐��E�̗v�����N���A����uOrbix/E�v�̒a�� |
�@���āA�����܂łŁA�g�ݍ��݂̐��E�ɂ�����CORBA�̕K�v���ɂ��ė������Ă����������Ǝv���B�ł́A���悢���ɒ���CORBA�ɑ���^��ɓ����悤�B
�@�����ŏЉ�����g�ݍ�����CORBA���i�uOrbix/E�v�́ACORBA���i�̎�����̃f�t�@�N�g�ł���Orbix 2000�����A�C�I�i�e�N�m���W�[�Y�̑g�ݍ�����CORBA���i�ł���B���́AOrbix/E�́A�č��I�u�W�F�N�g�E�I���G���e�b�h�E�R���Z�v�g�Ђ��J��������]����CORBA���i�uORBacus�i�I�[�o�b�J�X�j/E�v���x�[�X�ɂ��Ă���B�A�C�I�i�e�N�m���W�[�Y�́A�I�u�W�F�N�g�E�I���G���e�b�h�E�R���Z�v�g�Ђ�2001�N2���ɔ������A�G���^�[�v���C�Y�Ƒg�ݍ��ݎs�ꗼ���ɂ�����CORBA�Z�p�̋������s�����B�����āAORBacus�̊J���҂͔�������A�C�I�i�e�N�m���W�[�Y�̊J�����C���Ɏc��A�����������i�̋����Ɏ��g��ł���B
�@�����ŁA�g�ݍ��݂̐��E�ɂȂ�CORBA�Ȃ́H�̋^��Ƀ}�g���b�N�X�œ����悤�B�����̃t�@�N�g��Orbix/E�̃X�y�b�N�ł���B
| �^�� |
�� |
| �g�ݍ��ݗp�r�ɑς����鐫�\���o�Ȃ��̂ł͂Ȃ����H |
(TCP/IP�\�P�b�g�Ɣ�ׂāA�p�t�H�[�}���X�͖�20%�̃I�[�o�[�w�b�h���ɂƂǂ܂�)
1�b�Ԃɖ�1��3550���2�E�F�C�R�[��
1�b�Ԃɖ�4��6230���1�E�F�C�R�[��
�iOrbix/E for C�AC++�ł̑���l�j*1 |
| �ғ�OS��������̂ł͂Ȃ����H |
(�Ή�OS)
QNX/Neutrino
�g�ݍ���Linux
VxWorks
ENEA OSE
ITRON�i�Ή��\��j
Windows CE
Palm OS
Windows 2000
Solaris
|
| �g�ݍ��ƊE�ł̕��y���ꂪ�T�|�[�g����Ȃ��̂ł́H |
�i�Ή�����j
C/C++�AJava |
| ����������ʂ��傫���̂ł́H |
�N���C�A���g�����s�T�C�Y�i�`90KB�j
�T�[�o�����s�T�C�Y�i�`140KB)
�iOrbix/E C++�ł̑���l�B�gHelo World�h�̕\�������������ꍇ�j*2 |
�@�@*1�FPentium�V 800MHz/Windows 2000��
�@�@*2�FPentium�V/Windows 2000��
�@�܂��A�g�ݍ��ݗp�r�ɑς����鐫�\���o�邩�Ƃ�����肾���AIIOP���g�����ʐM�ł��ATCP/IP�Ɣ�r���Ė�20���̃I�[�o�[�w�b�h�̑���ɂƂǂ܂�B����̓��A���^�C������ɏ[���ς����鐫�\���B�܂��A�Ή�����OS�́A�g�ݍ��݂̐��E�ŗp�����Ă����v��OS�ɑΉ����Ă���B�����ŕ��y����ITRON�ɂ��Ă͍���̑Ή�����������Ă���B�Ή�����ɂ��Ă����A����͌���ʂɐ��i�̃o���G�[�V�������p�ӂ���Ă���B
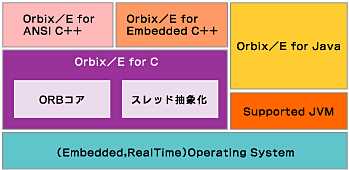 |
| �ł��J���҂ɓ���݂�����C����ɑΉ����Ă���B�܂��AC++�o�[�W�����ł�ANSI�Ɣ�ANSI�̗������T�|�[�g���Ă���BJava�ł̓I�u�W�F�N�g�w���J���҂ɂƂ��Ă͍������Y���Ƃ��������b�g�������炷 |
�@ ����������ʂɊւ��ẮA��L�̕\���́u����������ʂ��傫���̂ł́H�v�ɑ���̗����݂Ăق����B����́gHello World�h�̕\�������������ꍇ�̃N���C�A���g�A�T�[�o�̗����W���[���̃T�C�Y�ł���B�[���ɏ��������Ƃ���������ɂȂ邾�낤�B
�@Orbix/E���g�ݍ��݂̐��E�ł��[���Ɏ��p�ɑς�����CORBA���i�ł��邱�Ƃ��A�ȏォ�痝�������������Ǝv���B
|
ORBacus/E�̓�����������
�@Codonics�Ђ͈�ÁACAD�A�q��F���Y�Ƃŗ��p�����J���[�v�����^�̃��[�J�[�ł���A���̕���ł͐��E�̃g�b�v�V�F�A���ւ��Ă���B��ɋƊE��������[�h���邽�߂ɃX�s�[�f�B�[�Ȑ��i�̏o�ׂ�������������K�v�����邪�A���̂��߂ɂ͊m�����ꂽ�C���[�W���O�Z�p�����W���[�������A�V�Z�p�ƃX�s�[�e�B�[�ɁA�V�[�����X�ɂȂ����Ƃ��d�v�������B������������邽�߂ɁA��̓I�ȉۑ�Ƃ��ꂽ���Ƃ͈ȉ��̓��e���B
- C����ŊJ�����ꂽ���Y�̊��p
- �ė��p�\�ȃR���|�[�l���g�x�[�X�̃��W���[���̊J��
- �����̌���Ƃ��āAC++�AJava���T�|�[�g���邱��
- ����̃v���b�g�t�H�[���Ɉˑ����Ȃ�����
�@�����̗v���ɓ�������̂Ƃ��āACORBA�̓������œK�Ɣ��f���ꂽ�B������CORBA���i�̑I���ɂ́A��R�X�g���d�v�ȃ|�C���g�ɂȂ����B�g�ݍ��݈���@����ł��邾�������ɒ�������������ł���B�܂��A�����㐻�i�ɍ̗p�\��̃v���b�g�t�H�[���ł���Linux�ɂ��Ή����Ă���K�v���������B�����̏�������I�ꂽ�̂��AORBacus/E�ł���B
�@�I�ꂽ���R�͂ق��ɂ�����B�l�[�~���O�E�T�[�r�X�A�C�x���g�E�T�[�r�X�Ƃ������@�\���I�v�V�����ł͂Ȃ��W���@�\�ƂȂ��Ă���_���B����ɁAC++���g���������ɂ���āA�]���܂ŃT�|�[�g�ł��Ă��Ȃ������}���`�X���b�h�̗e�ՂȎ����́A�傫�ȃ����b�g�������炵���B�Ō�ɁA�\�[�X�R�[�h�����J����Ă������Ƃ��傢�ɖ𗧂����B�Ǝ��̃J�X�^�}�C�Y��L�x�ɂقǂ������Ƃ��ł��A���i�̍����\���Ɉ�����̂��B
 Codonics�� Codonics��
|
�@��҂̎���́AOrbix/E�̂���Ƀf�B�e�[���ɐG��Ă݂�BCORBA 2.3�̃T�u�Z�b�g�Ƃ��Ă̊�{�X�y�b�N�̏Љ�ɂ͂��܂�A�g�ݍ��݂Ƃ�������Ȋ��ł͏d�v�ȗv�f�ƂȂ�\�[�X�R�[�h���J�ɂ��|�[�e�B���O��J�X�^�}�C�Y�ւ̏_��ȑΉ��ATCP/IP�ȊO�̃v���g�R���T�|�[�g�Ƃ������������������B����ɂ́A���ۂ̓�������ƃA�C�I�i�e�N�m���W�[�Y�̃T�|�[�g�͂ɂ��Ă����Љ�悤�B
|