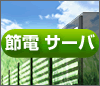
NECに聞く、省力化・効率化を両立するポイント
クラウド基盤を支える
ハードウェア設計へのこだわり
2011/8/5
今、企業にとって省電力と効率化は避けることのできない課題だ。その実現の鍵となるのがクラウドコンピューティングだが、その柔軟性と手軽さは、逆に無駄なコストを垂れ流す原因にもなりかねない。真の効率化を狙うためにはクラウド基盤にもそれなりの仕組みや工夫が不可欠――。こうした前提に基づき、NECでは省力化・効率化を徹底追求したクラウド基盤を提供しているという。では具体的にどのような技術、ノウハウが盛り込まれているのだろうか? 本連載ではサーバ、運用管理ソフト、ネットワークというクラウド基盤を支える3つの要素にフォーカス。省力化・効率化に対するNECのこだわりを“現場視点”で徹底解剖する。今回はアイティメディア オルタナティブ・ブログ主催のブロガーズ・ミーティングで省電力サーバに対するNECのこだわりを聞いた。
東日本大震災発生以降の電力不足を受け、今、国内企業にとって節電の取り組みが喫緊の課題となっている。7月1日には東京電力および、東北電力管内の大口電力需要家(契約電力500キロワット以上)に対して、昨年比15%の節電を義務づける電力使用制限令が発動。中小企業に対しても、強制力はないものの15%の節電が求められている。
 |
| アイティメディア オルタナティブ・ブログのブロガーの面々。会場の空調はもちろん節電モード。とても暑かったが、最新の省電力サーバについてNECの担当者と直接語り合えるとあって、皆嬉々とした表情だ |
こうした状況を受けて、アイティメディア オルタナティブ・ブログは7月19日、 「ブロガーズ・ミーティング@NEC 夏の節電をITでどうやって乗り切るか」を開催。日ごろIT活用の現場で活躍しているオルタナティブ・ブロガーらを前に、NECから省電力への取り組みと、省電力サーバの開発秘話などを披露してもらった。さらに、全員でディスカッションを行い、ITの省エネについて意見を交換。以下ではディスカッションでの意見を交え、ミーティングの模様を詳しくお伝えする。
空調の温度調節だけでは省電力と効率化は両立できない
NECのプレゼンに先立ち、まず登壇したのは、今回のミーティングのモデレータを務めた、いいじゃんネット 代表取締役の坂本史郎氏。氏は節電に取り組む企業の1つのモデルケースとして、自社の節電対策を紹介した。
 |
| いいじゃんネット 代表取締役の坂本史郎氏 |
同社では震災発生後から徹底的な節電を実施し、「2011年6月の電気使用量は前年比28%減を達成した」という。具体的には、冷房を 一律28℃に設定、勝手な冷房操作の禁止、冷房中の窓開け行為の禁止、サーバ室の空調の独立、という4つの対策を実施した。
しかし、「温度設定を28℃にするだけではオフィスでの体感温度が高く、当初は不快に感じる社員も多かった」という。そこで「28℃でも快適に過ごせるオフィス空間」を目標に、扇風機を使って熱が滞留しやすい上層空気を動かしたり、オフピーク電力を活用して早朝から冷房を入れておいたりすることで、空間的・時間的な温度ムラを平準化した。坂本氏はこの話を通じて、「省力化と業務効率を両立させるためには、それなりの工夫が求められる」ことを強く訴えた。
 |
ブロガー堀江氏:私が所属するアークコミュニケーションの場合、蛍光灯を3本から2本に減らす、ブラインドをなるべく下げるなどの対応をしている。また冷房を28℃に設定し、それより下げないというルールを決めた。冷房の温度ムラは解消できておらず、電源のオンオフで対応している。しかしそれでは電力を余計に使うようなので対策を考えている。 | |
 |
ブロガー木沢氏:うちの会社では7つのグループに分けて輪番休日を行っている。フロアごとに完全に電気も空調も止めている。私は電気を使わないのが一番の節電だと考える。ITシステムについても不要なサーバは完全に停止して、集約することを進めている。 | |
部材、制御方法、稼働環境―3つの視点で省電力を追求
この話を受けて、NEC プラットフォームマーケティング戦略本部 商品企画グループ グループマネージャー 本永実氏が登壇。氏はまず「弊社は他社に先駆けて、すでに5年以上にわたってIT機器の省電力化に取り組んでいる」と前置きした上で、クラウド基盤の核となるサーバに対してどのような工夫を盛り込んできたのか、省電力サーバ開発の取り組みについて説明した。
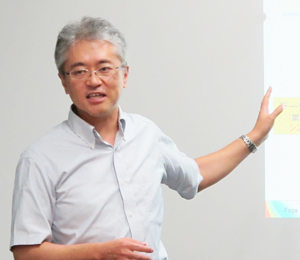 |
| NEC プラットフォームマーケティング戦略本部 商品企画グループ グループマネージャー 本永実氏 |
「そもそも省電力化に着手したのは、データセンターのスペース効率を高めるために、サーバの高密度化を目指したことがきっかけ。というのも、サーバをいくら小型化しても、ラック1本当たりの電力容量は決まっており、搭載できるサーバ数が限られてしまう。よって、消費電力の低いサーバが不可欠と考え、2005年7月、国内で初めてノート PC用CPUを採用したサーバをリリースしたのが、省電力サーバ開発に本格的に取り組む発端となった」(本永氏)
以来、省電力化の取り組みを継続。2011年6月には最新型のIAサーバ「Express5800シリーズ」を発表したが、ここに至るまでには3つの大きな進化があったという。
1つは、サーバ機器の“モノ”としての省電力化。省電力CPUや省電力メモリ、高効率電源の採用、ファン回転数制御、エアフロー改善といったコンポーネントレベルでのアプローチにより実消費電力の削減を図った。2つ目はサーバ機器の電力制御の強化。ソフトウェアによるコントロールで電力のピークを抑制、使用電力を平準化した。いわゆる「パワーキャッピングによる電力抑制策」だ。そして最新のExpress5800シリーズでは耐環境性能を大幅に向上。サーバ周辺温度の上昇という問題を見据えて、動作環境温度を従来の35℃から40℃まで向上。空調機器の消費電力削減に大きく寄与できるようにしたという。
「平均的なオフィスビルにおける用途別電力消費比率は、『空調機器』が最も多く48%。一方『OA機器』は16%程度という調査結果もある。また、データセンターにおける用途別電力消費比率を見ても、『ICT製品』が53%を占める一方で、『空調』も31%と3割を超えている。すなわち、ICT製品の省電力化だけではなく、空調の節電対策も重要度を増している。最新モデルは、こうした状況に対応した」
今後は仮想化技術を活用し、サーバ集約によるシステム全体での省電力化を推進していくという。さらに「冷却設備やUPS、CVCFなど電源設備まで含めたファシリティ全体での省電力化も狙う」。
実際、NECではファシリティ全体での省電力化に向けたソリューションとして、すでにクラウドビジネスを支えるデータセンターのエコ化を支援するサービス「データセンターまるごとエコ」を展開している。これはICT製品とファシリティソリューション、そしてコンサルティングサービスまでを組み合わせて提供する、というものだ。
また、今回の新モデル発売を機に、このソリューションをオフィス環境にも適用させた「オフィスまるごとエコ」の展開も計画中だという。これは省電力型のICT機器からオフィスファシリティ、エネルギー管理、さらにはワークスタイルまで視野に入れ、オフィスの環境負荷低減を全方位的に支援するトータルソリューションとして提供予定だという。
 |
ブロガー坂本氏:基本的に、人が利便性を求めるときには“簡単で小さくて軽いもの”を志向する。そのため必然的に、新しいモノを作ることとエコはつながっていくと考えている。もちろんIT機器も軽薄短小化が進み、効率化を求めていく限り、省電力化は必然的な流れだろうね。 | |
本永氏はこうした数々のトピックを基に、「弊社はITからネットワークまで、幅広い領域で高度な技術力と豊富なノウハウを持っている。これをフル活用して、“省電力”を1つの軸とした“日本発のデータセンター、サービスビジネス、クラウドコンピューティング”を提供していきたい」と締めくくった。
40℃での安定稼働を実現した筐体設計へのこだわり
本永氏が語ったNECの方向性について、より具体的な視点から解説したのが、プラットフォームマーケティング戦略本部 商品企画グループ主任の高橋輝圭氏だ。氏は40℃の室温でも安定稼働するExpress5800シリーズの一製品、省電力スリムサーバの「Express5800/GT110d-S」の実機を使って省電力設計のポイントや開発秘話を披露した。
Express5800シリーズは、ITによる節電支援を目指して「導入でエコ」「運用でエコ」「空調にエコ」という3つの観点から機能強化を図った点が大きな特長だという。まず「導入でエコ」としては、高効率電源や省電力CPUといった省電力パーツの採用により、サーバ単体での省電力性能を向上。一方で例えば「Express5800/GT110d-S」は、93mm幅の業界最小筐体にHDDを5台搭載可能。CPUはインテル XeonプロセッサーE3-1200製品ファミリーを採用。メモリは最大32GBのDDR3-1333メモリをサポートするなど、基本性能を大幅にアップさせ、仮想化によるサーバ集約への対応強化を図った。
 |
| NEC プラットフォームマーケティング戦略本部 商品企画グループ主任の高橋輝圭氏 |
「例えば既存のサーバ2台を、このスリムサーバ1台に置き換えて集約することで、消費電力を半減できる。まさに導入するだけで省電力化につながるスペックを備えている」
「運用でエコ」では、サーバに標準搭載している節電支援運用機能を強化した。具体的には、OS環境に依存することなく稼働監視や電源操作、リモートKVMを実行可能としたほか、UPS未接続のシステムでもスケジュール自動運転を使ったきめ細やかな節電対策が行えるという。さらに、サーバごとに消費電力を可視化・把握できるほか、消費電力のピーク制御によって最大30%の消費電力を抑制できるパワーキャッピング機能も標準でサポートしたという。
これらに加え、Express5800シリーズの省電力性能を際立たせているのは、「空調にエコ」という特性だという。具体的には、筐体内部のエアフローや冷却部材を徹底的に見直して動作環境温度を最高40℃まで向上。これにより、クールビズが実施されて空調設定温度が引き上げられたオフィス環境でも、安定稼働を可能にした。
「データセンターの節電にも有効だ。現在、一般的なネットワーク機器は40℃で稼働可能となっている。データセンターでそれらと本製品を組み合わせて使えば、例えば外気冷却を採用するなど、フロア空調の節電に大きく寄与できる」
 |
ブロガー新倉氏:この新モデルはしっかりと設計されているので壊れにくいはず。NECとしては、例えば7年など長期間の保証に対応すれば、運用コスト面でも製品のメリットを理解してもらいやすくなるのでは。設計のこだわりは長期保証が可能な裏付けとしても有効だ。 | |
 |
ブロガー方波見氏:あるいは逆に3年の短期保証とし、完全回収型のフルリサイクル型モデルにした方が受け入れられる可能性も。 | |
これを受けて、「どうやって40℃稼働を実現したのか」と、オルタナティブブロガーらの興味が集中。高橋氏は実際に「Express5800/GT110d-S」の内部構造を見せながら、こだわりのポイントを解説した。
 |
| 「Express5800/GT110d-S」は40℃の環境でも安定稼働が可能な省電力サーバ。93mm幅の業界最小筐体にHDDを5台搭載可能。CPUはインテルXeonプロセッサーE3-1200製品ファミリーを採用。メモリは最大32GBのDDR3-1333メモリをサポート(クリックで拡大) |
具体的には、高温稼働に対応するために部材レベルでパーツを選定。二重反転ファンや大型ヒートシンク、大型ダクトなどを採用した。ファンのオフセット配置もポイントで、「ファンを従来の位置からあえてずらして設置することで、1つのファンで2つの熱源をカバーするレイアウトに変更した」という。
また、マザーボードを自社で設計・開発している強みを生かし、エアフローを最適化できる部材を採用。「特に、風が筐体の前面から背面へストレートに流れるエアフローを重視し、メモリスロットの位置と方向を変更した点もポイントだ」という。さらに、熱対策に最適化した部材配置を実現するために、実機を使った熱流体シミュレーションなどの検証を徹底的に行ったという。
 |
ブロガー木沢氏:空気の流れに合わせて、ケーブルの引き回しがしっかり考えられた構造になっている。見た目も非常にきれい。 | |
 |
ブロガー山口氏:左右のパネルがメッシュになっていない。左右に間隔を置かなくても設置できるのは便利そうだ。グッとくる隠れ機能が随所に施されているので、深夜の通販番組で売られていたら思わず買ってしまいそう(笑)。 | |
 |
NEC 高橋氏:デスクの上に置いても使えるように、主な排気は下方に出すようにしている。また、上部のエアダクトに立体的なカバーを付け、上に物を置かれてもふさがらないような設計を施した。背面には防虫対策を施し、小さな昆虫などの侵入もブロックできるので、実は自宅で使うのにも適している(笑) | |
 |
ブロガー新倉氏:中小企業ではひどい環境にサーバを設置しているケースも多い。そうした現場を目にすると、細かいところまで配慮してサーバ設計を行うことはとても重要だと思う。長く使うものほど、こだわった部分がユーザーのメリットとして効いてくるはずだ。 | |
本モデルの設計・開発を担当したNEC ITハードウェア事業本部主任の多和田諭氏は、「100を超えるセンサーを筐体内の各所に配置し、温度分布をきめ細かく計測しながら、部材再配置、再設計を繰り返した。そうしてようやく40℃でも安定稼働できるレイアウト設計に行き着いた」と説明する。
この話を聞いたブロガーらからは、「こうした省電力設計へのこだわりをもっと強くアピールするべきなのでは? ここまで徹底してやっているメーカーはNECの他にはないのではないか」(新倉氏)との声も。
 |
ブロガー柳下氏:企業には、やはり節電をキーワードにして提案を? | |
 |
NEC 本永氏:製品自体の節電に加えて、運用でも節電を支援できること――特に40℃で稼働可能なことから、空調の電力削減に貢献できることを訴求している。また、低音で高速回転できるファンをベンダと共同開発し、冷却性能とともに静音性も高めた点もポイント。 | |
 |
ブロガー柳下氏:ただ、この新モデルは価格がやや高い。その点に着目すると、省電力を促進するドライバにはなりにくいのでは? | |
 |
NEC 本永氏:導入コストだけを見るとそう思われてしまうのは仕方がないと思う。ただ、これからはあらゆる面から複合的にコストを考える必要がある。特に導入コストが高くても、数年間使った際の電気代、運用コストには明らかな差が出てくる。この点は弊社自身がもっと事例を積み上げる必要がある。 | |
 |
| こだわりの設計にブロガーらも興味津々。ハードウェアはいくつになってもわれわれをとりこにする |
一方で、「ここまでの筐体設計がなされていると、逆に保守担当者のケーブリング対応が大変なのでは?」(山口氏)といった質問も。しかし、その点も織り込み済みであり、「保守サービスを手掛けるNECフィールディングの担当者に設計・開発の段階から参加してもらい、『実際にケーブリングができるか、しやすいか』も検証して設計した」(NEC多和田氏)という。省電力だけではなく、従来同様、運用・保守にも万全のこだわりをもって開発したというわけだ。
必要なとき、必要なだけ、迅速にITリソースを使えるクラウド基盤が、省力化・効率化のカギとなることを疑う人は、もはやいないだろう。しかし、まずは基盤を支えるハードウェアの無駄を徹底的に排除しなければ、クラウドの効用は大きく損なわれてしまう。仮想化によるサーバ集約にしても、サーバが無駄な電力を消費しているようでは意義が半減してしまう――この点は、意外にも盲点になりがちなのではないだろうか。
今回、紹介されたNECの省電力化への取り組み、そして新開発した省電力サーバに対する節電へのきめ細かなこだわりから、ブロガーらも“足元を固める”ことの重要性をあらためて認識したようだ。皆さんも、自社のIT基盤を支えるハードウェアを、あらためてチェックしてみてはいかがだろうか。もはや限界と思われていた省力化・効率化の大きな可能性が、そこに見つかるかもしれない。
関連リンク
関連記事
- 40度の室温でも安定稼働するサーバ/ストレージを発表 NEC(ITmediaエンタープライズ)
- データセンターの消費電力を最大30%削減 NECのサーバ/ストレージ新製品(TechTargetジャパン)
- NEC、Cloud Platform Suiteの新製品を発表(@IT)
- NECがサーバ製品ラインを2つに分割(@IT)
●特集INDEX● |
|
| 【第1回】 クラウド基盤を支えるハードウェア設計へのこだわり |
|
| 【第2回】 NECがWebSAMに込めたクラウド運用管理へのこだわりとは? |
|
| 【第3回】 クラウド時代に求められるネットワーク サーバのようにネットワークも仮想化できる |
|
