
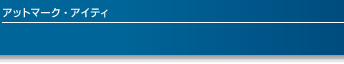
 |
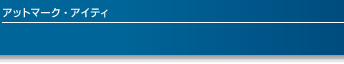 |
@IT|@IT自分戦略研究所|QA@IT|イベントカレンダー+ログ |
|
Loading
|
| @IT > SPSS Open House 2004 イベントレポート前編 |
| 企画・制作:アットマーク・アイティ
営業企画局 掲載内容有効期限:2004年12月19日 |
|
|
|
|
|
2004年11月9、10日の2日間にわたり「SPSS Open House 2004」が開催された。会場となった東京ドームホテル(東京・水道橋)では、基調講演、パネルディスカッション、SPSSの最新ソリューションのデモンストレーションなどに加えて、ユーザー企業の実践事例報告、大学研究者による研究発表、チュートリアル・セミナー、ハンズオン・ワークショップなど、多彩な内容で構成された合計33のセッションが組まれ、1200名以上もの参加者が来場。あちらこちらに設置されたデモブースにも人だかりができ、会場は熱い熱気に包まれていた。
同イベントは、来日したSPSS米国本社社長、ジャック・ヌーナン氏のあいさつを皮切りに始まった。ヌーナン氏は、参加者への謝辞を述べると同時に、2週間前にラスベガスで世界規模のユーザー会が開催され、先進的なユーザー企業を表彰するSPSS賞の最優秀賞に、「ギャガ・デジタルブレイン」(SPSS製品導入事例探求シリーズ第4回)が選ばれたことを報告した。それでは、基調講演を含め、いくつかのセッションについて、概要をご紹介していこう。
ジャック・ヌーナン氏に続いて、和田充夫氏が基調講演を行った。和田氏は、消費者が「生きる消費者」から「生活する消費者」へと大きく変貌していることを指摘。これまで主体であった「生きる」ために必要な消費は、「生活の豊かさを演出する」ための消費へとシフトしており、各個人が追求する「ライフスタイル」がキーワードであるという。以前のように、消費者全体が同質の需要(ニーズ)を持っているという「マス的な考え方」はもはや通用しないこと、したがって、市場全体の傾向を見るトレンドデータではなく、顧客セグメントベースのデータ、また、性別、年齢といったデモグラフィックデータではなく、ライフスタイル・データを見ることの重要性を説く。
「すでに周囲にモノがあふれている現代には“潜在需要”というのは存在しておらず、いわば“無需要(ニーズがない)”状態にあります。ですから、潜在需要に適合した商品を開発するというこれまでの考え方を改め、企業と顧客が『相互作用化(インタラクト=“interact”)』することによって新たなニーズを共に創り出す、すなわち“共創”することが必要となります」(和田氏)。これが「関係性マーケティング」の基本的な考え方である。 和田氏は、「価値共創」を実現する関係性マーケティングは、すでに生産財マーケティングやサービス・マーケティングでは実践されてきているが、最大の課題は、企業対特定多数(BtoC)、あるいは顧客間(CtoC)の関係性をどう作り上げるかだと指摘する。そのためには消費者の生活行動をいかにトレース(追跡)し、いかにインボルブ(関与)させ、いかにインタラクト(双方向の対話)に持っていくかということを考えなければならない。 PCや携帯電話などを通じ、インターネット上で消費者とのインタラクティブ・コミュニケーションを促進することができるいまこそ、企業と多数の消費者との間で価値の共創・共有が可能になるよう、時間的・空間的な場作りを工夫すべきであると和田氏は強調する。インターネットという特異な環境が、従来のマーケティング手法を単に手直しするに止まらず、大きく回転させる。すなわち「マーケティング・リボリューション」を起こすことができる、と述べて、和田氏は基調講演を締めくくった。
2日間を締めくくるプログラムとして、パネルディスカッションが行われた。コーディネーターは和田充夫氏である。まず、各社の取り組みについて、それぞれのパネリストから概要が説明された。
朝稲氏は、TSUTAYAのオンライン戦略について次のように語る。「TSUTAYA Online」では、リアル店舗への集客施策として、オンラインで半額クーポンを発行している。これは、携帯電話のディスプレイに半額クーポンを表示させ、それを店頭で見せることで割引が受けられるものである。しかし、ユーザーがクーポンを利用する際の気恥ずかしさや、また、その販促効果に対して当初、フランチャイズ店舗側の理解を得るのが難しく普及させるのが大変だったという。しかし、今ではクーポンの有効期間中には、10人のうち6人がクーポンを利用するほどの人気となっており、また、クーポン利用結果のデータを示すことで販促効果に対するフランチャイズ店の理解が得られたことから、現在は、ほぼ全店舗(約1150店)で展開されるようになった。 一方、リアルな場としての店舗においては、その保有会員数1840万人(2004年3月現在)という集客力を活かし、TSUTAYA Onlineの会員獲得促進を図っている。このおかげでTSUTAYA Onlineの会員数は、485万人(2004年3月現在)にまで増加したという。このように、TSUTAYAでは、クリック(オンライン)とモルタル(リアル店舗)の両者のシナジー効果を狙っていることが最大の特徴であるという。 朝稲氏は、今後の課題として「TSUTAYA Online」の自立を挙げる。すなわち、TSUTAYA Online自体をEコマースサイト化して収益を上げることを図っているという。現実的な問題として、数百万人のオンライン会員を維持するためのコストは、来店促進や消費喚起といった販促機能だけではカバーできないからだ。 次いで久保田氏が携帯電話の進化の方向性について、過去からの変遷を踏まえ説明を行った。携帯電話は当初、音声需要を満たす製品として普及したが、1999年2月の「iモードサービス」の開始により、「マルチメディア化」が進んだ。そして2004年7月、ICカード機能搭載端末、いわゆる「お財布ケータイ」の登場によって、「生活ツール化」していく流れにあるという。これからは、リアルとの連携、すなわち、コンサートチケットやフィットネスクラブの会員証、ポイントカード、マンションの入退室管理などへの応用が進む見通しだそうだ。 また、NTTドコモでは、CRMに積極的に取り組んでいるという。契約者の情報、利用情報、インフォメーションセンター(コールセンター)での対応履歴情報などを基幹システムのDBからデータウェアハウスおよびマイニングサーバに移し、顧客の解約を防止するための「顧客行動予測モデル」を開発、具体的な解約防止アクションに結び付けているそうだ。 ソニーファイナンスの取り組みについて吉田氏が紹介したのは「eLIO」である。「eLIO」はソニーの非接触ICカード技術「FeliCa」を利用したオンライン決済サービスである。「eLIOカード」とPC用のカードリーダー「パソリ」などを利用することで、インターネット経由でも安全なクレジット決済を行うことができる。通常のクレジットカード決済と異なり、カード番号などのデータをオンライン上でやり取りしないため、安全性が高いのが特徴だという。 また、すでに発売が始まっている「モバイルFeliCa対応携帯電話」では、FeliCaとiアプリの機能を利用してオンラインで購入した商品と連動したクーポンを携帯電話の画面に表示するといったことが可能になっている。こうした販売促進ツールとしての利用方法を紹介し、今後のソニーファイナンスの取り組みの方向性を示してくれた。 澁谷氏は、ネット環境における特徴的なマーケティング実践例として「口コミサイト」を取り上げ、研究者としての立場から論じた。特に注目すべき特徴として、ネット上での口コミは「会話しない」「交友しない」「見ているだけ(ROM)」「趣味や価値観が合う人の意見に影響を受ける」という点を指摘した。 「趣味や価値観が合う人の意見に影響を受ける」という特徴について、澁谷氏は次のように説明する。
「人は同じような考え方、価値観を持っていると感じる他人からの意見に影響を受けるものである。したがって、『口コミサイト』では、他人がどんな意見を述べているかという「意見情報」と同時に、その意見を述べている人の『属性(どんな人物か)』を知ることができるということが重要である。また、掲示板などのコミュニティをネット上に展開する場合においては、できるだけ絞り込まれた属性でのコミュニティを形成することが“口コミ”を誘発する上で効果的なのではないか」(澁谷氏) コーディネーターの和田氏は、パネリストそれぞれの組織が持つ強みを活かして展開しているインターネット上での取り組みを評価しつつ、今後の展開についてさらにコメントを求めた。 朝稲氏は、澁谷氏の口コミについての研究、特に消費者間のコミュニティの重要性を再認識したという。また、久保田氏は、携帯電話が今後ユーザーとコンテンツ/商品/サービスという3者との時間や空間における結び付きを深めるだろうという見解を示した。具体的には、ある特定の時間、場所において最適な情報をレコメンデーションしたりするというものである。一方、吉田氏はクレジットカードを通じた顧客情報を保有する同社が、ソニーグループ企業のシナジー効果を発揮できるような役割を担っていくだろうという可能性を示唆していた。そして、澁谷氏は、PCからのアクセスと携帯端末(モバイル)からのアクセスとでは、インターネットの利用形態が異なっている点を指摘し、PC、モバイルのどちらから利用されるかによって、コンテンツやサービスの内容を変えていく必要性があると強調した。 和田氏は、インターネット環境においても、やはり消費者をどうとらえるか、特に「one to many」の取り組みが今後の課題であり、PC環境、モバイル環境における消費者行動の分析の重要性とSPSSソリューションに対する期待を示してパネルディスカッションを終えた。
村田氏の講演はこれまでにない熱い意気込みが感じられるものとなった。SPSSが同社のコア・コンピタンスとして提唱してきた「Predictive Analytics」を実現する製品群をいよいよ日本のユーザーにも提供できる段階になったからであろう。 近年の経営課題は、過去の「コスト削減」から「利益の最大化」や「顧客の満足向上」へと変遷してきていると村田氏は指摘する。「Predictive Analytics」はこれらの課題に応えるものであり、分かりやすくいえば、“次に起こることを今知ること”であるという。すなわち、顧客が求めているものを「発見」し、顧客の行動を「予測」し、そうしたナレッジをマーケティングの現場に適用することで、顧客との関係性から生まれる「収益を最大化する」というものだ。 今回は、「Predictive Analytics」の成功事例として2社の事例を紹介するとともに、本邦初公開となる製品「Predictive Applications」のデモが村田氏自らの手によって行われた。
事例紹介に続き、「Predictive Applications」と呼ばれる製品群の特徴を説明するためのデモンストレーションが披露された。村田氏は、Aegonが採用している「Predictive Call Center」の画面を実際に操作しながら説明を行ったが、機能性と操作性の両者において高い品質を達成している製品だという印象を受けた。
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||