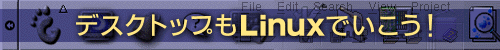
第5回 Linuxの印刷設定で七転八倒
|
宮原徹
2001/7/31
前回、Windowsで作成した文書を、Linux用オフィスソフトで程度見られることは確認したので、次は最終的な印刷物にするところまでをやってみたいと思う。
私のオフィスのプリンタは、キヤノンの「LBP-350」というモノクロレーザープリンタ。Windows 2000 ServerにUSBで接続して、プリンタを共有できるようにしてある。このプリンタをLinuxからも使えるようにするのだ。
Turbolinuxのプリンタ設定は、rootで管理ツールのコンソールであるTurboCentro-GTからturboprintcfgツールを起動する。このツールでプリンタの追加を選択すると、プリンタの種類を以下の3つから選択できる。
- ローカルプリンタ
マシンのパラレルポートに直接接続されているプリンタに出力する
- リモートLPDキュー
ネットワーク上にあるLPD(LPDはUNIX系の標準的なプリンタ出力方法)プリンタに出力する
- Samba/LAN Managerプリンタ
Windowsのファイル/プリンタ共有に使用されるSMBプロトコルを使って、Windowsネットワーク上のプリンタに出力する
まずは、現在の状態を変更しないで済む3番目の「Samba/LAN Managerプリンタ」の設定を行ってみる。設定項目は、
- NetBIOSホスト名
Windowsの「マイ ネットワーク」で表示されるマシン名を指定する
- リモートシェアネーム
Windowsで設定した共有名
- リモートIP/ホスト名
NetBIOSホスト名の名前解決の代わりに、ここで指定したホストに接続する
- ユーザー名・パスワード
ホストに接続する際に使用するユーザー名とパスワード
となっているので、現在利用しているWindowsクライアントの状態をベースに入力していく。プリンタは、幸いにもTurbolinuxのリストの中に使用している機種が見つかったのでそれを選択。リストはかなり充実している。このあたりは、海外製品ばかりがリストに並べられていた以前に比べて大きく改善された点だと思う。
設定が終わったので、早速前回利用したHancomSheet(表計算ソフト)を起動して印刷してみる。しかし、ウンともスンともいわない。そこで、とりあえず問題点を確認するために、LinuxからWindowsへ接続するsmbclientコマンドをいじってみることにする。
まずはファイル共有の確認。接続できない。どうやら指定しているホスト名の名前解決ができていないようだ。IPアドレスで接続先を指定する-Iオプションを使ってみると、今度は接続できた。そこで、smbclientコマンドで共有プリンタに接続し、ローカルドライブに作成しておいたテキストファイルを印刷するように指定してみたが、データの転送はしているようだがプリントアウトされない。
とりあえずネットワーク経由での接続はあきらめて、ローカル接続に切り替えることにする。プリンタをLinuxマシンにパラレルケーブルで接続し、/dev/lp0で出力するようにturboprintcfgで設定を変更した。出力テストに使うのはlprコマンドだが、これまたうまくいかない。原因を探るためにlpcコマンドでstatusをチェックすると、どうもハードウェアレベルでプリンタを認識できていない旨のエラーが出ている。
ケーブルの接続はしっかりしているのでBIOSレベルでの問題と推定し、一度マシンをシャットダウンしてBIOSセットアップ画面を呼び出してみた。BIOSではパラレルポートの転送モードが「STANDARD」になっていた。「標準で問題ないだろうに」と思いつつ、「Bi-directional」モードに変更。PCを再起動してみると、いきなりプリンタがうなり出してテスト出力したページがプリントアウトされたのだった。
Linuxからプリンタへのルートが開通したので、いくつかのアプリケーションでチェックをしてみよう。まずはLinuxの(というかGNOMEの)「メモ帳」的存在であるgEditエディタ。問題なし。まあ、テキスト情報をlprコマンドに投げているだけだから、すでに検証済みのようなものである。次にHancomSheetで実験。すると、前回紹介した「¥」(円マーク)が「バックスラッシュ」になってしまう問題が、ここではなぜか「W」に横棒(韓国通貨の「ウォン」?)になって表示されてしまうのだ。
次はHancomWord。前回作成した見積書を印刷してみることにする。ファイルを開いて印刷しようとすると「デバイスドライバを使用できません」のエラーが。そこで「プリンタ設定」からドライバを追加する。PostScriptで出力し、プリンタドライバのフィルタを通すとプリンタ用のイメージに変換して出力されるという具合だ。画面に表示されている「バックスラッシュ」がそのまま「バックスラッシュ」で印刷されるのは、イメージを変換しているせいだろうか。いずれにせよ、このままでは駄目なのだが……。
弱いといわれているLinuxの印刷環境だが、それほど大きな問題があるとは思えない結果となった。とりあえず、「lprを使ってプリンタへ出力する」という基本的な部分は確立されているのだから。では、問題となる部分はどこか。最大のポイントはプリンタドライバであろう。今回使用したのは、たまたまメジャーなメーカーのプリンタであり、かつ偶然にもディストリビューションがサポートしている機種であった。サポートされていたのは、現状では残念ながら「必然」ではなく「偶然」である。
もう1つは、同じメーカーのオフィスソフトでありながら、プリント環境設定が異なっている点が挙げられる。もちろん作り方の問題であるのだが、準拠しなくてはいけない「標準的な」プリント環境設定の方法が決まっていないところに大きな問題がある。確かにPostScript(GhostScript)といった標準的な技術はあるものの、より簡単で幅広くアプリケーションが準拠できる「標準」の不在が影響しているような気がする。
このあたりを改善するために、例えばミラクル・リナックスは大手プリンタメーカーと共同で「MLDPS(Miracle Linux Document Portal Server)協議会」を発足し、APIの標準化とともにLinux用ドライバの開発を促進しようと考えている。具体的な成果が出てくるのはまだ先ということであるが、期待したい。
ただ、現状においてLinuxで完結したドキュメント・プロセッシング環境を構築するのは難しいといわざるを得ないであろうか。例えば、Linux上で動作するプレゼンテーションソフトとして幅広く利用されている「MagicPoint」も、PowerPointなどのWindows用ソフトに比べて印刷機能が弱く、配布資料の作成に苦労することが多い。「見た目」を重視しなくてはならない機能の部分に関しては、やはりオープンソース開発モデルにおける制約が出てきているということなのであろうか。
統一化されたインターフェイスによる簡単なプリンタ設定と、アプリケーションから使いやすいプリンティングAPIの欠如がLinuxの大きな課題であることは間違いないのではないだろうか?
夏の雷に備えてUPSを付けた 夏の雷による瞬停(注)からPCを守るためにUPSを取り付けた。「男はやっぱり黒でしょう」ということで三菱電機製の黒い縦置き型を選択。 夏の雷による瞬停(注)からPCを守るためにUPSを取り付けた。「男はやっぱり黒でしょう」ということで三菱電機製の黒い縦置き型を選択。UPSの取り付けだが、いままで電源タップにつないでいた電源ケーブルをUPSのコンセントに差し、シリアルケーブルでUPSとPCを接続。あとは三菱電機のUPSのページから自動シャットダウンソフト(無償)をダウンロードしてインストール。 作業自体はごくごく簡単なのだが、1つだけ問題が。ソフトの設定時に指定するシリアルポートが、デフォルトでは/dev/ttyS0になっている。PCにはシリアルポートが1個しか付いていないので当然これだろうと思いきや、正常に動かない。そこで/dev/freqship/UPSFILEを変更して/dev/ttyS1を指定してみると無事に動き出した。このマシンの/dev/ttyS0はどこにいってしまったのだろう?
|
|
||||||||||||||||||||||
| 連載 デスクトップもLinuxでいこう! |
- 【 pidof 】コマンド――コマンド名からプロセスIDを探す (2017/7/27)
本連載は、Linuxのコマンドについて、基本書式からオプション、具体的な実行例までを紹介していきます。今回は、コマンド名からプロセスIDを探す「pidof」コマンドです。 - Linuxの「ジョブコントロール」をマスターしよう (2017/7/21)
今回は、コマンドライン環境でのジョブコントロールを試してみましょう。X環境を持たないサーバ管理やリモート接続時に役立つ操作です - 【 pidstat 】コマンド――プロセスのリソース使用量を表示する (2017/7/21)
本連載は、Linuxのコマンドについて、基本書式からオプション、具体的な実行例までを紹介していきます。今回は、プロセスごとのCPUの使用率やI/Oデバイスの使用状況を表示する「pidstat」コマンドです。 - 【 iostat 】コマンド――I/Oデバイスの使用状況を表示する (2017/7/20)
本連載は、Linuxのコマンドについて、基本書式からオプション、具体的な実行例までを紹介していきます。今回は、I/Oデバイスの使用状況を表示する「iostat」コマンドです。
|
|




