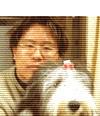
一志達也のSE、魂の叫び [7]
システムがもたらす幸せと不幸せ
一志 達也(ichishi@pochi.tis.co.jp)
TIS株式会社
2001/7/25
コンピュータを用いたシステムは、人間が楽をするため、より便利に生活や仕事をするために用いられる。こんなことはいまさらいうまでもないのだろうが、それが時として疑問に変わることはないだろうか。「このシステムって、本当に便利なのだろうか?」と感じる瞬間。疑問に感じる瞬間。筆者には少なからずそれがある。
避けて通れないシステムたち
筆者の勤めるようなIT関連企業でなくても、いまやオフィスにはコンピュータがあふれかえっているだろう。1人1台ずつのクライアントコンピュータと、それらがアクセスする多くのサーバコンピュータ。そこには、多くの業務をシステム化したものが搭載され、何をするにもコンピュータを使うことを強制される。例えば、勤怠管理や旅費清算そして何か物を買うための稟議決済もそうだ。すべては会社で決められたシステムを通じて行わねばならず、ほかの手段は許されない。
それでなくても、現代の日本(特に都心)で生きる者は、多くのコンピュータシステムに触れざるを得ない。電車の切符1枚買うにもコンピュータシステムのお世話になっている。改札機さえもコンピュータシステムとしか思えないし、銀行も病院もすべてがそうである。
自分でオペレーションしなくとも、日常生活を送るうえで多くのコンピュータシステムを間接的に利用しているのも事実だ。ビデオを借りるにしても、スーパーマーケットで買い物をするにしても、そこにはコンピュータシステムが介在する。これらは、いまや逃れられない、避けて通れないコンピュータシステムなのである。
便利じゃない人
では、これらのシステムによってすべての人が便利になっているのだろうか。楽ができ、仕事や生活の助けとなり、有益に働いているのだろうか。
少なくとも、先に挙げた筆者のオフィス内で活躍しているシステムに関しては、そうとはいいきれない。筆者のように、入力させられる(あえて「させられる」といおう)立場からすれば、面倒なだけで不便だと感じる人が少なくない。
勤怠管理なら、もっと軽快に動くExcelではダメなのか、稟議決済など手書きして持って回った方が早いのではないか。システムが統合化されていないため、普段利用しないシステムはどこにあるやらどうするものやら分からない。それにパフォーマンスが悪い、例外的な事態に対処できない、などなどの不満がある。システムの使い方が分からず、処理方法も知らず、結局知っている人を探し回るのは筆者のオフィスで日常的に見かけられる姿だ。
また、日常生活で避けて通れない多くのコンピュータシステムもそうだ。筆者のような世代で、しかも日ごろから慣れていればともかく、切符を買うにも乗り越し清算をするにも戸惑っている人を頻繁に見かける。いつからか新幹線の改札まで自動化されたが、行楽シーズンになれば、使い方の分からない人で大渋滞を起こす。
銀行は、ATMを使って振り込みをさせようと手数料まで値下げしているが、筆者の祖母にできるとは思えない。飛行機の搭乗手続きにしても、新幹線の座席予約にしても、いまだに人間のいる窓口の方が大人気だ。
日常生活にしても会社内にしても、システムがすべての人に歓迎されている例は珍しい。
便利な人
もちろん、だれにも歓迎されないシステムならば、そんなものはなくなってしまった方がいい。だれかが、そのシステムを「便利だ」「有益だ」と感じているからこそ必要とされるのである。
筆者のオフィスのシステムの場合、勤怠管理をシステム化することで全社的に勤怠状況を一元管理できる。給与計算も簡単になるのだろうし、上司は勤務状況をどこからでも管理できるようになる。また、作業明細も書くことになっているから、細かくは把握できなくとも、コスト計算が容易になっている。入力する方には不便なものでも、そのデータを活用する側にとってはなくてはならないシステムなのだ。
他方、電車や飛行機の場合、銀行の場合はどうだろう。当然ながら、こうしたシステムの導入には企業側の省力化やコストの削減がもくろまれている。そして、「サービスの向上」というのも主目的の1つにされているはずだ。これが実は問題で、自動化によって便利と思う人と思わない人がいる。窓口に並ぶことなく、素早く目的を果たすことができる。そう感じる人がいれば、使いにくいと感じる人もいるからだ。
お金とサービスと興味
「システムがすべての人に歓迎されている例は珍しい」と結論付けるのは簡単だし、それをシステムの宿命といってのけることもできる。だからといって、本当にそれでいいのだろうか。ここに挙げた例は、社会的であったり、大企業の中だけの問題だ。しかし、もっと身近なところ、特にSEたちが日ごろかかわるシステム構築ではどうだろう。
システムが導入された後のことまで考えているだろうか。そのシステムによって、だれがどう便利になり、だれがどんな負担を強いられるのか。それを覚悟のうえでも導入しなければならないのか。だれかが不便に感じ、負担に感じるのであれば、その問題を少しでも解決する手段を用意しているだろうか。
筆者は、何でもコンピュータで解決すべきなのか、といつも考えている。コンピュータでシステムを作るのも人間なら、それを使うのも人間。結局のところ、人間の手を介さなければコンピュータは何もできないのである。時には人手の方が有利なこともある。
余談になるが、中国ではコンピュータを使って世の中を便利にすることを良しとしないそうである。なぜなら、コンピュータで便利になる代わりに人が働く機会を喪失するからだそうだ。人が働いて済むことはコンピュータを使ってまでやらない、という感覚に筆者は感心した。
IT業界で働く1人でありながら、筆者はときどき、日常生活のうえで思うことがある。これを作るために、いくらかかったのだろう。それよりも人間を4人配置した方がよほど安上がりで、混乱を避けられるのではないか。顧客にとって、その方がサービスになるのではないだろうかと。
システム構築の現場では、時としてコンピュータを使い、システムを構築することに集中しすぎることがある。そうなると、本来の目的や必要性を見失う。そこに必要な金額やサービスを忘れ、場合によっては興味だけが優先したシステムが作られる。
コンピュータは、人間にさまざまなメリットをもたらすが、それには何らかの代償が付きまとうこと。人によって考え方も感じ方も違うこと。必ずしも自動化やシステム化がいい結果を生むとは限らないこと。それを忘れることなく、システムがより多くの人にとって便利になるように、そうでない人にも受け入れられるように。そんな企画や提案を行い、構築時にもそれを忘れないようにしようではないか。システム構築に携わるすべての方々と自分自身に対し、そう願ってやまない。
| 筆者紹介 |
 一志達也 一志達也1974年に三重県で生まれ、三重県で育つ。1度は地元で就職を果たしクライアント/サーバシステムの構築に携わるも、Oracleを極めたくて転職。名古屋のOracle代理店にてOracle公認インストラクターやサポートを経験。その後、大規模システムの開発を夢見て再び転職。都会嫌いのはずが、いつの間にやら都会の喧騒にもまれる毎日。TIS株式会社に在職中。Linux Squareでの連載をはじめ、月刊Database Magazineでもライターとして執筆するほか、Oracle-Master.orgアドバイザリー・ボードメンバー隊長など、さまざまな顔を持っている。無類の犬好きで、趣味は車に乗ること。 |
| 連載 一志達也のSE、魂の叫び |
- 【 pidof 】コマンド――コマンド名からプロセスIDを探す (2017/7/27)
本連載は、Linuxのコマンドについて、基本書式からオプション、具体的な実行例までを紹介していきます。今回は、コマンド名からプロセスIDを探す「pidof」コマンドです。 - Linuxの「ジョブコントロール」をマスターしよう (2017/7/21)
今回は、コマンドライン環境でのジョブコントロールを試してみましょう。X環境を持たないサーバ管理やリモート接続時に役立つ操作です - 【 pidstat 】コマンド――プロセスのリソース使用量を表示する (2017/7/21)
本連載は、Linuxのコマンドについて、基本書式からオプション、具体的な実行例までを紹介していきます。今回は、プロセスごとのCPUの使用率やI/Oデバイスの使用状況を表示する「pidstat」コマンドです。 - 【 iostat 】コマンド――I/Oデバイスの使用状況を表示する (2017/7/20)
本連載は、Linuxのコマンドについて、基本書式からオプション、具体的な実行例までを紹介していきます。今回は、I/Oデバイスの使用状況を表示する「iostat」コマンドです。
|
|




