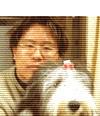
一志達也のSE、魂の叫び [10]
臆病なベテランSEと大胆な新人SE未満
一志 達也(ichishi@pochi.tis.co.jp)
TIS株式会社
2001/10/3
今回は、筆者が仕事用に購入したPCサーバが発端となった話をしようと思う。
以前にもこのコラムで書いたと思うが、筆者が勤務するような大手SI企業であっても、自由に使えるUNIXサーバの確保は難しい。業務(プロジェクト)で利用するサーバならともかく、勉強用・実験用というような目的で数百万円もするハードウェアを用意することなど、やすやすと許されるものではない。それに、置き場所の確保だって容易ではない。もちろん、ピザボックス型などの省スペースUNIXサーバも存在する。安価なものを選べば、100万円以下で購入することもできるだろう。しかしながら、それでも商用UNIXを自分の自由にするのは難しいものなのである。
今回筆者が購入したPCサーバにOSはプリインストールされていなかった(つぶやき:OSインストール未経験者が増えている)。当然、電源を入れてもウンともスンともいわない。できればすぐさまセットアップにかかりたかったのだが、筆者は最近多忙を極めていてその時間を捻出するのが難しい。そのとき、ふと周囲を見渡すと、配属間もない新人数名と少し前に入手していたMiracle Linuxのパッケージが視界に入ってきた。
新人さんにインストールできるのか!?
筆者の脳裏には、1つのアイディアが浮かび上がった。「配属間もない新人に、PCサーバとLinuxパッケージを与えるとどうなるんだろう」。
早速教育担当者に相談すると、それほど重大な課題があるわけでもなく、本人たちも勉強に飽きていたらしく興味津々。話は決まった。
開梱を待っているPCサーバを引き渡し、「3日以内に、組み立てからインストールまですべて終えるように」と指示を出した。ただし、そのまま利用するわけではなく、あくまでも配属後研修の一環だから、うまくできなくても構わないと付け加えてだ。
彼らは、多少戸惑いながらもMiracle Linuxのパッケージを受け取り、「やってみます」と答えた。始めのうちは新人たちがワイワイい言いながら(新人は4人いる)開梱して組み立て始めるのを見ていたが、自分の業務に取り掛からねばならず、そのまま3日間が過ぎた。
できたはできたけど……
翌週出社してみると、空いていたはずのデスクにPCサーバが置いてある。新人の1人を捕まえて「インストールはできたか?」と聞いてみると、「できましたよ。Oracleも動いてます」というではないか。これには、さすがに筆者も驚いた。
先輩諸氏に迷惑をかけぬよう、分からないことはマニュアルやインターネットを使って調べるようにと指示していた。従って、きっとマウントの概念やX Window Systemの設定で戸惑うに違いない。おそらく分からないことだらけで、結局は筆者が質問攻めにあうのではないか、と覚悟していたのだ。
それが、LinuxだけでなくOracleまで動いているという。信じられない気持ちでPCサーバに向かうと、確かにそこにはGNOMEの画面があり、SQL*Plusの入力に応えてデータ操作のできるOracleが動いていた。
このような状況が作り出された要因は2つあると筆者は考察している。1つは、現在のLinuxディストリビューションが、簡単なオペレーションでTypicalインストールを実現していること。もう1つは、彼らがまだ経験の浅い新人達であったことだ(ちなみに全体教育でOracleの知識はオラクル・マスターのシルバーレベルになっている)。
前者については、最近のLinuxパッケージに触れた経験を持つ方であれば十分に納得していただけると思う。Windows系の容易さにはまだ追いついていないものの、いまやLinuxのインストールは実にイージーだ。(もちろんハードウェアにもよるが)いわゆるカスタム・インストールを望まなければ、頭を悩ませるのはX Window Systemの設定(ディスプレイの設定など)くらいである。
しかも、彼らに与えたのはマニュアルもインストール用FDも完備したLinuxパッケージ製品だ。当然といえば当然のごとく、彼らは完全にTypicalインストールを行っていた。マウントポイントやパーティションの振り分け、インストールするパッケージなどは一切考えずにインストールしたのである。
しかし、それはそれで正解なのだ。筆者は「インストールしてほしい」としか指示していない。ここにポイントがある。
完璧を望めば道は険しい
技術者というのは不思議なもので、経験を積めば積むほど臆病になりがちだと思う。なにをするにも、安易に物事を決定することを恐れ、大胆な行動がとれなくなってしまう。やたらに前提を設けたり制約を付けてみたりして、発想さえも無難になりがちになる。
その点、今回登場した彼らは非常に大胆で、「とにかくやってみよう」という意識にあふれていた。これが2年目や3年目になると、「これは何に使うんですか」だの「もう少し細かい設定情報をください」だのと、理屈を先に持っていきたがる。5年目や6年目になると、「そんなのは自分の仕事ではない」という風潮が先立ってみたりする。あるいは、完全を期すことが使命のように感じるのか、「ひとまず動けばいいや」というような発想にはならなくなる。「やってみてダメだったらやり直そう、ついでにOracleも入れてみよう」そんな発想の前に、時間に対するコストを気にしたり、これで本当にいいのだろうかという不安が先行してしまう。
何でもかんでも安易で大胆。それでは困るのも事実なのだが、それを忘れてすべてにおいて臆病になるのはもっと困る。少し発想を変えればいいのに、悩む前に聞いてみればいいのに、できるところまでやってみれば違うものが見えるかもしれないのに。そう感じることが近頃多い。未知のものに直面した中堅社員たちが、一様に何もできなくなってしまっているのを目の当たりにしているからだ。
何にでも完全な知識を身に付け、完璧なアウトプットが出せれば、それはすばらしいことに違いない。しかし、そうなるためには、できるところまでやってみなければならない。そこで知識と経験を少し身に付け、足りない部分を知ることで一歩完全・完璧に近づけるのだ。
例えるなら、Windows 2000に備えられたサービスやレジストリの内容を極められている人など滅多にいない。それでも、ちゃんと使うことができるし、普段困っていないだろう。そして、それが当たり前になっているから、そのことを気にすることは少ない。
それでいいとはいわないが、ほかのことについても同様の発想をしたら、少しは悩みが解決するのではないだろうか。筆者自身も、以前は無闇な危機感に襲われ、何をするにも不安が付きまとっていた。しかし、この答にたどり着いたとき、仕事に対する意識が変わったのを覚えている。
適度な危機感を持ちながら、適度に大胆になる。このバランスを持った技術者は、少しばかり違うのかもしれない。
| 筆者紹介 |
 一志達也 一志達也1974年に三重県で生まれ、三重県で育つ。1度は地元で就職を果たしクライアント/サーバシステムの構築に携わるも、Oracleを極めたくて転職。名古屋のOracle代理店にてOracle公認インストラクターやサポートを経験。その後、大規模システムの開発を夢見て再び転職。都会嫌いのはずが、いつの間にやら都会の喧騒にもまれる毎日。TIS株式会社に在職中。Linux Squareでの連載をはじめ、月刊Database Magazineでもライターとして執筆するほか、Oracle-Master.orgアドバイザリー・ボードメンバー隊長など、さまざまな顔を持っている。無類の犬好きで、趣味は車に乗ること。 |
| 連載 一志達也のSE、魂の叫び |
- 【 pidof 】コマンド――コマンド名からプロセスIDを探す (2017/7/27)
本連載は、Linuxのコマンドについて、基本書式からオプション、具体的な実行例までを紹介していきます。今回は、コマンド名からプロセスIDを探す「pidof」コマンドです。 - Linuxの「ジョブコントロール」をマスターしよう (2017/7/21)
今回は、コマンドライン環境でのジョブコントロールを試してみましょう。X環境を持たないサーバ管理やリモート接続時に役立つ操作です - 【 pidstat 】コマンド――プロセスのリソース使用量を表示する (2017/7/21)
本連載は、Linuxのコマンドについて、基本書式からオプション、具体的な実行例までを紹介していきます。今回は、プロセスごとのCPUの使用率やI/Oデバイスの使用状況を表示する「pidstat」コマンドです。 - 【 iostat 】コマンド――I/Oデバイスの使用状況を表示する (2017/7/20)
本連載は、Linuxのコマンドについて、基本書式からオプション、具体的な実行例までを紹介していきます。今回は、I/Oデバイスの使用状況を表示する「iostat」コマンドです。
|
|




