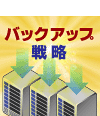
いまどきのサーババックアップ戦略入門(5)
アプリ対応で進化したバックアップ技術を使う
株式会社シマンテック
成田 雅和
2008/1/16
 Exchange Serverデータの個別アイテムのリストア
Exchange Serverデータの個別アイテムのリストア
従来Exchange Serverのバックアップは情報を格納する記憶領域(ストア)単位での処理が中心であった。バックアップはシステム障害からの復旧が主目的であり、ユーザーの誤操作などで削除されたメールやフォルダの復旧は対象としていなかった。それは、記憶領域単位でのリストアとなるため操作が複雑になり、リストア用のリソースも追加で必要になるなどの問題があったからである。
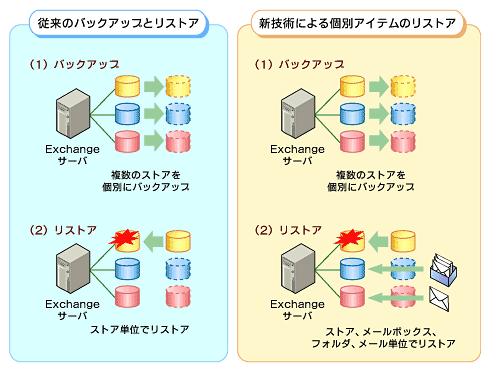 |
| 図2 Exchange Serverのバックアップ手法の進化 |
しかし、バックアップソフトウェアのExchange用エージェントの進化によりこれらの問題が解消し、個々のアイテムを対象としたリストアができるようになってきている。個々のアイテムをリストアする設定をいくつか行い、バックアップを実行する。リストアの際には、あたかもファイルサーバをファイル単位でバックアップしリストアするように、個々のアイテムを探してリストアを選択するだけでよい。
こうした新技術により、Exchange Serverにおける個々のアイテムのRTOは、数時間〜数日から、数十分程度へと劇的に改善されたことになる。これまで、RTOが数日では現実的でないため、実際には個々のアイテムのリストアは実施してこなかった組織もあるだろう。ユーザーの誤操作による削除だけでなく、監査目的のために特定データのみをバックアップから取り出すといった要件も増えてきている。このような場合、まず記憶領域をリストアしてから個々のアイテムを取り出すといった、長時間の作業を実施する余裕がない場合も出てくるだろう。このような、より粒度の高いリストア要件に対する策が必要な場合に有効な新技術である。
 仮想サーバのバックアップ
仮想サーバのバックアップ
仮想OS環境は、近年急激に利用が拡大している分野である。テスト環境、開発環境のみならず、本番環境においても仮想OSを使用したITサービスを提供するということが珍しくなくなってきている。仮想サーバの利用はもともと、CPUやメモリ、ネットワークなどのハードウェア資源の利用率向上といった、サーバ設備そのもののコストダウンが主目的だった。しかし、仮想環境の利用が拡大するにつれ、仮想サーバのバックアップに関する効率化やコストダウンも必須の要件となってきている。
従来、仮想環境は、(1)ホストOS上で仮想OSのデータ一式をファイルとしてバックアップする(ホストOSからは各仮想OSとその上のデータが1つのファイルとして見えることを利用する手法)、(2)仮想OSのそれぞれをクライアントとしてバックアップする(各仮想OSをバックアップ対象のサーバに見立て、それぞれでバックアップエージェントを稼働する)、のどちらかであった。
ホストOS上でのバックアップは、一括して行うことができるという長所と引き換えに、バックアップ実施の際には仮想OSの動作を止めてデータ静止点を作る必要がある上、仮想OS上ではファイル単位のリストアができず、ディスクボリューム単位でのリストアとなってしまうという短所があった。逆に仮想OSでバックアップを行う場合には、仮想OS上の個々のファイルがリストアできる代わりに、複数のバックアップを管理運用しなければならず、その煩雑さと負担が課題となっていた。
さらに、OS領域などは同じデータであるにもかかわらず、どちらの方法でバックアップするにしても複数回バックアップしてしまうことになり、そのデータ量も問題となっていた。
バックアップの新技術はこれらの問題を解決しつつある。バックアップの方式については、ホストOSのAPIを利用し、ホストOS上で仮想OSを停止することなくバックアップを取得できるようになり、かつ、そのバックアップから仮想OS上の個々のファイルをリストアできるようになった。また、第3回で紹介した重複排除の技術を併用することで、仮想OSのOS領域のバックアップも、複数個のデータを保管することなく最少量のデータのみを記録しておくことができるようになった。
2/3 |
| Index | |
| アプリ対応で進化したバックアップ技術を使う | |
| Page1 OSのバックアップにおける進化 |
|
| Page2 Exchange Serverデータの個別アイテムのリストア 仮想サーバのバックアップ |
|
| Page3 「アーカイブ」の意味の変化 暗号化ニーズにどう対応するか |
|
- Windows 10の導入、それはWindows as a Serviceの始まり (2017/7/27)
本連載では、これからWindows 10への移行を本格的に進めようとしている企業/IT管理者向けに、移行計画、展開、管理、企業向けの注目の機能について解説していきます。今回は、「サービスとしてのWindows(Windows as a Service:WaaS)」の理解を深めましょう - Windows 10への移行計画を早急に進めるべき理由 (2017/7/21)
本連載では、これからWindows 10への移行を本格的に進めようとしている企業/IT管理者に向け、移行計画、展開、管理、企業向けの注目の機能を解説していきます。第1回目は、「Windows 10に移行すべき理由」を説明します - Azure仮想マシンの最新v3シリーズは、Broadwell世代でHyper-Vのネストにも対応 (2017/7/20)
AzureのIaaSで、Azure仮想マシンの第三世代となるDv3およびEv3シリーズが利用可能になりました。また、新たにWindows Server 2016仮想マシンでは「入れ子構造の仮想化」がサポートされ、Hyper-V仮想マシンやHyper-Vコンテナの実行が可能になります - 【 New-ADUser 】コマンドレット――Active Directoryのユーザーアカウントを作成する (2017/7/19)
本連載は、Windows PowerShellコマンドレットについて、基本書式からオプション、具体的な実行例までを紹介していきます。今回は、「New-ADUser」コマンドレットです
|
|




