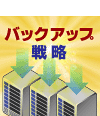
いまどきのサーババックアップ戦略入門(5)
アプリ対応で進化したバックアップ技術を使う
株式会社シマンテック
2008/1/16
サーババックアップの今日的なあり方を探る連載の最終回として、OSのバックアップ、復旧やデータのアーカイブおよび暗号化、Exchange Serverや仮想環境への対応など、バックアップ技術の進化で広がる選択肢について解説する
最終回となる今回は、OSやアプリケーションデータのバックアップの手法における最近の進化について解説していく。OSのバックアップ、Exchange Serverのバックアップ、仮想サーバのバックアップ、アーカイブ、暗号化について順に紹介する。
 柔軟なOS復旧の実現
柔軟なOS復旧の実現
第3回でも触れたが、OSの完全なバックアップは「コールド」状態で実施するというのが従来は一般的であった。Windows系OSは無論のこと、UNIX系OSでもシングルユーザーモードで実施するのが最も安全ということである。
だが、「コールド」状態でのバックアップは完全で安全であるものの、(1)自動化が難しく定期的なバックアップ実施が困難、(2)OSバックアップデータをリストアするために、最小限とはいえOS自身とリストアツールが必要、(3)ハードウェア障害の際などに異なる構成のハードウェアへのOSリストアが必要な時があるがそのような構成にOSをリストアしても正常に動かないことがある、(4)そもそも「コールド」状態にできる時間枠がとれない、などの問題があった。こういった事情から、OS領域のバックアップが適切なタイミングや方法で実施されていないケースは非常に多く、企業の80%以上で適切なOSバックアップがされていないという調査結果もある。
最新のバックアップ技術は、これらのOSバックアップに関する問題点を解決しつつある。具体的にはOSリストアは、(1)復旧用OSの起動、(2)OSデータのリストアの2段階のプロセスで行われる。
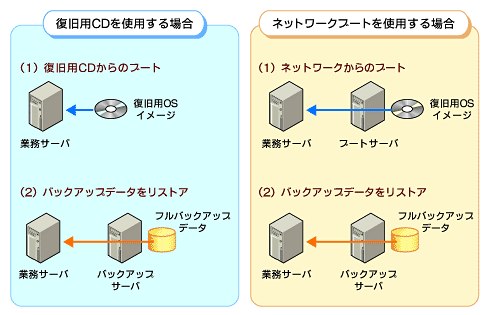 |
| 図1 2つのOSバックアップ手法 |
復旧用OSの起動は専用CDまたはネットワーク経由で行う。最近のIAサーバハードウェアはネットワークブートが可能なので、復旧するOSがWindowsやLinuxの場合でもSolarisなどと同じプロセスで起動できる(そのためには事前にBIOS設定でネットワークブートを許可するようにしておく必要がある。専用CDから起動する場合も同様にCDからの起動を許可する設定が必要)。ネットワークブートによる起動には専用のDHCPサーバや復旧用OSのダウンロードを支援するブート用サーバが必要になる半面、復旧するサーバの電源を入れた後はリモートオペレーションのみでの復旧も可能だ。一方、専用CDを使用する場合、メディアの出し入れやサーバ名などのパラメータ入力が必要となることもある。比較的規模が大きい環境で利用する場合にはネットワークブート、小規模環境では専用CDからのブートがよいであろう。
復旧用OSが起動すると、自動的にOSデータのフルリストアが実行される。この際、異なるハードウェア構成にリストアする場合、ドライバの追加インストールや構成変更の設定が必要となる場合がある。
当然のことながら、OSをリストアするためにはOS領域のフルバックアップが必要になるが、オープンファイルも含めたOS領域のオンラインバックアップが可能になったため、OS復旧までの一連のプロセスを自動化できるようになった。
1/3 |
| Index | |
| アプリ対応で進化したバックアップ技術を使う | |
| Page1 OSのバックアップにおける進化 |
|
| Page2 Exchange Serverデータの個別アイテムのリストア 仮想サーバのバックアップ |
|
| Page3 「アーカイブ」の意味の変化 暗号化ニーズにどう対応するか |
|
- Windows 10の導入、それはWindows as a Serviceの始まり (2017/7/27)
本連載では、これからWindows 10への移行を本格的に進めようとしている企業/IT管理者向けに、移行計画、展開、管理、企業向けの注目の機能について解説していきます。今回は、「サービスとしてのWindows(Windows as a Service:WaaS)」の理解を深めましょう - Windows 10への移行計画を早急に進めるべき理由 (2017/7/21)
本連載では、これからWindows 10への移行を本格的に進めようとしている企業/IT管理者に向け、移行計画、展開、管理、企業向けの注目の機能を解説していきます。第1回目は、「Windows 10に移行すべき理由」を説明します - Azure仮想マシンの最新v3シリーズは、Broadwell世代でHyper-Vのネストにも対応 (2017/7/20)
AzureのIaaSで、Azure仮想マシンの第三世代となるDv3およびEv3シリーズが利用可能になりました。また、新たにWindows Server 2016仮想マシンでは「入れ子構造の仮想化」がサポートされ、Hyper-V仮想マシンやHyper-Vコンテナの実行が可能になります - 【 New-ADUser 】コマンドレット――Active Directoryのユーザーアカウントを作成する (2017/7/19)
本連載は、Windows PowerShellコマンドレットについて、基本書式からオプション、具体的な実行例までを紹介していきます。今回は、「New-ADUser」コマンドレットです
|
|




