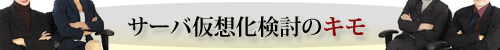
第1回 サーバ仮想化への取り組み方
池田 賢司
デル株式会社
アドバンスド システムズ グループ
ストレージ ソリューション アーキテクト
2008/9/8
 仮想化ソフトはOSと同じようなもの
仮想化ソフトはOSと同じようなもの
上記のように、ハイパーバイザ型の仮想化ソフトウェアは、物理マシン上に直接、実装される、つまり、物理マシンに直接、仮想化ソフトウェアをインストールすることになる。
IAサーバの場合、物理ハードウェアを利用するためには、カーネルが必要となり、デバイスドライバが必要となる。つまり、仮想化ソフトウェアには、カーネルやデバイスドライバが何らかの形で実装されていなければならない(そうでないと、仮想化ソフトウェアは物理ハードウェアに対して何の命令も下すことができない)。カーネルやデバイスドライバの実装方法は、仮想化ソフトウェア製品によってさまざまであるが、実装されている、という点においては共通である。
仮想化ソフトウェアがカーネルやデバイスドライバを持つということは、どういうことだろうか、従来のIAサーバの物理環境において使用してきたOSもカーネルやデバイスドライバを実装しているが、この点において仮想化ソフトウェアはOSと酷似していると考えてよいだろう。つまり、OSと仮想化ソフトウェアのアーキテクチャは異なるといえども、実装しているものは管理者から見た場合、ほぼ同一と考えることができる。よって、これまで物理環境で培ってきたOSの運用管理手法を仮想化ソフトウェアにも適用できることになる。
何でもかんでもOSと仮想化ソフトウェアが同一であると考えるのは危険であるが、ここで言いたいのは、仮想化ソフトウェアといっても、これまでの運用管理手法が全く通用しないような何か特別なものではなく、OSと同じような感覚で捉えていただきたい、難しくて敷居が高いものと捉えないでいただきたい、ということである。また、別の観点からいうと、ある統計データでは近い将来、市場のシステム環境における仮想環境の割合が40%に達する見込みとなっている。つまり、上記と合わせて考えると、仮想環境を導入することは、すでに当たり前のことになってきていることが分かる。
 運用管理は主体的に考える必要がある
運用管理は主体的に考える必要がある
さて、仮想環境の導入が今後は当たり前になり、仮想化ソフトウェアが特別なものではなく、OSと似たようなものと考えることができると述べてきたが、もちろん、OSと仮想化ソフトウェアが全く同一なものでないように、物理環境と仮想環境も当然ながら全く同一なものではない。管理者は物理環境での運用管理手法を応用して仮想環境を管理する必要がある。
最大のポイントは、前述した「物理ハードウェアリソースの共有」という概念、すなわち、複数の仮想マシンが物理ハードウェアリソースを共有して使用することになるので、どの仮想マシンにどれだけのリソースを割り当てるかを決めることが重要である。同時に、リソースの割り当てを決めないで仮想化ソフトウェアに任せてしまう、というのも1つの判断である。
いずれにしても、サーバの仮想化というのがすでに一般的なものになり、仮想化ソフトウェアがOSと似たようなものであるならば、管理者自らが(ベンダからアドバイスはもらうにしても)主体的に運用管理のスキームを考える必要があることは間違いない。
2/2 |
| Index | |
| サーバ仮想化への取り組み方 | |
| Page1 IAサーバ仮想化ソフトの重要な価値とは サーバ仮想化ソフトウェアの2つの実装方法 |
|
| Page2 仮想化ソフトはOSと同じようなもの 運用管理は主体的に考える必要がある |
|
- Windows 10の導入、それはWindows as a Serviceの始まり (2017/7/27)
本連載では、これからWindows 10への移行を本格的に進めようとしている企業/IT管理者向けに、移行計画、展開、管理、企業向けの注目の機能について解説していきます。今回は、「サービスとしてのWindows(Windows as a Service:WaaS)」の理解を深めましょう - Windows 10への移行計画を早急に進めるべき理由 (2017/7/21)
本連載では、これからWindows 10への移行を本格的に進めようとしている企業/IT管理者に向け、移行計画、展開、管理、企業向けの注目の機能を解説していきます。第1回目は、「Windows 10に移行すべき理由」を説明します - Azure仮想マシンの最新v3シリーズは、Broadwell世代でHyper-Vのネストにも対応 (2017/7/20)
AzureのIaaSで、Azure仮想マシンの第三世代となるDv3およびEv3シリーズが利用可能になりました。また、新たにWindows Server 2016仮想マシンでは「入れ子構造の仮想化」がサポートされ、Hyper-V仮想マシンやHyper-Vコンテナの実行が可能になります - 【 New-ADUser 】コマンドレット――Active Directoryのユーザーアカウントを作成する (2017/7/19)
本連載は、Windows PowerShellコマンドレットについて、基本書式からオプション、具体的な実行例までを紹介していきます。今回は、「New-ADUser」コマンドレットです
|
|




