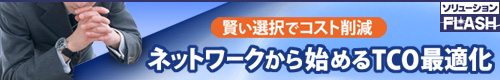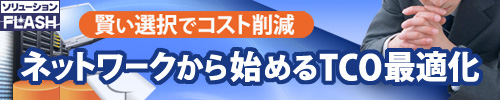
 |
ネットワークから始めるTCO最適化 見逃していませんか? 足元のネットワークの再検討 |
| 厳しい市場環境を背景に、IT部門はコスト削減という課題に迫られている。まず頭に浮かぶのは、サーバ統合やSaaS/ASP導入といった手法だろう。加えて、見落としがちな足元のネットワークインフラを再検討することで、限られた予算の中で、効率よい業務運営を支援することができる。この特集では、TCOを削減し、企業の体質改善に役立つネットワーク再構築のポイントを紹介する。 |
| コスト削減の切り札「サーバ統合」の実現にもネットワークは不可欠 | ||
厳しい市場環境を背景に、多くの企業があらゆる側面からコスト削減に取り組んでいる。IT部門もその例外ではない。業務を支援するITシステムのサービスレベルを落とすことなくコスト削減、総所有コスト(TCO)最適化を果たすという相反する課題の両立に、頭を悩ませている担当者も多いことだろう。
その切り札としてしばしば登場するのが、仮想化技術を核としたサーバやストレージの統合だ。これまで複数の拠点に分散し、部門ごとにばらばらに運用されてきたハードウェアを1カ所に統合することによって、まずハードウェア導入に費やすコストを削減できる。また、運用・管理を1カ所にまとめることにより作業が効率化され、結果としてTCOの削減につながる。
別のアプローチとして、SaaSやASPといった外部サービスの活用を検討することもあるだろう。自社で設備を抱えての運用には安心感があるが、その分運用コストを計算に入れる必要がある。代わりに、インターネットを介して外部のサービスをうまく利用することで、TCOの削減につなげることができるだろう。
しかし、こうしたITシステム全体の見直しの中で、見落とされがちな部分がある。企業インフラの足元を構成するネットワークだ。サーバ統合にせよSaaSの採用にせよ、十分な帯域を持ち、必要なときにはいつでも利用できる高い信頼性を備えたネットワークの存在が前提となる。これをいかに妥当なコストで導入し、運用していくかという部分の検討が欠けてしまうと、せっかくのインフラがかえって業務の流れを滞らせ、ユーザーにストレスを与えることになりかねない。
| 大事なところは手厚く、そうでないところはそれなりに | ||
まず、サーバを本社やデータセンターに集約し、そこに各拠点からリモートアクセスを行う場合を考えてみよう。
ここで、帯域やアベイラビリティが重要だからといって、例えばVPNとブロードバンドの組み合わせを捨て、安易に専用線を導入するのはナンセンスだ。もちろん、アプリケーションの用途や重要性によっては、専用線が提供する高い品質が不可欠という場合もあるだろうが、それはコスト増加につながる可能性もある。まずはきちんと要件を見極め、必要十分なスペックを提供してくれる回線を選択する必要があるだろう。
もちろん、コストをかければかけるほど、高品質で広帯域の回線を利用することができる。だが、現実の予算には限りがあるはずだ。優先すべき回線とそうでないものとを見極め、それに応じたサービスを選択することになるだろう。この場合は、サーバ統合を行ったデータセンター側には品質の高い回線を、そうでないところはそれなりの回線を予算に応じて割り振ることになる。
しかし、十分な帯域のない回線でWAN越しにファイルサーバにアクセスすると、ファイルを開くだけで延々待たされていらいらする……ということもある。中には、サーバ統合後に慌てて回線を増強し帯域を増やすこともあるだろうが、それでは本末転倒で、何のためのサーバ統合かが分からなくなる。
ここで有効な手段の1つが、WAN最適化製品の導入だ。一般にWAN最適化製品は、Windowsファイル共有で用いられるCIFSなど、これまで主にLANで利用されてきたプロトコルの特徴を踏まえ、遅延の大きなWAN回線越しでもスムーズに通信が行えるよう最適化が施されている。
また、QoSやトラフィックシェーピング機能を提供する製品も存在する。基幹アプリケーションは優先して処理し、メールやWebはほどほどに、業務には関係ないと思われるP2Pアプリケーションのトラフィックは絞るといった具合に制御することで、限りある帯域を有効に利用できる。
こうした製品の中には、データの圧縮機能を備えたものが多く、拠点間のトラフィック総量を減らすこともできる。それに合わせて品目の速度を調整すれば、拠点間の通信コストをさらに下げることも可能だ。
| せっかく下がったポート単価を生かして拡張性も視野に | ||
拠点間やインターネットといった社外接続に限らず、ネットワークのTCO最適化は、まず構成を把握してトラフィックを測定し、どこにどのくらいのトラフィックが流れているかをしっかり可視化することから始まる。そして、トラフィックの優先度はそれぞれどのくらいか、遅延やダウンタイムが許容できるのかを検討し、優先順位をしっかり付けることだ。そうすれば自ずと、最適な選択肢が絞られてくるだろう。
ただネットワークに関して難しいのは、今後に備え、拡張性をどのくらい持たせておくかという部分だ。ほかのITシステム同様、ネットワークもいったん導入したらなかなか取り替えが利かない。その上、ネットワークの帯域需要がこの先どのくらい伸びるのかも、一概には予測しにくい部分がある。
例えば、この1〜2年の間に、プライベートなシーンだけでなく企業においても、音声や動画といったリッチなコンテンツを利用するケースが増えてきている。また、不思議なことにPCが普及し、帯域が広がれば広がるほど、メールに添付されるファイルやプレゼンテーション用資料のサイズが肥大化する傾向にある。今後数年間にわたって、これらをストレスなくやり取りできるインフラを構築することを考えなくてはならない。
ただ、この点に関しては幸いなことに、ポート単価は年々安くなっており、数年前に比べれば初期導入費用ははるかに抑えることができる。ギガビットクラスのネットワーク、いや10Gクラスのネットワークも視野に入ってくるだろう。
もう1つ見落としがちなのは、ネットワーク運用のTCOだ。TCOに最も影響を与えるのはトラブルの有無である。企業を支えるネットワークが止まれば、業務に多大な影響を与えることになる。そうした見えないコストまで含めて考えると、1つの案はネットワークを冗長化しておくこと。しかしそれではコストが気になるという場合は、信頼性が高く、万一故障したときのトラブルシューティングが容易な機器を導入することを検討するのも一案だろう。
ソリューションFLASH Pick UP! |
||||||
|
提供:マクニカネットワークス株式会社
日立電線株式会社
アイティメディア営業企画
制作:@IT 編集部
掲載内容有効期限:2009年9月20日
ソリューションFLASH Pick UP!
WAN最適化アプライアンス「WXC」シリーズ
マクニカネットワークス
 サーバ統合によって得られるメリットとして、人件費を含む総所有コストの削減やシステム全体の信頼性向上、セキュリティレベルの確保が挙げられる。しかし、WANを流れるデータ容量の増加によって業務効率が低下してしまう可能性も潜んでいる。ジュニパーネットワークスの WAN最適化アプライアンス「WXC」シリーズで、この落とし穴を回避しよう。
サーバ統合によって得られるメリットとして、人件費を含む総所有コストの削減やシステム全体の信頼性向上、セキュリティレベルの確保が挙げられる。しかし、WANを流れるデータ容量の増加によって業務効率が低下してしまう可能性も潜んでいる。ジュニパーネットワークスの WAN最適化アプライアンス「WXC」シリーズで、この落とし穴を回避しよう。
エンタープライズ向けスイッチ「APRESIA」シリーズ
日立電線
 日立電線のエンタープライズ向けスイッチ「APRESIAシリーズ」は、「壊れにくくする」ことと「迅速な復旧」の両面で、ネットワークのTCO削減を実現する。そして同時に、シャーシ型スイッチに匹敵する性能と信頼性、拡張性を提供する。
日立電線のエンタープライズ向けスイッチ「APRESIAシリーズ」は、「壊れにくくする」ことと「迅速な復旧」の両面で、ネットワークのTCO削減を実現する。そして同時に、シャーシ型スイッチに匹敵する性能と信頼性、拡張性を提供する。
WAN最適化装置「Steelhead」
ネットマークス
 各地の拠点に散在していたサーバを統合するプランを練っている企業は少なくない。だがその際、ネットワークについても十分考慮しないと、コスト削減効果が得られるどころかかえって生産性を阻害する可能性もある。そんな事態を防いでくれるのが、リバーベッドテクノロジーの WAN最適化装置「Steelhead」だ。国内・海外ともにリバーベッド製品の豊富な導入実績を誇るネットマークスが手掛けた2つの事例を元に、その効果を見てみよう。
各地の拠点に散在していたサーバを統合するプランを練っている企業は少なくない。だがその際、ネットワークについても十分考慮しないと、コスト削減効果が得られるどころかかえって生産性を阻害する可能性もある。そんな事態を防いでくれるのが、リバーベッドテクノロジーの WAN最適化装置「Steelhead」だ。国内・海外ともにリバーベッド製品の豊富な導入実績を誇るネットマークスが手掛けた2つの事例を元に、その効果を見てみよう。
ホワイトペーパーダウンロード
コスト削減! サーバ統合+WAN最適化という最強解
サーバ統合の懸念点としては、想定していない問題により思わぬコストが発生することが挙げられる。 そこで、WAN最適化ソリューションWXCの導入により約30%の運用コスト削減を実現した例を紹介する。
1Gのコストで、10Gを。
TCO削減は、初期投資だけではない。一度導入すると5年は利用するネットワーク機器。実は運用コストが大事!! 障害発生時の回避策と壊れにくい設計ポリシー、しかも柔軟な拡張性を持った国産スイッチ。新たに「1Gのコストで、10Gを。」をキャッチコピーに新製品を投入。
事例から見る、WAN最適化アプライアンス導入の理由とは
今やファイルサーバ統合に欠かせないWAN最適化装置。ユーザ事例からその導入経緯をご紹介する。