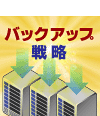
いまどきのサーババックアップ戦略入門(3)
バックアップのあり方を変える新技術
株式会社シマンテック
成田 雅和
2007/10/26
データの保護・保全に関するテクノロジーは進化を続け、バックアップ手法の選択肢が広がってきている。業務要件に適したバックアップ技術を容易に使えるようになってきているのだ
 無停止バックアップ
無停止バックアップ
いまや、アプリケーションやOSを停止せずにバックアップすることは当然になりつつある。
OSについてはシングルユーザー、あるいは専用OSで起動した状態で「コールド」バックアップを取るのが主流であった。このデータ(すなわちOSバックアップ)をリストアするためには、別途OSのインストールメディアとバックアップエージェントが必要だったり、構成の異なるハードウェアにリストアしてもOSとして正常に動作しないなどの問題があった。しかしいまでは、バックアップエージェントの進歩により稼働状態でもバックアップが取れるようになったうえ、ハードウェア構成が異なる場合でもドライバの追加インストールなどを行うことで正常に稼働させることができるようになっている。
アプリケーションデータのバックアップについても、アプリケーション専用のバックアップエージェントの進歩により、アプリケーションの停止なしでバックアップを行えるようになってきている(この部分の詳細は第5回で触れる予定である)。
 スナップショット
スナップショット
第2回でも簡単に触れたが、RPO/RTOを劇的に短縮する方法の1つがスナップショットである。スナップショットはもともと、ある時点でのデータの静止点を取り、変更されたデータとそのリンク情報を持つことにより、短時間でバックアップ元データを作成する方法であった(図1)。これはいまでも、差分のみを保持する方法として利用されている。
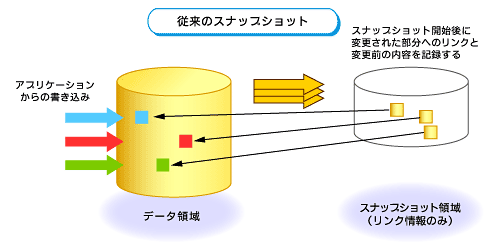 |
| 図1 従来のスナップショットはリンク情報を管理する |
その後さらに、リンク情報ではなく完全なデータとしてのコピーを作成することも可能になった。ここではその技術を「フルイメージスナップショット」と呼ぶことにしよう。具体的な方法は以下のとおりである。
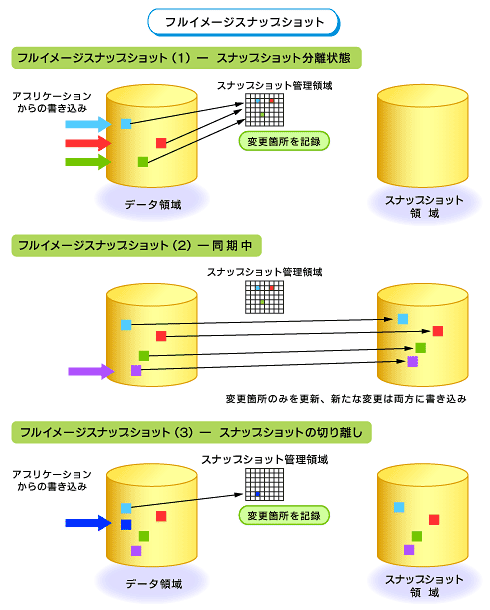 |
| 図2 フルイメージスナップショットではデータのコピーも行われる |
まずフルイメージスナップショット実施前は、データ領域(バックアップ元)とスナップショット領域(バックアップ先)が切り離された状態になっている(図2のフルイメージスナップショット(1))。この状態でアプリケーションがデータを書き込むと、データ領域のみに書き込みが行われ、スナップショット管理領域が更新される。
この状態からスナップショットを開始すると、この時点でデータ領域からフルイメージスナップショット領域へ、変更点のみのコピーが開始される。コピー処理中に新たにデータ領域にアプリケーションが書き込むと、そのデータは都度、スナップショット領域にも書き込みが行われる(図2のフルイメージスナップショット(2))。この処理を「フルイメージスナップショット領域の同期」と呼ぶ。初回はすべてのデータをコピーするために領域サイズに応じて長い時間がかかるが、2回目以降は変更点のみのコピーとなるために短時間で終了する。
同期終了後、アプリケーションをリードオンリーな状態にし、スナップショット領域を分離し、すぐまたアプリケーションを通常状態に復旧する(図2のフルイメージスナップショット(3))。この分離操作そのものは秒単位で終了するので、アプリケーションからみた場合のバックアップウィンドウの短縮につながる。
この状態は図2のフルイメージスナップショット(1)と同じであり、以後、同期処理とスナップショット領域の分離処理を繰り返すことで、フルイメージのバックアップを取得することができる。SAN上のストレージ装置にスナップショット領域を取り、バックアップサーバから直接アクセスして2次バックアップを取ることも可能だ。もともとのデータ領域が破損したような場合、スナップショット領域をそのままアプリケーションからアクセスさせることもできる。
フルイメージのスナップショットはストレージ装置の機能として実装されているほか、ボリューム管理ソフトウェアの機能でも実現されている。ボリューム管理ソフトの機能を使用する場合、異なるストレージ装置間でスナップショットを行うことができる。安価なストレージ装置をスナップショット専用として使用し、バックアップの高速化とコストダウンを両立する例も出てきている。スナップショット同期中に元のデータ領域が破損するとスナップショット領域のデータも一貫性が失われてしまうので、データ領域とスナップショット領域は異なるRAIDグループにする、同じハードディスクデバイスを共用しない、ストレージ筐(きょう)体を分ける、あるいは、スナップショット領域を複数個持つなどの対応策を必要に応じて選択するとよい 。
1/3 |
| Index | |
| バックアップのあり方を変える新技術 | |
| Page1 無停止バックアップ スナップショット |
|
| Page2 個別アイテムのリストア 連続データ保護(CDP) |
|
| Page3 重複データ排除 負荷分散 |
|
- Windows 10の導入、それはWindows as a Serviceの始まり (2017/7/27)
本連載では、これからWindows 10への移行を本格的に進めようとしている企業/IT管理者向けに、移行計画、展開、管理、企業向けの注目の機能について解説していきます。今回は、「サービスとしてのWindows(Windows as a Service:WaaS)」の理解を深めましょう - Windows 10への移行計画を早急に進めるべき理由 (2017/7/21)
本連載では、これからWindows 10への移行を本格的に進めようとしている企業/IT管理者に向け、移行計画、展開、管理、企業向けの注目の機能を解説していきます。第1回目は、「Windows 10に移行すべき理由」を説明します - Azure仮想マシンの最新v3シリーズは、Broadwell世代でHyper-Vのネストにも対応 (2017/7/20)
AzureのIaaSで、Azure仮想マシンの第三世代となるDv3およびEv3シリーズが利用可能になりました。また、新たにWindows Server 2016仮想マシンでは「入れ子構造の仮想化」がサポートされ、Hyper-V仮想マシンやHyper-Vコンテナの実行が可能になります - 【 New-ADUser 】コマンドレット――Active Directoryのユーザーアカウントを作成する (2017/7/19)
本連載は、Windows PowerShellコマンドレットについて、基本書式からオプション、具体的な実行例までを紹介していきます。今回は、「New-ADUser」コマンドレットです
|
|




