 メモリ
メモリ
■容量割り当て
メモリは、物理サーバが搭載している物理メモリを切り売りする形での割り当てとなります。つまり、仮想CPUのように、「オーバーコミット」といわれるような物理的な搭載量を超える割り当てを行うことはできません。メモリ容量の割り当てでは、まずゲストOSごとの最大容量を設定し、さらに実際に割り当てる容量を設定することができます。割り当て容量は最大容量の範囲内でゲストOSを稼働中、停止中を問わず設定を変更することが可能です。
■最大容量
最大容量はVM Managerで設定可能です。ただしこの値の変更はゲストOSが停止している状態でのみ可能です。
■実際の割り当て容量
実際の割り当て容量もVM Managerで設定可能です。ゲストOSが稼働中、停止中いずれの状態でも設定可能です。
 |
| 図2 VM Managerでのメモリ設定。ここでは実際の割り当て容量(Memory Size)を1024に設定している |
 ネットワーク
ネットワーク
■インターフェイス割り当て
ゲストOSのネットワークインターフェイス(ポート)はVM Managerから増減可能です。ゲストOSが稼働中、停止中いずれの状態でも設定可能です。
 |
| 図3 VM ManagerでのNIC設定 |
物理サーバが複数のネットワークインターフェイスを搭載している場合、既定ではポートごとにxenbrという仮想スイッチが作成されています。ゲストOSのネットワークインターフェイス設定にはどの仮想スイッチに接続するかという設定も含まれます。
例えば、物理サーバが2ポートのネットワークインターフェイスを搭載していたとすると、既定ではxenbr0、xenbr1という2つの仮想スイッチが作成され、それぞれが別々のポートに接続されます。このVM Server上でゲストOSのネットワークインターフェイスを2ポート作成するとき、それぞれのポートを別々の仮想スイッチに接続することでゲストOSを複数のネットワークセグメントに接続することができます。
また、別の構成ではネットワークセグメントを分けるのではなく、ネットワークのパフォーマンスを考慮してゲストOSごとに仮想スイッチを分けるということも可能です。各仮想スイッチが各物理ポートと1対1で構成してあれば、各ゲストOSのトラフィックがほかのゲストOSの影響を受けないようにすることができます。
■帯域幅しきい値設定
ゲストOSごとに使用できるネットワーク帯域幅のしきい値をVM Managerから設定することができます。ゲストOS毎にSLAがあるような場合に有用です。下図では帯域幅しきい値を50Mbpsに設定しています。
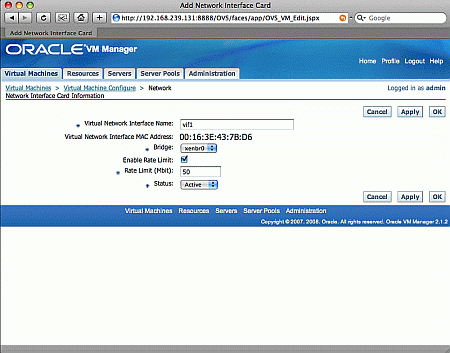 |
| 図4 VM Managerでの帯域幅しきい値設定 |
2/3 |
| Index | |
| Oracle VMにおけるハードウェアリソース管理 | |
| Page1 CPU |
|
| Page2 メモリ ネットワーク |
|
| Page3 ディスク |
|
- Windows 10の導入、それはWindows as a Serviceの始まり (2017/7/27)
本連載では、これからWindows 10への移行を本格的に進めようとしている企業/IT管理者向けに、移行計画、展開、管理、企業向けの注目の機能について解説していきます。今回は、「サービスとしてのWindows(Windows as a Service:WaaS)」の理解を深めましょう - Windows 10への移行計画を早急に進めるべき理由 (2017/7/21)
本連載では、これからWindows 10への移行を本格的に進めようとしている企業/IT管理者に向け、移行計画、展開、管理、企業向けの注目の機能を解説していきます。第1回目は、「Windows 10に移行すべき理由」を説明します - Azure仮想マシンの最新v3シリーズは、Broadwell世代でHyper-Vのネストにも対応 (2017/7/20)
AzureのIaaSで、Azure仮想マシンの第三世代となるDv3およびEv3シリーズが利用可能になりました。また、新たにWindows Server 2016仮想マシンでは「入れ子構造の仮想化」がサポートされ、Hyper-V仮想マシンやHyper-Vコンテナの実行が可能になります - 【 New-ADUser 】コマンドレット――Active Directoryのユーザーアカウントを作成する (2017/7/19)
本連載は、Windows PowerShellコマンドレットについて、基本書式からオプション、具体的な実行例までを紹介していきます。今回は、「New-ADUser」コマンドレットです
|
|





