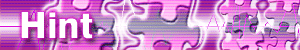| [Management] | |||||||||||
システムの電源を強制的にオフにする
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 解説 |
コンピュータを使っていると、ときにうんともすんとも反応しない、いわゆるハングアップの状態に陥ってしまう場合がある。特定のアプリケーション(ウィンドウ)がこの状態に陥っただけなら(マウスやキーボードを操作できるなら)、タスク・マネージャなどを使って、特定のアプリケーションを強制的に終了させ、Windowsをそのまま継続利用できる。
しかし特定のアプリケーションだけでなく、Windowsシステム全体がハングアップし、マウスもキーボードも使えなくなる場合もある。こうなったら、コンピュータの電源をオフにしてシステムを再起動するしかないのだが、最近のコンピュータは不用意に電源をオフにしたりしないように、ソフトウェアで制御可能なソフトスイッチになっている場合が多い。これにより、ユーザーが電源ボタンを押したとき、いきなり電源をオフにするのではなく、Windowsのシャットダウン処理を開始できるようにしている。
しかしシステムがハングアップしてしまうと、このシャットダウン処理もうまく起動しないので、電源ボタンを押してもコンピュータが反応せず、コンピュータの電源をオフにできなくなってしまう。
メーカーやコンピュータのモデルにもよるので、すべてのコンピュータで使える保証はないが、一般にこうしたソフトスイッチを搭載するコンピュータの多くは、電源スイッチを一定時間(数秒間など)押し続けることで、強制的に電源を遮断できるようにしている(電源ケーブルをいきなり抜くのとほぼ同じ状態)。シャットダウン処理をせずに電源をいきなり切断するので、Windowsシステムを破壊する危険性も高いが、ほかに手段がないなら、この方法で電源を切断しよう。
| 操作方法 |
すでに述べたとおり、電源を強制的に切断するには、電源ボタンを一定時間押し続ければよい。通常は数秒程度で強制的に電源が遮断される。コンピュータが物理的に破壊されていない限り、電源オフ後に再度電源ボタンを押せば、システムが再起動するはずだ。
適切なシャットダウン処理を実行せず、強制的に電源を遮断すると、場合によってはWindowsシステムを破壊してしまうこともあるので、慎重に実行していただきたい。最悪の事態を回避できる可能性を高めるには、以下の点に注意するとよいだろう。
-
ハードディスクのアクセス・ランプをチェックし、点滅中(アクセス中)でないことを確認する。
-
ネットワークのアクセス・ランプをチェックし、点滅中(アクセス中)でないことを確認する。
これらのアクセス・ランプが点滅するということは、システムの内部にはまだ稼働中のプロセスが存在する可能性がある。ランプが点滅している場合は、一定時間待ち、ランプが消えてから電源の強制遮断を実施する。
|
ただしこれらに注意しても、システムが破壊されない保証はない。Windowsを正しく再起動できなくなってしまった場合には、システムの復元機能などを使って、Windowsを以前の状態に戻す必要がある。詳細については、関連記事を参照されたい。
なお、強制的な電源切断後にシステムを起動すると、自動的にchkdskコマンドが実行されることがある。その場合、chkdskの実行前に何らかのキーを押すとスキップさせることもできるが、それはやめた方がよい。経験的には、強制遮断後の最初のchkdskでは何らかのエラー(インデックスの不整合など)が発見されることが多いといえる。chkdsk処理をスキップせず、全ドライブ(全ボリューム)について強制的にchkdskを行うのが望ましい。![]()
この記事と関連性の高い別の記事
- Windowsのpowercfg.exeコマンドで電源オプションの設定を変更する(TIPS)
- シャットダウン処理を省略した「緊急時シャットダウン」を実行する(TIPS)
- 電源ボタンで休止状態にするための設定方法(Windows 7/XP編)(TIPS)
- [Power]キー、[Sleep]キーに注意(TIPS)
- グループ・ポリシーとpowercfg.exeコマンドで電源オプションの設定を変更する(TIPS)
このリストは、デジタルアドバンテージが開発した自動関連記事探索システム Jigsaw(ジグソー) により自動抽出したものです。
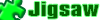
| 「Windows TIPS」 |
- Azure Web Appsの中を「コンソール」や「シェル」でのぞいてみる (2017/7/27)
AzureのWeb Appsはどのような仕組みで動いているのか、オンプレミスのWindows OSと何が違うのか、などをちょっと探訪してみよう - Azure Storage ExplorerでStorageを手軽に操作する (2017/7/24)
エクスプローラのような感覚でAzure Storageにアクセスできる無償ツール「Azure Storage Explorer」。いざというときに使えるよう、事前にセットアップしておこう - Win 10でキーボード配列が誤認識された場合の対処 (2017/7/21)
キーボード配列が異なる言語に誤認識された場合の対処方法を紹介。英語キーボードが日本語配列として認識された場合などは、正しいキー配列に設定し直そう - Azure Web AppsでWordPressをインストールしてみる (2017/7/20)
これまでのIaaSに続き、Azureの大きな特徴といえるPaaSサービス、Azure App Serviceを試してみた! まずはWordPressをインストールしてみる
|
|