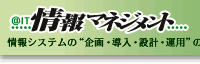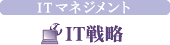国際会計基準導入に向け、情シスがすべきこと
2009/1/13
近年、国際的な会計コンバージェンス(全世界の決算書を比較しやすくしようとする動き)が進む中で、大きな動きがありました。金融庁が2008年9月17日に「国際財務報告基準(International Financial Reporting Standards:IFRS)」を日本で導入する前提で本格検討に入ったと正式表明したのです。
あまりよく現状をご存じない方のために補足をすると、IFRSとは、世界で最も広く採用されている会計基準のことです。
日本はこれまで独自の会計基準を持って財務報告を行ってきており、2つの基準の間には差異が存在します。
このため、同一企業であってもIFRSを基に作成された財務諸表と、日本基準で作成された財務諸表には内容が異なる場合があります。世界中の至る所でこのような現象が見られるのですが、これを是正しようとする動きを、会計コンバージェンスと呼んでいるのです。
米国やカナダ、韓国においてもIFRSを適用する方向を明らかにしてり、すでに2005年に先駆けてこの基準を導入した欧州も2009年には欧州以外の地域の企業に対して「IFRSまたは同等の基準」を強制することから、日本もこれに追随する形となりました。
このような大きな流れから、日本企業も近い将来、IFRSへの対応が求められるわけですが、1企業のレベルでは何が起こるのでしょうか。現時点では多くを語ることはできませんが、少なからず懸念されていることを本稿でお知らせしたいと思います。
なお、本稿のうち意見に当たる部分については、私見であることをあらかじめお断りしておきます。
IRFS導入の際の懸念
日本においてIFRSを導入するとなったら、その影響はどの程度なのでしょうか。現在、3つのことが懸念事項とされています。これは、2005年に欧州でIRFSが導入された際の経験から推測された事項です。
(1) IFRSの適用により、企業内における会計方針・会計処理がどのように変更されるのか、業務プロセスに変更は生じるのか
(2) IFRSの適用に、どの程度のコストが掛かるのか
(3) 準備期間に何をすればよいのか
IFRSは原則主義、各論は各国の制度が反映
結論からいうと、(1)は「変更は生じる。詳細は現時点では未定」ということになります。IFRSは「原則主義」という考え方を採っています。これは「詳細な規則は定めない主義」と解釈していただければよいと思います。いい換えれば「解釈は作成者と監査人の間の協議で決める」ということです。
つまり、IFRSを見ても、具体的にある会計処理はどうすればよいのかなどの各論は分からないのです。国々の個別のルールに配慮し、結果としては国ごとに少しずつ異なった解釈が生まれてくる可能性もあります。
とはいえ、IFRSと日本の基準を比較したとき、大きな差異がいくつか存在します。下に、IFRSと日本の基準との主要な差異をいくつか、特に情報システムに影響がありそうな項目を紹介します。
- IFRSには特別損益の項目がないなど、損益計算書の表示方法が異なる
- IFRSでは固定・流動の順だが、日本基準では流動・固定の順など、貸借対照表の表示順序や方法が異なる
- 収益の認識について、IFRSと日本の慣行とでは隔たりがある可能性がある。そのため、売リ上げ計上のタイミングなどが現状とは異なる可能性がある
- IFRSにおいて、研究開発費は一部資産計上し償却するが、日本基準においては発生時に費用処理する
- 実務上、有形固定資産の償却は税法の影響が大きいが、IFRSにおいては各国の税法の規定は関係ない
- IFRSにおいて、会計方針の変更は過去にさかのぼって適用するが、日本基準においては過去の財務諸表は修正しない
これらは、実務上相当の影響が出るものもありますので、担当の監査人と綿密な協議のうえ、対応を決定していく必要があります。
IFRSの導入コストは安くはない
(2)については、「導入には相当のコストが掛かるが、初期投資を適切に行えば、ランニングコストは抑制できる」といえるようです。参考までに欧州においてIFRS導入がなされた際の総コスト(導入の平均コスト)の推計データを紹介します。以下の資料は、「EU Implementation of IFRS and the Fair Value Directive - A report for the European Commission (October 2007)(ICAEW)」による(リンク先はPDF)。
企業の売上規模 |
導入費用 |
| 5億ユーロ以下の企業 | 55万4千ユーロ |
| 5億ユーロ以上、50億ユーロ以下の企業 | 86万7千ユーロ |
| 50億ユーロ超の企業 | 343万ユーロ |
また、ランニングコストは収益規模によらず、導入コストのおおよそ5分の1程度となっています。
単なる「制度に合わせるためのコスト」と見れば、あまり歓迎できる数字ではないといえますが、「業績を比較可能な形で測定できる道具の導入」と前向きにとらえ、積極的に事業展開に生かすことができれば逆にチャンスともいえます。
では、現在何をすべきか
最後に(3)ですが、「現在のところ、慌てる必要はない」といえます。現在はまだ日本においての導入検討が始まった段階であり、制度の各論が不明であるためです。
しかし、制度の導入には思ったよりも時間がかかります。準備はしておくべきでしょう。以下に、情報システムにおけるIFRS適用の推進手順の参考例を示します(図1)。
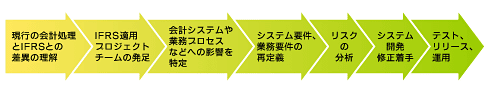 |
| 図1 IFRS適用の推進手順(出所:トーマツ イノベーション) |
現段階は、ちょうど1つ目から2つ目のボックスに当たる段階です。すなわち、現行会計基準とIFRSとの差異の理解に努め、担当監査人とのリレーションを保って情報収集を行うことが望まれます。
また、IFRS導入の際に求められる情報システム部の役割は、トップの方針により大きく変化します。極端な例を挙げれば、
- 現状の業務プロセスをできるだけ変化させることなく、IRFSを導入するために必要な情報システムの条件は何か?
という方針の企業と、
- IRFSの導入に伴い、より優れた管理会計を構築し、経営の意思決定に役立てるために必要な情報システムの条件は何か?
という方針の企業ではやるべきことが大幅に異なってきます。
昨今の金融危機、不景気に絡み、先行き不透明ではありますが、来るべき制度の導入に向けてプロジェクトチームを発足させておき、今後のあるべき情報システムの姿を、調査・検討しておくことをお勧めします。
トーマツ イノベーション株式会社 シニアマネージャ
筑波大学大学院環境科学研究科修了後、大手コンサルティング会社を経てトーマツ イノベーション株式会社に入社。現在、主としてIT業界を対象にプロジェクトマネジメント、人事・教育制度構築などのコンサルティングに従事する。そのほかにもCOBIT、ITサービスマネジメント、情報セキュリティにおいても専門領域を持ち、コンサルティングをはじめとして、企業内研修・セミナー活動を積極的に行う。
これまで日本の会計は、国際的な会計コンバージェンスを進める方向にあった。米国などでも国際会計基準(国際財務報告基準:IFRS)を適用するという話が出てきた。そのため、日本でも導入をという動きが出てきた。
実際に適用する場合の懸念事項は3つある。1つ目は、IFRSの導入により、会計方針・会計処理がどのように変更になるのか、業務プロセスに変更は生じるのか、というものである。これに関しては、変更は生じるが、詳細はまだすべてが分かる段階ではないという。IFRSは原則主義であり、会計処理などの各論は各国に任せているためだ。
2つ目の懸念は、IFRSの適用に、どの程度のコストがかかるかである。これはEUで導入した際の資料が存在し、やはりそれなりに掛かる。またランニングコストは、企業の規模に関係なく導入コストの5分の1程度掛かるようだ。
3つ目の懸念は、準備期間に何をすればいいかだが、いまのだんかいでは導入も未確定なので、慌てる必要はない。ただ、担当の監査人とのリレーションシップを維持し、情報収集をすることが重要だ。また、IFRS導入に当たって情報システム部が担う役割は、企業トップの方針によって変わる。
| Page 1 IRFS導入の際の懸念 IFRSは原則主義、各論は各国の制度が反映 IFRSの導入コストは安くはない では、現在何をすべきか |
キャリアアップ
スポンサーからのお知らせ
転職/派遣情報を探す
「ITmedia マーケティング」新着記事
社会人1年目と2年目の意識調査2024 「出世したいと思わない」社会人1年生は44%、2年生は53%
ソニー生命保険が毎年実施している「社会人1年目と2年目の意識調査」の2024年版の結果です。
KARTEに欲しい機能をAIの支援の下で開発 プレイドが「KARTE Craft」の一般提供を開始
サーバレスでKARTEに欲しい機能を、AIの支援の下で開発できる。
ジェンダーレス消費の実態 男性向けメイクアップ需要が伸長
男性の間で美容に関する意識が高まりを見せています。カタリナ マーケティング ジャパン...