
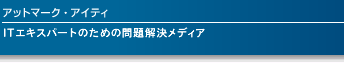
 |
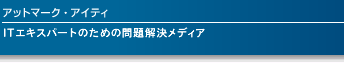 |
|
Loading
|
| @IT > デュアルコア、さらにクアッドコアへ性能向上と省電力を両立したプロセッサーを搭載、最新のHP ProLiant |
日本ヒューレット・パッカード(日本HP)は2006年11月、インテルのクアッドコアプロセッサー「クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー 5300番台」を搭載したサーバを、x86サーバ「HP ProLiant」ファミリのラインアップに追加した。クアッドコアプロセッサーは性能向上と省電力を両立するなどの特長を備え、今後のサーバ向けプロセッサーのメインストリームになるものと期待されている。新しいHP ProLiantサーバの優位性とソリューションについて、インテルの杉浦幸二郎氏および日本HPの香取明宏氏に聞いた。
2005年から2007年にかけて、インテルのx86プロセッサーは「64ビット化」「マルチコア化」「ハードウェア仮想化の実装」など新しい技術を次々と採用し、かつてない大きな転換を遂げつつある。中でも急速に発展しているのが、マルチコアの技術だ。
マルチコアプロセッサーは、1つのパッケージの中に、独立して動作することが可能な複数のコアを搭載している。「デュアルコア」は2つのコア、「クアッドコア」は4つのコアを搭載したものだ。 インテルXeon プロセッサーは、これまで「インテル® NetBurst® マイクロアーキテクチャー」を採用していた。NetBurstマイクロアーキテクチャーは、プロセッサーのクロック数を上げやすい設計になっており、実際にクロック数を上げることで性能向上を図ってきた。しかし、クロック数を上げれば上げるほど、消費電力は増加し、発熱量も増えるという弊害があった。 「クロック数を20%上げると、性能は10%程度しか上がらないのに対し、消費電力は1.5倍以上にもなります。ところが、クロック数を80%に下げた場合、性能は10%程度落ちるものの、消費電力は約半分に抑えられます。このクロック数を80%に下げた状態でプロセッサーをデュアルコアにすると、消費電力をほぼ同水準に抑えたまま、性能を大きく向上させることができます。これがマルチコアのメリットです」(インテル杉浦氏)
インテルはさらに、マルチコアプロセッサーを最適化するために、従来のNetBurst マイクロアーキテクチャーを見直し、新しいアーキテクチャーを開発した。それが「インテル® Core™ マイクロアーキテクチャー」である。このアーキテクチャーには、プロセッサーの消費電力をきめ細かく管理する「インテルインテリジェント・パワー機能」、1クロック当たり4命令の並列処理を可能とする「インテルワイド・ダイナミック・エグゼキューション」、複数のコアが1つのL2キャッシュを共有する「インテルアドバンスト・スマート・キャッシュ」など、省電力と性能向上を同時に実現する新機能を搭載している。 Coreマイクロアーキテクチャーを採用した初のインテル Xeon プロセッサーは、ボリュームゾーンサーバ向けの「デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5100番台」。以降、エントリサーバ向けにも「デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3000番台」というデュアルコアプロセッサーを投入。 そして、2006年11月には、初のクアッドコアプロセッサー「クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー 5300番台」を発売し、わずか1年あまりでプロセッサーコアは、1つから4つへと増えたわけだ。 では、Coreマイクロアーキテクチャーは、どれだけの性能向上が期待できるのだろうか。杉浦氏によると、サーバ・レベルで同等の消費電力のもの同士を比較した場合、シングルコアのインテル Xeon プロセッサー 3.60GHz(コードネームIrwindale)を搭載したサーバに比べ、「デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5160」(3GHz)を搭載したサーバは、約3倍の性能を実現。「クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサーE5345」(2.33GHz)を搭載したサーバでは、さらに1.5倍の性能を実現しているという。つまり、クアッドコア インテル Xeon プロセッサーはシングルコアのXeon プロセッサーに比べ、同じ消費電力で約4.5倍も性能を向上させていることになるのだ。
そうした性能向上と低消費電力を両立したクアッドコアプロセッサーをいち早く採用したのが、「HP ProLiant」である。タワー型サーバの「HP ProLiant ML350/ML370」、ラックマウント型サーバの「HP ProLiant DL140/DL360/DL380」、ブレードサーバの「HP ProLiant BL20p、 ProLiant BL460c/BL480c」にクアッドコア インテル Xeon プロセッサー 5300番台を採用したモデルを追加した。 クアッドコアプロセッサーを搭載した新製品は、もちろん従来モデルに比較して高速処理と低消費電力がメリットになるが、日本HPの香取氏はこの2つの特長により、TCOを大きく削減できると話す。 「サーバには、さまざまなクライアントからの要求をマルチで処理しなければならないという使命があります。従来は、その要求を満たすためにプロセッサーの数を増やすということで対応してきました。しかし、デュアルコアからクアッドコアへとコアを増やすことで、1つのプロセッサーで要求に対応できるようになりました。これにより、筐体は小さくなってスペースの縮小につながり、サーバ運用のコストが削減できるというように、TCOの削減にすべてつながってきます。さらに削減できたコストを新規システムへ投資することが可能になります」(日本HP 香取氏)
TCO削減という意味では、データセンターでの運用に最も大きな影響を与える。 まずは電源の問題だ。現在、多くのデータセンター事業者が、サーバの消費電力の急増に頭を悩ましている。1ラック当たり30アンペアの電源容量の場合、最大1000ワットのサーバなら単純計算で3台しか搭載できないことになる。これでは追加の電源工事を行わない限り、ラックに空きのある状態で運用しなければならない。 「例えば、1ラックに10台のサーバを収納したとすると、これまでは10コアでしたが、クアッドコアプロセッサーのサーバなら40コアになります。ラック当たりで利用可能な電源容量は決まっているので、処理能力を増強するには消費電力を維持し、プロセッサーのコアを増やす以外の方法はありません」(香取氏) 香取氏によれば、サーバの重量を削減できるメリットもあるという。「同じコア数で比較すると、サーバの重量は4分の1になるわけです。お客様からよく『建物が古いので、サーバがこれ以上の重量になると耐えられない』という声が届きます。クアッドコアプロセッサーのサーバにすれば、そのままの施設でも問題なく使えるわけです。これは、データセンターに限らず、一般のオフィスにも当てはまることです」(香取氏)。
1プロセッサーに4つのコアがあるクアッドコアプロセッサーに最も適しているのは、サーバの仮想化ソリューションだ。クアッドコア インテル Xeon プロセッサー 5300番台には、インテルのハードウェア仮想化技術「インテル® バーチャライゼーション・テクノロジー(インテル® VT)」が搭載されている。これは、VMwareやMicrosoft® Virtual Server、Xenなどの仮想化ソフトウェアに対し、仮想マシン上のゲストOSがプロセッサーを扱う機能を提供するもの。この機能とマルチコアを組み合わせると、各コアに対して個別にゲストOSを割り当て、稼働させることが可能になる。 「クアッドコアプロセッサーにとって、仮想化は最も特徴的なソリューションのひとつです。クアッドコア インテル Xeon プロセッサー 5300番台では、デュアルコア インテル Xeon プロセッサー 5100番台に比べ、仮想マシンを収容できる数が約2倍になっています。そのため、サーバの仮想化を考えている企業にとって、非常にメリットがあります。インテルのホワイトペーパーでは、8台のサーバをクアッドコアプロセッサーを搭載した1台のサーバに集約したという例も紹介されています」(杉浦氏) 「今までは、1プロセッサー1コアでした。つまり、1つのOSが稼働することが想定されていたわけです。ところが、1つのプロセッサー上に4つのコアがあり、それを仮想化すると、各コアに1つずつのOSを稼働させることができます。ハードウェア的にコアレベルで集約ができれば、サーバコンソリデーションも容易になります」(香取氏)
クアッドコアプロセッサーの採用により、性能向上と低消費電力を両立したHP ProLiantの新モデルだが、製品価格は据え置きになっているという。むしろ、仮想化を利用することによって、ソフトウェアライセンスを大幅に削減できる場合もある。 例えば、MicrosoftのWindows Server® 2003 Enterprise Editionの場合、マイクロソフトのライセンスではシングルコアであろうが、マルチコアであろうがプロセッサーの種類は問われない。また、Windows Server 2003 Enterprise EditionをホストOSにした場合、同じライセンスのWindows Server 2003 Enterprise Editionを最大4つの仮想マシンに導入することができる。これにより、シングルコアプロセッサーを搭載した4台のWindowsサーバを、1台のクアッドコアサーバにコンソリデーションした場合、OSに掛かるコストは4分の1になるわけだ。 なお、ソフトウェアライセンスについては、ベンダーまたはソフトウェア製品によって体系が異なる場合もある。ただし、オラクルがOracle Databaseのライセンス体系の変更を予定しているように、今後はクアッドコアプロセッサーであっても「コア数」ではなく、「プロセッサー数」として利用できる方向へと変わっていくことだろう。
提供:日本ヒューレット・パッカード株式会社 企画:アイティメディア 営業局 制作:@IT編集部 掲載内容有効期限:2007年4月9日 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||