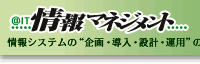| 環境変化に俊敏に対応する企業を目指して |
アジャイル・エンタープライズとは何か?
ベリングポイント株式会社
土谷 伸司
南出 修
2006/1/17
|
|
| IT革命はビジネスにスピードをもたらしたが、それは同時に競争の激化を生み出した。そこから必然的に導き出される、これからの企業が目指すべき“アジャイル・エンタープライズ”とは?(→記事要約<Page 2>へ) |
|
|
| - | 俊敏な企業だけが生き残る |
- - PR -
企業を取り巻く環境が目まぐるしく変化している。規制緩和や経済のボーダレス化、インターネットやユビキタスネットワークの浸透など、その要因は枚挙にいとまがない。
こうした中、企業が生き残りをかけて競争優位を築く際に、見逃せないのが変化への対応能力である。市場を見回してみても、斬新なビジネスモデルやアイデアだけで成長した企業はなかなか見当たらない。製品やサービスのライフサイクルが短くなり、成功パターンが長期的に有効であり続けることはまれだ。成功した企業があれば、何らかの形で模倣・追随する企業が出現し、先行成功企業の競争力は急速に失われるのが常だ。
企業が継続的に成長するためには、常に競合の半歩先を走り続ける「俊敏な自己変革能力」をDNAとして内在していなければならない。ダーウィンの進化論によれば、生物進化の歴史の中で生き残ったのは“強い種”ではなくて、“変化に適応した種”なのである。
| - | 顧客指向で業務プロセスを改革する |
変化に対する俊敏な対応とは何か? 企業の主要なステークホルダーを、(1)顧客、(2)株主および社会、(3)自社経営陣および従業員、に分類して考えてみよう。
最も重要なのは、いうまでもなく顧客だ。先に述べた環境の変化は、顧客の要求を多様化させる。対応する側の企業にとっては、多様な付加価値を提供しないことには価格の引き下げ幅だけが競争の軸となり、収益性が低下してしまう。提供する付加価値を考える際に、強く意識してほしいポイントがある。
顧客の視点でエンド・ツー・エンドの業務プロセスを検討することだ。言葉にすると当たり前に感じるかもしれないが、実態はなかなかそうなっていない。多くの大企業は、営業、製造、経理といった機能別の組織によって構成されており、それぞれが業務の効率を高めるために努力を重ねてきた。そのため、どうしても全体最適の視点が不十分になりがちだ。
しかし、競争力のある企業は、自社だけでなく顧客やパートナー企業を巻き込んで、一連のサプライチェーンを構成し、その中で業務の効率化を図っている。デルやシスコといった企業がその代表例だ。
| - | 株主および社会への説明責任を果たす |
企業の社会的責任(CSR)、コンプライアンス、内部統制などが注目を浴びるようになり、国内でも2008年3月度から日本版SOX法の適用が始まる見込みだ。日本版SOX法によって経営者は「財務報告の信頼性確保」のため、会社全体および業務プロセスにおける内部統制の整備と運用について、評価と報告を求められることになる(参考:内部統制強化のアプローチ)。b
株主および社会へ開示する財務情報の高い信頼性を証明できること、すなわち財務情報がどの業務のどの情報から生成されたものか明確で、かつそれらの業務やデータ処理が統制されていることが重要である。財務情報を生成する業務は多岐にわたるが、各業務が分断または業務アプリケーションが細切れで、数多くのインターフェイス処理によってデータが連携されている企業は多い。財務情報までつながる業務プロセスを正しく設計し、その業務プロセスに沿ってデータの流れをモニタリングできる仕組みを構築することが必須である。
|
| - | 自社の業務効率を向上させる |
企業の経営者や従業員といったステークホルダーにとっては、外部環境の変化を抜きに考えても、自社の業務を効率化しコストを低減させる取り組みの重要性は明らかだ。この目的を実現すべく、多くの企業がBPRに取り組んだが、必ずしも芳しい結果を得ていない。BPRの提唱者であるM.ハマーが籍を置いていたマサチューセッツ工科大学(MIT)が1997年に実施した調査では、実にBPRプロジェクトの70%が失敗に帰している。
その原因にはさまざまなものがあるだろうが最もポイントといえるのが、ある時点で最適なBPRを構想しても、それを実現するIT化や運用の過程でも、経営環境は変化を続けており、適切な業務プロセスも様変わりするということだ。これに対応するためには、継続的な業務改善を意図したプロセス更新、すなわち環境と戦略の変化に合わせて、あるべき業務を定義し実行に移すサイクルの短縮および俊敏性の向上が必要であり、変化の激しい時代においては競争優位として重要性を増すのである。
| - | 経営とITの融合 |
企業の俊敏性は、別の切り口からも考えることができる。企業活動は3つの階層──(1)戦略立案、(2)業務管理、(3)実行、に分けられる。互いの整合性の欠如や連携の遅さが俊敏性を妨げている。主要な原因として以下の問題点を指摘できる。
- 現状をタイムリーに把握できない
- IT対応が後手に回る
この中身をそれぞれ詳しく見ていこう。
■ 1. 現状をタイムリーに把握できない
改善を図るには実態を把握せねばならない。逆にいえば“見えないものは改善できない”。ERPに代表される情報システム導入などによって、財務状況や在庫量などのサプライチェーン情報の把握は一般的になってきた。
しかし、業務プロセスそのものの状況、例えば一連のプロセスのどこでどのくらい例外処理が発生しているかなどは、あらためて調査をしなければ分からない場合が多い。業務の効率低下にはこうした一部の例外処理が大きく影響している。一般的には20%の例外処理が非効率の80%を占める(80:20の法則)。何が原因で例外処理が発生しているか見極め、一定以上の割合で恒常的に発生するなら定型処理としてIT対応を行うことが効果的だ。一方で、頻度の少ない例外処理に対してIT対応を施し、効果の割に費用が肥大してしまうこともある。コンサルの現場で接する大企業では後者の例が多い。
また、バランスト・スコアカード(BSC)などの業績評価の仕組みを導入しているものの現場寄りの指標(KPI)については十分に値を入手できず、取りあえず測定できる値を集めて運用を開始し、効果が疑問視される例も見受けられる。
■ 2. IT対応が後手に回る
企業の俊敏性に照らしてITを考えると、システムの構築や改変に要する期間がボトルネックだと気付く。経営判断の基になる決算は四半期や月次での開示が一般的になり、戦略も同程度のサイクルで見直される。しかし、基幹情報システムの再構築であれば通常1年以上かけて行われる。継続的な業務改善を実施するにも、緊急度が高くなければある程度要件がまとまってからシステムに手を入れることが多い。
また、戦略立案、業務管理、実行の実施部署が異なり、業務要件とシステム要件の整合性が取りづらい。さらに業務要件を作成してからシステム要件に翻訳する流れの中で、IT化にそぐわない業務要件やITそのものを目的化したシステム要件などが生み出されてしまうという問題もある。運用開始後のシステムに改変を重ねる際には、設計ドキュメントとの整合性が正しく確保されない例も散見される。
| 1/2 |
|
||||||||