
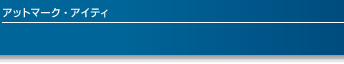
 |
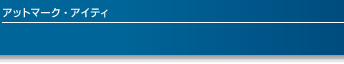 |
@IT|@IT自分戦略研究所|QA@IT|イベントカレンダー+ログ |
|
Loading
|
| |
| @IT > 業務システムのフロントエンドとしてのMicrosoft Office Systemの実力(1) - Page1 |
|
企画:アットマーク・アイティ 営業企画局 制作:アットマーク・アイティ 編集局 掲載内容有効期限2004月5月31日 |
|
|
|
|
|
マイクロソフトが提供するビジネス・アプリケーションの最新版、Microsoft Office Systemが先ごろ発表された。このMicrosoft Office Systemでは、各アプリケーションの機能向上がなされているだけでなく、XMLベースのカスタム・スキーマ対応や、Webサービス対応により、ビジネス・フロントエンドの領域におけるデスクトップ・アプリケーションの可能性が大きく広げられている。 しかしアプリケーション単体の機能向上やグラフィカル・インターフェイスの改良など、ひと目で分かる機能拡張/改良に比較すると、XMLスキーマ対応やWebサービス対応などは、Officeアプリケーションの業務への応用という意味では非常にポテンシャルが高いものの、そのメリットを容易には評価しづらいものだ。 そこで本稿では、特に業務アプリケーションへの応用という視点に立ち、2回にわたり、Microsoft Office SystemのXML対応とWebサービス対応によってビジネス・コンピューティングに新たにもたらされる価値について解説していく。
周知のとおり、XML(Extensible Markup Language)は、異なるシステム間でのデータ交換を可能にする標準技術として、ここ数年で急速に普及したマークアップ言語である。XMLの大きな特徴は、文書構造を決定するための規則を文書の作成者が決定できることだ。HTML同様、XMLもタグを利用してデータを記述するのだが、XML仕様にはタグそのものに対する規定はない。XMLが規定するのは、タグとタグ同士の関係、文書に書式情報を付加するための標準的な方法などで、HTMLのようにあらかじめ固定的に定義されたタグは存在しない。このようにXMLは極めて柔軟性の高いメタ言語であり、あらゆる文書をモデル化することが可能だ。 XMLでは、タグによってデータの構造(意味)をデータ内部に記述することができる。この機能を応用すれば、従来は1対1の対応が必要だった異なるシステム間でのデータ交換において、多対多のデータ交換が可能な、開かれた標準データを構成できる。 例を挙げて説明しよう。現在でも、CSV形式でのデータ交換が広く行われている。CSV形式とは、データベースのデータをカンマ区切りのテキストで表したものだ。CSV形式では、データの並び順に重要な意味があり、その並び順を知るもの同士しか正しいデータ交換ができない(例えば「2003」という数字があったとして、それが「2003円」なのか「2003個」なのか「2003年」なのかは分からない)。これに対しXMLでは、データの意味をタグとして記述できるため、互いに相手を知らないシステム同士でも、データの意味を解釈して、連携することが可能だ。 こうしたXMLの長所を利用して、情報システムを利用するあらゆる産業、あらゆる場面で、標準データ形式としてXMLベースのデータ・スキーマ(文書構造)を規定する動きが加速している。例えば金融サービスや保険、医療などの産業において、各業界特有の構造を持ったスキーマが開発され、標準化されている。
これまでXMLの利用といえば、サーバ・サイドのデータ交換が中心だった。しかし企業に存在する情報は、現場の担当者レベルで発生、収集されるものも少なくない。例えば、現場の営業マンが収集した顧客の生の声や、日々の営業活動の中で気付いた拡販のヒントなどは、より高い利益率追求に大いに役立つ情報である。しかしこうした情報を組織的に管理し、業務に生かしている企業は多くないだろう。ほとんどの企業においてこれらの情報は、電子メールやワードプロセッサの文書、スプレッド・シートなどとして、担当者のPCやファイル・サーバ上に散在している。このような状態では、たとえ情報がどこかに存在したとしても、必要な情報を見つけ出すのは容易ではなく、運よく見つけたとしても、それを希望する形式に再構築するために多大なコストが必要になってしまう。 この問題を解決するには、データを最初に入力する段階の末端ユーザーのレベルから、将来の情報共有を前提としたアプリケーションを利用することだ。Microsoft Office SystemがXMLに対応する根本的な目的はここにある。 情報が散在する最大の理由は、情報のコンテンツ(データ)と表現手段がアプリケーションのデータとして混然一体化しているためだ。これに対しユーザーが触れるデスクトップ・アプリケーションにXMLテクノロジを活用することで、コンテンツと表現手段を分離することが可能になる。これにより、特定のアプリケーションや表現手段に依存することなく、コンテンツに含まれる情報を特定の作業やユーザー、業務プロセスなどに応じて構成し直し、再利用できるようになる。
OfficeのXML対応自体は、Microsoft Office Systemの2世代前に当たるOffice 2000の時代から行われている。ここでは、Office 2000、Office XP(Office 2002)、今回のMicrosoft Office Systemで、それぞれXML対応がどのように進化したのかを追ってみよう。 ■Office 2000:データ形式は独自で活用も困難 XMLデータをOffice 2000アプリケーションの中で操作することは可能だったが、これにはVBA(Visual Basic for Applications)によるカスタム・コードを記述しなければならなかった。このようにOffice 2000のXML対応は、データ形式も独自で活用も容易でなかったため、あまり利用は進まなかった。 ■Office XP:XML対応はデータ部分のみ XML対応がメタデータの追加に限定されたOffice 2000に対し、Windows XPでは、数値などの定量的なデータを扱うアプリケーションにおいて、それらの値をXML形式で出力する機能が付加された。具体的には、定量データを扱うExcel、Access、Visioがこの機能を搭載していた。データをXML形式で出力する機能が追加されたことで、バックエンドのシステムとOfficeアプリケーションの間で定量的なデータを同期させることが可能になった。 ただし、Office XPでのXML対応は、あくまでデータ部分を固定的なスキーマに応じてXML形式のタグで出力するのみであり、任意のスキーマに対応してデータをインポートしたり、データの表現形式を規定するスタイル・シートに対応したりはしていなかった。カスタム定義のスキーマに対応するには、VBAを使って独自のプログラムを作成する必要があった。 さらにOffice XPでは、XML Webサービス対応が追加された。バックエンドのデータベースとOfficeアプリケーションを連携させる場合、それまではODBC(Open DataBase Connectivity)やADO(ActiveX Data Objects)などを利用する必要があった。ローカル・ネットワークだけで閉じたシステムならばこれでもよいが、ファイアウォールを超えて異なるシステムを連携させるBtoBシステムに用いることは難しい。これに対しXML Webサービスでは、通信プロトコルとしてWebアクセスとしても利用するHTTPを利用可能であり、ファイアウォールを超えた通信が容易である。 具体的には、Office XP Web Services Toolkitという無償提供されるアドオンソフトウェアをOfficeに追加することで、ExcelとAccessをXML Webサービスのフロントエンドとして機能させることが可能であった。ただしこれには、各クライアントに.NET対応アプリケーションを実行するためのランタイム環境である.NET Frameworkを追加インストールしなければならない。特に大量のクライアント・コンピュータを抱える大企業では、.NET Frameworkの展開だけでも大幅な工数がかかる。またクライアント・アプリケーションに加え、.NET Framework自体のバージョン管理も加わることになる。クライアント・アプリケーションのバージョン管理は、TCOを悪化させる大きな要因の1つである。そのためこれは、積極的に選択されるソリューションとはなりにくかった。 ■Microsoft Office System:カスタムXMLスキーマに対応 すでに企業内には、さまざまな情報システムが存在しており、データベース(スキーマ)があったり、場合によってはXML Webサービスがある。これらの情報システムと連携する場合、従来はクライアント側で連携先のバックエンド・システムに合わせてカスタム・プログラムなどを作り込む必要があった。これに対しMicrosoft Office Systemでは、ユーザーが定義したXMLスキーマをOfficeアプリケーション内部に取り込むことが可能になり、既存のバックエンド・システムとの連携が極めて容易になった。具体的には、XSD(XML Schema Definition Language:スキーマ定義言語)のスキーマを与えれば、Excel 2003、Word 2003の各アプリケーションで特別なプログラムなどを作成することなしにXMLデータを扱える(XSDにはAccess 2003も対応している)。ERPやCRM、SFA、経理システムなど、既存の情報システムのフロントエンドとして容易にMicrosoft Office Systemを位置付けられるわけだ。 またMicrosoft Office Systemには、企業内の情報収集と再利用のプロセスを大幅に効率化するアプリケーションとして、InfoPath 2003が追加された。InfoPath 2003を利用することにより、スキーマに対応した入力用のフォームを簡単に作成し、ユーザーの入力結果をXMLデータ形式で保存できる。この際のデータの保存先はハードディスクばかりではなく、XML Webサービスでもよい。InfoPath 2003を利用することで、複数の業務や企業間で利用されるデータの情報収集プロセスを格段に効率化することができ、データの再利用も円滑化される。InfoPath 2003の詳細については、以下の記事を参照されたい。
さらに続けて、企業で日常的に行う定型業務と定型化できない非定型業務の連携に一役買うMicrosoft Office Systemの機能を紹介しよう(次ページへ続く
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||