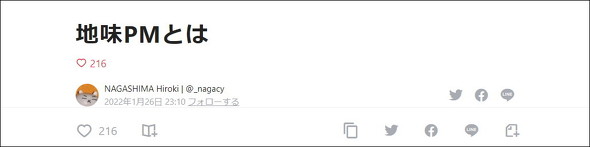「地味だからつらいのではなく、地味だけど楽しい」 地味プロダクトマネジャーのススメ:明日を輝かせる「地味PM」(1)
華やかなイメージが強いプロダクトマネジメントだが、実際は地味な仕事がほとんどだ。しかし、その地味な仕事こそが企業のビジネスを支えている。そうした「地味PM」たちの「誇りある地味な仕事」を紹介する本連載。第1回は「地味PM meetup」を主催した2人に、イベントを開催したいきさつについて聞いた。
企業のビジネスを革新し、成長させるためには新たなプロダクト開発が欠かせない。どの企業も画期的なプロダクトをいち早く生み出し、世に送ることに注力している。プロダクトマネジャー(PM)はそうしたプロダクトやプロジェクトをリードする役割を担っている。
IT業界の中でもきらびやかなイメージがあり、尊敬や称賛の目で見られることも多いが、実際にPMを経験したことがあるなら、輝かしさの水面下には地味な努力が広がっていることを痛感しているはずだ。表面がキラキラしているかどうかはさておき、認知されている仕事の水面下には認知されていない仕事も膨大にある。
本連載は、そんな“地味だが重要”な「地味PM」の仕事ぶりを紹介する。第1回は“地味PM”という造語の生みの親である、heyの永嶋広樹氏とNstockの佐藤 潤氏に話を聞いた。
地味PMは楽しんで仕事をしている
永嶋氏と佐藤氏は2022年4月に、地味PMの仕事内容について共有するイベント「地味PM meetup」を主催した。イベント開催に至る最初のきっかけは少人数で実施した「業務に関する勉強会」だという。
2人は決済システムやFintech(フィンテック)に関連したマネジメントの経験が多く、決済系のプロダクトとは切っても切れない関係にある「審査」について互いの会社のPM同士で話す機会があった。すると、経験者ならではの「あるある」で共感の輪が広がり、貴重な情報交換の場になったという。
「『世間では“PMはキラキラしていてすごい”と言われることもあるけれど、実際の業務の水面下は細かなタスクも多く、混沌(こんとん)とした部分もある。目に見える分かりやすい成果物の他に、地味に進めていかなくてはならないことも多いよね』といった話をしたところ、めちゃくちゃ盛り上がったんです」(佐藤氏)
その中で印象に残ったのが「話し合いの中で“地味”というキーワードがポジティブに受け入れられていたこと」だ。永嶋氏はそのときのことを「地味だからつらい(浮かばれない)のではなく、地味だけど、楽しい(やりがいがある)と受けとめる人が多かった。何よりもその場にいたPM全員が楽しんで仕事をしていた」と振り返る。
「6人いれば形になる」でスタートしたイベント
そうした出来事もあり、永嶋氏は「地味PMの概念がどれくらい皆に受け入れられるのか」について興味を持ち始めた。カジュアル面談サービス「Meety」を通じて「地味PMについて語ろう」と呼び掛け、さまざまなPMの話を聞いた。永嶋氏によると「『PM』と入れているにもかかわらず、実際の応募者はPMやエンジニアだけではなく、広報や営業など、他の職種の方も少なくなかった」そうだ。
永嶋氏は、こうしたカジュアル面談で得た情報やこれまで考えてきたことを「note」に記事を投稿した。
記事はTwitterを中心に多くの反響があり、「このテーマは需要がありそうだ」と手応えを感じた永嶋氏は佐藤氏と相談し、イベント開催を決定。「たくさんの反響をいただいて大変ありがたいと感じると同時に、需要のあるテーマなんだと確信しました」と永嶋氏は語る。
ただ、イベントといっても、多くの参加者を集めた大々的なものは期待していなかった。もともと少人数の勉強会で盛り上がったこともあり、「『登壇者6人だけのイベントになるかもしれないけどそれでもいいや』くらいの気持ちで考えていました」と佐藤氏は言う。だが実際は、参加希望者が200人を超える大きなイベントとなった。
「イベントで興味深かったのは登壇者全員の“地味に対する切り口”が違っていたことです。評価にフォーカスする人もいれば、組織にフォーカスする人もいました」(永嶋氏)
興味深い出来事はイベント終了後にもあった。「次があるなら自分も話したい」と登壇の立候補が相次いだのだ。「地味という言葉のハードルの低さと共感の強さから『人の話をただ聞いて終わり』ではなく『自分も持っているものを出したい』という気持ちをくすぐったのかもしれない」と佐藤氏は振り返る。
「トラブルを発生させないための仕事」は尊い
「地味」といいながらも、こうも多くの人の心をつかんでいるのはなぜだろうか。永嶋氏がMeetyに載せている文章にそのヒントがある。
“PMは、誰に言われるでもなく、誰も気付いていない課題を見つけ、誰も理解できていない構造に着目し、誰もやらないタスクを率先して取り、誰もが理解できる価値をアウトプットし、アウトカムを生み出さねばなりません”
この話はPMを想定しているものの、究極的にはPMだけではなく他の職種にもどこか当てはまる普遍性がある。だから多くの人の琴線に触れるのではないだろうか。永嶋氏は「普段自分の仕事に誇りをもって取り組んでいても、本当に貢献できているのか悩んでいたり、(その仕事や意義を表す)ラベルが付いておらず悩んでいる人が多いのではないでしょうか」と分析している。
ビジネスを継続させるために重要な仕事でも、地味なだけに周囲から見過ごされてしまうことはある。自分の気遣いや配慮が職場を支えているのに、気付いてもらえないとなると悔しさを感じてしまうのも無理はない。
一方、目立つのは“派手な展開を伴う実績”だ。例えば、IT業界ならシステムで障害が起きるなどの緊急事態に対し、間一髪で危機を脱したようなパターンが分かりやすい。こういうドラマチックな要素があると目を引くし、評価されやすい。しかし、「そもそも危機的な状況に陥らないようにすることも、PMとして重要な仕事なはずです」と永嶋氏は指摘する。地味PMの活動はそうした事実に気付くきっかけになっているのかもしれない。
「PMの解像度を上げていきたい」
永嶋氏は「地味というと“キラキラ”の対極をイメージしてしまうかもしれません。しかし実際は、地味とキラキラは表裏一体であり、共存しています」と指摘する。
永嶋氏と佐藤氏の両者に共通しているのは「地味なところも受け入れてPMの仕事を楽しみたい」と考えていることだ。純粋に楽しく、喜びを感じられる体験は繰り返したくなるし、他の人とも共有したくなる。noteやTwitterでの話題の広がりもそれに拍車を掛けている。
今後のイベントや活動について聞くと、佐藤氏は「PMの解像度を高めていきたい」と言う。今も2022年7月に開催する2回目のイベント「地味PM meetup #2」に向けて準備中だ。地味もキラキラもあるPMのリアリティーをいろんな人がいろんな角度から語るようになると、PMへの理解が深まり、現役または未来のPMの役に立つことがあるだろう。
一方で永嶋氏は「(自分が)地味PMを象徴する存在にはなりたくない」と笑う。地味PMは、あくまでも“地味な部分もある仕事の中で大切なもの、価値があるものを見いだすためのキーワード”だからだろう。「地味PMという言葉の賞味期限は短いと思います。理念や価値が自然に広まることで、誰も“地味PM”と言わなくなる時が早く来るといいですね」と永嶋氏は語る。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
関連記事
 企業やサービスをつなぐ分散トランザクションマネージャを目指して
企業やサービスをつなぐ分散トランザクションマネージャを目指して
マイクロサービスアーキテクチャが注目される一方、課題として浮き彫りになっているのが「分散トランザクション管理」です。「分散トランザクション」とは何か、どのような解決策があるのか、分散トランザクションマネジャーを提供するScalerへのインタビューを交えながら紹介します。 「DXを支える開発マネジャー」を一からつくる方法
「DXを支える開発マネジャー」を一からつくる方法
DXの機運の高まりもあり、プロダクト開発にかかる期待は大きい。ただ、開発チームのマネジメントは高度化しており、「どのようにマネジメントスキルを身に付ければいいか」と悩む人も多いだろう。本稿は「DX時代に必要なマネジメントスキル」について解説する。 「管理職」をネガティブに捉えるのがもったいない理由――古川陽介氏、和田卓人氏、松本亮介氏らが語るスペシャリストまでの歩み
「管理職」をネガティブに捉えるのがもったいない理由――古川陽介氏、和田卓人氏、松本亮介氏らが語るスペシャリストまでの歩み
キャリアの問題が「エンジニア35歳定年説」として議論されて久しい。では、ITの最前線で活躍するエンジニアはキャリアをどう考えているのか。2021年1月下旬にForkwellが主催した「Engineer Career Study #1」でITの最前線で活躍する古川陽介氏、和田卓人氏、松本亮介氏らが語った。