
連載:IEEE無線規格を整理する(3)
〜ワイヤレスネットワークの最新技術と将来展望〜
ZigbeeとBluetooth、UWBをめぐる動き
千葉大学大学院 阪田史郎
2005/10/12
| IEEE無線企画を整理する連載第1回目「無線ネットワークの規格、IEEE 802の全貌」では、拡大するIEEE 802規格の全貌を、第2回では、実用化が始まった「標準化が進むRFIDと日本発ucode」について説明してきた。ZigbeeやBluetoothなどの無線PAN(パーソナル・エリア・ネットワーク)についてまとめたい。 |
| 無線PAN |
IEEE 802.15委員会で標準化の議論が進展している無線PANには、UWB、ZigBee、Bluetoothがある。図1に無線PANのそれぞれの技術開発、標準化の推移を示す。
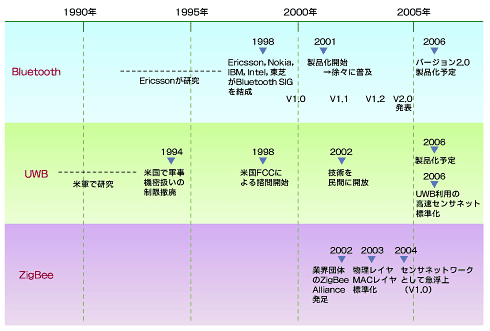 |
| 図1 無線PAN標準化の変遷(クリックすると拡大表示します) |
表1にIEEE 802.15委員会における現在活動中の主なTG(Task Group)の構成を示す。製品としてはBluetoothが先行したが、速度的にBluetooth(700kbps強)の約1/3のZigBeeがセンサネットワークとして、Bluetoothの100倍強のUWBが高品質マルチメディア通信用のPANとして、それぞれの特徴を生かし2005年から2006年にかけて製品化される状況である。
|
|||||||||||||||||||||
| 表1 無線PAN IEEE 802.15の現在の構成 |
| 1. UWB |
1.1 UWBとその特徴
UWBは、超広帯域無線と訳されるように、短距離ながら100Mbps以上の高速な通信が可能である。帯域幅に関しては、例えばFOMA等の第3世代携帯電話サービスで採用しているW-CDMAの帯域幅が5MHzであるのに対し、UWBの帯域幅は下記のように7.5GHzで約1500倍の帯域幅があり原理的にはGbpsオーダの通信が可能である。また、UWBにおける送信電波の出力はPCから出るノイズ以下程度と微弱で、電波干渉の問題は少ないと考えられている。
UWBは、1980年代後半より米国国防総省DoD(Department of Defense)の軍事研究の一環として、壁などの障害物を通過してその向こう側に存在する物体の認識を可能にするレーダ技術として研究されてきた。この中で、広帯域インパルス、特に変調キャリアを必要とせず、ベースバンド信号を直接電波として送出できる技術としてUWBという用語が使われ始めた。その後、1994年の米国による軍事機密扱いの制限撤廃、1998年の法制度変更に関する米国連邦通信委員会FCC(Federal Communications Commission)による諮問開始を経て、2002年2月にはFCCがUWB通信方式を正式に認可し民間での利用を許可したため、各国において無線デバイス、情報家電、PC業界を中心とした技術開発競争が急速に激化した。
UWBは非常に広い帯域を用いることにより、以下のような特徴がある。
| (1) マルチパスの遅延時間を1ns以下に分解でき、RAKE受信が可能となるため、マルチパスフェーディングの影響を抑えることができる (2) 高いパス分解能力により、室内の高品質近距離無線通信が可能 (3) フェーディングの影響を低く抑えられるため、送信電力が小さくて済む (4) 送信電力が小さくて済むため、電力スペクトル密度が非常に低くなり、ほかの狭帯域伝送に影響をほとんど及ぼさない (5) 位置検出の精度が高く、誤差は数cm内 |
1.2 UWBの標準仕様概要と応用分野
UWBの特徴を一言でいえば、100Mbps以上の高速通信と200mW以下の低消費電力であり、この2条件を満たす技術は、UWB以外には考えにくいといえる。表2にUWBの主要諸元を示す。
|
||||||||||||||||||||||
| 表2 UWBの主要諸元 |
2005年9月現在、法制度および産業界からの技術的な要望が以下の6点にまとめられている。
| (1) 送信帯域は、3.1〜10.6GHzを対象とし、これ以外の帯域への電力放射は法制度下で漏えい電力の規制を受ける (2) (1)の送信帯域で送信可能な最大電力は、法制度の許可する範囲で平均41.25dBm/MHzとする (3) 送信シンボルとしてのUWB信号は、500MHz以上の帯域幅を持つ (4) 通常室内環境10mの距離で、スループットとしては、上記通信品質を維持する条件の下で110Mbps以上を達成する (5) スループットに関して、見通し内近距離3mで480Mbps以上を達成するデバイスの通信時消費電力を最大200mW以下に抑える。 |
これらの要請が満たされたうえで、図2に示すような多様な応用が検討されている。

|
|
| 図2 想定されるUWBアプリケーション例 |
1.3 UWBの標準化動向
標準仕様については、当初20以上の方式が提案されたが、2005年8月現在、搬送波による変調を用い、OFDMを応用したMB-OFDM(Multi-Band Orthogonal Frequency Division Multiplexing)方式と、インパルス無線方式とDS(Direct Sequence)-SS方式のハイブリッド方式であるDS-UWB方式の2つの方式が残っており、一本化に向けた審議が続けられている。MB-OFDM方式はIntelやTI(Texas Instruments)などが推し、DS-UWB方式はMotorolaやFreescaleなどが推している。いずれの方式も5GHz帯の既存システムとの被与干渉を回避できる方式となっている。
1.4 UWBをめぐる動向
国内では、2002年に総務省を中心に国内での利用の検討が開始されたが、周波数の干渉の問題で、屋外での利用のめどが立っていない。3.1〜10.6GHzにおける被干渉システムとなる、電波天文、第4世代携帯電話、デジタル放送、地球探査衛星、衛星地球局、固定無線システム、リモートセンシング等との調整が続けられている。
UWBのMACレイヤ以上の標準化、相互接続を目的としたWiMedia Alliance と呼ばれる業界団体(2005年9月時点で142社が加盟)が、MB-OFDM方式 を採用したワイヤレスUSB(Wireless Universal Serial Bus。有線のUSB2.0を無線化し仕様も同等)を業界標準として支持することを表明している。 MB-OFDM方式の普及や製品化を促進するためMBOA(MultiBand OFDM Alliance)と呼ぶ業界団体も結成されたが、2004年にWiMedia Allianceに 移行している。
2004年に開催されたUSBフォーラムでは、無線ネットワークとして用いるUWBについて、MB-OFDM方式の採用を決定した。ワイヤレスUSBは、PCの周辺機器のワイヤレス接続に加え、情報家電や携帯電話の接続インターフェイスとしてもその利用が期待されている。図3に、UWBを用いたワイヤレスUSBを含むシステム体系を示す。
 |
| 図3 UWBを用いたワイヤレスUSBのシステム体系 |
DS-UWB方式に対しては、MB-OFDM 方式におけるMBOAに相当するUWB Forumと呼ぶ業界団体が結成され、DS-UWB方式の普及と製品化を推進している。
また、2004年には、UWBを物理レイヤに用い、IEEE 802.15.3aよりも低速ながらZigBeeよりも高速なセンサネットワークへの対応を狙いとした標準化の議論が、IEEE 802.15.4aにおいて開始された。ZigBeeの250kbpsに対し、数Mbpsの通信を目指している。MACレイヤにZigBeeの仕様を適用することも検討されている。
| 関連リンク | |
| 特集:Voice
over Wireless LANの実現 第1回 無線IP電話の思わぬ落とし穴 第2回 無線IP電話の音質を左右する機器の選び方 |
|
|
特集:エンタープライズ・ワイヤレス |
|
| 【トレンド解説】802.11n、UWB、WiMax 2005年のワイヤレスの行方を占う |
|
| 連載:進化するイーサネット(安価・高速・簡素なネットワーク媒体) 「パケット」を運ぶイーサネット物理層/MACフレームを運ぶイーサネット物理層/SAN WANにも広がるイーサネット |
|
| 「Master of IP Network総合インデックス」 |
- 完全HTTPS化のメリットと極意を大規模Webサービス――ピクシブ、クックパッド、ヤフーの事例から探る (2017/7/13)
2017年6月21日、ピクシブのオフィスで、同社主催の「大規模HTTPS導入Night」が開催された。大規模Webサービスで完全HTTPS化を行うに当たっての技術的、および非技術的な悩みや成果をテーマに、ヤフー、クックパッド、ピクシブの3社が、それぞれの事例について語り合った - ソラコムは、あなたの気が付かないうちに、少しずつ「次」へ進んでいる (2017/7/6)
ソラコムは、「トランスポート技術への非依存」度を高めている。当初はIoT用格安SIMというイメージもあったが、徐々に脱皮しようとしている。パブリッククラウドと同様、付加サービスでユーザーをつかんでいるからだ - Cisco SystemsのIntent-based Networkingは、どうネットワークエンジニアの仕事を変えるか (2017/7/4)
Cisco Systemsは2017年6月、同社イベントCisco Live 2017で、「THE NETWORK. INTUITIVE.」あるいは「Intent-based Networking」といった言葉を使い、ネットワークの構築・運用、そしてネットワークエンジニアの仕事を変えていくと説明した。これはどういうことなのだろうか - ifconfig 〜(IP)ネットワーク環境の確認/設定を行う (2017/7/3)
ifconfigは、LinuxやmacOSなど、主にUNIX系OSで用いるネットワーク環境の状態確認、設定のためのコマンドだ。IPアドレスやサブネットマスク、ブロードキャストアドレスなどの基本的な設定ができる他、イーサネットフレームの最大転送サイズ(MTU)の変更や、VLAN疑似デバイスの作成も可能だ。
|
|




