SAN/WANにも広がるイーサネット:進化するイーサネット(3)
この3回の連載では、イーサネットの本質と進化を分かりやすく紹介しています。第1回「『ネットワーキング』から『データリンク』提供へ」ではイーサネットがリンク技術として高速化してきた進化の背景を、第2回「MACフレームを運ぶイーサネット物理層」では伝送媒体にMACフレームを送出する部分(物理層)の進化を紹介しました。
最終回は、イーサネットがSANやWANに進出する背景を紹介します。パケットを運ぶLANに対して、従来のSANやWANの仕組みがどう異なっているのか見ていきます。パケットを安く高速に運べるイーサネットは、IPネットワーク全盛の時流に乗って、SANやWANにもその適用領域を広げています。
物理層の共通化が進むSAN/LAN/WAN
まず、従来のSAN/LAN/WANのすみ分けを見てみましょう。SAN(サン:Storage Area Networ)はストレージ・エリア・ネットワークの略称です。大規模なデータセンタなどで、多数のサーバとハードディスクアレイを相互接続するために使われています(図1)。
図の上部に、皆さんがホームページを閲覧する場合を例示してあります。オフィスのパーソナルコンピュータ(PC)から、データセンタのサーバに向けて、Web閲覧要求サインを運ぶIPパケットを送ります。サーバは、デバイスインターフェイス経由でディスクアレイからHTMLデータを読み出し、IPパケットに加工してPCに返送します。
このとき、まずPCからオフィス内のルータまで、LANでIPパケットを運びます。ここで普及しているのが、IEEE標準802.3イーサネットです。パケットにヘッダとトレイラを付けたフレームにして、確実にルータまで送り届けます。最近では、イーサネットではなく、IEEE標準802.11無線LANを使う場合も増えています。
次に、データセンタまでは、通信事業者の専用線で構築されたWAN(ワン:Wide Area Network)を経由します。ここでは、光ファイバを使うSDH/SONET規格が主流です。SDH/SONETは「連続したバイト列を運ぶ」ための規格で、例えば、電話回線64kbpsを780本も束ねた52Mbps専用線を運びます。
インターネット経由の場合であっても、サービスプロバイダ(ISP)のルータまで、さらにはISPのルータからルータへは、こうした専用線(WAN)を経由してIPパケットが運ばれています。なお、SDH(エス・ディー・エイチ:Synchronous Digital Hierarchy)が国際電気通信連合ITU-Tの定める国際標準規格で、SONET(ソネット:Synchronous Optical NETwork)はそれに対応する米国規格です。ほぼ同じ規格なのですが、歴史的経緯から、SDHとSONETでは伝送単位の名称や監視信号の利用方法などが微妙に異なっています(参考文献の8章3節コラム1「SDHとSONET」参照)。
データセンタに到着したIPパケットは、センタ内LANを経て、最終目的地サーバに届きます。その結果、SANに接続されたサーバのデバイスIF(インターフェイス)経由で、ディスクアレイからデータブロックが読み出されます。このSANにおいては、「ブロックデータを運ぶ」ための規格であるファイバチャネルが利用できます。ファイバチャネルは、SCSIと同様にアメリカ標準規格協会ANSI(American National Standards Institute)が定めるデバイスインターフェイス規格で、独自のネットワーク機能が充実しています。
このように、SAN/LAN/WANはそれぞれ独自の発達を遂げてきましたが、近年、その垣根が低くなっています。特に「光ファイバを使ってデジタルビット列を送る」という物理層レベルでは、技術の共通化が進んでいます。受信したアナログ波形からタイミング情報を抽出してデジタルビット列を復元して並列展開するLSIチップや、電気信号と光信号を変換する光トランシーバなどは、流用できる場合が増えてきました。
以下では、まずその前提知識として、パケットを運ぶLANに対して、従来のSANやWANがどのように異なるのか、順番に解説していきます。
SANのファイバチャネル
SANのファイバチャネルとLANのイーサネットはよく似ていて、どちらもデータを塊として運ぶ規格です。フレーム形式(レイヤ2)や動作速度が微妙に異なるだけなので、物理層(レイヤ1)のLSIチップや光トランシーバを共用できる場合もあります。両者の関係を図2に示します。サーバを境に、ファイバチャネルはデバイスIF側(バックエンド)、イーサネットはネットワークIF側(フロントエンド)をネットワーキングします。
ファイバチャネルは、バス型のパラレルデバイスIF(例えばSCSI)をシリアル化する光IFとして発達してきました。ループ型のネットワーク構成も検討されましたが、現在は、スイッチを中心に置くスター型ネットワーク構成に収束しつつあります。
ファイバチャネルの基本速度は1.0625Gbpsです。毎秒100メガバイト、すなわちビット伝送速度839Mbps(=8bit×100×1024×1024)でブロックデータを運ぶために、約25%のオーバーヘッドを設けました。この速度上昇分を、8B/10Bブロック符号化(BはBinaryの略)やフレーム化、さらにはインターフレームギャップ(IFG)として活用しています。ファイバチャネルが最初に標準化されたのは1994年、イーサネットでは100Mbps規格すらいまだできていない時期です。ファイバチャネルは、構内網向けの低コスト光部品市場の開拓者となりました。
1998年に標準化されたギガビット・イーサネット規格は、このファイバチャネル規格の物理層部分を参考にしました。8B/10Bブロック符号化などその基本仕様が同じなので、クロック信号やデータ信号を復元するLSIチップや光トランシーバを共通化できます。企業内LANの市場規模は大きいので、Gbps光部品の価格低廉化が一気に進展しました。
ファイバチャネルとイーサネットでは、フレーム形式が微妙に異なります(図3)。ビット誤りがないかフレームをチェックできるように付加するトレイラは同じ4バイトですが、ヘッダや最大ペイロードはファイバチャネルの方が長めです。特にファイバチャネルのヘッダは、相手先や自分を特定するためのアドレスだけでなく、デバイスアクセスやデータブロック処理に便利な「その他のヘッダ」部分が豊富に準備されています。
ファイバチャネルとイーサネットはどちらもブロック符号を利用し、IFG特殊符号を含むアイドル信号を送信し続ける点も共通です。唯一、目立って異なるのは、ファイバチャネルでは、IFGで4バイト長のプリミティブ信号(ショートフレーム)を使ったシグナリング方式が規定されていることです(図4)。バッファあふれを防止するフロー制御などに利用することがあります。
バイト列を運ぶWANのSDH/SONET
WANで普及しているSDH/SONET規格は、電話回線や専用線など「連続するバイト列」を束ねて効率的に運ぶために発達したレイヤ1(物理層)の規格です。「パケット」を運ぶLANのイーサネットとの関係を図5に示します。SANのファイバチャネルよりもさらに早く、1988年には2.5Gbps規格が標準化されていて、まさに、光ファイバ通信技術のパイオニアです。
SDH/SONET規格を用いる従来のWANは、広域に点在するルータとルータの間に、所定帯域(例えば50Mbps)の連続バイト列を運ぶ「パス」(いわば「パイプ」のようなもの)を配管します。
SDH/SONET規格は、もともと、地域に点在する多数の電話機から発生するトラフィックを交換機に集めて、広域に点在する交換機と交換機の間に「パス」をメッシュ状に配管するために発達しました。50Mbpsで広域光ファイバを占有するのは非効率なので、実際は多数の「パス」を束ねた2.5Gbpsや10Gbpsで光伝送します。
SDH/SONET網とは、「パス」を配管するクロスコネクト装置(XC)や、リング状の高速光伝送路に「パス」を挿入(Add)したり分岐(Drop)したりする多重化装置(ADM:Add/Drop Multiplexer)を使って構築する、「パス」のネットワークです(図6)。
WANで普及したSDH/SONET規格には、広域に点在する伝送装置(XC、ADM、中継器)を遠隔から運用管理する工夫が凝らされています。例えば、広域網のEdge to Edgeに配管する「パス」ごとに、そのビット誤り率をモニタして品質を保証し、さらには所望の「パス」であることを示すID番号(パス・トレース)を付けて送ることができます。
これは、パス・オーバーヘッドと呼ぶ管理情報を、125μ秒ごとに定期的に送る仕組みが標準化されているおかげです。また、複数の「パス」を束ねた「ライン」ごとに、同様なオーバーヘッド情報を送る仕組みが標準化されているので、大規模な網を階層化して効率的に管理できます。
例えば、「ライン」単位で障害が発生したら、「ライン」ごと予備経路に迂回させ、「パス」ごとに障害対応する煩雑さを避けることができます。さらに、障害がどの「セクション」で発生したかを端局に伝えるセクション・オーバーヘッドもあるので、どこの中継器にエンジニアを派遣すればよいかまで分かります。
SDH/SONET規格では、125μ秒ごとに1フレームを送ります。元は、125μ秒ごとに1バイト(=64kbps)を連続的に送る電話回線を、多数束ねて効率的に運ぶための仕組みだからです。図7に、155.52 MbpsのSDH/SONET規格のフレーム構造を例示しました。
155.52Mbpsでのフレーム長は2,430byteです。SDH/SONET規格では高速化しても1フレーム時間は不変なので、2.488Gbps 規格でのフレーム長は16倍(3万8,880 byte)、10Gbpsでは64倍(15万5,520byte)になります。1フレームを9分割するサブフレーム構造は、米国・日本と欧州とで異なる基本多重化単位(T1とE1)(1.5Mbpsと2.0Mbps)に対応するためです。
サブフレームごとに、10byteがオーバーヘッド情報を運ぶために確保されています。このオーバヘッド領域には、バイトごと、さらにはサブフレームごとに、あらかじめ異なる役割が定められていて、上述した「パス」「ライン」「セクション」の管理情報を125μ秒ごとに運びます。
このように、SDH/SONET規格のフレーム構造は、可変長のデータ塊を送るためのイーサネットやファイバチャネルとは本質的に異なります。そもそも、パケットを運ぶためのレイヤ2機能がありません。このため、従来のWANでは、SDH/SONET網の提供する「パス」の上でパケットを運ぶために、PPP over SDH/SONET(POS)と呼ぶレイヤ2機能を併用しています。
パケットにヘッダとトレイラを付けたHDLCフレームにして、「フラグ」と呼ぶ特定の8ビットパターンでフレーム区切りを明示します。パケットの中に「フラグ」バイトが含まれるときには、あらかじめ、異なる2バイトのパターンに置換しておきます。パケットの中身次第でフレーム長が伸びるので、厳密な帯域保証には向きません。
イーサネットによるSAN/WAN
イーサネットの強みは、企業内LANに支えられた巨大な市場規模と、多数のネットワークエンジニアが存在することです。出荷数が多いので機器コストは低く、スキルのあるエンジニアが多いので運用コストも抑えられます。イーサネットのインターフェイス速度が高速化した結果、現在では、イーサネットでSANやWANを構築する動きが出てきました。
SANの世界では、イーサネットを利用する2種類の技術が開発されつつあります(図8)。いずれもIETFで標準化が進んでいる技術で、FCIPはFibre Channel over Internet Protocol、iSCSI(アイスカジ)はInternet SCSIを意味します。
FCIPは、IP網上で、ファイバチャネルのスイッチ同士をトンネリング接続する仕組みです。ファイバチャネルで構築したSAN同士を、イーサネットLAN経由で連結できます。すでに、イーサネットのインターフェイスを持つファイバチャネルのスイッチが登場しています。
iSCSIは、データブロックをIP網で運ぶ仕組みです。SANそのものを、低コストなイーサネットスイッチで構築できるようになります。サーバのデバイスインターフェイスをネットワークインターフェイスと共用できるのも利点です。現状では、ソフトウェア処理によってiSCSIを実現しているので、性能(スループット)に課題があります。このため、TCP/IP処理をハードウェア化する試みが進んでいます。
一方、WANの世界にも、いわゆる広域イーサネットサービスとして、イーサネット技術が進出しています(図9)。こうした広域イーサネット網を構築するには、2通りの方法があります。
第1の方法では、従来のSDH/SONET網やその上位のATM網を使って、レイヤ1の「パス」でイーサネットスイッチを結びます。イーサネットのMACフレームなど、任意の可変長フレームをSDH/SONETで運ぶための国際規格GFP(Generic Framing Procedure)がITU-Tで標準化され、利用され始めています。
さらに意欲的な第2の方法では、レイヤ1の物理層にも、イーサネット技術をそのまま使います。SDH/SONET網が利用していない光ファイバ(光を入射していないことから「ダークファイバ」と呼ばれる)を使って、ギガビット・イーサネットや10ギガビット・イーサネットでスイッチ間を直結します。ブロック符号化されたイーサネットのMACフレームが、そのまま、WANの光ファイバ網を流れ始めています。
第2の方法なら、LANのイーサネットスイッチをWANでも利用できます。すでに、プラガブルな光トランシーバとして、WAN用に数十kmも届く製品があります。さらに、イーサネットの物理層でも、光ファイバ網を管理運用するためのオーバーヘッド情報を送ることが可能になりつつあります。例えば10ギガビット・イーサネットの物理層は、ファイバチャネルのプリミティブ信号と同じ仕組みが使えるように標準化されました。このため、インターフレームギャップのアイドル信号の一部をリンク信号に置換することで、WANのSDH/SONET規格のように、オーバーヘッド情報を定期的に運ぶことができます(図10)。
以上、3回にわたって、イーサネットの本質と進化を分かりやすく紹介しました。30年前にブロードキャスト型のLANとして発明されたイーサネットは、全2重通信するリンク技術にその役割を変化させ、既存の物理層技術を取り込んで高速化してきました。今後も、SANやWANにその適用領域を広げるなど、さらなる進化を続けていくことでしょう。
【参考文献】
「10ギガビットEthernet教科書」IDGジャパン(著者と日立電線 瀬戸康一郎氏の共同監修)
ご愛読どうもありがとうございました
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

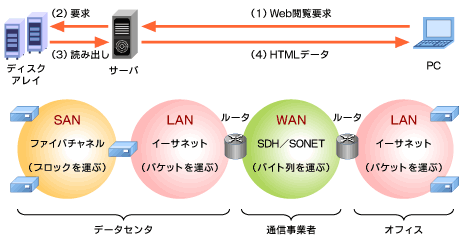 図1 SAN/WAN/LANの役割(ホームページを閲覧する場合)
図1 SAN/WAN/LANの役割(ホームページを閲覧する場合)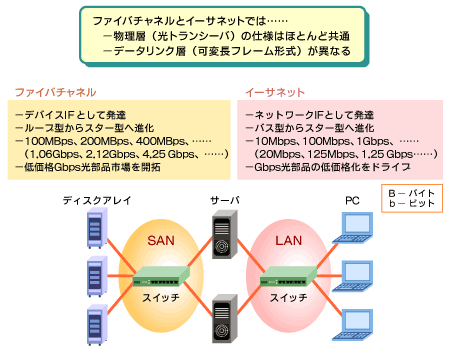 図2 SANのファイバチャネル vs LANのイーサネット
図2 SANのファイバチャネル vs LANのイーサネット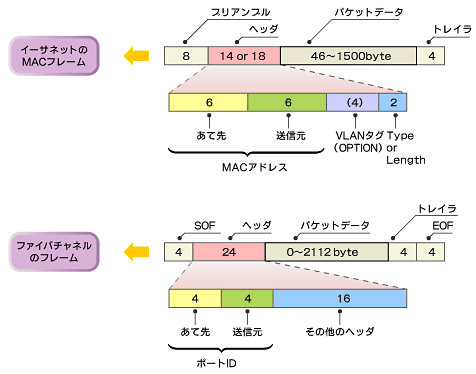 図3 可変長フレーム形式の違い(イーサネット vs. ファイバチャネル)
図3 可変長フレーム形式の違い(イーサネット vs. ファイバチャネル)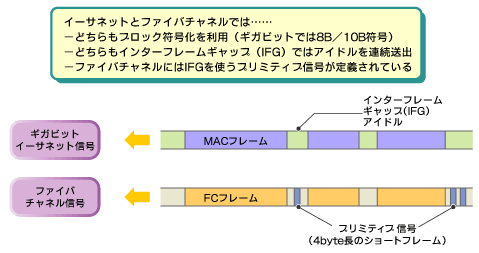 図4 物理層での違い(イーサネット vs ファイバチャネル)
図4 物理層での違い(イーサネット vs ファイバチャネル)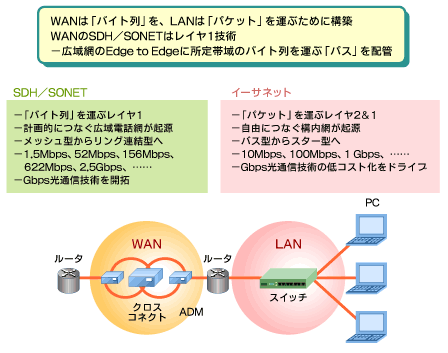 図5 WANのSDH/SONET vs LANのイーサネット
図5 WANのSDH/SONET vs LANのイーサネット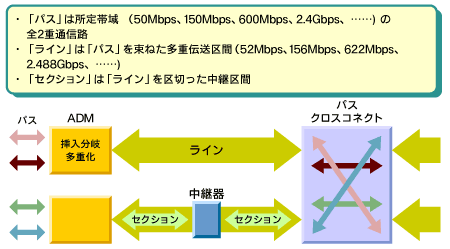 図6 SDH/SONETが実現する通信路「パス」の配管例
図6 SDH/SONETが実現する通信路「パス」の配管例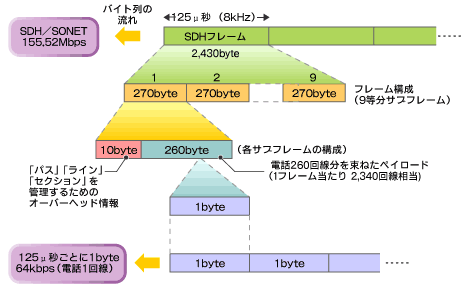 図7 SDH/SONETの固定長フレーム形式
図7 SDH/SONETの固定長フレーム形式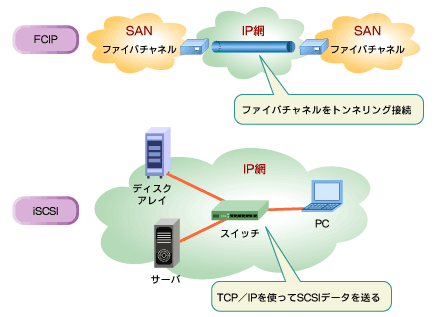 図8 イーサネットによるSAN
図8 イーサネットによるSAN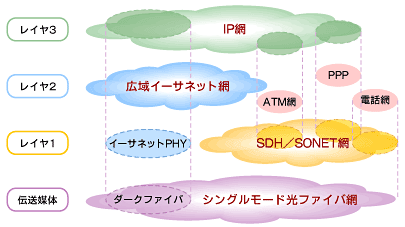 図9 イーサネットによるWAN
図9 イーサネットによるWAN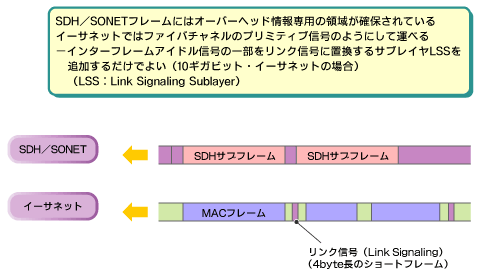 図10 ファイバ網を管理運用するためのオーバーヘッド情報の転送方法
図10 ファイバ網を管理運用するためのオーバーヘッド情報の転送方法



