|
Ultra DMA/66の性能を徹底検証 3.Ultra DMA/66の実力を測る3-3. IDEコントローラ間の比較澤谷琢磨 |
|
PCのIDEコントローラに性能差が存在するのかどうかを確認するため、表に示した代表的なUltra DMA/66対応コントローラについてベンチマーク テストを行った。IDEコントローラの世代間の性能差も確認するため、比較対象としてUltra DMA/33対応のIntel PIIX4Eを選んだ。PIIX4Eは、出荷開始から2年以上経っているうえ、現在も現役のコントローラであるため、比較対象としては適当だと思われる。テスト対象のハードディスクには、Maxtor 53073U6を用いている。
| ベンダ | コントローラ チップの型番 | 採用されている製品 |
| Intel | 82801AA(ICH1) | Intel 810、810E、815、820チップセット |
| VIA | VT82C686A | VIA ApolloPro 133A、KX133、KT133チップセットなど |
| Promise Technology | PDC20261 | Promise Ultra66 |
| Intel | 82371EB(PIIX4E) | Intel 440BX、440ZX、440LX、450NXチップセットなど |
| テスト対象に選んだIDEコントローラ | ||
| ランダム アクセス |
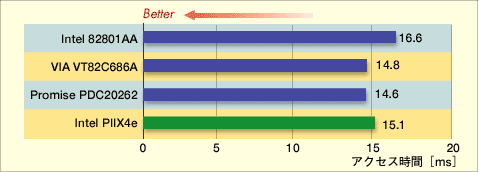 |
|
アクセス時間は、Intel 82801AAのみ1ミリ秒遅いだけで、そのほかのコントローラでは、ほとんど同じ値を示している。本来ランダム アクセスの性能は、IDEコントローラの性能とはほとんど関係せず、ハードディスク内部で決定されるはずだが、Intel 82801AAが遅くなる原因は不明である。 |
| バースト転送速度 |
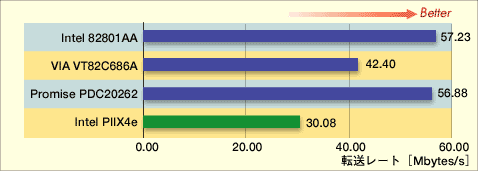 |
|
Ultra DMA/33までしか対応していないPIIX4Eと、Ultra DMA/66対応コントローラの性能差は、バースト転送の測定値ではっきりと現れる。バースト転送の速度差は、Maxtor 53073U6のように転送速度がUltra DMA/33の33Mbytes/sに達しないハードディスクの場合、あまり意味を持たない。 ただ、Ultra DMA/66対応コントローラである以上、バースト転送の測定値は、66Mbytes/sに近い値が得られなければならないのだが、VIA VT82C686Aが42.4bytes/sと、ほかのUltra DMA/66対応IDEコントローラと比べてかなり低い値しか出ていない。VT82C686AがUltra DMA/66の規格を満たしているのかどうか、この結果から見る限り疑わしいといわざるを得ない。 |
| 平均転送速度(読み出し) |
 |
|
平均読み出し速度は、Maxtor 53073U6ハードディスク自体がUltra DMA/33の限界を超えていないため、PIIX4eでもUltra DMA/66対応コントローラと変わらない結果となった。バースト転送速度で遅れを取ったVT82C686Aも、ここではほかのUltra DMA/66対応IDEコントローラと変わらない性能を示している。 |
| 平均転送速度(書き込み) |
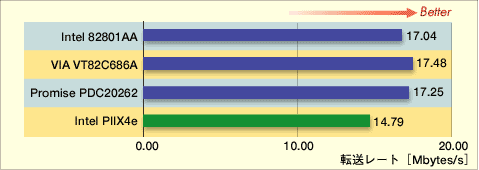 |
|
書き込みではPIIX4EとUltra DMA/66対応コントローラで2割弱の差が現れた。しかし、82801AAはモード4とモード2でほとんど性能差がなかったことを考えると、この結果だけで、これがUltra DMA/66とUltra DMA/33の性能差とはいえない。そこで、Ultra DMAモード2に落として同様のベンチマークを行った結果が次の「平均転送速度(書き込み、Ultra DMAモード2)」のグラフだ。 |
| 平均転送速度(書き込み、Ultra DMAモード2) |
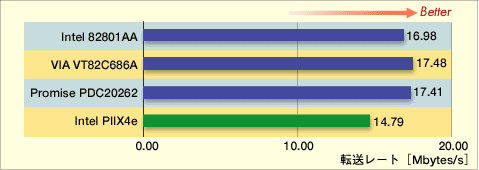 |
|
Ultra DMAモード2における各コントローラの書き込み性能は、「平均転送速度(書き込み)」のグラフの場合とほとんど変わらない。PIIX4Eとほかのコントローラに速度差が現れたのは、Ultra DMA/33か、Ultra DMA/66かによるものではなく、IDEコントローラ自体の書き込みバッファの容量など、IDEコントローラ自体の性能差によることがはっきりした。Ultra DMA/66対応コントローラを用いると、Ultra DMA/33対応ハードディスクでも書き込み性能が向上する可能性がある。 |
結論:Ultra DMA/66対応のIDEコントローラ間の差はほとんどない
バースト転送速度と書き込み速度以外では、Ultra DMA/66対応IDEコントローラ間はもちろん、Ultra DMA/33対応のPIIX4Eでも性能差は現れなかった。一般的なアプリケーションの実行環境を考えると、書き込みに比べて、読み出しが圧倒的に多い。そのため、読み出し速度が大幅に向上しなければ、ハードディスクの速度差を感じることが少ない。つまり、現在市場に流通している大半のIDEハードディスクは、Ultra
DMA/33対応コントローラでも、十分にその性能を引き出せると予想できる。書き込み速度は、IDEコントローラの備えるバッファ メモリの容量が、Ultra
DMA/66対応コントローラでは大幅に増やされたため、2世代前のコントローラであるPIIX4Eと大きな性能差が生じたものと考えられる。最新のIDEコントローラは容量の大きなデータバッファを備えることをカタログでうたっているが、書き込みの性能においては、これが一定の効果を持つことが分かった。
| INDEX | |||
| [実験]Ultra DMA/66の性能を徹底検証 | |||
| 1. | Ultra DMA/66、Ultra DMA/100登場の背景 | ||
| 2. | 実験前の下準備 | ||
| 2-1. | 機材を揃える | ||
| 2-2. | 設定の確認 | ||
| 2-3. | デバイス ドライバを設定する | ||
| 3. | Ultra DMA/66の実力を測る | ||
| 3-1. | ハードディスク間の比較 | ||
| 3-2. | 転送モード間の比較 | ||
| コラム Windows 2000における転送モード間の比較 | |||
| 3-3. | IDEコントローラ間の比較 | ||
| コラム Windows 2000におけるIDEコントローラ間の比較 | |||
| 3-4. | Windows 98標準ドライバとベンダ製ドライバとの性能比較 | ||
| 3-5. | アプリケーション ベンチマーク テストで性能差は現れるのか? | ||
| 4. | Ultra DMA/66は必要なのか? | ||
| 「PC Insiderの実験」 |
- Intelと互換プロセッサとの戦いの歴史を振り返る (2017/6/28)
Intelのx86が誕生して約40年たつという。x86プロセッサは、互換プロセッサとの戦いでもあった。その歴史を簡単に振り返ってみよう - 第204回 人工知能がFPGAに恋する理由 (2017/5/25)
最近、人工知能(AI)のアクセラレータとしてFPGAを活用する動きがある。なぜCPUやGPUに加えて、FPGAが人工知能に活用されるのだろうか。その理由は? - IoT実用化への号砲は鳴った (2017/4/27)
スタートの号砲が鳴ったようだ。多くのベンダーからIoTを使った実証実験の発表が相次いでいる。あと半年もすれば、実用化へのゴールも見えてくるのだろうか? - スパコンの新しい潮流は人工知能にあり? (2017/3/29)
スパコン関連の発表が続いている。多くが「人工知能」をターゲットにしているようだ。人工知能向けのスパコンとはどのようなものなのか、最近の発表から見ていこう
|
|





