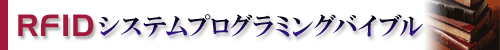
第5回
奥義その壱 ソフトウェアシーケンス図を制する
西村 泰洋
富士通株式会社
マーケティング本部
フィールドイノベーション
プロジェクト員
2008年1月24日
 シーケンス図作成のポイント
シーケンス図作成のポイント
次の説明に進む前に、シーケンス図作成のポイントをまとめておきます。参考にしてください。
| システムレイヤ | ポイント | 内容 |
|---|---|---|
| 業務アプリケーション層〜API層 | OPENコマンドの意味・範囲・動作 | OPENコマンドはAPIのOPEN、搬送波の供給など、どこまでを含むのか |
| CLOSEコマンドの意味・範囲・動作 | CLOSEコマンドはAPIのCLOSE、搬送波の停止など、どこまでを含むのか | |
| API層〜物理層 | 物理層の動作・処理の順序とその推測 | ポート番号、IPアドレス、動作設定、電力供給、アンテナ設定などの何を設定・動作させるコマンドなのか |
| 読み取り方法などの設定 | モード、アクセスメソッドなどの設定はどうなっているのか | |
| 読み取り処理の動作 | READコマンド1回で何回のアクセスが行われるのか | |
| 物理層〜RFIDタグ層 | リトライ回数 | デフォルトでは何回か、プログラムでの設定は可能なのか |
| 読み取り処理のサイクル | OPEN、READ、CLOSEのサイクル | READの1サイクルまたはリピートしていくときに、どのようなサイクルになるのか |
 システム設計におけるシーケンス図の活用
システム設計におけるシーケンス図の活用
それでは、ソフトウェアシーケンス図をプログラミングの詳細設計で活用する例を見てみましょう。ここでは次のような想定で検討してみます。
- UHF帯のリーダ/ライタ一式とアンテナ一式を接続した基本構成で、リーダ/ライタはOPEN、READ、CLOSEで読み取りをするタイプ
- リーダ/ライタの読み取り処理のリトライ回数は10回
- 通信範囲は垂直に4.5メートル、水平(左右)は2メートルのラグビーボール形状で、十分な性能が出ている
1と2の条件でソフトウェアシーケンス図を作成してみます。
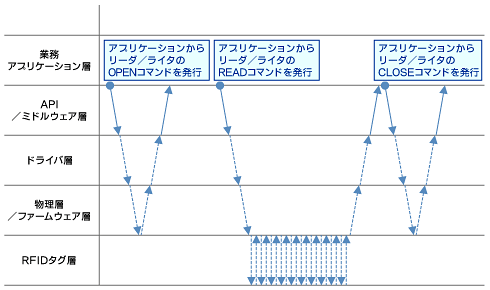 |
| 図3 1と2の条件を満たすソフトウェアシーケンス図 |
この図では動作の順番しか分かりませんので、さらに時間軸を付け足します。実際の各処理の動作時間(レスポンスタイム)はメーカーに確認するか自身で検証しないと分かりませんが、ここでは確認または検証できたものとして作成してみます。
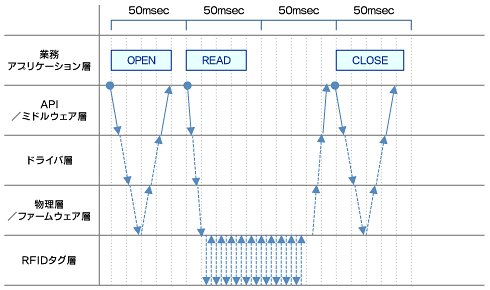 |
| 図4 図3に時間軸を追加したもの |
図4の状態になるとリーダ/ライタの基本的なソフトウェアシーケンスを読み取ることができます。
2/4 |
| Index | |
| 奥義その壱 ソフトウェアシーケンス図を制する | |
| Page1 ソフトウェアシーケンスの基本 プログラミングレベルのシーケンス |
|
| Page2 シーケンス図作成のポイント システム設計におけるシーケンス図の活用 |
|
| Page3 「BPOE」を踏まえてシーケンスを考える |
|
| Page4 現実の世界への適用 リーダ/ライタを見抜く、それはシーケンス図を描けること |
|
| RFIDシステムプログラミングバイブル 連載インデックス |
RFID+IC フォーラム 新着記事
- 人と地域を結ぶリレーションデザイン (2008/9/2)
無人駅に息づく独特の温かさ。IT技術を駆使して、ユーザーが中心となる無人駅の新たな形を模索する - パラメータを組み合わせるアクセス制御術 (2008/8/26)
富士通製RFIDシステムの特徴である「EdgeBase」。VBのサンプルコードでアクセス制御の一端に触れてみよう - テーブルを介したコミュニケーションデザイン (2008/7/23)
人々が集まる「場」の中心にある「テーブル」。それにRFID技術を組み込むとコミュニケーションに変化が現れる - “新電波法”でRFIDビジネスは新たなステージへ (2008/7/16)
電波法改正によりミラーサブキャリア方式の展開が柔軟になった。950MHz帯パッシブタグはRFID普及を促進できるのか
|
|
Master of IP Network 記事ランキング
本日
月間




