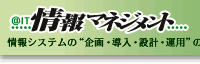高収益・高成長企業のIT投資は、どこが違うのか?
2006/2/9
- - PR -
社内外の環境がどのような状況にあっても競合他社と比較して平均以上に高い収益性と成長性を保ち続ける企業が存在する。アクセンチュアでは、このような企業をハイパフォーマンス企業と呼び、その秘密を探ってきた。
調査・研究を通じて、ハイパフォーマンス企業と一般の企業との間には、価値基準や行動様式に明らかな差異があることが分かってきた。CIOを対象としてグローバルで実施した最新の調査結果も交えて、ハイパフォーマンスを実現するためのIT投資がどのようなものであるかについて考察する。
今回は、まずIT投資にまつわる日本企業の課題を分析し、次回で具体的な施策について触れる。
IT投資の現状と課題
■IT支出が効果を生む投資にならない
ここ数年、過去最高益を更新するなど、業績が好調な企業も多数見られるにもかかわらず、IT投資を手控える企業が多いのはなぜだろうか。アクセンチュアの調査を通じて、経営者をIT投資に対して慎重にさせる要因は大きく2つあることが分かった。1つには近年のIT関連のプロジェクトが予測・実行しにくくなっていること、もう1つには経営者がIT支出に対する効果を実感できていないことである。
後者に関して、2003年に総務省が実施した調査によれば、情報化投資に対して十分な効果が得られたとする日本の企業はわずか3.5%にすぎず、米国の22.3%に対して大きな隔たりがある。いずれにしても、IT支出が必ずしも効果を生み出すための投資になっていないとはいえ、日米の差異は何によるのか。
日本企業のIT ROIを低下させている要因は、以下の4点と考えている。
(1)IT支出に占める投資/コストの配分が不適切
IT支出は、効果を生むことが期待される投資(機動的IT支出)と、効果は生まないがシステムの維持・運用のために必要なコスト(固定的IT支出)に分けて考える必要がある。
図1を見て分かるように、日本企業は概して効果を生み出すための投資が少ない。つまり、既存システムの保守・運用のために予算の多くを割かれてしまい、新しいビジネス効果を創出するような戦略的な投資ができていない。結果としてITの効果を十分に引き出すことができなくなる。
|
||
| 図1 日本企業はビジネス効果創出に向けてのIT投資が十分ではない。出典:「ハイパフォーマンスのためのIT投資:CIOを対象としたグローバル調査」(アクセンチュア/2005年) |
機動的IT支出は、投資対効果が経営判断として明確化されるべきIT投資で、単なるシステム導入だけでなく、“業務プロセス”“人・組織”“IT”の総合的な改革に向けての投資である。いったん作ったシステムへの支出であっても、システムの技術的先進性や、ビジネス上の競争優位を保つための投資は機動的支出として扱う。
固定的IT支出はシステムの安定稼働、機能向上、制度変更対応などのためにシステムを改修する費用、ハードウェア/ソフトウェア保守費用、システム運用費用など、システムを運営する際に必ず生じる費用である。このほかに、個人情報保護法対応などのいわゆるコンプライアンス対応も、ビジネス的な価値は生み出さないが取り組むことが必須であり、固定的IT支出ととらえることができる。図2にこれらをまとめた。
|
|
| 図2 機動的IT支出と固定的IT支出を分けて管理する必要がある。出典:アクセンチュア資料 |
機動的IT支出と固定的IT支出が適正な配分になるようにマネージすることが必要である。
(2)IT投資先の視野が狭い
戦略的IT投資に期待する効果としては、コスト削減だけでなく、売り上げ拡大や資本効率向上などを含めた広い視点が必要である。上記のような投資を行わないと、企業の業績向上への貢献がないばかりでなく、コスト削減の一時的効果はやがて固定的なIT支出の増分によって食いつぶされてしまう。本来は、コスト削減の効果を原資に、さらなる戦略的IT投資を行っていくのが効果的なやり方である。
米国では戦略的IT投資の目的は、コスト効率化から売上拡大へとシフトしているが、他方で日本のIT投資は依然としてコスト効率化が主目的となっている。図1でグローバルと日本の比較をすると、IT効率化のための投資は同等レベルであるが、売上拡大などのビジネス効果を生み出すための投資が少ないことが分かる。
IT部門主導で、業務部門ユーザーの巻き込みが不足しているプロジェクトでは、コアビジネスを改革してさらに競争力を高めるという視点が欠如しがちになるため、概してコスト削減目的に走りやすい。
(3)IT投資/コスト管理の方法が貧弱
企業がIT戦略の立案をする際には、多くの場合事業戦略に結び付けているにもかかわらず、定量的な投資効果の検証は行われていない場合がほとんどである。
総務省が2003年に実施した調査によれば、導入後の定期的かつ定量的な効果検証は米国企業の62.4%が実施しているのに対し、日本企業の実施率はわずか13.5%である。
(4)IT投資を生かすための施策が不十分
システムを作っても業務ユーザーがそれを活用することができなければ効果は生まれない。IT投資を十分に活用するためには、業務プロセス・組織の改革、ユーザートレーニング、定着化支援などハードウェア導入・ソフトウェア開発以外に多大な労力を要する。
同じく総務省の調査によれば、システム導入に合わせての業務の見直しは82.7%の米国企業が実施しているのに対し、日本企業は68.8%である。組織・制度の改革にまで踏み込んでいるのは米国の64.9%に対して日本は47.8%にすぎない。
■悪循環と好循環の2つのシナリオ
効果を生むための投資が十分に行われないと何が起きるか。図2の「懸念されるシナリオ」のように、IT投資をしても効果が限定的なため、結果として投資分が次期以降の固定的IT支出としての仕掛け、全体支出枠が増えないとすると機動的IT支出がじり貧になっていく。これは企業の競争力低下につながっていく。
逆に「目指すべきシナリオ」では投資効果を明確に定義して実現・可視化していくことで得た効果を次期の機動的IT支出の原資に当てることができる。また、継続的にコスト削減に向けての投資を行うことにより、IT支出の構造は固定的IT支出を削減しつつ、機動的IT支出を増やすという好循環に持っていくことができる。
■45%の機動的IT支出を確保する
では、機動的IT支出の割合はどのくらいが適切なのか。アクセンチュアの調査では、機動的IT支出の比率と企業のパフォーマンスに強い相関関係があり、少なくとも45%以上の機動的IT支出を確保することが必要だと考えている。
|
|
| 図3 IT投資効果を明確に定義し、実現・可視化することで、継続的な機動的IT支出を確保していく。出典:アクセンチュア資料 |
| Page1 IT投資の現状と課題 −IT支出が効果を生む投資にならない (1)IT支出に占める投資/コストの配分が不適切 (2)IT投資先の視野が狭い (3)IT投資/コスト管理の方法が貧弱 (4)IT投資を生かすための施策が不十分 −悪循環と好循環の2つのシナリオ −45%の機動的IT支出を確保する |
|
| Page2 ハイパフォーマンスIT組織の特徴 −新規技術への取り組み姿勢 −IT組織の時間の使い方 −インフラ導入の優先順位 −評価指標 |