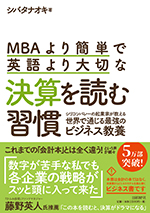えふしん×シバタナオキ対談 伸びるエンジニアが持つ「哲学と数字感覚」:自分たちが決断できないことをユーザーに委ねるのはやめろ(3/3 ページ)
これからの時代は、エンジニアも数字を意識しないとダメ?――モバツイで経営を経験したえふしんこと藤川真一氏と、ベストセラー『MBAより簡単で英語より大切な決算を読む習慣』の著者シバタナオキ氏が、なぜエンジニアは数字を味方に付けなければならないのかを探った。
エンジニアも知っておくべき、ビジョンと数字の良い関係
シバタ BASEが誕生した2012年時点で、ECマーケットプレースの世界には巨大な競合がいたわけじゃないですか? えふしんさんは、なぜ後発であるBASEにジョインしようと思ったんですか?
えふしん 鶴岡のビジョンを信頼していた、という部分が大きいですね。
競合といっても、「楽天市場」はショップの出店料も取るビジネスモデルですし、そこは被らないと思っていました。
「Yahoo!ショッピング」とは出店料が無料という点で競合はしていますが、BASEもサービス開始1カ月で1万店舗のショップ数を確保できましたし、無料モデルで世のEC化率を高めていく余地はまだまだあるかなと感じていました。
シバタ なるほど。
えふしん ちなみに、鶴岡はもともとオンライン決済をやりたかったんですよ。でも、起業した当時、彼はまだ大学生だったので、いきなり決済をやるのは得策ではないと自分で気付いたそうなんです。
それでまずはBASEというマーケットプレースを作って、そこにお金が回るようにしたんですね。で、改めて決済をやろうと始めたのが、2015年から始めた「PAY.JP」です(※編集部注:PAY.JPは2018年1月4日よりBASEの100%子会社「PAY株式会社」として分社化)。
BASEを作った時点で、流通総額がどれくらいになるかなどがどれだけ見えていたかは分からないですけど、結果的に両方スケールさせられたのは彼の商才だと思います。
シバタ このビジネスモデルならうまくいく、という話ではなくて、ビジョンから入って、その実現のために必要なものを次々と身に付け、実現していったという感じですかね。
えふしん そうだと思います。鶴岡はいわゆるエンジニア社長ですが、ビジョンで引っ張っていく部分と数字ありきで事業を推進するバランス感覚に優れたタイプかもしれません。
自分たちが決断できないことをユーザーに委ねるのはやめろ
シバタ エンジニアから見たサービス開発の難しいところは、売上やKPIのような数字にインパクトがあることだけをやろうとすると、どんどんつまらなくなってしまうところで。
鶴岡さんはその辺りのバランス感覚も良さそうですが、開発面にはどんな影響が出ていますか?
えふしん 先ほど話に出たKPIとのつなぎにもかかわる部分ですが、鶴岡が昔からずっと言っていることの1つが、「自分のアイデアに自信がないからABテストをやろうとするのはダメだ」です。
ABテストは、自分たちが「ユーザーにとってこれが一番いいはずだ」と思ったモノを作った上で、それを改善するプロセスとしてやるもので。自分たちで決断できないことをユーザーに委ねるのはやめろということですね。
シバタ 「自分たちが決断できないことをユーザーに委ねるのはやめろ」。すごくいい言葉ですね。
えふしん ビジョンを基にサービスを作り、数字を判断基準に伸ばしていくという順番が大事というか。
シバタ そうですよね。本来目指しているところとズレていても、数字が伸びていれば気持ちよくなってそのまま行ってしまう、という可能性もありますし。
えふしん だからビジョンや哲学みたいなものが先にないといけない。その意味では、最近BASEが始めた「ライブEC」も、このパターンに当てはまります。
動画の視聴環境が整ってきたこともあって、いずれECでのモノ売りというのは、Webサイトに商品を置いておくというパラダイムから、商品をプレゼンテーションしながら売っていくスタイルにシフトしていく、そういう未来を想定して作っています。
シバタ 日本だと「ジャパネットたかた」、米国だと「QVC」がTV通販としてやっているようなインフォマーシャルは、ECでも応用できるでしょうね。
えふしん 後は先ほど話したように、ビジョンドリブンで作ったライブECを、ビジネスとして数字を判断基準に伸ばしていかなければなりません。
僕らはECビジネスに10年以上遅れて参入した立場で、足りない機能を挙げていったらキリがないですし、スタートアップがそれを負い目に感じていてはダメじゃないですか。ですから、差別化要因を日々模索しているところです。
シバタ 今日はいろいろと勉強させてもらいました。ありがとうございました!
書籍
シバタナオキ著 日経BP社 1944円(税込み)
東大、スタンフォード、楽天、シリコンバレーで結果を出し続けてきた著者が続けてきた、膨大な数字から未来を先読むすごいやり方をひもとく、実務に役立つ決算分析法。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
関連記事
 決算短信で読み解く「アイティメディア」の財政状況
決算短信で読み解く「アイティメディア」の財政状況
元ITエンジニアで現会計士の吉田延史さんが、アイティメディアの決算短信を題材に「決算書の読み方」を伝授します- MBAより簡単で英語より大切な決算を読む習慣(守銭奴エンジニアが考えていること)
一人法人ではありますが、私は法人を持っており現在5期目です。だからこそ4期分の決算書を作ってきたのですが、ほとんどが税理士任せです - 決算を読む習慣 -テレビの時代からインターネットの時代に!(IT技術を日常生活で活かそう)
「決算書って、読むの苦手」「だって担当業務に関係ないし」この本はそんなふうに思っているあなたに読んで欲しい内容です。とあったので、決算書を読むのが苦手な代表として読んでみました - 【書評】MBAより簡単で英語より大切な決算を読む習慣(5分間キャリア・コンサルティング)
私たちがある会社の情報を知りたいと思ったとき、直ぐに考えられるのはネットを検索することだろう。その会社のWebサイトを閲覧することもそうだし、ネット上の噂を拾うこともするだろう。しかし、それ以上に、もっと正確な情報を入手する方法がある。それが決算書を読むということだ - MBAより簡単で英語より大切な決算書を読む習慣を読んだがさっぱり分からなかったので別の観点で読み解いて書評を書くことにした(101回死んだエンジニア)
通しで三回くらい読んでみた。そこで分かったのは、本の内容ではなく著者の理論の組み立て方だ。データの引用が非常に上手い。個人的な感想に走らずに、データを元に丁寧に話を組み立てている