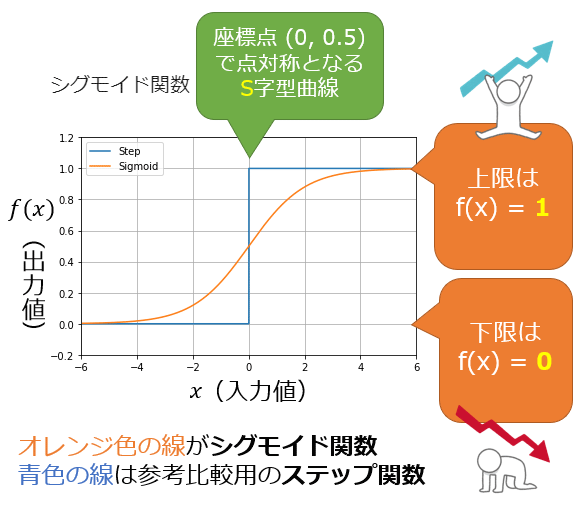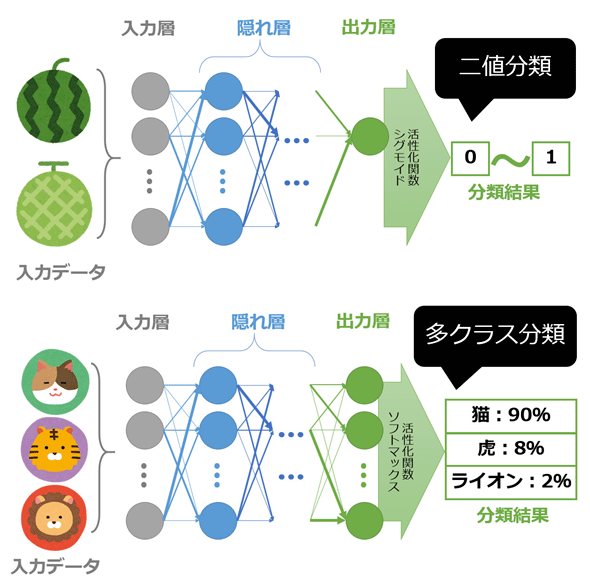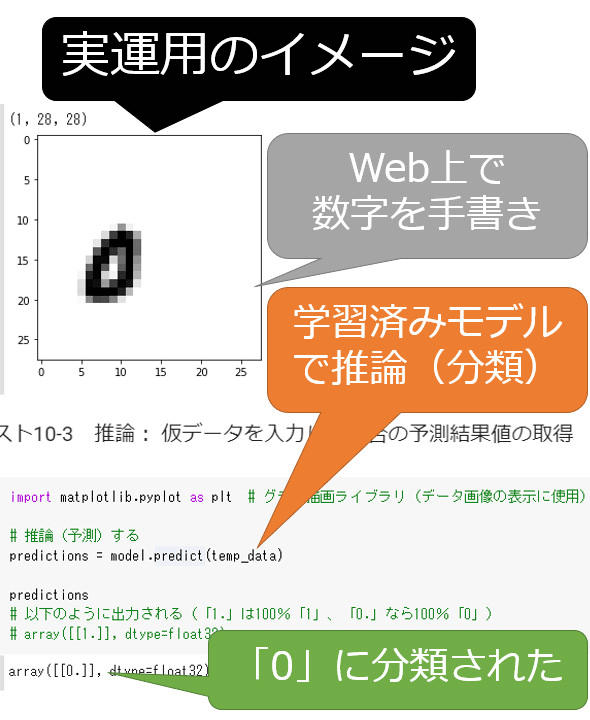第8回 分類問題をディープラーニング(基本のDNN)で解こう:TensorFlow 2+Keras(tf.keras)入門(1/3 ページ)
回帰問題の次は、分類問題の基礎をマスターしよう。二値分類/多クラス分類の場合で一般的に使われる活性化関数や損失関数をしっかりと押さえる。また過学習問題の対処方法について言及する。
本連載では、第1回〜第3回で、ニューラルネットワークの仕組みと、TensorFlow 2.x(2.0以降)による基本的な実装コードを説明した。また、第4回〜第6回で、TensorFlow 2の書き方をまとめた。さらに前回(第7回)では「回帰問題」についてあらためて取り上げ、これまでの連載記事で学んできた知識だけでも「基本的なディープ ニューラル ネットワーク」(以下、DNN)の実装が十分かつ自由に行えることを体験していただいた。
これをもっと続けよう。あとは、ディープラーニングの実装パターンを繰り替えしながら、慣れていくだけである。数をこなせばこなすほど、最初は「難しい」「分からない」と思っていた部分はなくなっていく(最初は覚えることが多いが、覚えることが減っていけば、それだけディープラーニングが楽になり、より好きになるはずだ)。さっそく始めよう。
今回の内容と方針について
分類問題とは?
分類(classification)という用語は、一般的な意味と同じなので、説明は不要だろう。推論で出力された予測値により、事前に定義された複数の分類カテゴリー(=機械学習では基本的に「クラス:class」と呼ぶ)の中のどれに最も該当するかを判別することである。
出力層の性質上、ニューラルネットワークの分類問題は、下記の2つに大別される。
- 二値分類(Binary classification)
- 多クラス分類(Multi-class classification)
二値分類
第1回〜第3回でも、座標点の色が「オレンジ色(-1.0)か」「青色(1.0)か」を分類するニューラルネットワークについて説明してきた。このような分類を二値分類と呼ぶのである。ただし、
- 「-1.0か」「1.0か」
という数値は実は扱いにくい。連載初回の3回は「ニューラルネットワーク Playground - Deep Insider」の挙動にサンプルコードを完全一致させることで、理解がスムーズになるよう、-1.0/1.0という数値範囲にしたが、これは一般的ではない。
通常のニューラルネットワークでは、
- 「0か」「1か」
の二値で分類を判断する。例えば、今述べたオレンジ色を-1.0ではなく0で、青色を上と同じく1で表現したとすると、0(推論の結果、オレンジ色である確率)が80%のとき、1(青色である確率)は20%である。また、0が0%のとき、1は100%となる。つまりこの「0か」「1か」は1つの値にまとめられる(一方の値を「x%」とすれば、もう一方の値は「(100-x)%」と表現できる)。よって二値分類では、出力層には1つの「ニューロン」(第2回で説明したように、場面に応じて「ユニット」や「ノード」とも呼ばれる)を用意すればよい。
「0か」「1か」(つまり合計100%)にするには、出力層のニューロンが出力する値を0.0〜1.0の範囲に収める必要がある。この処理を一般的にはシグモイド関数(Sigmoid function)という活性化関数によって実現する(図1)。ちなみに、合計100%にするのは人間が分かりやすいからだ。-1.0〜1.0だと合計200%となってしまい、例えば
- 「-1が132%で、1が68%」
と言われても直感的にピンと来ないのではないだろうか。一般的な人間にとっては「普通に100%確率値で言ってよ」となるだろう。
二値分類のために、活性化関数としてシグモイド関数を使った場合、セットで使われる損失関数が基本的に決まっており、具体的には二値分類用の交差エントロピー(Binary Cross Entropy)が使われる(※ちなみに交差エントロピーは、日本語では「クロスエントロピー誤差」と表記されることがあり、英語では「Cross Entropy Loss」と表記されることが多いので注意してほしい)。「二値分類用」と書いたのは「多クラス分類用」もあるからである。次にその多クラス分類について説明しよう。
多クラス分類
「0か」「1か」だけでなく、「2か」「3か」〜「9か」と、多数の分類カテゴリー(=クラス)があるようなケースを、多クラス分類と呼ぶ。これまで連載記事では取り扱っていないので、今回はこの多クラス分類が主題となる。この、
- 「0」「1」〜「9」
といった0スタートの番号は、クラスインデックス(class index)と呼ばれる(ライブラリによってはスパースラベル:sparse labelsと記載されていることもある)。ちなみに0スタートであることは、配列インデックスと一致するので、プログラミングしやすいというメリットもある。
クラスインデックスは、主にカテゴリー変数(categorical variable、カテゴリカル変数)に割り当てられる。例えば「猫」「虎」「ライオン」というカテゴリー変数がある場合、
- 「猫=0」「虎=1」「ライオン=2」
といったように割り当てられる。このような割り当てを、カテゴリー変数エンコーディング(Categorical variable encoding)と呼び、特にクラスインデックスにエンコーディングする手法は数値エンコーディング(integer encoding)などと呼ばれる。
少し脱線するが関連情報として、数値エンコーディング以外で特に有名なのが「ワン ホット エンコーディング」(one-hot encoding)である。これは、カテゴリー数分の変数(数学的には「ベクトル」、プログラミング的には「配列」)を用意しておき、そのうちの1つだけが1で、それ以外は0になるようにエンコーディングする手法である。例えば10個のカテゴリー(例:猫、虎、……、ピューマ)があり、対応するカテゴリー変数がクラスインデックス(例:猫=0、虎=1、〜、ピューマ=9)となっている場合に、10個の変数を用意し、例えば、その10個目(=クラスインデックスは9)の変数のみが1で、それ以外は0になるようにする。つまり、
- 「クラスインデックス=9」
という1つの変数が、
- 「0、0、0、0、0、0、0、0、0、1」
という10個の変数(one-hotベクトルやone-hot表現と呼ばれる)に展開されるわけである。one-hotエンコーディングは、多クラス分類を行う際に直感的で便利ではあるが、上記のように特殊なエンコーディングを行う必要性が発生するというデメリットもある。そこで本稿ではクラスインデックスを用いる。
クラスインデックスを使うにしろ、one-hot表現された複数変数を使うにしろ、先ほどの二値分類とは異なり、出力層のニューロンが1つというわけにはいかない。例えば「猫」「虎」「ライオン」……と3つ以上あるのであれば、出力層もそれぞれに対応する3つ以上のニューロンが必要になる。
なお、二値分類の場合と同様に、出力層のニューロンが出力する値は100%確率値で表現した方が分かりやすい。例えば、
- 出力値の例1: 「猫=3.2」「虎=1.2」「ライオン=0.3」
- 出力値の例2: 「猫=10.2」「虎=5.2」「ライオン=0.6」
という予測結果値が出力されるよりも、
- 出力値の例1: 「猫=68.1%」「虎=25.5%」「ライオン=6.4%」
- 出力値の例2: 「猫=63.7%」「虎=32.5%」「ライオン=3.8%」
というような100%確率値で表現された方が、理解や(例1と例2などで)比較がしやすいだろう。
このように多クラスを合計100%にする活性化関数が、ソフトマックス関数(Softmax function)である。図2は「虎(Tiger)=緑色の線」に1.0、「ライオン(Lion)=赤色の線」に0.0という固定値を入力し、「猫(Cat)=オレンジ色の線」をX軸に取り-6.0〜6.0で変化させたときのグラフである。X軸上のどこを取っても、3つの値の合計は1.0(つまり100%)となる。
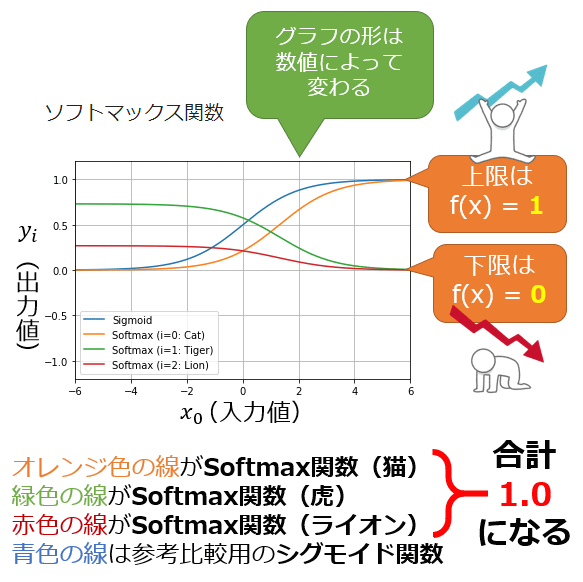
図2 ソフトマックス関数が出力する予測値の合計は100%になる
図中のiはクラスインデックスを意味するので、猫(i=0)/虎(i=1)/ライオン(i=2)となる。
x0は、入力値(x)が「猫(i=0)」であることを指す。
yiは、猫(i=0)/虎(i=1)/ライオン(i=2)それぞれの入力値に対する、ソフトマックス関数の出力値(y)を意味する。
ソフトマックス関数により例えば、
- 「猫=0.0」「虎=1.0」「ライオン=0.0」なら
→ 「猫=21.2%」「虎=57.6%」「ライオン=21.2%」(図2のx軸が0のところを参照) - 「猫=-0.5、虎=1.0、ライオン=0.0」なら
→ 「猫=14.0%、虎=62.9%、ライオン=23.1%」 - 「猫=4.0、虎=1.0、ライオン=0.0」なら
→ 「猫=93.6%、虎=4.7%、ライオン=1.7%」
というように予測値が確率値に変換される。いずれも合計すると100%になる。
多クラス分類のために、活性化関数としてソフトマックス関数を使った場合も、セットで使われる損失関数は基本的に決まっている。具体的には多クラス分類用の交差エントロピー(Categorical Cross Entropy)である。二値分類用とは計算方法が異なるが、要するに分類では基本的に「交差エントロピーを使う」ということである。なお、交差エントロピーの中身の計算式を知っておくに越したことはないが、知らなくても実用上の問題は基本的にないので、本稿では説明を割愛する。
二値分類と多クラス分類の出力層の比較
以上、ニューラルネットワークで表現できる2つの分類方法を紹介した。簡単に図3にまとめておこう。
今回、取り扱う分類問題について
今回の記事で一番重要な部分は、ここまでに説明してきた内容である。あとは、いつものワンパターンのコードをちょこちょこっと書き換えて実装していくことになる。強いて本稿のもう一つのポイントを挙げるなら、過学習の体験である。そこに注目して読み進めてほしい。
分類問題として、本稿では最初に多クラス分類を取り扱う。そこで使用するデータは、「Fashion-MNIST」というファッション商品(写真)の画像データセットである(詳細後述)。必要な箇所にはしっかりと解説を入れている。
次に、二値分類を取り扱う。そこで使用するデータは、「MNIST」という手書き数字の画像データセットである(そのうちの「0」と「1」の手書き数字だけを使用する。詳細後述)。こちらは、多クラス分類とほぼ同じようなコードとなっており、活性化関数や損失関数などを少し書き換えるだけである。よって、コードの変更箇所を簡単に示すだけで詳しくは解説しない。
おまけとして二値分類の最後では、実運用をイメージし、Web上で「0」か「1」の数字を読者自身が手書き入力をして、その画像を「0」か「1」かに分類する実例(Webアプリ)を説明している。ここまで試すことで、ディープラーニングの実用に現実感が持てるだろう。
今回、採用するTensorFlow 2の書き方について
前回に引き続き、サブクラスモデル(Subclassing API)で実装する。学習/トレーニングでは、compile()&fit()メソッドを利用することとする。
本稿で説明する大まかな流れ
基本的な実装の流れはワンパターンで、具体的には以下の通りだ。
- (0)本ノートブックを実行するための事前準備
- (1)データの準備
- (2)モデルの定義
- (3)学習/最適化(オプティマイザ)
- (4)評価/精度検証
- (5)テスト/未知データによる評価
- 実運用のイメージ
―――【二値分類編】―――(※上記と同様の手順から変更箇所のみ説明)
- (6)データの準備
- (7)モデルの定義
- (8)学習/最適化(オプティマイザ)
- (9)評価/精度検証
- (10)テスト/未知データによる評価
- 実運用のイメージ
それでは、実際にTensorFlow 2を使って、この分類問題を基本的なDNNだけで解いてみよう。
(0)本ノートブックを実行するための事前準備
前提条件
今回は、Python(バージョン3.6)と、ディープラーニングのライブラリ「TensorFlow」の最新版2.2を利用する。また、開発環境にGoogle Colaboratory(以下、Colab)を用いる。
前提条件の準備は第1回など、これまでと同じなので、説明を省略する。詳しくはColabのノートブックを確認してほしい。
次のページは……
前置きが少し長くなったが、いよいよ実践だ。次のページで多クラス分類を実装してみよう。
Copyright© Digital Advantage Corp. All Rights Reserved.