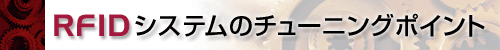
第1回
RFIDシステムへの期待と現実
布施 圭介
ソーバル株式会社
ワイヤレス事業部
フィールドエンジニアリンググループ
ユビキタスプラットフォーム開発チーム
課長
2007年2月9日
RFIDシステムを導入したものの期待どおりのパフォーマンス向上につながらない。高度な無線通信技術のノウハウを持つエンジニアがチューニングポイントを伝授する(編集部)
いよいよ普及期に入り始めたRFIDですが、2007年から2008年に導入を検討されている企業も多いことと思います。RFID技術は、これまでの「動く/動かない」という実験レベルから、「動いたらどれくらい効果的か」という実用レベルにまで成熟してきました。
しかしながら、RFIDシステムでは従来の業務のシステム化とは異なる側面があり、期待どおりの効果が得られない場合もあるようです。本連載ではRFIDを導入検討している企業のシステム担当者に向けて、RFIDシステムの特性に着目してポイントを押さえたチューニングについて述べたいと思います。
今回は、まずシステムの目的について明確にします。次にRFIDに期待される効果を述べ、最後に実際の問題点について説明します。
 何のためにシステムを導入するのか
何のためにシステムを導入するのか
これから述べるのは一般的な内容で、ご存じの方も多いと思いますが再確認と思っていただければ幸いです。
皆さんは業務システムに何を期待しますか? 単純作業の効率化やデータ集計の自動化、特定のベテランにしかできない業務の平準化など具体的な目的や理由はさまざまですが、本来システム化は何らかの業務改善効果を狙って行うものです。
逆にいえば、業務改善効果が期待できない業務はシステム化に適していないことになります。どのような業務がシステム化に適しているか、そしてどのような効果が期待されるか考えてみましょう。
|
||||||
| 表1 システム化の効果 |
表1にあるように、ある程度定型化された業務がシステム化しやすいことは明らかです。これは人とコンピュータの特性差から来るものと思われます。
|
||||||||||
| 表2 人とコンピュータの特性差 |
例えば、ビギナーレベルの人物は、当初作業効率も品質も上がりません。しかし、経験を積むにつれて効率も品質も向上していきます。また、十分な経験と知識のあるベテランともなれば未知の事態にも判断しながら対応することができます。
このように人は適応性、柔軟性に優れていることが特徴といえますが、引き換えに作業の安定性、継続性、正確性、速度などはコンピュータにはかないません。人の適応性、柔軟性は周辺環境に対する感受性ともいえます。常に周辺の状況を感じ取り、その場その場で判断し対応することで、さまざまな事態に柔軟に適応しているのです。
一方、コンピュータは明確に定義された手順をそのとおりに処理し続けます。与えられたデータ以外の周辺環境に合わせて処理手順を変えることはありません。同じデータを処理すれば必ず同じ結果を出力します。また、人の場合はビギナーとベテランの生産性の差が大きくありますが、コンピュータでは同種のマシンを使う限り同一です。
このような特性を踏まえたうえで、互いの得意分野を人とコンピュータが分担し合って、総合的な業務効率向上を目指すのがシステム化の目的といえます。
 デジタル化社会が期待するRFID
デジタル化社会が期待するRFID
システムの進歩、発展は、その分担領域を広げることであったともいえるでしょう。実際、現在のシステムはデータ化されてしまえば、膨大な情報処理も瞬時に行います。さらに、来たるユビキタスネットワーク時代にはデータがネットワーク上で共有され、データ化された情報は時間や地理条件を越えて利用されます。
しかし、誰がデータ化するのでしょうか。コンピュータ自身がデータ化をできれば良いのですが、残念ながらできません。結局、データ化は別の手段を使うことになりますが、こうなってくると情報のデジタル化とデータ化がシステムのボトルネックになってきます。どんなにコンピュータやネットワークが速くてもデータ化に時間がかかっていては、総合性能は高くなりません。
そこで登場するのが、現実世界の主観的存在を客観的数値表現化する「情報のデジタル化」です。難しいことのようにも聞こえますが、例えば距離を「km」で表現したり、重さを「g」で表現したりするのもデジタル化です。このように皆さんも日々の生活で無意識のうちに行っているものです。
では、なぜこのように数値表現化するのでしょうか。もし距離を「遠い」「近い」「ちょっと先」「すぐそこ」などと表現したらどうなるか考えてみてください。気持ちは伝わるかもしれませんが、これらの表現では客観的な距離は不明です。そこまで何分掛かるかも分かりませんし、ほかの距離と比較することもできません。
ところが、例えば「4km」と表現されれば一目瞭然です。徒歩で1時間とか自転車で15分とか計算することも可能になります。このようにデジタル化は人にも大きなメリットのあるものといえるでしょう。
コンピュータは、情報がデジタル化された状態で入力されて、初めてそれを取り扱うことが可能になります。簡単にいえば、数値をデータ入力することです。いかにコンピュータが高性能になろうとも現実世界の実体を直接操作することはできません。この現実世界とコンピュータ間のインターフェイスが必須であることはご理解いただけると思います。そして、このインターフェイスとしてRFIDが期待されています。
1/3 |
| Index | |
| RFIDシステムへの期待と現実 | |
| Page1 何のためにシステムを導入するのか デジタル化社会が期待するRFID |
|
| Page2 RFIDの理想―RFIDの得意分野と業務の効率化 RFIDの現実―エラーによるパフォーマンス低下 |
|
| Page3 RFIDの難しさ―不確定要素とその対応 RFID導入成否の鍵は? |
|
| RFIDシステムのチューニングポイント 連載インデックス |
- 人と地域を結ぶリレーションデザイン (2008/9/2)
無人駅に息づく独特の温かさ。IT技術を駆使して、ユーザーが中心となる無人駅の新たな形を模索する - パラメータを組み合わせるアクセス制御術 (2008/8/26)
富士通製RFIDシステムの特徴である「EdgeBase」。VBのサンプルコードでアクセス制御の一端に触れてみよう - テーブルを介したコミュニケーションデザイン (2008/7/23)
人々が集まる「場」の中心にある「テーブル」。それにRFID技術を組み込むとコミュニケーションに変化が現れる - “新電波法”でRFIDビジネスは新たなステージへ (2008/7/16)
電波法改正によりミラーサブキャリア方式の展開が柔軟になった。950MHz帯パッシブタグはRFID普及を促進できるのか
|
|




