電子メールアドレス収集に悪用か
トレンドマイクロの対策ソフト装うトロイの木馬
2008/01/15
トレンドマイクロのセキュリティ対策ソフト「Rootkit Buster」を装い、ユーザーの電子メールアドレスを収集しようと試みる悪質ソフトが発見された。トレンドマイクロが1月12日、自身のブログで報告し、注意を呼び掛けている。
この偽ソフトウェアの実体は、トロイの木馬「TROJ_FAKEBUSTR.A」だ。実際のRootkit BusterとそっくりなGUIを備えており、さらにアクティベートやアップデートのため登録を促すウィンドウを表示させる。しかしこれは、ユーザーの電子メールアドレスを収集するための「わな」だ。もしこのフォームにアドレスを記してボタンを押してしまうと、悪意あるユーザーの手にそれらの情報が渡り、さらなるスパム配信などに悪用される恐れがある。
トレンドマイクロによると、この偽ソフトウェアへのリンクは、「www.bestfreewaredownload.com」や「betterwindowssoftware.com」といったフリーウェアダウンロードサイトの登録ユーザー向けにばらまかれたスパムに記されていた。
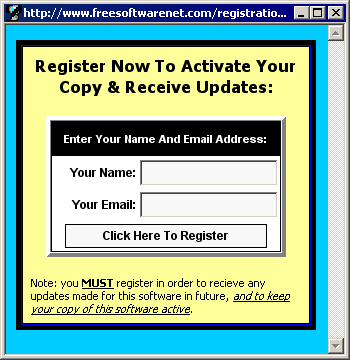 Rootkit Busterに似せた偽ソフトウェアが表示するウィンドウ
Rootkit Busterに似せた偽ソフトウェアが表示するウィンドウトレンドマイクロによると、今のところ、偽Rootkit Busterについての国内からの報告は寄せられていない。
しかし同社では「トレンドマイクロのツールに限らず、どのようなソフトウェアであっても出元を確認してほしい」(広報部)とし、改めて注意を呼び掛けている。基本的には、電子メール中に記されたURLをそのままクリックすることは避け、ベンダのサイトに直接アクセスするほうが望ましい。また、リンク先は必ずしも期待したとおりのものであるとは限らないことを踏まえ、URL情報を確認し、ジャンプ後もデザインなどに不審な点がないかに注意を払うといったポイントに留意すべきという。
Rootkit Busterは、トレンドマイクロが2007年1月に公開したセキュリティ対策ソフトだ。通常のウイルス対策ソフトでは検出が困難な、rootkit技術を用いたマルウェアを検出、削除することができる。
関連リンク
情報をお寄せください:
- Windows起動前後にデバイスを守る工夫、ルートキットを防ぐ (2017/7/24)
Windows 10が備える多彩なセキュリティ対策機能を丸ごと理解するには、5つのスタックに分けて順に押さえていくことが早道だ。連載第1回は、Windows起動前の「デバイスの保護」とHyper-Vを用いたセキュリティ構成について紹介する。 - WannaCryがホンダやマクドにも。中学3年生が作ったランサムウェアの正体も話題に (2017/7/11)
2017年6月のセキュリティクラスタでは、「WannaCry」の残り火にやられたホンダや亜種に感染したマクドナルドに注目が集まった他、ランサムウェアを作成して配布した中学3年生、ランサムウェアに降伏してしまった韓国のホスティング企業など、5月に引き続きランサムウェアの話題が席巻していました。 - Recruit-CSIRTがマルウェアの「培養」用に内製した動的解析環境、その目的と工夫とは (2017/7/10)
代表的なマルウェア解析方法を紹介し、自社のみに影響があるマルウェアを「培養」するために構築した動的解析環境について解説する - 侵入されることを前提に考える――内部対策はログ管理から (2017/7/5)
人員リソースや予算の限られた中堅・中小企業にとって、大企業で導入されがちな、過剰に高機能で管理負荷の高いセキュリティ対策を施すのは現実的ではない。本連載では、中堅・中小企業が目指すべきセキュリティ対策の“現実解“を、特に標的型攻撃(APT:Advanced Persistent Threat)対策の観点から考える。




