
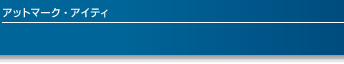
 |
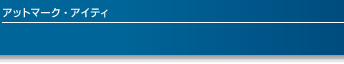 |
@IT|@IT自分戦略研究所|QA@IT|イベントカレンダー+ログ |
|
Loading
|
|
|
| @IT > Linuxの真実、Windowsの真実(5) |
|
企画:アットマーク・アイティ 営業企画局 制作:アットマーク・アイティ 編集局 掲載内容有効期限2004年12月31日 |
|
|
|
|
|
開発者コミュニティによるオープンソース・ベースのソフトウェア開発は、LinuxやSambaなどのシステム・ソフトウェアばかりでなく、ビジネス・アプリケーションにも及んでいる。米Sun Microsystems社は、ビジネス・アプリケーション市場で圧倒的なシェアを誇るMicrosoft Officeに対抗するため、独Star Division社が開発したビジネス・アプリケーション・スイートである「Star Office」を買収し、オープンソース・ソフトウェアとして公開した。これがOpenOffice.org(以下OpenOffice)で、インターネット・サイトから無償でダウンロードできる(SunはOpenOfficeをベースとしたアプリケーション・スイート・パッケージとして「Star Office(日本名はスタースイート)」を販売している。以下、特に明記しない場合は、OpenOfficeとStar Officeの双方をまとめて「OpenOffice」と表記する)。
OpenOfficeには、「Writer」(ワードプロセッシング)、「Calc」(表計算)、「Impress」(ビジネス・プレゼンテーション)、「Draw」(図形描画)の3つが統合されている。OpenOfficeはMicrosoft Officeとの互換性確保を強く意識して開発されており、基本的にMicrosoft Officeとの間でドキュメントの交換ができる(ただしこの互換性は完全ではない。詳細は後述)。
オープンソースであるOpenOfficeは無償でダウンロードして利用できるし、Sunが販売するStarSuiteも非常に安価である(Sunが販売するフル・パッケージ版で9,800円、ソースネクストが販売する1年間の使用権つきのパーソナルパックは1,980円)。対するMicrosoft Office(Office 2003)は、標準的なパックであるStandard Editionで単体パッケージの価格は5万2800円(推定小売価格)であり、単純なライセンス・コストの差は歴然としている。 しかし、こうした目先のライセンス・コストだけを考えるのは非常に危険である。特に多数のクライアントPCに対するビジネス・アプリケーション・プラットフォーム選びでは、導入や運用、エンド・ユーザー教育、ヘルプデスク、障害対応、セキュリティ修正によるソフトウェア更新などのトータル・コストに目を向ける必要がある。以下ではこれらについてもう少し踏み込んで見ていこう。
OpenOfficeの特徴の1つは、マルチ・プラットフォーム対応であることだ。具体的には、Windowsを始めLinux、FreeBSD、Solaris、Mac OS Xに対応している。 OpenOfficeならWindowsだけでなくLinux上でも利用できる。額面上はこのとおりだが、実用的には、この選択は重大な負担を伴う。 まず、LinuxではMSゴシック/MS明朝などのWindows標準フォントは提供されないため、Windows環境で作成したドキュメント(これらのWindows標準フォントを使用したもの)の体裁は完全には再現できない。このためMicrosoft Officeとのデータ交換では、罫線位置がずれたり、文字間隔や行間が変わり、ページ区切りの位置が変わったりする可能性がある。 またWindowsとは異なり、Linuxには複数の統合デスクトップ環境(GNOME、KDEなど)がある。しかしOpenOfficeはこれらのいずれのデスクトップ環境にも統合されていないため、OpenOffice以外のアプリケーションとの間では、ドラッグ&ドロップやネイティブデータのコピー&ペーストなどの高度な機能を使うことができない。ピュアテキスト・ベースのコピー&ペーストがせいぜいである。 これらを考えると、少なくとも現時点では、ビジネス・アプリケーション・プラットフォームとしてLinuxを選択するのは困難である。従って以下本稿では、Windowsプラットフォームを前提としたOpenOfficeとMicrosoft Officeについて比較する。
■アプリケーションの展開 ■データの互換性 例えば次の画面は、Word 2003(Microsoft Office)とWriter(OpenOffice)で、同じドキュメントを開いたところである。ひと目で分かるとおり、Word 2003では存在する罫線(表の左上にある斜め罫線)がWriterでは表示されていない。また、表のサイズやレイアウトが再現されないため、レイアウトの崩れが結果としてページ数の増加を招く危険性があることに注目したい。
罫線表示以外にも、文字間隔や改行位置、行間、禁則処理などが双方で異なるという報告がある。表示だけの問題ではなく、場合によってはドキュメント内の情報が一部失われたり、属性が変わったり(色が変わるなど)する場合もある。このためMicrosoft Office/OpenOfficeの混在環境でドキュメントの編集と保存を繰り返すと、伝言ゲームのように元の情報が失われてしまう危険がある。 データの互換性でもう1つ問題になるのは、ドキュメントのカスタマイズを行っている場合である。Excelであれば各種のセル関数やフィルタ設定、ピポット・テーブルなどの設定、そのほか一般にはVisual Basic for Application(VBA)などの言語を利用したカスタマイズを実施している場合がこれに当たる。OpenOfficeのマクロ言語StarBasicは現在のところVBAとは互換性がないので、VBAでカスタマイズされたドキュメントはOpenOfficeでは正しく機能しない。またExcelとCalcでは、サポートさせるセル関数の互換性が完全ではないため、複雑な計算式を含むExcelシートはCalcではそのままでは使えない可能性が高い。 昨今では、電子メールに添付してドキュメントを交換することが一般化している。このようなデータの互換性問題を考えると、OpenOfficeで編集したドキュメントをMicrosoft Officeユーザーに送付することには多大なリスクが伴うと考えるべきだ。 Microsoft OfficeとOpenOfficeの互換性や相互運用については、松井幹彦氏が公開する以下のサイトが詳しい。
■操作の互換性 ■ソフトウェアの更新管理 ■「XML対応」の違い ■高度なセキュリティ機能
オープンソース・ベースのアプリケーション開発というのは興味深い試みだが、残念ながら歴史の浅いOpenOfficeは、多様なビジネスの現場で安心して活用できるレベルに洗練されているとはいえない。特に、Microsoft Office資産との相互運用は現実的ではない。Microsoft Officeと直接データをやりとりする場合はもちろん、過去に作成したドキュメント、Microsoft Officeの自動化機能を使ってカスタマイズされたドキュメントなどを取り扱う必要があるなら、OpenOfficeの導入は困難だ。万一目先のライセンス・コストだけで導入を決定すると、アプリケーションの導入・展開、ユーザー教育、日々の運用・管理、将来の拡張など、あらゆる場面で暗礁に乗り上げたり、追加のコストが必要になったりするだろう。両者を比較する際には、目先のライセンス・コストだけでなく、トータルなコストを視野に入れる必要がある。
|
|