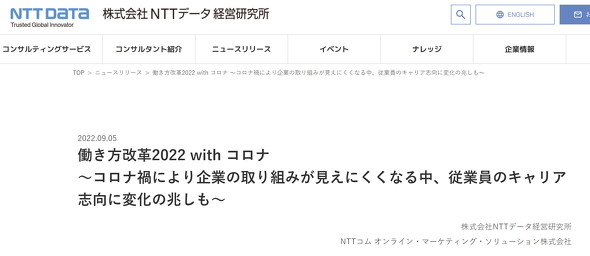日本でも進む「つながらない権利」、時間外には電話やメールを受け付けない:NTTデータ経営研究所が調査
NTTデータ経営研究所は、新型コロナウイルス感染症と働き方改革に関する調査結果を発表した。働き方改革に取り組む企業は、調査開始以降初めて減少に転じた。キャリア志向に関しては二極化が進んでいる。
NTTデータ経営研究所は2022年9月5日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)と働き方改革に関する調査結果を発表した。同調査は、NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューションが提供する「NTTコム リサーチ」に登録しているモニターを対象に実施したもの。その結果、働き方改革に取り組む企業は、調査開始以降初めて減少に転じ、その割合は46.1%だった。
「働き方改革の進捗状況が分からない」という企業が増加
NTTデータ経営研究所は、働き方改革の取り組み状況に関する調査を2015年から毎年実施している。2019年からは、「就業時間外の連絡(つながらない権利)」についても調査し、従業員のキャリア志向の変化を分析している。調査結果によると、働き方改革に取り組む企業の割合が2021年の調査と比べて9.9ポイント減っていた。企業規模別に見ても、全ての規模の企業で10ポイント前後減少していた。ただし「(進捗《しんちょく》状況が)分からない」と回答した割合が増加していることから、NTTデータ経営研究所は「コロナ禍が長期化する中で、勤務先の働き方改革に関する取り組みが従業員から見えにくくなっている可能性がある」としている。
つながらない権利については、就業時間外での連絡ルールの整備が進展した兆しが見えた。
就業時間外に上司から業務に関する緊急性のない電話やメールなど「通話や返信などを週1回以上の頻度で対応している」という人の割合は、対前年比6.5ポイント減の16.0%だった。なお、同僚間のやりとり(電話やメールの対応)は、同9.1ポイント減の15.9%。どちらも「調査開始以来、初めての減少に転じた」という。
キャリア志向は二極化
キャリア志向に関しては、新しいことに挑戦し続けたい層と、同じ職場で同一業務に従事し続けたい層との二極化が進んでいる。「コロナ禍を経て、働き方や今後のキャリア志向に何らかの変化があった」と回答した人の割合は24.2%だった。それに対して「何らかの変化がなかった」人は75.8%。
これら2つのグループの間でキャリア志向の変化を比べると、前者は「自身の専門性の有無にかかわらず、新しいことに挑戦し続けたい」(28.1%)という回答が多かったのに対して、後者は「雇用の安定性を重視して働きたい」(35.6%)や「同じ職場で同一業務に従事し続けたい」(32.9%)との回答が多かった。
コロナ禍前と比べて「転職時に重視する条件に変化があった」と回答した人の割合は11.8%。重視する条件について聞くと「テレワークが導入されている、または許可される頻度が高いこと」を挙げた割合が35.4%と高かった。この割合は、「給与水準が高い」(38.5%)の次に高く、「自身の目指すキャリアと業務内容が合致している」(31.5%)よりも上位に挙がった。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
関連記事
 SaaS利用やテレワークの拡大で高まるセキュリティリスク、どう対応すべきかをMenlo Securityに聞いた
SaaS利用やテレワークの拡大で高まるセキュリティリスク、どう対応すべきかをMenlo Securityに聞いた
国内外問わずさまざまな組織が被害を受けるランサムウェア。被害が多発する背景には、どのような攻撃手段があるのか、それらの攻撃にどう対処すればよいのかをMenlo SecurityのAmir Ben-Efraim氏とPoornima DeBolle氏にインタビューした。 テレワーク、続ける? 続けない? 企業と従業員で割れる意見の決着は
テレワーク、続ける? 続けない? 企業と従業員で割れる意見の決着は
パーソル総合研究所は、「第七回・新型コロナウイルス対策によるテレワークへの影響に関する調査」の結果を発表した。テレワーク実施率は第6波のときから微減したが、テレワークの継続意向を持っている人の割合は、同調査過去最高の80.9%だった。 テレワーク普及で“学習できない理由”が消えた――リクルートが会社員の学びに関する実態調査
テレワーク普及で“学習できない理由”が消えた――リクルートが会社員の学びに関する実態調査
リクルートマネジメントソリューションズは、「リモート下の会社員の学びに関する実態調査」の結果を発表した。テレワーク下での学びの機会は増加傾向にあることが分かった。同社は、テレワークに、意欲の高い会社員の学びを促進する効果があるとしている。