「データドリブンな組織に共通した7つの特性」、ガートナーが明らかに:最大の阻害要因は「変化に対抗しようとする組織文化」
ガートナージャパンは、データドリブンな組織に共通して見られる7つの特性を発表した。同社は、データドリブンな組織になるためには、何のためにデータドリブンになるのか、その目的を明確にすることが重要だと指摘する。
この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。
ガートナージャパンは2022年6月17日、データドリブンな組織に共通して見られる7つの特性を発表した。
データドリブンとはデータに基づいて戦略策定や計画立案、ビジネスの意思決定などを行うことで、ガートナージャパンはそうしたことが広く定着している組織を「データドリブンな組織」と定義している。
定着させるには「日々のビジネスで実践すること」が重要
ガートナージャパンの堀内秀明氏(マネージングバイスプレジデント)によると「データドリブンな組織を目指すリーダーは増えているが、データドリブンに対してはさまざまな誤解や過度な期待がある」という。
「例えば、データドリブンになれば人間は判断しなくてもよいと考えている人がいる。だがデータは参考にするものの、判断するのは人間だ。また『データドリブンな組織になるためにはとにかくデータが必要だ』と考える人がいるが、データを集めることよりも前に重要なことは、何のためにデータドリブンになるのか、その目的を明確にすることだ」
ガートナージャパンはデータドリブンを実現している組織を分析し、共通した7つの特性を見つけた。
意図的である
データドリブンな組織はデータを管理、指標化、収益化する目的が明確になっている。
有責
“データを活用した変化”の実行責任の所在が明らかになっている。
分析的である
データドリブンな組織は、好奇心旺盛で常に新たな洞察を探求し、根拠に基づいて判断している。
革新的である
新しい価値を常に追求し、失敗を許容する文化を持っている。
協調的である
データドリブンな組織は、データや洞察の共有に積極的で、他者と協調して問題を解決する傾向にある。
共感的である
多様性を尊重し、偏見を最小化している。データに基づく意思決定の表明が不利益にならないよう心理的安全性が確保されている。
データリテラシーがある
環境や状況に応じて、データを読み、書き、伝えられる能力がある。
ガートナージャパンは「データに基づく意思決定を組織に定着させるには日々のビジネスで実践することが重要だ」と指摘している。同社によるとデータを積極的に使えるようにする支援には「直接的な支援」と「コミュニティーによる支援」の2つがあるという。
「直接的な支援は、実務や標準的なツールの使い方に関する支援だ。例えば、IT部門などによるユーザーの支援がこれに当たる。利用者が参加するコミュニティーによる支援は、ユーザーによる自発的な情報発信や事例共有、悩み相談など、問題意識を持った参加者による、決められた形のない支援の場として機能するものだ」
堀内氏は「人の意識や行動を変えることは簡単ではない。当社の調査でもデータ活用推進の最大の阻害要因は『変化に対抗しようとする組織文化』という結果が出ている。データドリブンな組織になるための第一歩として、少なくともデータとアナリティクスのリーダーは、データドリブンな組織に共通して見られる7つの特性を体現する必要がある」と述べている。
関連記事
 「1時間に90回以上コピペ」という業務は問題ない? 業務見直しから始まる「DXジャーニー」
「1時間に90回以上コピペ」という業務は問題ない? 業務見直しから始まる「DXジャーニー」
長時間労働の是正で止まっている「働き方改革」をもう一歩進め、「業務変革」を実現する。その手法を紹介する本連載。第1回は「変われない現場」と題し、ワークログを使った業務の可視化について解説する。 データドリブンな組織の構築にエンタープライズアーキテクチャが果たす役割
データドリブンな組織の構築にエンタープライズアーキテクチャが果たす役割
エンタープライズアーキテクチャ(EA)とテクノロジーイノベーション(TI)のリーダーは、全社的な視点からビジネスの戦略的優先事項に対応したデータのニーズを把握することで、データドリブンな組織の構築に重要な役割を果たせる。 データドリブン、データオービス、データ免停
データドリブン、データオービス、データ免停
データドリブン野球が全ての元祖と言われています。※皆さんご存じかとは思いますが、本作はフィクションです。
関連リンク
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

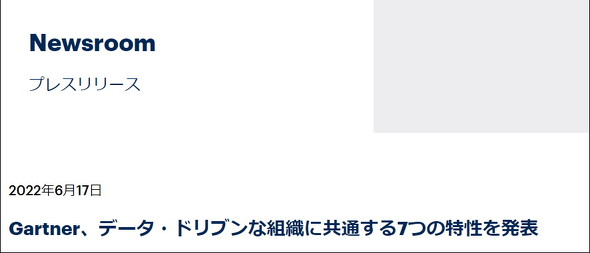 プレスリリース
プレスリリース



