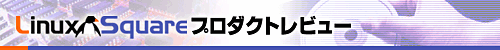
Zend Studio 2.5 日本語版
| 小山 哲志 2002/8/27 |
|
PHP向けの統合開発環境「Zend Studio 2.5日本語版」が発売された。これは、PHPのスクリプトエンジンを開発し、同時にPHPの周辺ツールも製品として提供しているイスラエルのZend Technologies社が開発した「Zend Studio 2.5」の日本語対応版で、日本での販売・サポートはテンアートニが行っている
Zend Studioの日本での販売は、本製品の前バージョンである「Zend Studio 2.0日本語版」が2002年3月にリリースされており、約4カ月ぶりのバージョンアップとなる。PHPの統合開発環境はフリー/商用含めいくつか存在するが、本製品はPHPの本家であるZendが開発しただけあって完成度も高く、PHPをアクティブに使用しているユーザーには強力なツールとなるだろう。ここでは、2.0から2.5へのバージョンアップで変更・強化された点などを中心にレビューをしていきたい。
![]() Zend Studioの製品構成
Zend Studioの製品構成
Zend Studioは単一のパッケージ製品名だが、内部的には以下に挙げるモジュールで構成されている。
- Zend Server Center
- Zend Debug Server
- Zend Information Center
- Zend Development Environment
このうち最後のZend Development Environment(以下ZDE)が、いわゆるIDEといわれる統合開発環境である。ちなみにZend Studio 2.0より前は、ZDEは「ZendIDE」という単独の製品だった。
対応プラットフォームもクライアントとサーバとでそれぞれ分かれている。
| OS | サーバ | クライアント | |
| Windows 98 | − | ○ | |
| Windows NT 4.0 | ○ | ○ | |
| Windows 2000 | ○ | ○ | |
| Windows XP | ○ | ○ | |
| Linux | ○ | ○ | |
| Solaris 2.x | ○ | − |
上記のモジュールでいうと、Zend Server CenterとZend Debug Serverの2つがサーバ、Zend Information CenterとZend Development Environmentの2つがクライアントということになる。クライアント単独でもPHPのデバッグは可能なので、サーバのインストールは必須ではない。
![]() 強化されたIDE「ZDE」
強化されたIDE「ZDE」
ZDEはJavaで記述されており、実行にはJRE(Java Runtime Environment)が必要だ。パッケージに含まれるインストーラには、JREを一緒にインストールしてくれるものとそうでないものがあるので、自分の好きな方を選べばよい。
では早速ZDEを立ち上げてみよう。
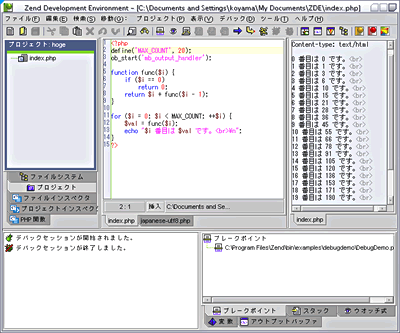 |
| 画面1 Zend Development Environment全体像(画像をクリックすると拡大表示します) |
ZDEは、画面1のように5つのペインから構成される。このうち上段中央のエディタウィンドウ以外はすべて表示/非表示を切り替えることができる。例えば、新規にPHPプログラムを書くときなどは、エディタウィンドウとインスペクタ領域(後述)のみにして画面を有効に利用することができる(画面2)。
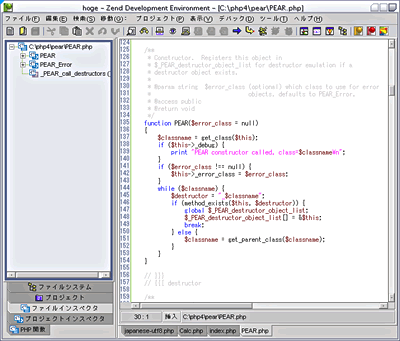 |
| 画面2 表示をエディタとインスペクタのみにしたZDE(画像をクリックすると拡大表示します) |
ソースコードのさまざまな情報を表示するインスペクタ領域が、2.0から2.5へのバージョンアップで最も強化された点で、
- ファイルシステム
- プロジェクト
- ファイルインスペクタ
- プロジェクトインスペクタ
- PHP関数
の5つの情報をタブで切り替えて表示できる。2.0のときは「ファイルシステム」と「プロジェクト」の2つしかなかったので、2.5になってようやく使いでのあるツールになったともいえる。
では、追加されたファイルインスペクタとプロジェクトインスペクタを詳しく見てみよう。
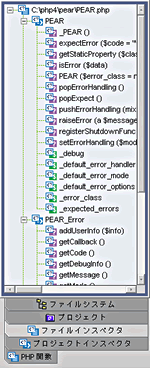 |
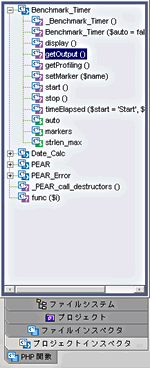 |
|||||||
|
||||||||
どちらもPHPプログラムの内容を解析して、関数や変数などをツリー上に表示してくれるツールだ。ファイルインスペクタが現在編集中のソースの内容を表示するのに対して、プロジェクトインスペクタはプロジェクトに含まれるソースすべてを表示するという違いがある。それぞれのエントリをダブルクリックすると、該当ソース行にジャンプするという機能を持っている。
ファイルインスペクタを表示させた状態でソースを記述していくと、書いたそばから次々と表示が更新されて、新しいエントリが追加されるのが分かる。つまり、PHPのコードを書いたまさにその場で解析しているわけで、なかなか重たい処理のはずなのだが、エディタはそんなことをみじんも感じさせない軽快さで動作する。
エディタ部分は、商用IDEとしてはもはや当然といえるシンタックスカラーによるハイライトとキーワード補完機能が充実している。シンタックスカラーはPHP、HTMLそれぞれの構文属性に対して色の変更が可能で、カスタマイズ度はかなり高い。キーワード補完機能も、2.5でPHP変数やHTMLタグの補完が可能になり、かなり使えるものになっている。いちいちポップアップが出てうるさいという人は、カテゴリごとに有効/無効を切り替えることができる。
驚嘆するのはメソッド名の補完機能で、変数$objがあるクラスのオブジェクトであると固定的に決まる場合は、
$obj-> |
を入力した時点で、そのクラスや親クラスのメソッド名がポップアップ表示される。ZDEは構文を解析して、$objのクラスやそのクラスの継承関係を理解しているのである。当然ながら、変数のクラスがプログラムにより動的に変化する場合は、この機能は働かない。
一例を見てみよう。画面5は、PHP標準ライブラリ「PEAR」のパッケージの1つであるBenchmark_Timerクラスを利用して、プログラムを記述しているところだ。
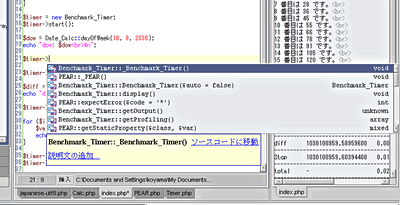 |
| 画面5 メソッド名の補完(画像をクリックすると拡大表示します) |
Benchmark_TimerクラスはPEARクラスを継承しているのだが、
$timer-> |
を入力して表示されるポップアップに、Benchmark_Timerクラスのメソッドに並んで親クラスであるPEARクラスのメソッドも表示されているのが分かる。
|
1/2
|
|
||||
|
||||
| Linux Squareプロダクトレビュー |
| Linux Squareフォーラム 製品情報・レビュー関連記事 |
| 特集:2007年、Linuxディストリビューションの歩みを振り返る 商用、非商用ともにメジャーバージョンアップが相次いだ2007年。主なディストリビューションを取り上げ、アップデート内容を紹介します |
|
| プロダクトレビュー[Ubuntu 7.10 日本語ローカライズド Desktop CD] 海外のみならず日本国内でも人気急上昇中のUbuntu。優れたインターフェイスを備えるとともに、豊富な機能がコンパクトにパッケージされている |
|
| 特集:業務で使うデスクトップLinux カタログ 定型業務さえこなせればよいという部門も多い企業環境は、コンシューマ市場以上にLinuxへの移行が容易ともいえる。そこで、6つのLinuxディストリビューションを紹介する |
|
| 特集:Linuxで動くリレーショナルデータベース・カタログ データベースサーバのOSとしてLinuxを採用するケースが増えている。Linuxで動作する7つの主なリレーショナルデータベースを紹介する。製品導入の際の参考にしてほしい |
|
| 特集:Windowsで動くXサーバ・カタログ やや特殊な用途に用いられてきたXサーバだが、活用しだいでは普通の管理用途にも有用だ。そこで、Windowsで動作する6本のXサーバを紹介する。選択の参考にしてほしい |
|
| 特集:Linuxで動くJavaアプリケーションサーバ・カタログ アプリケーションサーバは、いま最も開発競争が激しいジャンルの1つだ。その中から、Linuxに対応する5つの商用製品を紹介する。製品導入の際の参考にしてほしい |
|
| 特集:Linuxで動くWebグループウェア・カタログ Linuxを業務用サーバに採用するケースも増えている。そこで、Linuxをサーバとして利用するWebベースのグループウェアを紹介しよう |
|
|
- 【 pidof 】コマンド――コマンド名からプロセスIDを探す (2017/7/27)
本連載は、Linuxのコマンドについて、基本書式からオプション、具体的な実行例までを紹介していきます。今回は、コマンド名からプロセスIDを探す「pidof」コマンドです。 - Linuxの「ジョブコントロール」をマスターしよう (2017/7/21)
今回は、コマンドライン環境でのジョブコントロールを試してみましょう。X環境を持たないサーバ管理やリモート接続時に役立つ操作です - 【 pidstat 】コマンド――プロセスのリソース使用量を表示する (2017/7/21)
本連載は、Linuxのコマンドについて、基本書式からオプション、具体的な実行例までを紹介していきます。今回は、プロセスごとのCPUの使用率やI/Oデバイスの使用状況を表示する「pidstat」コマンドです。 - 【 iostat 】コマンド――I/Oデバイスの使用状況を表示する (2017/7/20)
本連載は、Linuxのコマンドについて、基本書式からオプション、具体的な実行例までを紹介していきます。今回は、I/Oデバイスの使用状況を表示する「iostat」コマンドです。
|
|





