|
特集 9. ディスク・インターフェイスの基礎「SCSI」「IDE」を知る |
|
ここまでは、IAサーバの概要からネットワークまで解説してきた。ここからはIAサーバのディスク・サブシステムに注目する。
IAサーバにおいて最も一般的な使い方であるファイル・サーバやWebサーバではハードディスクへのアクセスが多いため、ディスク・サブシステムの性能がシステム全体に影響を及ぼす。また、ディスク・サブシステムにはOSやデータが格納されることから、一度システムの設定を行ったあとでは、追加や拡張がしにくいという面もある。サーバに搭載されるデバイスのなかで、故障の頻度が高いのもディスク・サブシステムである。つまりサーバ管理者にとって、おそらくは最も初期設定に気を遣い、メンテナンスの頻度が高いのが、ディスク・サブシステムということになる。そこで、今回はディスク・サブシステムの基礎になっているSCSIとIDEという接続インターフェイスと対応ハードディスクに注目し、その成り立ちや2002年のトレンド、選択のポイントなどを明らかにしよう。
IAサーバではSCSIが一般的でIDEはほぼエントリのみ
IAサーバのディスク・サブシステムは、インターフェイスの種類によってその性能や機能、拡張性が大幅に変わる。そうした「要(かなめ)」であるディスク・インターフェイスから解説を始めることにする。
IAサーバのディスク・インターフェイスは、SCSIとIDEに大別できる。このうち「SCSI」を正確に記すなら、8bits幅または16bits幅のデータを同時に伝送する「パラレルSCSI」を意味する(現在は16bits幅が主流で、8bits幅は限定的である)。一方のIDEについては、現在クライアントPCで多用されているIDEと何ら変わらないものだ(パラレルATAとも呼ばれる)。両者を比較すると、以下のようになる。
| SCSI(パラレルSCSI) | IDE(パラレルATA) | |
| 主要な規格 | Ultra2 SCSI、Ultra160 SCSI、Ultra320 SCSI | Ultra ATA/66、Ultra ATA/100、Ultra ATA/133 |
| ハードディスク接続に用いられるIAサーバのセグメント | ワークグループ以上 | エントリ・クラス、ワークグループの一部 |
| 最大転送速度 | Ultra2 SCSI:80Mbytes/s Ultra160 SCSI:160Mbytes/s Ultra320 SCSI:320Mbytes/s |
Ultra ATA/66:66Mbytes/s Ultra ATA/100:100Mbytes/s Ultra ATA/133:133Mbytes/s |
| データ幅 | 16bits(Ultra2 SCSIは8bitsもあり) | 16bits |
| ケーブル1本あたりの最大接続デバイス数 | 15台*7 | 2台*8 |
| 最大ケーブル長 | 25m(2台のデバイス)、12m(3台以上のデバイス) | 0.46m |
| 外付けデバイスとしての使用 | ○ | ×(ケーブル長が短いため) |
| コマンド・キューイング*9 | ○ | ×*10 |
| CRCによる転送データのエラーチェック | ○(Ultra160 SCSI以降) | ○(Ultra ATA/33以降) |
| マルチ・イニシエータ*11 | ○ | × |
| ハードディスク以外のデバイス・サポート | リムーバブル・ドライブ、テープ・ドライブ、スキャナ、CD-ROMドライブなど | リムーバブル・ドライブ、テープ・ドライブ、CD-ROMドライブなど |
| 対応製品の価格 | 総じて高め | 安価 |
| 現行のSCSIとIDEのインターフェイス比較 | ||
| ここ数年の間でIAサーバに採用されたSCSIとIDEの各規格を、それぞれ比較してみた。SCSIは高性能/高機能を、IDEは低価格を優先した仕様になっている。各規格については後述する。 | ||
| *7 これはデータ幅が16bitsの場合。Ultra2 SCSIで8bits幅の場合は7台まで(いずれもホスト・コントローラの分は省いている)。なお、Ultra160/320 SCSIは16bits幅のみ | ||
| *8 サーバでは性能優先のため1台に限定していることが多い | ||
| *9 ホスト・コントローラからデバイスに発行される複数のコマンドを待ち行列にいったん格納し、実行順序の最適化などを実現する機能。複数台のデバイス接続時に効果的 | ||
| *10 規格には盛り込まれており、製品への実装が進んでいるが、ソフトウェアがサポートしていないことが多い | ||
| *11 複数のホスト・コントローラを1本のケーブルに接続して、各デバイスを2つのシステム間で共有できる機能。クラスタリングで利用することがある | ||
簡単にSCSIとIDEの特徴を表すなら、「高価だが汎用的でサーバに適したSCSI」と「機能や性能では劣るがコストが非常に安いIDE」となるだろう。IAサーバのハードディスク接続インターフェイスとしてはSCSIの方が一般的で、エントリ・クラス以外の全セグメントで使われているが、IDEはエントリ・クラスからIAサーバ市場に食い込み始めたところだ。
もともとSCSIは、「Small Computer System Interface」という名が表すように、PCやワークステーションなど小規模なコンピュータ・システムにおける汎用的なドライブ/デバイス接続用インターフェイスとして誕生した。それがクライアントPCの世界ではIDEとの標準化争いに敗れ、サーバ用途に特化していったという経緯がある(クライアントPCでもSCSIは使われたが、PCの標準装備機能としては普及しなかった)。
一方のIDEは、IBM PC/ATの時代のディスク・インターフェイス(ST-506など)をベースに考案された規格で、クライアントPC向けに徹底して低コストかつ互換性維持を重視して拡張されてきた。それゆえ接続台数の少なさや、あまりにも短いケーブル長、実質的に外付けデバイスを利用できない点など、標準的なクライアントPCでは十分でも、IAサーバには不十分な仕様が散見される。実際、一昔前のIAサーバでは、IDEはCD-ROMドライブの接続程度にしか使われていなかったくらいだ。
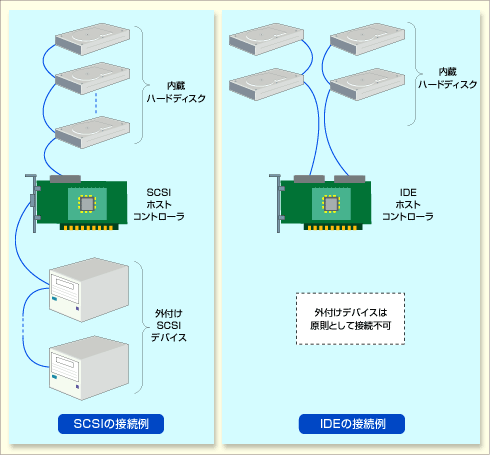 |
| SCSIとIDEそれぞれのデバイス接続例 |
| SCSIでは、1本のケーブルに3台以上のドライブを接続できるし、外付けも可能だ(内蔵と外付けは、それぞれにコントローラを設け、チャネルを分けるのが一般的)。一方、IDEはケーブル1本あたり2台までしか接続できない。実際には、2台のハードディスクを1本のケーブルに接続し、両方同時にアクセスすると速度が落ちやすいため、IAサーバではケーブル1本につき1台に制限していることが多い。このようにIDEの拡張性は限定的だ。 |
にもかかわらず、IAサーバのハードディスク接続にIDEが採用され始めたのは、IDEハードディスクの性能向上と容量増大によるところが大きい。1台のIDEハードディスクでも数十Gbytesという大容量を実現できるし、またIDEハードディスク×2台でRAID 1(ミラーリング)という構成も可能になり、エントリ・クラスのIAサーバならIDEハードディスクでも十分に耐えられるようになったからだ。また、CRCによるデータ転送のエラーチェックがIDEで実現されたことも、(クライアントPCに比べて)信頼性が重視されるIAサーバでは重要な要素だろう。もちろん、クライアントPC向けに大量生産されているIDEハードディスクは、量産効果により、SCSIハードディスクに比べて非常に安価であり、低価格のエントリIAサーバの価格競争力を高めるのに適していた、という理由もある。
| SCSI | IDE | |
| 容量 | 9G〜182Gbytes | 20G〜160Gbytes |
| 回転速度 | 7200〜15000RPM | 7200RPM |
| 内部転送速度 | 約400M〜700Mbits/s | 約300M〜600Mbits/s |
| 平均シーク時間 | 約3.6〜7.4ms | 約8.5〜10ms |
| プラッタ1枚当たりの容量 | 9G〜18Gbytes | 20G〜40Gbytes |
| 最大プラッタ枚数 | 12枚 | 5枚 |
| サイズ | 3.5インチ幅/1インチ・ハイトおよびハーフ・ハイト | 3.5インチ幅/1インチ・ハイト |
| インターフェイス | Ultra160 SCSI | Ultra ATA/100、Ultra ATA/133 |
| ホットプラグ(ホットスワップ) | 対応製品あり | 単体では非対応(非標準の特殊なアダプタを装着して対応) |
| 現行のSCSIとIDEのハードディスク比較 | ||
| IAサーバに搭載されるものに限定して、主要なハードディスク・ベンダの製品から仕様をまとめてみた。一般的なクライアントPCに比べて、IDEでも性能の高いものが採用されていることが分かる。各項目において、SCSIでもIDEでも少なからず幅があるのは、エントリからハイエンドまでラインアップされているため。IDEはプラッタ枚数を抑えつつ記録密度を高めて容量を稼いでいる(つまりコスト重視)のに対して、SCSIは回転速度やシーク時間など性能を重視していることが分かる。また、RAID構成時に故障したハードディスクを交換するホットスワップにも、SCSIハードディスクは標準で対応している製品が存在するが、IDEハードディスクにはない。 | ||
上表は、2002年現在のSCSI/IDEハードディスクそれぞれの仕様をまとめたものだ。これを見ると、まず回転速度は圧倒的にSCSIが速いことが分かる(回転速度が速いほど、目的のセクタが磁気ヘッドの下へ来るまでの「回転待ち時間」が短くなり、高速になる)。平均シーク時間(ヘッドが記録トラック間を移動する平均時間)も同様にSCSIが段違いに速い。内部転送速度(プラッタとのデータ転送速度)はそれほど大きな差はないように見えるが、2002年夏に登場予定のUltra320 SCSI(後述)対応の製品では、900Mbits/sに近い速度になるはずだ。IDEに比べ、SCSIハードディスクが速度重視なのがよく分かる。なお、7200RPMのSCSIハードディスクは性能的にIDEと競合しがちなため、各ハードディスク・ベンダとも販売中止にする方向にある。つまり10000RPMの製品がSCSIハードディスクの新しいエントリ・クラスになる。
容量については一見IDEと拮抗しているように見えるが、実際はIDEより少な目だ。現行のIAサーバでは、1台あたり9G/18G/36G/72Gbytesというラインアップが一般的である。182GbytesのSCSIハードディスクは、12枚という多数のプラッタを収めるために厚さがハーフ・ハイトになっており、一般的な1インチ・ハイト向けのドライブ・ベイに収まらないことがあるので注意が必要だ。 一方、IDEハードディスクはプラッタ数が少ない割に容量が大きい。それだけ単位容量あたりのコストが安く、すなわち低コスト重視なのが分かる。なお、上表には記していないが、ブレード・サーバなど超高密度IAサーバでは2.5インチIDEハードディスク(4200〜5400RPM/10G〜40Gbytes/内部転送速度200M〜250Mbits/s程度)が用いられている。現在はノートPC用のものが流用されており、性能面ではサーバに適してはいないが、今後はこうした市場の伸びによってはサーバ向けの高速なモデルが登場する可能性もある。 |
Ultra160 SCSIからUltra320 SCSIへの移行が始まる
IAサーバのSCSIにおける2002年の一大トピックは、Ultra320 SCSIへの移行だろう。
| 規格名 | 概要 | 主な用途 | ほかの呼び名 |
| Ultra2 SCSI | 以前のUltra SCSIに対して、LVD*12方式の伝送を採用することで高速化とケーブルの延長を実現した規格。最大速度は80Mbytes/s(16bitsデータ幅) | テープ・ドライブなどのデバイス接続 | Fast-40、SPI-2(SCSI Parallel Interface-2) |
| Ultra160 SCSI(Ultra3 SCSI) | 最大160Mbytes/sのSCSI規格。Ultra2 SCSIをベースに、ダブル・エッジ・トリガ*13で2倍に速度を高めた。Ultra160 SCSIは、もともとのUltra3 SCSIに対し、オプション機能から必須のものを選んで定めることで、仕様上の曖昧な部分を排除した規格 | 内蔵ハードディスクやRAIDコントローラのディスク・インターフェイス(Ultra2 SCSIの後継) | Fast-80、SPI-3 |
| Ultra320 SCSI | 最大320Mbytes/sのSCSI規格。Ultra160 SCSIをベースに、ビット・レートを2倍に高めた。2002年夏から対応ハードディスクが流通し、次第にUltra160 SCSIを代替していくものと思われる | 内蔵ハードディスクやRAIDコントローラのディスク・インターフェイス(Ultra160 SCSIの後継) | Fast-160、SPI-4 |
| IAサーバのSCSI規格 | |||
| 現在の主流はUltra160 SCSIで、Ultra2 SCSI(およびそれ以前のSCSI規格)はハードディスクではなくテープ・ドライブなど、データ転送速度の遅いデバイスとの接続に使われる。ハードディスクのインターフェイスにはUltra160 SCSI以降に対応した製品を選ぶことになる。 | |||
| *12 LVDはLow Voltage Differentialの略で、低電圧の差動駆動による信号伝送方式のこと。差動駆動(差動伝送)とは、2本の信号線を駆動してその間の電圧(電位差)で、「0」か「1」を決める伝送方式で、ノイズ耐性に優れ、より高速な伝送を可能とする | |||
| *13 伝送時の基準クロック信号の立ち上がり時と立ち下がり時の両方のタイミングで、データを転送する仕様。DDR SDRAMのデータ伝送と原理的には同じ仕組みだ | |||
IAサーバにおけるSCSIの役割は、RAIDコントローラとハードディスクとの接続か、あるいはテープ・ドライブの外付け接続のどちらか、といってもそう過言ではない。このうち前者については、1チャネルに複数台のハードディスクを接続して、ほぼ同時に各ハードディスクをアクセスするため、SCSIにはハードディスク単体の速度×台数分の転送速度が要求される。
|
拡張バスも高速化が必要 |
SCSIハードディスクの実質的な転送速度は現在、最大でも60Mbytes/s弱だが、2002年中には80Mbytes/sに達しようとしている。つまり、2台でUltra160 SCSIの帯域をすべて消費してしまうため、このままでは1チャネルで3台以上のRAID構成を組むとSCSIがボトルネックになってしまう。しかしUltra320 SCSIなら4台分の帯域を確保できるため、容量と速度の両立を図れる。これがUltra320 SCSIの登場を促した理由といえる。ハードディスクの性能向上が、規格の進歩を促進している点は、IDEもSCSIも変わらないわけだ。
Ultra320 SCSI対応のハードディスクやホストアダプタ、RAIDコントローラは、すでにいくつかの製品発表が行われており、ハードディスクは夏にも本格的に量産出荷されるようだ。実際にIAサーバへ搭載されるようになるのは、検証作業などのため多少遅れて、2002年末くらいからになるだろう。もし2002年度にSCSIハードディスクのシステムを増強する予定があるなら、Ultra320 SCSI対応製品もターゲットに入ることを覚えておきたい。
大きな変化はない? IAサーバのIDE動向
次にIDEインターフェイスの動向をチェックしよう。
| 規格名 | 概要 | 主な用途 | ほかの呼び名*14 |
| Ultra ATA/66 | 最大転送速度66Mbytes/sのATA/ATAPI(IDE)規格。以前のUltra ATA/33に対して、ケーブルを改良して伝送能力を強化し、倍速化を実現した | ATAPI CD-ROMドライブの接続 | ATA/ATAPI-5 |
| Ultra ATA/100 | 最大転送速度100Mbytes/sのATA/ATAPI(IDE)規格。Ultra ATA/66に対して、信号タイミングの改良により1.5倍の速度向上を実現した | 内蔵ハードディスクやRAIDコントローラのディスク・インターフェイス(Ultra ATA/66の後継) | ATA/ATAPI-6 |
| Ultra ATA/133 | 最大転送速度133Mbytes/sのATA/ATAPI(IDE)規格。Ultra ATA/100の信号タイミングをさらに短縮して1.33倍の速度向上を実現した | 内蔵ハードディスクやRAIDコントローラのディスク・インターフェイス | ATA/ATAPI-7 |
| IAサーバのIDE規格 | |||
| 現在の主流はUltra ATA/100だ。Ultra ATA/66(およびそれ以前のUltra ATA/33)はATAPI CD-ROMドライブ専用となっている。Ultra ATA/133については対応ハードディスクが少なく、今後Ultra ATA/100から移行するかどうかは微妙な情勢だ。ただしUltra ATA/133対応なら間違いなくUltra ATA/100にも対応しているので、Ultra ATA/100以降に対応した製品を選べば問題ない。 | |||
| *14 「ATA/ATAPI-X」とは、ANSIによるIDEの正式な規格の名称。「Ultra ATA/XX」とは必ずしも1対1で対応しない(複数の規格にまたがって定義されている場合もある) | |||
Ultra ATA/133は当初、1ベンダ(Maxtor)の独自仕様のように扱われていたが、現在はATA/ATAPI-7の草案に含まれており、標準規格になる可能性が出てきた。実際、IDE RAIDコントローラには、Ultra ATA/133に対応する製品が増えてきている。しかし、Maxtor以外のハードディスク・ベンダはUltra ATA/100から後述のシリアルATAへ直接移行する意志を示しており、Ultra ATA/133対応製品が2002年度の主流になるかどうかは微妙だ。
もっともUltra ATA/100がUltra ATA133になったところで、エントリIAサーバ向けというIDEの位置付けはまず変わらない。Ultra ATA/100とUltra ATA/133の性能差も大きなものではないので、ユーザーとしては、Ultra ATA/100対応製品を選ぶのが無難なところだ。むしろ注意すべきは、IDEに存在する137Gbytesの容量の壁だろう(この詳細は「実験:137Gbytes超IDEディスクの正しい使い方」を参照)。大容量ハードディスクの全容量を無駄なく使うために、IAサーバの対応状況を確認しておきたい。
|
IAサーバにシリアルATAが導入されるのはいつ? さらに2002年2月には、現行のシリアルATAをサーバ/ネットワーク・ストレージ向けにも拡張する規格「シリアルATA II」を策定するワーキング・グループが設立されている。シリアルATA IIでは、シリアルATA 1.0に対して下表のような強化が図られる予定だ。
つまりシリアルATA IIの第1段階が予定通りに実現できると、エントリ・クラスのIAサーバへの導入も2003年半ばから始まる。また、より上位のIAサーバには、第2段階を経て2004年ごろから実装が始まることになる。 ただ、クライアントPC向けに計画されているIntel製チップセットでのシリアルATA対応は、2003年前半に行われる予定だ。このチップセットが登場して初めて、クライアントPCへのシリアルATA導入が本格化する。また、シリアルATA対応ハードディスクも、このチップセットでの検証を経てから本格的に出荷されるようだ。シリアルATA IIの実装はこの後になるだろうから、第1段階に対応する製品は予定より遅れるかもしれない。 いずれにせよ2002年度においては、シリアルATAの動向に注目しておく必要はあっても、製品の導入まで考慮する必要はなさそうだ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■
IAサーバのディスク・インターフェイスとして、SCSIとIDEは指向がまったく異なり、すみ分けもできているので、用途に応じて一方を選ぶことはそれほど難しくない(コスト重視ならIDE、性能や拡張性重視ならSCSI)。注意が必要なのは、SCSIにもIDEにも複数の規格があり、選び方を間違えると本来の性能が発揮できないなどトラブルが発生する点だ(SCSIもIDEも下位互換性は重視されているため、まったく動作しないというトラブルは比較的生じにくい)。ホスト側のコントローラとハードディスクの間で対応規格が異なる場合は、ベンダにより動作確認がなされている製品を選ぶなど、注意すべきだろう。
次のページでは、電源ユニットとケースについて解説していく。
| 関連記事 | |
| 137Gbytes超IDEディスクの正しい使い方 | |
| 次世代の標準ディスク・インターフェイス『シリアルATA』のすべて | |
| 「System Insiderの特集」 |
- Intelと互換プロセッサとの戦いの歴史を振り返る (2017/6/28)
Intelのx86が誕生して約40年たつという。x86プロセッサは、互換プロセッサとの戦いでもあった。その歴史を簡単に振り返ってみよう - 第204回 人工知能がFPGAに恋する理由 (2017/5/25)
最近、人工知能(AI)のアクセラレータとしてFPGAを活用する動きがある。なぜCPUやGPUに加えて、FPGAが人工知能に活用されるのだろうか。その理由は? - IoT実用化への号砲は鳴った (2017/4/27)
スタートの号砲が鳴ったようだ。多くのベンダーからIoTを使った実証実験の発表が相次いでいる。あと半年もすれば、実用化へのゴールも見えてくるのだろうか? - スパコンの新しい潮流は人工知能にあり? (2017/3/29)
スパコン関連の発表が続いている。多くが「人工知能」をターゲットにしているようだ。人工知能向けのスパコンとはどのようなものなのか、最近の発表から見ていこう
|
|






