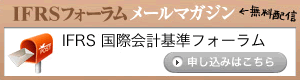連載:IFRS基準書テーマ別解説(4)
「無形資産」「リース」の会計基準を見てみよう
吉田延史
仰星監査法人
2010/1/6
無形資産とリースについてのIFRSの会計基準を、日本基準との違いも含めて解説する。特に無形資産については、開発費をはじめとして多くの企業に影響が及ぶことが想定されるため、留意する必要があるだろう。
PR
今回は無形資産とリースについての会計基準を解説する。特に無形資産については、開発費をはじめとして多くの企業に影響が及ぶことが想定されるため、留意する必要があるだろう。
無形資産
IFRS(国際財務報告基準、国際会計基準)では、無形資産についてIAS38号が規定しており、無形資産の定義、認識、測定について定めている。
一方、日本会計基準では、無形資産について直接的に扱った会計基準は存在せず、主に以下の会計基準により、個別具体的に定めている。
- 企業会計原則、財務諸表等規則:無形資産として計上すべきものが例示列挙されている(例:特許権、借地権、ソフトウェア、電話加入権など)
- 研究開発費等に係る会計基準:研究開発及びソフトウェアの取り扱いについて記載されている。
- 税法:会計基準とは直接関係がないものの、日本の会計実務上、償却計算などについて税法に規定されている方法に従っていることが多い。例えば、自社利用のソフトウェアは、残存価額を0として5年間の定額法により償却計算される。ただし、市場販売目的のソフトウェアなどについては研究開発費等に係る会計基準に従って会計処理する必要がある。
|
日本基準とIFRSの考え方
IFRSでは無形資産について、どういった性質を持つものかについての定義している。具体的には以下の通りである。
過去の事象の結果として企業が支配し、それを使用すると将来、企業が経済的な便益を得られると期待できる資源のうち、物質的実体のない、識別可能な非貨幣性の資源。
日本基準において認識されている無形資産のうちの多くは上記の定義を満たしているが、一部例外も存在する。例えば、新経営組織の採用に伴う支出について、日本基準では、開発費(繰延資産)として計上することが容認されているものの、これは、IFRSの定める無形資産の要件は満たさず、発生時に費用処理することが求められる。
一方、日本基準では、無形資産についての定義はなく、企業会計原則などの例示列挙にとどまっている。
以下、主要な論点について、日本基準と違いが生じている部分を解説していく。
研究開発費
IAS38号では研究開発費については、新知識の発見などの研究局面と知識の具体化に代表される開発局面に分けて記載している。
IAS38号においては、研究局面の支出は発生時に費用化し、開発局面の支出は下記事項を立証可能な場合にのみ、無形資産として資産計上しなければならない。
- 使用または売却できるように無形資産を完成させることの技術上の実行可能性
- 無形資産を完成させ、さらにそれを使用または売却するという企業の意図
- 無形資産を使用または売却できる能力
- 無形資産の将来の経済的便益創出方法
- 無形資産の開発を完成させ、さらにそれを使用または売却するために必要となる、適切な技術上、財務上及びその他の資源の利用可能性
- 開発期間中の無形資産に起因する支出を、信頼性をもって測定できる能力
日本基準においても、研究開発費について、研究と開発を定義し、それぞれについて取り扱いを定めている。ただし、日本基準では研究開発費は原則として支出時に費用処理することとされており、開発局面において、上記要件を満たした場合に資産計上が強制されているIAS38号とは、ずれが生じている。

 IFRS任意適用の要件緩和へ、企業会計審議会に新しい流れ
IFRS任意適用の要件緩和へ、企業会計審議会に新しい流れ