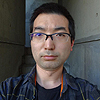CentOS 7のシステム管理「systemd」をイチから理解する:CentOS 7で始める最新Linux管理入門(2)(4/4 ページ)
» 2015年12月24日 05時00分 公開
[大喜多利哉,@IT]
systemdが抱える課題
initからsystemdへの変更は小規模ではなく、大規模な変更です。systemdのアーキテクチャ自体も不必要なほど複雑ではないとしても、複雑なものであることから「systemdのアーキテクチャはUNIX哲学を破壊する」などとしてさまざまな議論が繰り返されています。実際にsystemdを批判する反対派の存在もあります。
筆者はシステム管理者の視点から、initからsystemdへの移行に際して以下の課題があると考えています。
- initからsystemdへの変更で、コマンドが大幅に変わることによる学習コストが掛かる
- systemdの実装が完成形であるとはいえないこと(「半端な改善は、完全な欠陥よりもたちが悪い」という批判がある)
前者は、systemdの機能が多岐にわたっているため、「よく利用する部分、特にサービス起動系にフォーカスして理解していく」ことで、ある程度は回避できると考えます。
後者については、ポッターリング氏はsystemdの開発を「決して終了せず、決して完成しないが、技術の進歩を追い求める」としています。これまでのOSS(オープンソースソフトウエア)もそのように進化してきたことから、現状が完成形と思わず、絶えず進化していくシステムだと考えれば、正しいアプローチだと思います。
次回はCentOS7の「ネットワーク管理」について解説します。
関連記事
![Linux起動の仕組みを理解しよう[init/inittab編]](https://image.itmedia.co.jp/ait/articles/0204/02/news002.gif) Linux起動の仕組みを理解しよう[init/inittab編]
Linux起動の仕組みを理解しよう[init/inittab編]
カーネルが呼び出されてからログインプロンプトが表示されるまでの間に、一体どのような処理が行われているのか。これを理解するには、この部分の全般をつかさどるinitとその設定ファイルであるinittabがカギとなる。 エンタープライズでもInfrastructure as Code――Chef 12/Chef-Zero/Knife-Zeroの基礎知識とインストール
エンタープライズでもInfrastructure as Code――Chef 12/Chef-Zero/Knife-Zeroの基礎知識とインストール
エンタープライズ向け機能が充実してきたChefを使って高速かつ精度の高いサーバーインフラを構築/管理する方法について解説する連載。初回は、Chef 12、Chef Solo、Chef Server、Chef-Zero、Knife-Solo、Knife-Zeroの概要と、Chef-ZeroをKnife-Zero経由で利用するCookbook開発環境の構築について解説します。![Linuxで作るファイアウォール[パケットフィルタリング設定編]](https://image.itmedia.co.jp/ait/articles/0112/18/news002.gif) Linuxで作るファイアウォール[パケットフィルタリング設定編]
Linuxで作るファイアウォール[パケットフィルタリング設定編]
いよいよパケットフィルタリングの設定を始める。しっかりと不要なパケットをブロックできれば、ファイアウォールの内側の安全度はより向上する。パケットの性質やiptablesの動作をここでマスターしてほしい。 アクセス制限の設定とCentOSのアップデート
アクセス制限の設定とCentOSのアップデート
前回はsshでVPSにログインして、一般ユーザーを作成しました。今回は、アクセス制限、パケットフィルタリングといった不正アクセス対策の設定をしてから、CentOSをアップデートします(編集部) 環境構築自動化の手順と評価検証、Puppetの基礎知識
環境構築自動化の手順と評価検証、Puppetの基礎知識
サーバー構築の自動化で利用される技術、自動化ツールとして「Kickstart」「Puppet」を紹介し、構築から運用まで、システムライフサイクル全体にわたる運用管理の自動化についても解説する連載。 無線LAN接続の設定を操作するには? iwconfigコマンドの使い方
無線LAN接続の設定を操作するには? iwconfigコマンドの使い方
無線LANインターフェースがカーネルまたはモジュールでサポートされていれば、アクセスポイントとIPアドレスを設定する程度で接続できます。「iwconfig」は、アクセスポイントへの接続に必要なESSIDおよび暗号化キーを登録するときに利用するコマンドです。 NginxをWebサーバー“以外”でも徹底活用する
NginxをWebサーバー“以外”でも徹底活用する
Nginxは高速化だけではありません。Webサーバー以外への応用事例として、ロードバランサー、HTTPS対応、WAFとしての利用を紹介します。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
SpecialPR
アイティメディアからのお知らせ
スポンサーからのお知らせPR
SpecialPR
システム開発ノウハウ 【発注ナビ】PR
あなたにおすすめの記事PR