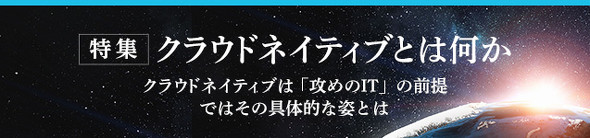詰まるところ、「クラウドネイティブ」で何をすればいいのか:草間一人×青山真也 クラウドネイティブ対談(3)(2/2 ページ)
青山 一般的にクラウドネイティブ化というと、アプリケーションやそのアプリケーション実行基盤のインフラ部分(高レイヤー)のクラウドネイティブ化が中心に語られることが多いですが、低レイヤーのインフラ層も実際にはクラウドネイティブ化していかなければなりません。その部分の考慮も必要なことを考えると、パブリッククラウドを使ったほうが近道とも言えます。オンプレミスに環境を用意するかどうかは、商用製品を利用するか否か、そして拡張性、セキュリティ、コストといった観点から考える必要があります。
 青山真也氏 「Kubernetes好き」を公言し、Certified Kubernetes Application Developer、Certified Kubernetes Administratorの認定資格を持つインフラエンジニア。サイバーエージェントに所属しながら、他の事業会社に対する技術アドバイザーや客員研究員も務めている。Cloud Native Meetup Tokyo/Kubernetes Meetup Tokyoのオーガナイザーでもある。著書に「Kubernetes完全ガイド」「みんなのDocker/Kubernetes」
青山真也氏 「Kubernetes好き」を公言し、Certified Kubernetes Application Developer、Certified Kubernetes Administratorの認定資格を持つインフラエンジニア。サイバーエージェントに所属しながら、他の事業会社に対する技術アドバイザーや客員研究員も務めている。Cloud Native Meetup Tokyo/Kubernetes Meetup Tokyoのオーガナイザーでもある。著書に「Kubernetes完全ガイド」「みんなのDocker/Kubernetes」クラウドネイティブの定義には「オープンソースでベンダー中立プロジェクトのエコシステムを育成・維持して……」と書かれていますし、さまざまな標準化も進められています。とはいえ、Kubernetesを利用しても、特定パブリッククラウドの独自なコンテナ環境を利用したとしても、活用することでクラウドネイティブに近づくことができるという意味では変わりありません。技術として何を選択するかという話だと思います。また、独自サービスを利用したとしても、クラウドネイティブなアーキテクチャを取っている場合には、疎結合なアーキテクチャに基づいていたり、可搬性の高いイメージが利用されていたりと、従来のロックインに比べて多少依存度は低いと思います。CNCF(Cloud Native Computing Foundation)に関わっている者としては、OSS、または標準化された仕様に基づいた独自実装を推進したいとは思います。
先ほどの、「パブリッククラウドを使っていれば、70%くらいクラウドネイティブになっていることもあり得る」という言葉は、マネージドデータベースの利用や、インスタンスグループやオートスケールの機能による自動復旧、ロールごとに分割されたインスタンスの利用、VMのイメージ化などが自然に使えることにあります。このため、「パブリッククラウドに適した開発をちゃんと行っていれば、それはもはやクラウドネイティブに近い」という意味合いで言いました。コンテナやマイクロサービスを使うことはあくまでも手段に過ぎません。
――草間さんは、パブリッククラウドとクラウドネイティブの関係をどう考えますか?
草間 多くの企業では、最初はパブリッククラウドを使うことになると思います。先ほども話しましたが、クラウドネイティブでは、人の関与を減らしていくというのが大前提で、これを一番早く確実に実現できるのはパブリッククラウドです。Kubernetesではなく例えば「Amazon ECS」「AWS Lambda」など、Amazon Web Services(AWS)独自のサービスで固めてしまったとしても、それで人の関与を減らせるのであれば、CNCF的にどうかは別として、クラウドネイティブ的だと思います。
ちょっと視点が変わりますが、1人の人間としてできることは限られています。このため、自分の代わりに働いてくれる誰かを探すということは、昔も今もこれからも、大事なテーマです。そして、クラウドネイティブでは、コンピューターに自分の代わりをしてもらうことが重要になっていると思います。
かといって、全部が全部コンピューターに任せられるかというとそうではありません。これについては、人の力を借りる必要もあります。コミュニティーの力を借りるのが、現代的なやり方なのかなと思います。すぐに役に立つかどうかは別として、コミュニティーを広げていくことは大事だと思いますし、このことは、ベンダーとしても、エンジニアとしても考えていく必要があります。
「ベンダーロックイン」と呼ばれることのリスクも、この延長線上で考えられると思っています。特定ベンダーの独自製品に関するノウハウを持った人が少ない場合、人材採用の点でリスクがあると言えます。そこまで考えるなら、単一のベンダーだけでなく、複数ベンダーがサポートしているものを選択するのは1つの考え方です。
コミュニティーが集まる場で情報を交換し、助け合っていくということ
――これまでのお2人のお話には、「自動化」というキーワードが頻繁に出てきました。「結局、クラウドネイティブで具体的にやるべきことを1つだけ指摘するなら、それは自動化だ」といえるのでしょうか?
青山 まず、一番クラウドネイティブからかけ離れている状態とは、「人が全てをオペレーションしている状態」ですね。その逆は「全てを人がオペレーションしていない状態」です。言い換えると、コンピューターが自分自身で全てを考え、最適化された状態でサービスを提供することだと思っています。クラウドネイティブで完全にその状態を実現できるというわけではないですが、将来的にそれを実現していくために何が必要かを考えると、自動化なのではないでしょうか。
もう1つ、どうしても言いたいことがあります。個人と組織のどちらも、クラウドネイティブにしていくというときに、「オープン」「コミュニティー」「オープンソース」と寄り添う姿勢を作っていってほしいなと思います。最近はいろいろな技術、いろいろな考え方が出てきていて、一個人、一組織内で行動していても、考え方からしてスケールしません。外に出ていって、コミュニティーなどと協力しながらやっていくのがベストかなと思います。
CNCFによるクラウドネイティブの定義には、「Cloud Native Computing Foundationは、オープンソースでベンダー中立プロジェクトのエコシステムを育成・維持して、このパラダイムの採用を促進したいと考えています」という記述があります。ベンダーやプロバイダー、ユーザーを問わず、オープンなところに出てきて、皆でエコシステムを作っています。
海外で開催されているCNCFのイベントに行けなくても、国内のイベントや勉強会に出てきていただいて、お互いにディスカッションを重ね、日本としても、クラウドネイティブをもっと進めていければいいなと思います。
組織としても、個人としても、こういう場に出てきていただければ、他の組織や人がやってどうだったかを知ることもでき、「意外にできるものなのだな」と分かってもらえるかなと思っています。
特集:クラウドネイティブとは何か? クラウドネイティブは「攻めのIT」の前提 ではその具体的な姿とは
今や、あらゆるWebテクノロジー企業が「クラウドネイティブ」を目指している。一般企業においても、デジタル化への取り組みに伴い、この言葉が最重要キーワードとして浮上している。クラウドネイティブは、これからの攻めのITにおける前提になったといって過言ではない。そこで次に語られるべきは、「具体的に何をやっていくのがいいか」ということだ。パブリッククラウドを使えば自動的にクラウドネイティブになるわけではない。本特集では、クラウドネイティブに一家言を持つ青山真也氏と草間一人氏の対談や、事例を通じ、クラウドネイティブの具体的な姿を明らかにしていく。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.