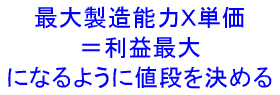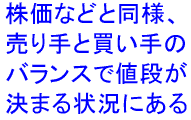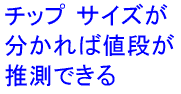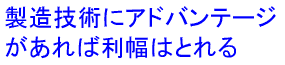第5回 プロセッサの値段は足元で決まる:頭脳放談
プロセッサの値段はどう決まるのだろうか? 今回は、プロセッサ価格の内訳と売値が決まるまでの話をしていこう。
普通、工学は自然科学として分類されるが、ある意味純粋な自然科学と大きく違うのは、「工学の対象はお値段なんぼ」という概念があり、社会科学的な意義付けが常に裏側に存在していることだ。逆に銭もうけの対象であれば、大抵のものは、工学的手法の対象になる。プロセッサは、「ハイテク」の代表選手に見られているが、値段決めに人知を傾けた「アルテ(技術)」の結晶ともいえ、また資本主義哲学の純粋な発露でもあるものなのだ。そこで、今回はプロセッサの値段について考察してみよう。
プロセッサの値段は取引条件で決まる
考察すると書いた瞬間、ぶっちゃけたところを書いてしまうが、値段の決め方など事情に応じて千差万別、一言で言い切ることはできない。だいたいほとんどの半導体製品は定価で販売するものでなく、営業担当者が相手の足元を見て、イチイチ個別に値段を決めているような製品だからだ。足元というとちょっと胡散臭い感じだが、数量、期間、支払方法などなど、取り引き条件は千差万別、そのため値段も違うといえば納得してもらえるだろうか。秋葉原でバラ売りしている値段でPCベンダが仕入れているわけではないのだ。
スパッと気合をいれて値段の決め方を無理矢理分類すれば、売り手が強い立場の場合と、買い手が強い立場の場合に分けられるのは、何もプロセッサに限った話ではない。ことにプロセッサについては、古典的といってよいほど資本主義の論理が貫徹している。
売り手が強ければ、粗利益7割、8割はあたり前
まずは売り手が強い場合を考えよう。誰もが考える代表選手は、インテルのプロセッサである。何せどのPCベンダも、インテルからプロセッサを仕入れないことには商売あがったり、という状況はまさに売り手の強さを証明している。筆者が以前勤めていた会社の元社長は、「インテルはお金を刷っているようなもんや」とよく言っていたものだ。確かに原価がたかだか数十ドルのPentiumが1000ドルで売れたのだから、造幣局とインテルを比較したくなる気持ちが分かる(経済学的には異議があると思うが)。
このように売り手が強い場合は、単純に工場の最大製造能力X単価=利益最大となるように単価を決めるのが、よいマーケティング担当者の行動である。あまり単価を高くしすぎれば、1個あたりの利益が大きくても、数量がでないので、折角の工場能力を余らせることになるし、かといって限りある工場能力を安売りしても困る。というのも、最先端の半導体工場は、数千億円もかかる巨大設備投資であり、その投資は最終的に製造される個々のプロセッサの頭数で割って償却しなければならないからだ。正に時は金なりなので、工場の製造能力に釣り合うデマンド(需要)が市場から出てきて、かつ利益が最大となるような単価を設定しないとならない。当然、インテルの先端プロセッサのように、強いデマンドのあるもの(あったもの)は、原価とはほぼ無関係といってよい値段になり、粗利益7割、8割はあたり前という世界になっている(ものと推測している)。
競争が起きれば値段が動く
もちろん、競争がない世界ならば、上述のような売り手の都合で値段を決定することが可能だ。自社の速いプロセッサの出荷の準備が整えば、それまでのプロセッサの値段を下げて、より個数を売る方向に誘導し、速いプロセッサにプレミアを付けて高い値段で売るといった調整もできる。自社の出荷時期は当然コントロールできるから、自社だけであれば計画的な生産、計画的な値段提示となる。しかし、いったん他社に競合品を出されると、デマンドの強いプロセッサといっても、値段が動いてくる。インテルとAMDの競争は、発表だけでまだ量産出荷もされていないプロセッサが次々と値下げされる、といった不思議な局面もあった。これは、デマンドは常に速いプロセッサに向かうことを考えれば、株価などと同様、売り手と買い手のバランスで値段が決まる状況にあるということで、一種、気配値とでもいうべきものだったのかもしれない。このような局面では、先手を取ったほうが市場をコントロールでき、有利なポジションを取れるから、両者が不毛なまでに速度競争に走ったことも理解できる。このような場合、値段は後述するようなローカルな価格形成にはならず、グローバルなものとなるのが一般的である。
このようなハイエンドのプロセッサでは、あるところまで値段が下がるとディスコン(生産中止:discountinue)となる。大体ディスコンになるのは、原価が見えてきて、原価からの積み上げベースで売り値を考えなければならなくなるあたりだ。どうも粗利が3割5分くらいだと、そろそろ危ないという感じではないだろうか。インテルのようなプロセッサ メーカーにしてみれば、利益が取れない製品に限りある工場の容量を取られてしまうくらいならスッパリ止めて、より高性能で高く売れるものにシフトしたほうが全体の利益は大きいに決まっているのだ。この結果、この系統のプロセッサは、製品寿命が短く、直ぐに高性能な新製品に切り替わっていくことになる。
蛇足になるが、主流のプロセッサがこうした販売形態になっているため、どうもインテル系の組み込み用プロセッサは供給に問題のあるものが多い。組み込み用途となると、製品寿命が長いことが多いので、ユーザーはよく5年間の安定供給といった要求を行うが、そういうことをすると古い利幅が取れない製品に工場のラインを割り当てることになってしまうため、インテルのように利幅の大きい製品を持つ会社は、こういうことを嫌う。
買い手が強いと利益は薄い
今度は買い手が強い場合を考えみよう。組み込み用途のプロセッサを始めとしたほとんどの半導体が該当する。買い手はPC向けプロセッサの場合のように、無闇に性能を求めたりしない。自分の製品に適合するそこそこのところで十分、その中でなるべく安いところから買いたいと思う。もちろん、その適合するような製品は何社からも出ている、といった場合である。そういう状況下の製品(実はほとんどのプロセッサはこのカテゴリに入ってしまう)の場合は、昨今のように半導体の需要が大きく、半導体の需給がひっ迫して相対的に売り手が強いという状況でも、そうそうPC用のプロセッサのような大きな利幅は取れない。何せ、いったん下がった値段を上げるのは容易ではないし、半導体は好況の期間よりも不況の期間のほうが長いような商売だ。好況時に買い手に不義理をしていると不況時には真っ先に切られてしまう。
さらに面倒なのは、買い手のほうも売り手の原価を大体つかんで話をしてくるところだ。半導体の買い手は、システム メーカーになる。当然ながらシステム メーカーの担当者は、半導体メーカーの手の内をよく知っている手強い相手である。つまるところプロセッサの原価は、プロセス テクノロジとチップ サイズとパッケージが分かれば、彼らにも大体計算できてしまうからだ。半導体メーカーによって、多少の高い安いはあるが、同じ業界で長年商売していると自然と基本的なコストが見えてくる。
原価はチップ サイズでだいたい分かる
材料代の第1はウエハー代だが、ウエハーを作っている会社はごくごく限られており、どこの半導体メーカーの仕入れ先も似たような状況だろう。ウエハーといっても、種類やサイズがいろいろあるが、同じサイズで同じようなプロセス テクノロジ向けのウエハーなら、どこも同じ程度のコストで買っているはずだ。ウエハーに設計を焼き付けるためのマスクにしても、同じような寡占状況にある。というわけで、どこも仕入れ価格は似たようなものになる。また、プロセスの加工コストにしても、同程度のプロセスなら同じような値段の同じような生産設備(これまた寡占だ)を使って、似たような繰り返しで作っているのだから、それほどの差はないはずだ。もちろん、人件費や電力料金などは国によりかなり差はあるけれど、桁が違うほどではない。するとウエハーでみたコストは、どこも似たり寄ったりとなるはずだから、結局、1枚のウエハーからどれだけの個数の製品がとれるか、つまりチップ サイズが分かればだいたいの値段が推測できてしまう。
もう1つの値段を決める要因であるパッケージは、ものを見れば分かってしまう。さらに半導体メーカーは、どのようなプロセスかも教えるのが普通だ。何せこのごろは、コアの電源電圧が3.3Vなら0.35μ、2.5Vなら0.25μ、1.8Vなら0.18μといった具合に、いわなくともプロセスは知れてしまう。大体、どのようなテクノロジを使っているのか説明しないと、先々の計画(ロードマップ)を話しても、顧客は納得しないので、普通はむしろ積極的に説明するものなのだ。そこで、こればかりは御勘弁ということで、半導体メーカーは顧客にチップ サイズだけは教えたがらない。けれど買い手もさるもの、機能から大体のところは当ててくる。というわけで、お互い原価のイメージが頭の中にあるなかでの交渉となる。システム メーカーとしては、彼らの持つ原価のイメージに限りなく近い価格提示を引き出したい、というのが希望だ。半導体メーカーとしては、彼らのイメージする価格にそって、満足していただきつつ、実はもっと安いコストで製造できて、がっぽりと利益が取れるのが理想である。
結局システム メーカーの思うツボ
とはいいつつも、このように理想的にいくことはまずない。まず、半導体メーカーにとっては嫌な、原価ぎりぎりでほんの僅かな利益をのせてというケースを考えよう。同じような機能、同じようなプロセスの製品で競合メーカーとバッティングし、値段の叩き合いになったりすると、そうなることが多い。こういう商売はなるべく避けたいというのが、半導体メーカーすべての本音だろう。しかし、半導体は非常に適切な競争状態にあり、談合などまずあり得ないので、大事な顧客をライバルに取られるくらいなら、あるいは売れずに工場のラインを空けておくよりは、ということでこの手の原価にほんのわずかな利益をのせたオファーになることが多い。この場合、わずかといっても、原価の差が致命傷となるので、先ほど述べたような細かな積み上げによる各半導体メーカーのコスト競争力が試されることになる。この手の商売は、インテルなどの最先端PCプロセッサの対極にあり、マーケティング担当者はコスト計算と競合会社の価格との間の、わずかな隙間にただよっている存在でしかなくなり、カッコいい価格戦略などは打ち出す余地がない。この場合は、正にシステム メーカーの思うツボである。
次に、コンペとぶつかっても自社のコストが十分安い、めでたい場合がある。例えば、同じような機能の製品でも競合会社が、0.5μプロセスで製造しており、当方が0.25μプロセスといったような場合だ。2世代のプロセスの開きがあると、コスト的には当方がかなり有利である。同じ大きさのウエハーから、2倍以上の個数の製品が取れることになるはずだからだ。単純に計算してコストは半分になる。このような場合には、ともかく競合会社の価格を探り、それよりいくらか安い値段を提示する。この場合、受注できれば自社の製造技術のアドバンテージの分だけ利幅がとれることになって、とても嬉しいことになる。しかし、こういっためでたいケースはあまりない。それどころか、逆のケースで一巻の終わり、ということのほうが多いように思うのは、半導体営業のサガであろうか。
上と似たケースで、複数の機能を集積したチップと、それぞれの機能を持つ単品のチップの競合というのもよくある。システム メーカー側の論理は、複数の機能を1個にしたのだから、それぞれの機能の単品製品を足した値段より安くしてくれということになる。ところが、半導体メーカーからすれば、複数の機能を集積するとチップ サイズが大きくなり、ある程度以上大きなチップ サイズになると収率(イールド−yield:1枚のウエハーから取れるはずの数のうち、正常に動作する製品の率)が急速に悪くなるので、集積した分値段が高くなってしまう、ということもままある。この場合、集積したもののチップ サイズがある程度小さく、収率をあまり落とさずに作れれば、システム メーカーの論理どおりで決まり、そうでないときは、システム メーカーは単品を採用することになるので、尻尾を巻いてスゴスゴ帰っていくことになる。集積チップも楽じゃない!
ともかく、このような買い手が強い立場にあるケースでは、地味な営業活動によりきわめてローカルな価格が形成される。ローカルというのは、同じものでも買い手によって、価格が大分異なるということだ。これも資本主義の一面である。
昨今はインターネット ベンチャーばかりだが、一昔前までは半導体ベンチャーは花形だった。今や巨人のインテルも昔はベンチャーだった。そのころは半導体メーカーは、ほかに先駆けて製品を出し、大きな先行者利益を取って、それをさらに開発に投資して大きくしていくというのが、ビジネス モデルであった。いまどきIPOを狙っているインターネット ベンチャーのビジネス モデルに比べたら余りにも他愛のない。昔は、こんなものでも十分だった。あの頃が懐かしい。
筆者紹介
Massa POP Izumida
日本では数少ないx86プロセッサのアーキテクト。某米国半導体メーカーで8bitと16bitの、日本のベンチャー企業でx86互換プロセッサの設計に従事する。その後、出版社の半導体事業部を経て、現在は某半導体メーカーでRISCプロセッサを中心とした開発を行っている。
「頭脳放談」
Copyright© Digital Advantage Corp. All Rights Reserved.