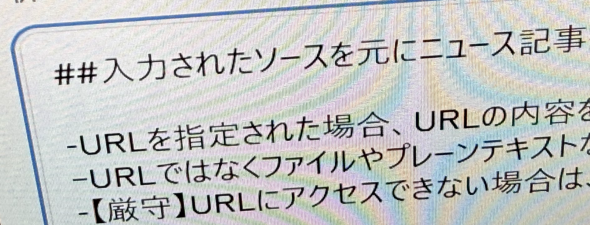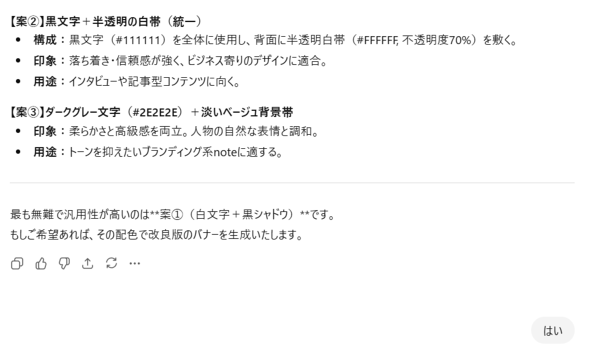AIで「メンドクサイ」は減ったけど、「オモシロイ」は増えてない:やつらには「良い」記事を作る嗅覚がない(いまのところ)
記事の体裁にはなっている、間違ってもいない、でも何かが欠けている。これが2025年11月時点のAIによる記事作成能力です。
この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。
生成AI(人工知能)がホワイトカラーの仕事を大きく変えつつあります。「手作業のコーディングがほとんどなくなった」というプログラマーの声も聞くようになりました。
筆者のようなライター業も、AIで仕事の形が変わりました。特に感じているのは「メンドクサイ」の減少。嫌だなあ、やりたくないなあ、と思っていた仕事のかなりの部分をAIに任せられるようになり、気持ちがラクになりました。
一方で、記事の核である「オモシロイ」を見つけることは、AIには全然できないし、いまのところできる気配もないなあ、と思っています。
記事を全自動で執筆……できるわけない!
現在、筆者が最も活用しているAIの用途は、プレスリリースに基づいた速報記事の下書き作成です。
専用プロンプトを作ってソースとなるリリースURLを入力すると、一発で記事が完成……するといいなあ、と思っていましたが、そんな夢みたいなことは起きません。
プロンプトは何度も練り直しましたが、一発OKの記事ができる気配はない。リリースの「重要な部分」をAIが判断できないから、記事を「重要な順」に構成できず、ちぐはぐな文章になりがちなのです。
重要な部分は、文脈や掲載媒体によって変わります。ライターは、「この会社は、ライバル企業の発表に対抗して、このリリースを出したんだな」とか「この仕様で、いまのトレンドに乗ろうとしている」「内容自体はたいしたことはないが、表現が面白い」「媒体の特集の方向性に合っている」など、リリースを読みながら、ポイントを判断していきます。
こうした「ニュースバリュー」や「面白さ」の判断、経験による“嗅覚”がAIにはない。その結果、ニュース記事の体裁にはなっているものの、まったく重要でないことをえんえん書いた“ダメ記事”が出来上がってきます。
テーマやジャンルごとに文脈や面白さを細かく教え込めばいいのかもしれませんが、1記事、1テーマずつその手間をかけるぐらいなら、人間が瞬時に判断して書いた方が早い。それにAIは、洗練されたニュース風の日本語は得意ではないので、都度、修正が必要です。
最初の一歩がラクになった
ただ、書き始めるまでの一歩はラクになりました。
筆者は、リリースを見て「書かなきゃなあ」と思ってから1文字目をタイプするまで、短くて5分ぐらい、長いと1時間かかります。
空白の時間に何をしているかというと、友人とチャットで雑談したり、「X」に不要不急の書き込みをしたりダラダラしているのですが、その合間にAIツールを開き、ニュースリリースのURLをインプットするだけで、“記事っぽい体裁の草稿”までは全自動で出来上がります。
この草稿を基に、「AI、日本語下手だな!」「何でそこにそれを書くんだよ!」とツッコミながら手直しする。イチから重い腰を上げるまでに必要なエネルギーは節約できています。
AIは“自分でワクワクしない”から
インタビュー記事づくりもラクになりました。インタビュー後の書き起こしが、AIによってほぼ不要になったからです。
ただAIによる書き起こしには間違いもあるので、聞き直してチェックする必要はあります。それでも、イチから起こすことと比べたら、労力は3分の1ぐらいになったと思います。
文章構成もAIに任せることはできますが、ここでリリース起こしと同じ問題が起きます。「テンプレ通りに構成された記事」を作ることはできても「重要な部分をきちんとカバーした記事」や「読んだ人が面白いと思える記事」の構成を作るのが、AIには困難なのです。
結局、「面白い」とか「興味深い」はAIに任せられません。AIには人格や感情がないため、「面白い」を自分で感じたり、「これが実現すれば、未来がこうなりそうでワクワクするから主題にしよう」とか「本筋とは関係ないけど、笑えるから入れておこう」といった判断をしたりできないから、AIだけで「面白い記事」を完成させられません。
苦手分野はAIと二人三脚で
ライターや記者の仕事では、「苦手な分野でも、記事を書かなくてはならない」というシーンがままあります。例えば私の場合、経営系の数字や分析に苦手意識がありますが、AIを使い始めてから、不安なく挑めるようになりました。
決算など経営の数字にはルールとロジックがあり、ネットに豊富なデータがあるため、AIがかなり正確な解説や分析をしてくれます。「これで大丈夫かな?」と不安になりながら書いていた決算記事も、AIと共に仕上げることで、自信を持って出せるようになりました。
苦手分野といえば、デザインもそうです。自分でバナー画像を作らなくてはならない場合に、「何か違うが、どうすればいいか分からない」と思うことがままあります。そんなとき、AIにデザインを読み込ませて修正案を出してもらい、アドバイスに基づいて修正できるようになりました。
「苦手かつ、分からないことを質問できる相手もいないけれど、やらなくてはいけない」ジャンルで、AIは強力なパートナーになってくれています。
AIで“心と頭脳”を温存する
AIは、ある程度のルールが決まってるとかデータが豊富な場合の“作業”は得意です。
例えば、取材依頼を箇条書きから丁寧なメール文にしてもらうなどの作業は得意。「失礼にならないように書く」など気を遣う作業を自力でやると、脳や心がちょっと疲れますが、ここをまるっとAIに任せることで、疲れにくくなったと感じています。
ただ、「面白い」を任せられる気配はまだない。「面白い」の判断はいまのところ人間の専売特許のようだから、ライター仕事の面白さは、いまのところ変わっていません。
AIが感情を持ち、ワクワクしたり一喜一憂したりするようになるまで、ライターの仕事がAIに取って代わられる日は来ないのかなあ……とも思います。
関連記事
 AIが意外とできない“簡単な”お仕事
AIが意外とできない“簡単な”お仕事
2023年は、AIの得手不得手がある程度明確になった1年でした。来年は精進して私の仕事をもっと奪ってほしいものです。 私、AIにパワハラしちゃうんです
私、AIにパワハラしちゃうんです
人間相手に同じことをやったら、訴えられちゃうかも。 エンジニアじゃないけれど、AI使っていいですか?
エンジニアじゃないけれど、AI使っていいですか?
道具を使いこなして、楽になりたい。
関連リンク
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.