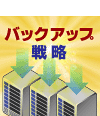
いまどきのサーババックアップ戦略入門(2)
サーババックアップに関するいまどきの選択肢
株式会社シマンテック
後藤 博之
2007/9/28
サーバのバックアップでは、業務要件に応じてバックアップ技術を使い分けるべきだ。では、使い分けるバックアップ技術にはどのような選択肢があるのか。今回はこれを説明する
前回は「サーババックアップ戦略を左右する基本要素」と題して、サーババックアップにおける課題とリストア要件に基づくバックアップ設計について解説したが、今回はバックアップにおける選択肢の詳細を説明していく。
まずバックアップ手法の選択肢について内容や特徴を説明し、次にバックアップポリシーとバックアップ手法との組み合わせについて、最後にバックアップシステム構成の選択肢について紹介する。
バックアップ手法の選択肢
■ファイルバックアップ
1つ目のバックアップ手法の選択肢としてファイルバックアップがある。ファイルバックアップの特徴として、ファイル単位によるバックアップを行うことができる点が挙げられる。ファイル単位でのバックアップ手法であることから、バックアップ元に格納されているファイルは「静的ファイル」であることが望ましい。一般的には静的ファイルが多く存在しているバックアップ対象として、ファイルサーバやアーカイブされたログ格納サーバ、Webサーバなどに適用される。従来から用いられている、業界標準のバックアップ手法であるといえる。
バックアップ手法としてファイルバックアップを選択した際には、バックアップ取得のタイミングをどうするかを考える必要がある。一般的に、バックアップ作業は業務時間帯以外の夜間などに行われている。その理由の1つは、業務時間帯にはオープンファイルが多く存在しているが、ユーザーアクセスが少ない時間帯であれば静的ファイル状態が多いだろう、という想定にある。バックアップ取得時にファイルがオープンされている場合、多くのバックアップソフトウェアでは、そのファイルをスキップしてデータ取得する。バックアップステータスとしてはファイルの取りこぼしとなってしまうため、オープンファイルの扱いには注意が必要である。
リストアの観点からファイルバックアップが選択される理由としては、バックアップ取得したデータをそのまま戻し、バックアップ対象でリストアしたデータをそのまま再利用したいというバックアップ運用上のニーズが挙げられる。ファイルバックアップの場合、後述するイメージコピーと違い、ファイル単位でリストアすることが可能だ。ただし、フルリストアを行う運用が多いと考えられる場合や、RTOよりサービス停止期間(ダウンタイム)を短くする必要があるシステムの場合には、ファイルバックアップ手法とは別の選択を考える必要がある。
■イメージコピーバックアップ
2つ目のバックアップ手法の選択肢としてイメージコピーバックアップがある。前回はイメージコピーバックアップとスナップショットをまとめて紹介したが、ここではこの2つを切り離して説明したい。
イメージコピーバックアップは、サーバの電源を1度オフにして、ディスク上のデータイメージのコピーを取得するコールドイメージの手法である。ディスク上のデータ全体をイメージとして取得することから、バックアップ対象のOSシステムをバックアップする目的で利用される。またディスク全体のデータイメージであることから、バックアップ目的の利用だけではなく、ほかのサーバへのクローニング(複製)や配布も可能だ。コールドイメージであることにより、ある特定の時間帯までに書き込みされた状態のバックアップデータとして特定しやすく、バックアップデータとして信頼できる。また、サーバを停止して取得するためにオープンファイルも存在しないことにより、ファイルの取りこぼしはない。
イメージコピーバックアップではバックアップ取得のタイミングが問題となる。このバックアップ手法では、サーバの電源を1度オフにする必要がある。従って、バックアップ作業は、サーバの計画停止を実施したタイミングに行われているのが一般的だ。ファイルバックアップと違い、業務時間でイメージコピーバックアップを行うことは難しいので、管理者の悩みどころだ。
リストアの観点からイメージコピーバックアップが選択される理由としては、コールドイメージであることより、データの整合性が高く、確実にリストアを行えるという信頼度の高さが挙げられる。OSやアプリケーションにパッチを適用する前にイメージコピーバックアップを実行し、その後にパッチを適用し、さらにOSやアプリケーションの動作に問題がなければ、再度イメージコピーバックアップを実行するといったバックアップ運用が多い。また、ファイルバックアップと違い、ディスクのコールドイメージであるため、ファイル単体では戻せないことに注意が必要だ。OSがクラッシュして起動できない場合には、イメージコピーバックアップからのリストアとなるが、最新のイメージコピーバックアップ取得後からどのくらい期間が経過しているかが問題となる。半年も前のイメージの場合、そのままではデータが古過ぎて使えず、RPO要件を満たせないといった状況にならないように、イメージコピーバックアップとファイルバックアップの組み合わせが必要だといえる。
■無停止バックアップ
3つ目のバックアップ手法の選択肢として、ストレージやボリューム管理ソフトウェアなどで提供されるスナップショット技術を使い、データベースやオープンファイルなど稼働中のサービスを止めずにバックアップを取得する無停止バックアップがある。無停止バックアップの特徴として、ファイル単位またはイメージ単位の両方のバックアップが行えることが挙げられる。
ファイル単位のスナップショットは、バックアップソフトでオープンファイルを一時的にコピー(スナップショット)し、コピーされた静的ファイルをバックアップすることで、ファイルの取りこぼしがなくすのが目的である。一方、イメージ単位のスナップショットは、前述で説明したイメージコピーバックアップと違い、ホットイメージ(システムが立ち上がった状態)バックアップであるため、データベースやメールサーバ、大容量の外部ストレージ上に大量のデータを格納するサーバ、大量のI/Oが発生したりオープンファイルが存在するサーバなど、に適したバックアップ手法である。
バックアップ取得タイミングについては、スナップショット技術がホットイメージであるため、ほかのバックアップ手法と違いバックアップ取得の準備における制限事項が少ない。このため、業務要件に応じて柔軟にバックアップタイミングを設定できる点に、このバックアップ手法のメリットがある。例えば、日中の業務時間帯以外の夜間においても頻繁にデータ更新されているシステムや、ある一定期間のサーバ停止ができないシステムにおいては、この無停止バックアップを適用すれば業務に影響が少ない。
無停止バックアップにおけるリストアは、バックアップがファイル単位かイメージ単位かによって方法が異なる。ファイル単位でのバックアップの場合にはファイル単位で戻すことができるが、イメージ単位の場合はフルリストアとなる点には注意が必要だ。バックアップ取得時に稼働中のサービスのデータを、スナップショット時点の状態に戻す形となるため、リストア後の動作確認には十分注意していただきたい。そのため、バックアップする際に対象となるサービスやアプリケーションの特徴を把握したうえで、静止点の仕組みを検討する必要がある。
1/3 |
| Index | |
| サーババックアップに関するいまどきの選択肢 | |
| Page1 バックアップ手法の選択肢 |
|
| Page2 バックアップポリシーの選択肢 |
|
| Page3 バックアップシステム構成の選択肢 本連載の今後の記事予定 |
|
- Windows 10の導入、それはWindows as a Serviceの始まり (2017/7/27)
本連載では、これからWindows 10への移行を本格的に進めようとしている企業/IT管理者向けに、移行計画、展開、管理、企業向けの注目の機能について解説していきます。今回は、「サービスとしてのWindows(Windows as a Service:WaaS)」の理解を深めましょう - Windows 10への移行計画を早急に進めるべき理由 (2017/7/21)
本連載では、これからWindows 10への移行を本格的に進めようとしている企業/IT管理者に向け、移行計画、展開、管理、企業向けの注目の機能を解説していきます。第1回目は、「Windows 10に移行すべき理由」を説明します - Azure仮想マシンの最新v3シリーズは、Broadwell世代でHyper-Vのネストにも対応 (2017/7/20)
AzureのIaaSで、Azure仮想マシンの第三世代となるDv3およびEv3シリーズが利用可能になりました。また、新たにWindows Server 2016仮想マシンでは「入れ子構造の仮想化」がサポートされ、Hyper-V仮想マシンやHyper-Vコンテナの実行が可能になります - 【 New-ADUser 】コマンドレット――Active Directoryのユーザーアカウントを作成する (2017/7/19)
本連載は、Windows PowerShellコマンドレットについて、基本書式からオプション、具体的な実行例までを紹介していきます。今回は、「New-ADUser」コマンドレットです
|
|




